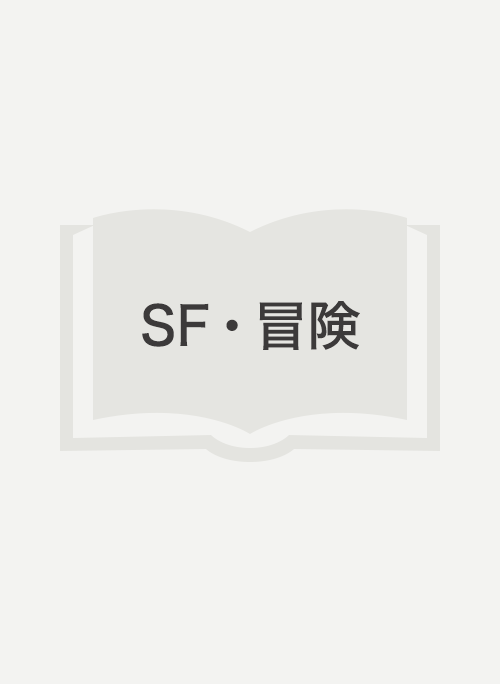「オレミ君は本当によく破損品(はそんひん)を見つけるよね」と主任が言った。それが褒めているわけではないということは、声で分かる。
「はあ。確かに、袋の空気が抜けていたり、中身の形が崩れていたりするものは、一応、取り除くようにはしていますけど……」
ローラーラインを次々と流れてくる袋詰めの商品――食パン・総菜パン・菓子パン・和菓子――それらを店舗ごとに指定された数だけケースに詰めていく手を止め、僕は答えた。
すると主任は表情を変えず、あらかじめ決められていた言葉を紡ぐ。
そう、僕がなんと答えようと関係がない。主任は最初から説教をするつもりでいたのだ。彼のシナリオにはもともとルート分岐など存在せず、つまり僕の返答なんてものは、どちらを選んでも同じ結果になる無意味な選択肢と同じことなのだ。
「いいか。メーカーから送られてきた商品をここで仕分け、各販売店に出荷するだろう。販売店が破損品だと判断すれば、それはここではなくメーカーに返品される。だから、わざわざ我々が破損品を見つけて返品する必要なんてないんだ。どの段階で破損したのかなんて、分かりゃしないんだしな。……それに、返品したらそのぶんだけ、新たにメーカーから商品を送ってもらわにゃならんだろう。無駄な手間だ」
主任は言うと、僕が『破損品用』のケースに仕分けた商品を一つずつ手に取って検分し、「これも問題ないじゃないか。これも。これもだ」と呟いては、それを仕分けラインの上へと戻していく。
「でも、破損品だと分かってるんですから……。それに、お店側が困るじゃないですか。ほしい数だけちゃんと、売れる商品が届かないと」
「……販売店側だって、いくつか破損品が混じってくることくらい、分かってるだろうさ。それを見越して多めに発注してるだろう、当然」
「でも、……じゃあ、販売店も気付かずに破損品を売っちゃったら、どうするんですか」
「そしたら客が返品するだけの話だ。とにかくゴチャゴチャ言うな。全部仕分けておけ」
「いや、でも……」
「でもでも言うな」
僕はそれでもまだ反論しようとしたのだけれど、主任はケースの中に残った破損品を突くように鋭く指さし去っていく。
僕は仕方なく、一番近隣の店舗へ出荷されるケースにそれらを入れた。破損品分の追加発注があっても、近場なら早く届けることができる。
「はあ。確かに、袋の空気が抜けていたり、中身の形が崩れていたりするものは、一応、取り除くようにはしていますけど……」
ローラーラインを次々と流れてくる袋詰めの商品――食パン・総菜パン・菓子パン・和菓子――それらを店舗ごとに指定された数だけケースに詰めていく手を止め、僕は答えた。
すると主任は表情を変えず、あらかじめ決められていた言葉を紡ぐ。
そう、僕がなんと答えようと関係がない。主任は最初から説教をするつもりでいたのだ。彼のシナリオにはもともとルート分岐など存在せず、つまり僕の返答なんてものは、どちらを選んでも同じ結果になる無意味な選択肢と同じことなのだ。
「いいか。メーカーから送られてきた商品をここで仕分け、各販売店に出荷するだろう。販売店が破損品だと判断すれば、それはここではなくメーカーに返品される。だから、わざわざ我々が破損品を見つけて返品する必要なんてないんだ。どの段階で破損したのかなんて、分かりゃしないんだしな。……それに、返品したらそのぶんだけ、新たにメーカーから商品を送ってもらわにゃならんだろう。無駄な手間だ」
主任は言うと、僕が『破損品用』のケースに仕分けた商品を一つずつ手に取って検分し、「これも問題ないじゃないか。これも。これもだ」と呟いては、それを仕分けラインの上へと戻していく。
「でも、破損品だと分かってるんですから……。それに、お店側が困るじゃないですか。ほしい数だけちゃんと、売れる商品が届かないと」
「……販売店側だって、いくつか破損品が混じってくることくらい、分かってるだろうさ。それを見越して多めに発注してるだろう、当然」
「でも、……じゃあ、販売店も気付かずに破損品を売っちゃったら、どうするんですか」
「そしたら客が返品するだけの話だ。とにかくゴチャゴチャ言うな。全部仕分けておけ」
「いや、でも……」
「でもでも言うな」
僕はそれでもまだ反論しようとしたのだけれど、主任はケースの中に残った破損品を突くように鋭く指さし去っていく。
僕は仕方なく、一番近隣の店舗へ出荷されるケースにそれらを入れた。破損品分の追加発注があっても、近場なら早く届けることができる。