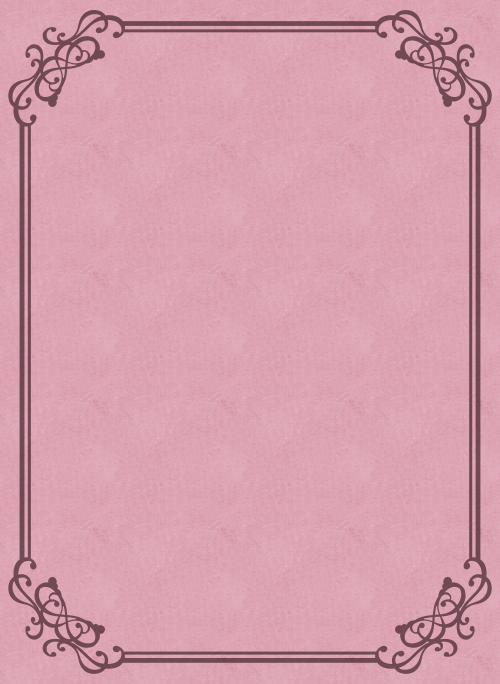「それで、どうだったの。ゆーふぉーの中は」
「タイムマシン、な」
「ゆーふぉーじゃないの?」
「いや、未確認飛行物体って意味ではゆーふぉーだろうよ。でも、瀬都奈と僕には見えるし、それが何であるか知っている。もう、それは未確認じゃないだろう」
「ふーん。そっか。じゃあ、何話したの?」
「それは、その。秘密だ。あっ、でも次年号教えてもらった」
「へえ、なんて言うの」
「そんなの。言えるわけない」
「僕は君の空想上の存在だ。知っても知らなくても、タイムパラドックスは起こらないと思うよ。君が知っていた方がヤバい気がするけどね」
「確かに。それは、そうかもしれない」
「ふふっ。冗談だよ」
エデンは僕の答えに微笑んでいる。答えなんてなんでもいいみたいだった。言葉なんて何でもいいかのようであった。UFOなんて、タイムマシンなんて気にもしていないかのようだった。実際そうなのだろう。彼はいつもそうだし、そういう存在だ。
エデンの姿は僕にしか見えない。
明星瀬都奈にだって見ることができない。僕の頭の中にしかいなくて、現実には存在しない架空の友人。美形の顔で、さらりとした髪をしている。前髪は目線まで長いが、その優しい瞳はしっかりと見える。彼は空想上の存在だが、僕にとっては実存する本当そのものなんだ。今回の未確認飛行物体も、その想像ばかりの世界の延長だと最初は思っていた。だからある程度は諦めていたし、誰かに話すようなことでもないと、そう思っていたんだ。
でも、今回はそういう意味では違う。空想上でも、想像上でもない。瀬都奈という共通点が確かにある。
未確認飛行物体、unidentified flying objectの頭文字三文字でUFOと呼ぶそれは、今回の場合に限りタイムマシンである。瀬都奈が未来から今を侵略するために使用したタイムマシン。未来から過去への時間移動。明星瀬都奈の事は僕のクラスメイトも、担任の先生も、他の教職員も認識している。話もしているし、その認識に差異は微塵もない。ただ、タイムマシンとなると話は別。確認はしていないが、あれは瀬都奈と僕以外には多分見えていない。通行人という、名前の知らない第三者が指を刺さない事実がそうだと示している。実際、僕はタイムマシンに乗った。あの未確認飛行物体は存在している。触れることもできる、実在するそのものだ。だけど、第三者には認識できない。瀬都奈と僕にはタイムマシンを認識できる。第三者は瀬都奈を認識できるが、タイムマシンを認識できない。エデンの事を僕は認識できるが、瀬都奈も第三者も認識できない。これが架空上の存在、非存在だとすると、タイムマシンはより不明瞭な存在となる。架空上の存在、想像の世界における事物と言えばそこまでだが、それは同時に間違いでもある。タイムマシンの存在を否定すれば、それは瀬都奈の存在を否定することになり、瀬都奈こそが想像上の人物であるという事になる。瀬都奈という存在が偽物でなく、記憶の改竄出ない限り、やはりタイムマシンは存在するということになる。
「それで、あのミサイルも君の仕業?」
「いや、それは違うと思うんだけど」
タイムマシン搭乗から二時間半後であった。晩飯のハンバーグを白米と共に掻き込んでいる最中、速報で入ったミサイルが東京に飛来したというニュースはあまりにもショッキングな出来事だった。また、そのミサイルの出どころがこの現代科学をフルに稼働させても解明できないというから、尚の事である。テロ行為だと言う首相と報道番組の発表は僕に瀬都奈とタイムマシンの事をすぐに想起させた。瀬都奈はあれでも自称侵略者である。それが誰かの仕業だと言うなら、僕より瀬都奈のほうが妥当で疑わしかろう。
「でも、君は今日乗ったんだろう? そのタイムマシンとやらに」
「うん」
「何か操作したのかい?」
「いや、特にはしなかったと思うんだけど」
「勇気が無かった?」
「覚悟なかった、かな。責任を取るだけの覚悟を持ってなかったんだと思う。興味と好奇心と冒険心に中二病持ち合わせての行動だったけど、何か動かすという度胸は無かったと思う」
「そうだね。君はそういう賢い子だ」
「でも、やっぱり」
「気になるかい?」
うん。そりゃ、そうだろう。こうも現実離れしたことが続くと本当に夢を見ているんじゃないかと思ってしまう。現実ではない。僕の夢想。空想上の世界の話。エデンと会話しているその延長線上。不可思議と空想を想うあまりに産んだ、ただの作り話。その日はそう思って、電気を消した。
瀬都奈が悪者なんて、テロリストなんて嫌だった。なぜそう思うのかはまだ分からないし、考えてなかっけど無性にそう思ったんだ。夢ならいいのに。夢じゃなければいいのに。
だけど、現実は厳しかった。本当に、それに限る。
「タイムマシン、な」
「ゆーふぉーじゃないの?」
「いや、未確認飛行物体って意味ではゆーふぉーだろうよ。でも、瀬都奈と僕には見えるし、それが何であるか知っている。もう、それは未確認じゃないだろう」
「ふーん。そっか。じゃあ、何話したの?」
「それは、その。秘密だ。あっ、でも次年号教えてもらった」
「へえ、なんて言うの」
「そんなの。言えるわけない」
「僕は君の空想上の存在だ。知っても知らなくても、タイムパラドックスは起こらないと思うよ。君が知っていた方がヤバい気がするけどね」
「確かに。それは、そうかもしれない」
「ふふっ。冗談だよ」
エデンは僕の答えに微笑んでいる。答えなんてなんでもいいみたいだった。言葉なんて何でもいいかのようであった。UFOなんて、タイムマシンなんて気にもしていないかのようだった。実際そうなのだろう。彼はいつもそうだし、そういう存在だ。
エデンの姿は僕にしか見えない。
明星瀬都奈にだって見ることができない。僕の頭の中にしかいなくて、現実には存在しない架空の友人。美形の顔で、さらりとした髪をしている。前髪は目線まで長いが、その優しい瞳はしっかりと見える。彼は空想上の存在だが、僕にとっては実存する本当そのものなんだ。今回の未確認飛行物体も、その想像ばかりの世界の延長だと最初は思っていた。だからある程度は諦めていたし、誰かに話すようなことでもないと、そう思っていたんだ。
でも、今回はそういう意味では違う。空想上でも、想像上でもない。瀬都奈という共通点が確かにある。
未確認飛行物体、unidentified flying objectの頭文字三文字でUFOと呼ぶそれは、今回の場合に限りタイムマシンである。瀬都奈が未来から今を侵略するために使用したタイムマシン。未来から過去への時間移動。明星瀬都奈の事は僕のクラスメイトも、担任の先生も、他の教職員も認識している。話もしているし、その認識に差異は微塵もない。ただ、タイムマシンとなると話は別。確認はしていないが、あれは瀬都奈と僕以外には多分見えていない。通行人という、名前の知らない第三者が指を刺さない事実がそうだと示している。実際、僕はタイムマシンに乗った。あの未確認飛行物体は存在している。触れることもできる、実在するそのものだ。だけど、第三者には認識できない。瀬都奈と僕にはタイムマシンを認識できる。第三者は瀬都奈を認識できるが、タイムマシンを認識できない。エデンの事を僕は認識できるが、瀬都奈も第三者も認識できない。これが架空上の存在、非存在だとすると、タイムマシンはより不明瞭な存在となる。架空上の存在、想像の世界における事物と言えばそこまでだが、それは同時に間違いでもある。タイムマシンの存在を否定すれば、それは瀬都奈の存在を否定することになり、瀬都奈こそが想像上の人物であるという事になる。瀬都奈という存在が偽物でなく、記憶の改竄出ない限り、やはりタイムマシンは存在するということになる。
「それで、あのミサイルも君の仕業?」
「いや、それは違うと思うんだけど」
タイムマシン搭乗から二時間半後であった。晩飯のハンバーグを白米と共に掻き込んでいる最中、速報で入ったミサイルが東京に飛来したというニュースはあまりにもショッキングな出来事だった。また、そのミサイルの出どころがこの現代科学をフルに稼働させても解明できないというから、尚の事である。テロ行為だと言う首相と報道番組の発表は僕に瀬都奈とタイムマシンの事をすぐに想起させた。瀬都奈はあれでも自称侵略者である。それが誰かの仕業だと言うなら、僕より瀬都奈のほうが妥当で疑わしかろう。
「でも、君は今日乗ったんだろう? そのタイムマシンとやらに」
「うん」
「何か操作したのかい?」
「いや、特にはしなかったと思うんだけど」
「勇気が無かった?」
「覚悟なかった、かな。責任を取るだけの覚悟を持ってなかったんだと思う。興味と好奇心と冒険心に中二病持ち合わせての行動だったけど、何か動かすという度胸は無かったと思う」
「そうだね。君はそういう賢い子だ」
「でも、やっぱり」
「気になるかい?」
うん。そりゃ、そうだろう。こうも現実離れしたことが続くと本当に夢を見ているんじゃないかと思ってしまう。現実ではない。僕の夢想。空想上の世界の話。エデンと会話しているその延長線上。不可思議と空想を想うあまりに産んだ、ただの作り話。その日はそう思って、電気を消した。
瀬都奈が悪者なんて、テロリストなんて嫌だった。なぜそう思うのかはまだ分からないし、考えてなかっけど無性にそう思ったんだ。夢ならいいのに。夢じゃなければいいのに。
だけど、現実は厳しかった。本当に、それに限る。