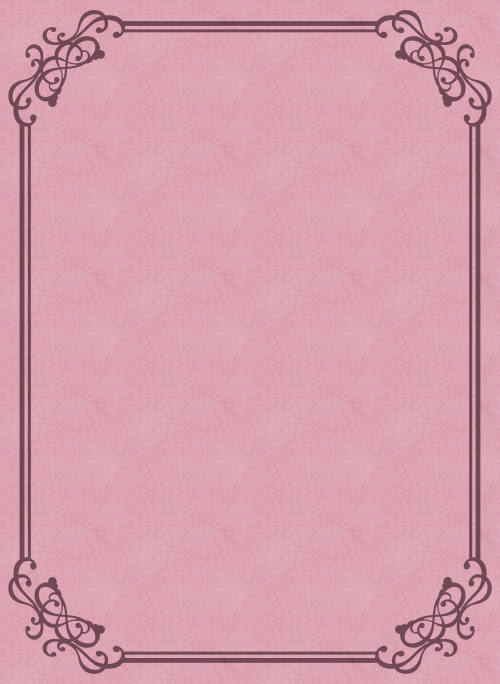「ありがとう。いや、何って泳いでいたのさ……あっ」
油断した。大人だ。そこに少女ひとりだと、なぜそう思い込んだんだ。施錠され、普段であれば立入禁止の管理された施設に、自分以外に居たのが同級生ぐらいだったから安心したのか。そこにはもうひとり居た。
大人だ。
ジャケットを肩にやって上半身がどこか光り気味なのはワイシャツになっているからか。そのおかげか否か、スーツ姿の大人の男だと分かった瞬間青ざめた。近くの荷物の方へ駆け寄り、それを手にして逃げようとした。とにかく急がないと、矢も盾もたまらずプールサイドへあがり、焦眉の急だ、と焦り急いだ。
…………が、その声に足を止めてしまった。
「泳いでいたのか……そうか、今日は夏休み最後の日だもんな」
僕は振り返り、相手を見据え、睨みつける。
「そんな、警戒すんなよ。大丈夫、チクったりしないから。安心しな、坊主」
その代わりーー、と男は続ける。
「今日ここで僕らが出会ったことは秘密だ。もちろんこの娘の事も。国家機密レベルで、秘密だ」
そういうの、嫌いじゃないだろう?
男はそれだけ言うと彼女を連れて出て行った。男に逆らえない状況である以上、それ以上何かを聞くことも抵抗することも、泳ぐこともできなかった。ただ二人が出ていくのを見送るだけだった。『気が済むまで泳ぐと良い』とは言われたが、それ以上泳ぐ気にもなれなかった。心のどこかではバレたのでは無いかと、気が気じゃなかったのだ。二人は『泳ぎたかったか?』『知り合いか?』『話していないよな』などと会話をしていたような気がしたが、正確には覚えていない。姿が見え無くなるや否や、その無き二つの影とまた出くわすのではないかと警戒を最大にしながら、早急かつ慎重に脱出して帰宅するのが最優先事項だったからだ。
* * *
翌日。登校日。
転校生が来た。
名前は明星瀬都奈。無論、昨夜の彼女だ。夏休みの宿題をすべて忘れたと白状し、怒鳴られる先生をたらい回しにされた挙げ句、小言を言われ続けながら担任と戻った教室の入り口に彼女は居た。そういえば担任が今日は忙しいとかなんとか言っていた気もしたが、そうか、このことか。
もちろん驚いた。
だけど、ワクワクした高揚や、ときめきは無かった。どこか無関係だと思っていたんだ。学祭とか体育祭とか。イベントや行事とかのいわゆる青春だぁ! って言う出来事は自分とは別の世界にあるものだと思ってきた。これまでそのような出来事に遭遇しなかったからと言うのもあるけど、世の中には青春が作品化されすぎて、それがどこか現実っぽくないと思っていたのが大きいと思う。だから、驚いたけど、この時はまだ自分事だとは思わなかったのだ。
その日、クラスの中で彼女と話すことはなかった。あのプールでの出来事が噂されたりクラスの話題に登ることも無かった。ゆーふぉーの話なんて、SNSにも流れない。身近な人はみんな、転校生の話で手一杯だった。だからこそ、午前授業が終わり、図書館準備室に籠もっていた所に、彼女が来た時は本当に驚いた。
時間は十四時前ぐらいだったと思う。
「なにしてるの?」
「な、何って。整理だよ。先生にお願いされてるんだ。図書室の本の整理は図書委員がやる事になっているんだけど、みんな仕事しないから。だから、鍵を貰って整理整頓してる」
「ふーん、ひとりで」
「うん」
「本、好きなんだ」
「うん」
「部活とかはやってないの?」
うん。
最後は声になっているか怪しかったし、今この活動を文芸同好会と名付けている事など、それこそ言えることではなかった。
友達どころか、女子と話すのは久しぶりだった。
「あ、これ知ってる! イギリスの名探偵だ」
「そう、だね。僕も好きだ」
彼女はなんとなく辺りにある本を手にとってオモテウラを確認するように眺めていた。その手は綺麗というより、暖かみと親しみを感じる幼げさえ感じる美しさという表現の方が相応しかろう。その黒く白い肌と対象的な、しかしそれでいてショートな耳に掛かっていた髪をそっとかきあげるその仕草は、どこかドキリとさせた。制服のワイシャツからチラリと見える首周りというのは、どうも僕を落ち着かなさせる。儚さと刹那ーーこの二語は最近小説で読んで得た言葉で、特にお気に入りであるーーがその面影から感じられる文字通りの美少女は、不純と不条理を噛み潰して純粋を貫き通す瞳をしていた。どこか先を憂いているような、そんな眼差し。
「ーーねえ、昨日会ったよね」
昨日。昨夜。それはもちろん、あのプールで会ったということだよな。
「ゆーふぉー、見た?」
え? たぶん声にできなかった疑問符は、それでも表情だけで彼女に僕の言葉は伝わったのだろう。続ける。
「ほら、プールの屋根の上。上に何か浮いていたでしょう」
「いや、でも、あれ」
「そう。普通は見えないの。カメラにも映らない。でも、あなたは見た」
「うん」
「名前は?」
「ええと、」
「同じクラスだっけ? お名前は?」
「タケル。健康の健でタケル。鎌倉健」
「健ね。自己紹介聞いてたかな? 私は明星。明星瀬都奈。ええと、漢字はーー」
「大丈夫。聞いていた」僕はそう答える。「それより、その昨日って」
「うん」
「あれ、何?」
「うーんと、」彼女は指を口に当てながら、こちらを見てそう言った。人差し指が妙に魅力的に感じてしまった僕は、ほんとどうしてしまったのだろう。彼女は続ける。「説明はできない、かな。禁則事項? ってやつ? 話せるのは、私が侵略者だってこと。未来から来たのよ、わたし」
彼女はとても美しく、可愛らしくそう言った。
油断した。大人だ。そこに少女ひとりだと、なぜそう思い込んだんだ。施錠され、普段であれば立入禁止の管理された施設に、自分以外に居たのが同級生ぐらいだったから安心したのか。そこにはもうひとり居た。
大人だ。
ジャケットを肩にやって上半身がどこか光り気味なのはワイシャツになっているからか。そのおかげか否か、スーツ姿の大人の男だと分かった瞬間青ざめた。近くの荷物の方へ駆け寄り、それを手にして逃げようとした。とにかく急がないと、矢も盾もたまらずプールサイドへあがり、焦眉の急だ、と焦り急いだ。
…………が、その声に足を止めてしまった。
「泳いでいたのか……そうか、今日は夏休み最後の日だもんな」
僕は振り返り、相手を見据え、睨みつける。
「そんな、警戒すんなよ。大丈夫、チクったりしないから。安心しな、坊主」
その代わりーー、と男は続ける。
「今日ここで僕らが出会ったことは秘密だ。もちろんこの娘の事も。国家機密レベルで、秘密だ」
そういうの、嫌いじゃないだろう?
男はそれだけ言うと彼女を連れて出て行った。男に逆らえない状況である以上、それ以上何かを聞くことも抵抗することも、泳ぐこともできなかった。ただ二人が出ていくのを見送るだけだった。『気が済むまで泳ぐと良い』とは言われたが、それ以上泳ぐ気にもなれなかった。心のどこかではバレたのでは無いかと、気が気じゃなかったのだ。二人は『泳ぎたかったか?』『知り合いか?』『話していないよな』などと会話をしていたような気がしたが、正確には覚えていない。姿が見え無くなるや否や、その無き二つの影とまた出くわすのではないかと警戒を最大にしながら、早急かつ慎重に脱出して帰宅するのが最優先事項だったからだ。
* * *
翌日。登校日。
転校生が来た。
名前は明星瀬都奈。無論、昨夜の彼女だ。夏休みの宿題をすべて忘れたと白状し、怒鳴られる先生をたらい回しにされた挙げ句、小言を言われ続けながら担任と戻った教室の入り口に彼女は居た。そういえば担任が今日は忙しいとかなんとか言っていた気もしたが、そうか、このことか。
もちろん驚いた。
だけど、ワクワクした高揚や、ときめきは無かった。どこか無関係だと思っていたんだ。学祭とか体育祭とか。イベントや行事とかのいわゆる青春だぁ! って言う出来事は自分とは別の世界にあるものだと思ってきた。これまでそのような出来事に遭遇しなかったからと言うのもあるけど、世の中には青春が作品化されすぎて、それがどこか現実っぽくないと思っていたのが大きいと思う。だから、驚いたけど、この時はまだ自分事だとは思わなかったのだ。
その日、クラスの中で彼女と話すことはなかった。あのプールでの出来事が噂されたりクラスの話題に登ることも無かった。ゆーふぉーの話なんて、SNSにも流れない。身近な人はみんな、転校生の話で手一杯だった。だからこそ、午前授業が終わり、図書館準備室に籠もっていた所に、彼女が来た時は本当に驚いた。
時間は十四時前ぐらいだったと思う。
「なにしてるの?」
「な、何って。整理だよ。先生にお願いされてるんだ。図書室の本の整理は図書委員がやる事になっているんだけど、みんな仕事しないから。だから、鍵を貰って整理整頓してる」
「ふーん、ひとりで」
「うん」
「本、好きなんだ」
「うん」
「部活とかはやってないの?」
うん。
最後は声になっているか怪しかったし、今この活動を文芸同好会と名付けている事など、それこそ言えることではなかった。
友達どころか、女子と話すのは久しぶりだった。
「あ、これ知ってる! イギリスの名探偵だ」
「そう、だね。僕も好きだ」
彼女はなんとなく辺りにある本を手にとってオモテウラを確認するように眺めていた。その手は綺麗というより、暖かみと親しみを感じる幼げさえ感じる美しさという表現の方が相応しかろう。その黒く白い肌と対象的な、しかしそれでいてショートな耳に掛かっていた髪をそっとかきあげるその仕草は、どこかドキリとさせた。制服のワイシャツからチラリと見える首周りというのは、どうも僕を落ち着かなさせる。儚さと刹那ーーこの二語は最近小説で読んで得た言葉で、特にお気に入りであるーーがその面影から感じられる文字通りの美少女は、不純と不条理を噛み潰して純粋を貫き通す瞳をしていた。どこか先を憂いているような、そんな眼差し。
「ーーねえ、昨日会ったよね」
昨日。昨夜。それはもちろん、あのプールで会ったということだよな。
「ゆーふぉー、見た?」
え? たぶん声にできなかった疑問符は、それでも表情だけで彼女に僕の言葉は伝わったのだろう。続ける。
「ほら、プールの屋根の上。上に何か浮いていたでしょう」
「いや、でも、あれ」
「そう。普通は見えないの。カメラにも映らない。でも、あなたは見た」
「うん」
「名前は?」
「ええと、」
「同じクラスだっけ? お名前は?」
「タケル。健康の健でタケル。鎌倉健」
「健ね。自己紹介聞いてたかな? 私は明星。明星瀬都奈。ええと、漢字はーー」
「大丈夫。聞いていた」僕はそう答える。「それより、その昨日って」
「うん」
「あれ、何?」
「うーんと、」彼女は指を口に当てながら、こちらを見てそう言った。人差し指が妙に魅力的に感じてしまった僕は、ほんとどうしてしまったのだろう。彼女は続ける。「説明はできない、かな。禁則事項? ってやつ? 話せるのは、私が侵略者だってこと。未来から来たのよ、わたし」
彼女はとても美しく、可愛らしくそう言った。