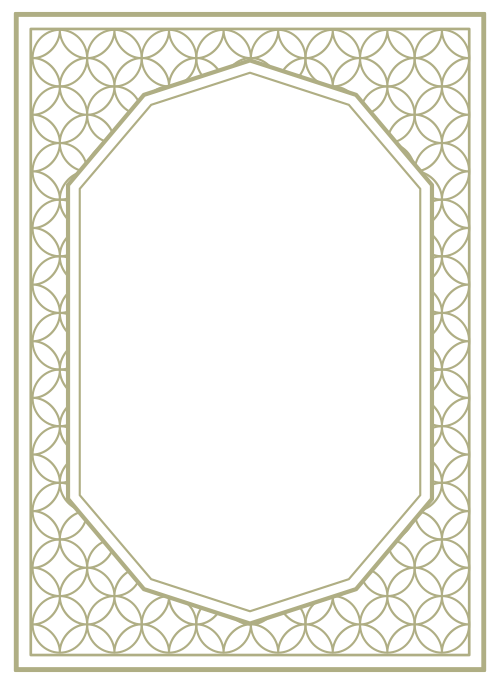授業が終わった教室でノートと問題集を広げていたら、本当に尾上がやって来た。
「おお、エライエライ。ちゃんと居たな」
からかうように言われて、一瞬席を立とうかと思った。一応牽制で聞いてみる。
「……先輩……。本当に受験勉強しなくていいんですか?」
「なに? 心配してくれてんの?」
にっこりと微笑んで言われると、やっぱりからかわれているような気がしてならない。いいざまに、ついっと顔を覗き込まれてぎょっとする。反射的に体が仰け反ったのを、やっぱり笑われた。
「すごい。ユデダコだな」
頬が熱いから、きっと真っ赤になっているんだろう。そんなことまでからかうなんて、本当に意地悪だとしか思えない。
いや、これは本当にいじめだ。だって、あんなことをしてきた人と二人だけで教室に、なんて状況、とんでもなく怖いことじゃないか。
「…………」
……怖い、っていうか、恥ずかしいっていうか、……あのことを思い出しすぎて、心臓が破裂しそうなんだけど。
ちら、と前の席の椅子に後ろ向きに座った尾上のことを盗み見る。小春の机から取り上げた問題集の設問を目で追っている、その口許に、どうしても視線がいってしまう。
形の良い、少しふっくらした唇。あれが、自分に触れたのだ。
「………っ」
やっぱり思い出してしまって、頬が熱くなる。
どうして、この恥ずかしさを、自分はこんなに我慢しなければならないのか。
ぎゅっと目を瞑って、全身に鼓動が打つような感覚を耐える。指先さえも震えないように、慎重に呼吸をした。ゆっくり、ゆっくり、と言い聞かせて、どうにか頭の中をわあんと駆け巡っていた血流の波が収まる。
「……ち? 竹内?」
力を篭めて目を瞑っていたら、聴覚が少し疎かになっていたらしい。前の席から問い掛ける声に、はっとする。見ると尾上は心配そうな顔をしてこちらを窺っていた。
「……具合悪いか?」
深い瞳の色でそんな風に言われたら、誰だってどきっとするに決まってる。ましてや、こんなに綺麗な顔立ちをしているのだから。
不意を付かれて、思わず動悸が早くなったことを自覚した。折角収めた鼓動を、今度は収めきれない。思わずあからさまに、ふい、と顔を逸らしてしまった。頬と耳先が熱い。きっと紅くなっているのだろう。
じっと、あさっての方向に顔を向けていた小春に、尾上が、ふ、と息を漏らした。それがまるで、小さな子供を宥めるときの笑みによるものに聞こえて、なんだか悔しかった。そんな風に、思われるのが。
顔を逸らしていた小春の机の上に、問題集が戻ってきた。ほら、なんて普通に声を掛けてくるのも、あまりにも普通でますます悔しい。まるで弄ばれているような気分だ。
「気分、悪いわけじゃないんだったら、ほら、問題集見て。問一からいくか?」
まるで親切な先輩を装っているのも、腹が立つ。だって、本当はあんなこと、する人なのに。
話しかけてくる尾上の姿勢も無視できなかったけど、きっと視線はぎりぎりと睨むようなものになっていたんだと思う。尾上が問題集を指差して俯いていたのから顔を上げて、そうして一瞬視線が合った後、困ったような、そしてちょっとすまなさそうな表情をして、ぽり、と頭を掻いた。
「……そんなに、敵意剥き出しにしないでくれないかな。……この前のことは、謝るから」
「……謝ったら、なんでもなしになると思ってるんですか」
低く、威嚇するような声が出てしまった。実際、まだ尾上を前に、体の力が抜けない。
「……そうだな。全面的に俺が悪い。……でも、竹内もちょっとは悪い」
「私が!? なんで!」
いきなり、キ……キスなんてしてくる人に、お前も悪い、なんていわれる筋合いはない。小春が食って掛かると、尾上はなんというか、情けないように口許を歪めるくせに、眼は射抜くように小春のことを見てきた。
「だって、そりゃ、好きな奴に興味沸くとか言われたら、期待しない方が無理だって。それに、あんな眼で自分のこと見られたら、そのまま掻っ攫いたいとか思うだろ、普通」
興味が沸くと言ったのは確かに小春だから、そこは黙って聞いた。でも、あんな眼、なんて言われても、何のことだか分からない。おまけにもって、言葉の最後なんて、全くもって勝手な意見だ。
「そんなの、先輩の勝手な考えです。そんなの、見ず知らずの後輩に押し付けるものじゃ、ないです!」
「でもさ、お前人気あるんだもん」
は? と思う。とげのある視線を向けたら、尾上は前の席でちょっと拗ねたような顔をしていた。
「知らないだろ。竹内、自分が人気あるの。この前、お前が南来た時に茶化してた奴ら、全部お前狙ってんの。そんなの知ってたら、焦るじゃん? やっぱり」
「そんなの、知りません! っていうか……っ」
聞かされた内容が頭の中を駆け巡る。確かに山澤以外にも、自分が気を許している以上に親しく声を掛けてくる男子も居る。だからと言って、そんなクラスメイトのことまで侮辱されたくない。それに。
「……私……っ、……初めてだったのに……っ!」
初めてだった。あんな風に、容易く触れられてしまうなんて、思ってもみなかった。
なんだか、一気に感情が高ぶってしまって思わず涙腺が緩んだ。悔しいのと、恥ずかしいのと。兎に角頭の中がごっちゃになって、整理のつかない思考が涙になって溢れ出てしまったようだった。
情けないことに、ぼろぼろと涙が零れる。この人の前で泣くなんて、したくなかったのに。この、強引な、自分を襲うような人の前で泣くなんて、これ以上弱みを見せてどうするというのだろうか。
がたんと椅子を引く音がした。咄嗟に身構えようとした小春は、その前にあたたかい温度に包まれていた。
「………っ」
尾上が、小春の頭を抱きかかえて、自分の制服に小春の顔を押し付けていた。頭を抱えてきた腕が聴覚を鈍く奪っていて、遠い音は聞こえない。押し付けられた制服のシャツとニットを通して、穏やかな温度が伝わってくる。
……突然のことに驚いて、ぼろぼろ零れていた涙が引っ込んでしまった。夕刻の静かな教室の中で、グラウンドからの音も聞こえず、ただ、ほんのりと温度だけを感じる。
「………俺にしとけ」
小さな呟きは、頭の上から聞こえる。それも、随分と横柄な言葉なのに、なんでこんなに不安そうな声音なのか。
「……これから先、きっと竹内の嫌がることはしない。ちゃんと、大事にする。……だから、俺にしとけ?」
低く囁かれる言葉が、どうしてだか、すごく優しい。あんな、強引にキスをしてくるような人なのに。混乱する小春の前に現れては、悪戯に関わってくるような人なのに。
……悔しい。
何かに引っ張られそうになる。そのことに気付きたくなかったから、小春は勢い良く席を立って尾上の腕を振り切ると、机の横にかけてあった鞄を手に取った。
「なら、もう二度と私の前に姿見せないで下さい!」
眼を見ては、言えなかった。ぎゅっと目を閉じて叫ぶように言うと、小春はそのまま教室を飛び出した。動悸が早い。きっと走っている所為に違いなかった。
「おお、エライエライ。ちゃんと居たな」
からかうように言われて、一瞬席を立とうかと思った。一応牽制で聞いてみる。
「……先輩……。本当に受験勉強しなくていいんですか?」
「なに? 心配してくれてんの?」
にっこりと微笑んで言われると、やっぱりからかわれているような気がしてならない。いいざまに、ついっと顔を覗き込まれてぎょっとする。反射的に体が仰け反ったのを、やっぱり笑われた。
「すごい。ユデダコだな」
頬が熱いから、きっと真っ赤になっているんだろう。そんなことまでからかうなんて、本当に意地悪だとしか思えない。
いや、これは本当にいじめだ。だって、あんなことをしてきた人と二人だけで教室に、なんて状況、とんでもなく怖いことじゃないか。
「…………」
……怖い、っていうか、恥ずかしいっていうか、……あのことを思い出しすぎて、心臓が破裂しそうなんだけど。
ちら、と前の席の椅子に後ろ向きに座った尾上のことを盗み見る。小春の机から取り上げた問題集の設問を目で追っている、その口許に、どうしても視線がいってしまう。
形の良い、少しふっくらした唇。あれが、自分に触れたのだ。
「………っ」
やっぱり思い出してしまって、頬が熱くなる。
どうして、この恥ずかしさを、自分はこんなに我慢しなければならないのか。
ぎゅっと目を瞑って、全身に鼓動が打つような感覚を耐える。指先さえも震えないように、慎重に呼吸をした。ゆっくり、ゆっくり、と言い聞かせて、どうにか頭の中をわあんと駆け巡っていた血流の波が収まる。
「……ち? 竹内?」
力を篭めて目を瞑っていたら、聴覚が少し疎かになっていたらしい。前の席から問い掛ける声に、はっとする。見ると尾上は心配そうな顔をしてこちらを窺っていた。
「……具合悪いか?」
深い瞳の色でそんな風に言われたら、誰だってどきっとするに決まってる。ましてや、こんなに綺麗な顔立ちをしているのだから。
不意を付かれて、思わず動悸が早くなったことを自覚した。折角収めた鼓動を、今度は収めきれない。思わずあからさまに、ふい、と顔を逸らしてしまった。頬と耳先が熱い。きっと紅くなっているのだろう。
じっと、あさっての方向に顔を向けていた小春に、尾上が、ふ、と息を漏らした。それがまるで、小さな子供を宥めるときの笑みによるものに聞こえて、なんだか悔しかった。そんな風に、思われるのが。
顔を逸らしていた小春の机の上に、問題集が戻ってきた。ほら、なんて普通に声を掛けてくるのも、あまりにも普通でますます悔しい。まるで弄ばれているような気分だ。
「気分、悪いわけじゃないんだったら、ほら、問題集見て。問一からいくか?」
まるで親切な先輩を装っているのも、腹が立つ。だって、本当はあんなこと、する人なのに。
話しかけてくる尾上の姿勢も無視できなかったけど、きっと視線はぎりぎりと睨むようなものになっていたんだと思う。尾上が問題集を指差して俯いていたのから顔を上げて、そうして一瞬視線が合った後、困ったような、そしてちょっとすまなさそうな表情をして、ぽり、と頭を掻いた。
「……そんなに、敵意剥き出しにしないでくれないかな。……この前のことは、謝るから」
「……謝ったら、なんでもなしになると思ってるんですか」
低く、威嚇するような声が出てしまった。実際、まだ尾上を前に、体の力が抜けない。
「……そうだな。全面的に俺が悪い。……でも、竹内もちょっとは悪い」
「私が!? なんで!」
いきなり、キ……キスなんてしてくる人に、お前も悪い、なんていわれる筋合いはない。小春が食って掛かると、尾上はなんというか、情けないように口許を歪めるくせに、眼は射抜くように小春のことを見てきた。
「だって、そりゃ、好きな奴に興味沸くとか言われたら、期待しない方が無理だって。それに、あんな眼で自分のこと見られたら、そのまま掻っ攫いたいとか思うだろ、普通」
興味が沸くと言ったのは確かに小春だから、そこは黙って聞いた。でも、あんな眼、なんて言われても、何のことだか分からない。おまけにもって、言葉の最後なんて、全くもって勝手な意見だ。
「そんなの、先輩の勝手な考えです。そんなの、見ず知らずの後輩に押し付けるものじゃ、ないです!」
「でもさ、お前人気あるんだもん」
は? と思う。とげのある視線を向けたら、尾上は前の席でちょっと拗ねたような顔をしていた。
「知らないだろ。竹内、自分が人気あるの。この前、お前が南来た時に茶化してた奴ら、全部お前狙ってんの。そんなの知ってたら、焦るじゃん? やっぱり」
「そんなの、知りません! っていうか……っ」
聞かされた内容が頭の中を駆け巡る。確かに山澤以外にも、自分が気を許している以上に親しく声を掛けてくる男子も居る。だからと言って、そんなクラスメイトのことまで侮辱されたくない。それに。
「……私……っ、……初めてだったのに……っ!」
初めてだった。あんな風に、容易く触れられてしまうなんて、思ってもみなかった。
なんだか、一気に感情が高ぶってしまって思わず涙腺が緩んだ。悔しいのと、恥ずかしいのと。兎に角頭の中がごっちゃになって、整理のつかない思考が涙になって溢れ出てしまったようだった。
情けないことに、ぼろぼろと涙が零れる。この人の前で泣くなんて、したくなかったのに。この、強引な、自分を襲うような人の前で泣くなんて、これ以上弱みを見せてどうするというのだろうか。
がたんと椅子を引く音がした。咄嗟に身構えようとした小春は、その前にあたたかい温度に包まれていた。
「………っ」
尾上が、小春の頭を抱きかかえて、自分の制服に小春の顔を押し付けていた。頭を抱えてきた腕が聴覚を鈍く奪っていて、遠い音は聞こえない。押し付けられた制服のシャツとニットを通して、穏やかな温度が伝わってくる。
……突然のことに驚いて、ぼろぼろ零れていた涙が引っ込んでしまった。夕刻の静かな教室の中で、グラウンドからの音も聞こえず、ただ、ほんのりと温度だけを感じる。
「………俺にしとけ」
小さな呟きは、頭の上から聞こえる。それも、随分と横柄な言葉なのに、なんでこんなに不安そうな声音なのか。
「……これから先、きっと竹内の嫌がることはしない。ちゃんと、大事にする。……だから、俺にしとけ?」
低く囁かれる言葉が、どうしてだか、すごく優しい。あんな、強引にキスをしてくるような人なのに。混乱する小春の前に現れては、悪戯に関わってくるような人なのに。
……悔しい。
何かに引っ張られそうになる。そのことに気付きたくなかったから、小春は勢い良く席を立って尾上の腕を振り切ると、机の横にかけてあった鞄を手に取った。
「なら、もう二度と私の前に姿見せないで下さい!」
眼を見ては、言えなかった。ぎゅっと目を閉じて叫ぶように言うと、小春はそのまま教室を飛び出した。動悸が早い。きっと走っている所為に違いなかった。