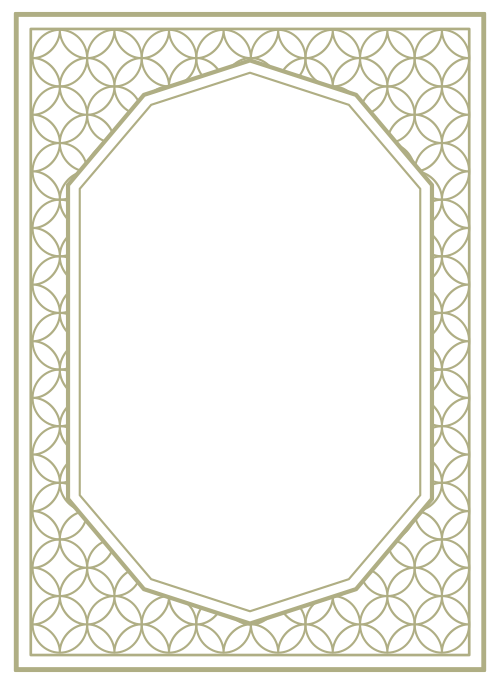教室を出て図書室へ向かう廊下には、霞むような金色の光が射していた。小さな塵が、まるで生き物みたいにふわふわと浮いていて、空気の中を漂っている。それだけで空気が濃厚になるような気がして、小春は深く息を吸い込んだ。
図書室の扉の前には、もう笠寺が来ていた。鞄を脇に抱えて、廊下の壁に凭れて立っている。
「笠寺先輩」
「あ、竹内。ごめんな、呼び出して」
いいえ、と返事をする。そのまま図書室に入るのかと思ったら、笠寺は小春のほうへと歩いてきて、そうして、小春が今来た方を指差した。
「図書室では、話出来ないからな」
私語厳禁の図書室は、今も生徒が沢山居て、多分、受験生の先輩たちもここで勉強しているのだろう。ちょっと独特の、張り詰めた空気が扉の外からも窺えた。
元来た方を歩いて、そうして途中で二階に降りる階段へと曲がった。北校舎の三階の端にある図書室から一番近いその階段は、冬の午後の日差しが零れるくらいに溢れていて、どこか穏やかな空気になっていた。
踊り場の硝子から差し込む金色の日差しの中で、笠寺が階段の途中に腰を下ろす。放課後になって少し経ってしまったので、もう廊下を行き来する人影もあまりない。階段は明るい静寂に包まれていた。
……小春も、笠寺の隣に腰を下ろした。鞄を膝に抱える。
「………あのさ……」
とても言いにくそうに、笠寺が口を開いた。視線は足元を見たまま、頭の中で言葉を探しているようだった。静かな空気の中で、竹内は笠寺の続きの言葉を待つ。
笠寺は、足元を見ていた視線を、ややあってから天井に向けたり、首を傾けたりして思案している様子だった。……なにか、重要なことだろうか。
「ああっ! 俺、本当に気が利いたこと言えないから、単刀直入に聞くけど」
やっと言葉を継いだ笠寺は、頭を掻き毟ってそう言うと、小春の方を向き直ってきた。がしっと肩に手を置かれる。えっ、と一瞬で心臓が跳ねた。
「竹内はさ、尾上のこと、嫌い?」
ぎょっとして、別の意味で心臓が跳ねた。……何故、笠寺の口からそんな言葉が出てくるのだろうか。
「仲良くしてただろ? お昼も一緒に食べたし、駅まで一緒に帰ったりもした。勉強も教えてもらったんだろ? そういうこと、嫌いな相手と竹内はするのか?」
矢継ぎ早に問われて、小春は混乱した。何を、どうやって答えたらいいのか、分からない。どうして、笠寺がそんなことを聞いてくるのかも。
「尾上のこと、……よく知らないからってことだけで、否定してない? そういうの、抜きにして考えてみてくれよ」
笠寺が続けた言葉から、漸く分かったことがひとつあった。……どういう理由でかは知らないけれど、尾上は、小春とのことを彼に話したのだ。
かあっと、頬に熱が集まる。……一体、尾上はどんなことまで笠寺に話したのだろう。
「なあ、竹内」
混乱する。何から考えたらいいんだろう。だって、いきなりキスをしてくるような人で、からかうように小春に寄ってきて、でも本当にからかったことなんてなくって、親切で、すごく小春に良くしてくれている、……でも、好きだった人じゃない。
まともに笠寺の目が見れない。逃げるように視線を外すと、笠寺が肩を掴んだ手に力を篭めた。
「なあ、竹内。……本当に、尾上のこと知らないからってことだけで、あいつを嫌いって言うんだったら、もうちょっと考えてくれないかな。……尾上はいい加減な奴じゃないし、だから、余計に本気だと思うんだよ」
本気? 小春に対して、本気で好きだっていうことなんだろうか。……あの尾上が? あんなに整った顔の、如何にもモテます、っていう顔をした、あの尾上が?
肩をぎゅっと掴まれて、少し痛い。ようように出た声は、なんとも情けない声だった。
「………よく、……わかりません……」
「……竹内?」
問うような笠寺の視線に答える言葉がない。だって、本当に分からないのだ。自分の気持ちが一体どこにあるのかなんて。
尾上が、強引で、ちょっと意地悪なのかと思ったけど、でも本当はやさしくって親切なんだってことを、もう小春は知っている。あんなにカッコいい人が、小春に対して本気だなんて言われて、どう考えろというのだろう。
思考も感情も混乱してしまう。何が先で、どこから考えていいのか、全然分からない。ただ、笠寺の言葉が津波のように押し寄せてきて、それで小春を飲み込んでしまっていた。
ぎゅっと、喉を締めて目を閉じる。なにか、零れだしてはいけないものが、出てきてしまいそうだった。
廊下の奥の方からばたばたと足音がする。今、ここで気を抜いたら、きっと涙が零れてしまって、笠寺が小春を苛めているみたいに見られてしまうだろう。そんなことは、避けなければならなかった。
足音が大きくなってくる。きゅっ、と上履きが廊下と擦れた音がして、そして足音がそこで止まった。
「笠寺っ!」
大きな声は、目を閉じていた小春にも分かる人のものだった。
ばたばたと足音が階段を下りてくる。そうして、ぎゅっと掴まれていた笠寺の手が引き剥がされるように外れた。
「お、尾上……っ」
「なにしてるんだよ、お前!」
竹内の肩を掴んでいた笠寺の手を取り上げると、尾上は背丈の差をものともせず、笠寺を小春から引き剥がした。
「なにを、してたんだ……。事と次第によっては、容赦しないぞ」
「……だ、だって、尾上……」
階段の二段上からねめつけるようにして、笠寺を睨む。笠寺が大きな体で小さな子供のように、だって、と繰り返した。
「よけいなことするなって、言ったよな?」
「だって、尾上! お前、本当にそれでいいのかよ!?」
笠寺の叫びに、廊下を歩いていた人が立ち止まった。これ以上注目を集めるのは良くない。尾上は笠寺を引っ張りあげて、兎に角この場所を去ろうとした。
と。
きゅっと、ブレザーの裾を引かれた。小さなその力に、尾上は体が強ばるのを自覚した。
「……あ、……あの……」
竹内だった。
竹内が尾上のブレザーの裾を引いて、笠寺を引っ張っていこうとした尾上を押し留めている。笠寺と何を話していたのかは分からないけれど、目に一杯涙を溜めて、必死でこちらを見てきていた。
「……笠寺が、なんか変なこと言ったんだろ。……悪かったな。……なんか、ここに居ると、注目集めるから、竹内も早く帰った方がいいよ」
そう言って踵を返そうとする尾上を、竹内が尚も止めた。
「か、笠寺先輩は、悪くない、……です……。……だから、怒らないでください……」
「悪くないって……。じゃあ、お前、なに泣きそうな顔してるの」
言うと、竹内はきゅっと唇を引き結んで、一瞬何かを堪えたようだった。そうして、膝に抱えていた鞄をもう片方の手で握ると、彼女も立ち上がってきた。
「……たけうち?」
ブレザーの裾を引いたまま。立ち上がって俯いていた竹内は、もう一度尾上のことを見据えて、こう言った。
「……先輩。……私に、時間をください。……色々、整理する時間を、私にください……」
言った後に、竹内が堪えていた涙をひとつだけ零した。こんな苦悩の表情をさせた自分を、尾上は尚も許せない気持ちになった。