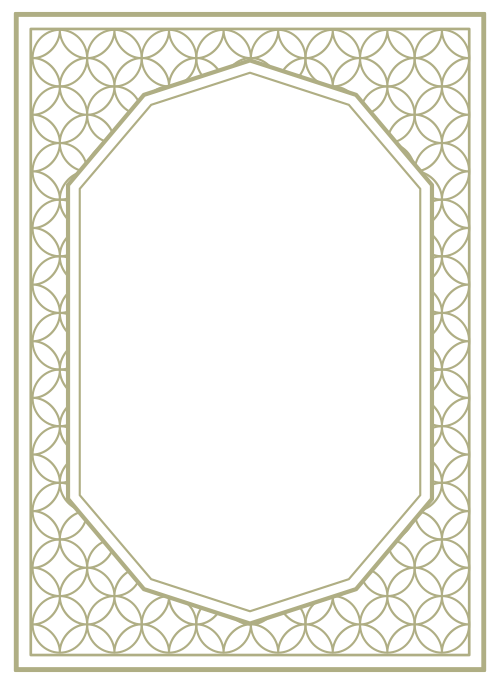尾上は、竹内の去った教室で、肩を落として椅子に座りなおした。窓も閉ざされた教室には、物音ひとつ落ちてない。深々とついたため息が、やけに大きく耳に聞こえた。項垂れて額に落ちかかる髪の毛を、緩慢な動きで払いのける。すると、躊躇いがちに教室の扉の陰から声を掛けられた。
「……尾上……」
扉の隙間から顔を覗かせたのは、長身の背中を丸めている笠寺だった。とても遠慮がちにこちらを見ている。……きっと、今走って出て行った竹内のことは、見ていたんだろう。
「……俺、四人で一緒に帰ろうと思って……。……どうしたんだよ。なんか、あった?」
主人の様子を窺う忠犬のようだ。扉を開けたはいいけど、中に入って来れないのなんて、まるきりそれだ。
「どうもこうも」
尾上は自嘲気味に唇を歪めた。どうせこういう結果が待っているとは思っていたけれど、だったらやっぱり行動になんて移さなければよかった。あの時聞いた言葉を、そのまま鵜呑みにしてはいけなかったのだ。
「竹内、走って行っちまったし、なんか大きな声も聞こえたから……。……なにがあったんだよ」
心配そうに、漸く教室に一歩入ってきた笠寺を見ることもなく、尾上は竹内の机に残された問題集を見つめたままで、ぽつりと呟いた。
「……フラれた」
「へ?」
突然の言葉に、笠寺が意味を図りかねている。きょとんとしている親友に、コイツは悪い奴じゃないけど、こういう時に考えが及ばないんだよなあと思った。
「……だから、もう顔見せるな、って言われた。……まあ、しかたないな」
「どどどーしてっ! 仲直りしたんじゃなかったのかよっ!?」
全くもって、その鈍さに驚きだ。ますますは口許を歪めるしかない。
「お前さぁ。本当に俺が、竹内のことキーホルダー見かけただけで、それ欲しいって思ったんだって思てるんだろ」
「え? 違うの?」
本当に分かってない。その鈍さに天を仰ぎたくなるが、彼が居たから竹内とも会話を交わすことが出来るようになった。竹内の気持ちは分かっていたはずなのに、この数日間、竹内の傍に行けることが嬉しくて、ちょっとその気持ちを忘れていたのかもしれない。
「……俺が、興味ないものに執着すると思うか? ……竹内は、そういうのは嫌だってさ。まあ、当然だけど。……だから、もう竹内とは顔も合わせない。……ああでも、お前は別に関係ないから、竹内とでも岡本とでもつるんでたら良いんじゃない?」
淡々と言う尾上に、笠寺は唖然とする。ええと、だから、……どういうことだ?
「……え、……っと、尾上? つまり、尾上は、竹内のこと……」
ごくりと唾を飲み込んで、笠寺は尾上に聞いた。尾上は答えることはしなかったけど、その代わりに自虐的な笑みを浮かべた。
うわあ、そうなんだ。この、ルックスからはモテるくせに、一切女の子たちの誘いを受けたことのなかった尾上に、好きな相手が出来ていたんだ。
そんな想いを託して、あのキーホルダーが欲しいなんて言っていたなんて、知らなかった。知っていたら、彼の恋路に何か役に立つようなことが出来たのかと問われると、笠寺は即答できなかったけど、それでも、応援してやることは出来たかもしれないのに。折角、仲良くなったんだし。
「……笠寺。なんか変なこと考えてるだろ。余計なことするなよ?」
尾上が低い声で釘を刺す。笠寺は考えていたことを見抜かれて、うっと言葉に詰まっていた。
「……だって、尾上……」
「だってもなにもない。……竹内にはもう、嫌な思いさせちゃったから、これ以上はごめんだ」
尾上はそう言うと、もう後は何も言わなかった。
笠寺はすごく寂しい思いで、尾上のことを見つめて居た。