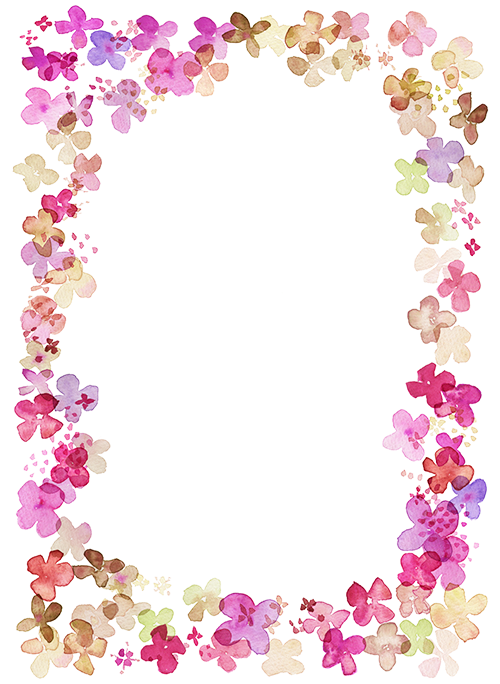しかし、追い打ちをかけてくるように、状況は悪くなるばかりだった。
ナチスは、さらに、あたしたちの生活を追い詰めていった。
食料は配給制になり、券がなければ、何も手に入らなくなった。
しかも、その配給自体も名ばかりのもので、
あたしたちは、どんどん飢えさせられていった。
子どもも、大人も、みんなが空腹の日々を過ごすことになった。
あたしも、いつもお腹を空かせるようになった。
そんな中、季節は冬に入り、
寒さまでもが、あたしたちを襲った。
飢えと寒さに、人々は苦しめられた。
けれど、それ以上に、
心の方が、ずっと辛かった。
あたしは、冷えた体と空腹を抱えながら、ずっと同じことを考えていた。
このまま、ずっとレメックとは会えないのだろうか…。
レメックは、毎日、どうやって過ごしているんだろう。
この苦しい日々を、どう思っているんだろう。
あたしと会えていないことを、少しでも、寂しいと思ってくれているんだろうか。
彼も、あたしと同じような気持ちでいるのだろうか……。
レメックのいない日々は、光のない、ぼんやりとした世界のようだった。
けれど、あたしの想いを分かってくれる人はいなかった。
両親は、あたしを追い詰めるだけだった。
「これでいいんだ」と父は言った。
「今までが間違っていたのよ」母も言った。
あたしの心は、とうとう限界に達した。
「…あたしが何を間違ってるっていうの!?
レメックは、たった一人の友達なんだよ!!
たった一人、あたしを見捨てないでいてくれたんだよ!!
だから、あたしだって、レメックたちを見捨てない!!!
ユダヤ人だからって、ポーランド人だからって、ドイツ人だからって、
そんなのは関係ない!!
ユダヤ人だから付き合っちゃいけないなんて…
お父さんとお母さんは、ナチスの奴らと同じだよ!!!」
確かに、あたしたちポーランド人は、ナチスにひどいことをされた。
けれど、ユダヤ人を差別し、苦しめたのは、
ナチスだけではなかった。
ユダヤ人たちの悲劇を大きくさせたのは、
あたしたち普通の市民でもあったのだ―――。
最後の日が訪れたのは、それから間もなくのことだった。