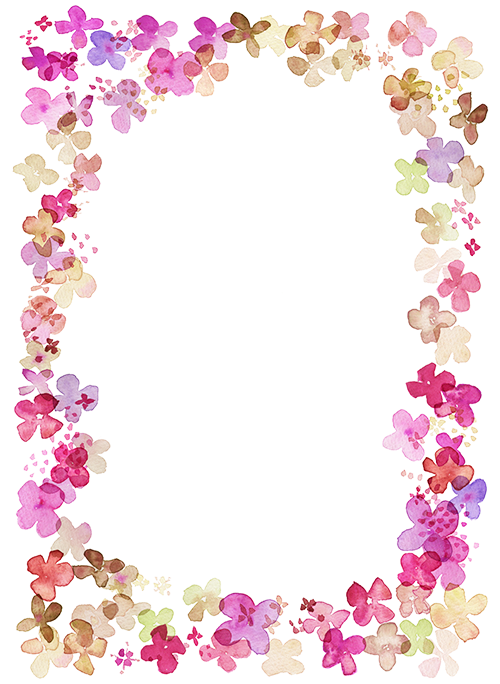レメックは、いつも独りぼっちのあたしを気にかけて、友達の輪の中に入れようとしてくれた。
実際に仲間に入ることは出来なくても、あたしは、レメックの思いが、とても嬉しかった。
優しさに、感謝していた。
あたしと友達でいてくれるのは、レメックだけだった。
あたしを問題児扱いしないのは、レメックとその家族だけだった。
あたしが唯一安心して過ごせる時間は、レメックと一緒にいる時だけだった……。
「レメック…?」
「ん?」
まだ髪や服を濡らしたままのレメックが、あたしを見た。
「…これからも、仲良くしてくれる?」
あたしが尋ねると、
レメックは「えっ?」と驚いたように口を開いた。
「どうしたのさ?急に改まっちゃって」
そう言って笑うレメックを睨みながら、あたしは「だって…」と言った。
「だって…ちょっと無理してるでしょ?
あたしと一緒にいること」
初めて、ずっと心のどこかで悩んでいたことを口に出すことが出来た。
いつも、気になっていた。
レメックは、無理をして、あたしと仲良くしてくれているんじゃないか。
あたしみたいな問題児とは、本当は付き合いたくないんじゃないかと。
クラスの人気者で、常にたくさんの友達に囲まれているレメックと、
いつも独りぼっちのあたしとでは、全く釣り合わない。
好きなのは、あたしだけなんだ……―――。
「…バカ」
「えっ?」
顔を上げると、
そこには、怒ったような表情を浮かべているレメックがいた。
その目が、あたしを見た。
「アネタのバカ!アホ!」
「ハアッ!?なんでそんなこと―…」
いきなり大声で言うレメックに、腹が立って言い返そうとしたけど、
途中で遮られた。
「僕は…みんなが間違ってると思う!
アネタは、問題児なんかじゃない。
みんなが言うような子じゃないよ…僕は、知ってる」
いつも穏やかなレメックがこんなに声を荒げるのは、珍しいことだった。
あたしは呆気にとられて、その言葉を聞いていた。
「楽しいよ…こうして、アネタと一緒にいる時間。
だから、そんなこと言うな。
僕は……アネタのこと、好きなんだ」
「えっ…?」
思わず、聞き返した。
今、何て―――?
目の前にいるレメックの顔は、これまで見たことのないほど、真っ赤に染まっていた。
「…お姫様」
レメックが、あたしに向かって言った。
「僕を、王子様にしてくれないかな?」
「…え?」
ビックリ仰天状態のあたしを前に、レメックはさらに続けた。
「お姫様……
僕の背がもっと伸びたら、王子様にしてくれる?」
あたしは、しばらく、
目の前で起きていることが現実なのか信じることが出来なかった。
けれど、レメックの真っ赤な顔を見ると、
それが現実なのだと知ることが出来た。
これまで、ずっと悩んできていたことが事実ではなかったということを知った。
好きなのは、あたしだけじゃなかったんだ……?
疑いたい思いだったけど、レメックの表情を見れば、嘘ではないと分かった。
「君のお父さんとお母さんが怒るかと思って、なかなか言えなかったんだ…。
でも、今、言えて良かったよ」
そう言って、レメックはニコッと笑った。
それは、あたしの大好きな笑顔だった――。
あの日は、あたしの人生の中で最も幸せな時間だった。
何をしても楽しい気分で、夢見心地だった。
そのせいで、いろいろと聞きたかったことを聞かないままになってしまった。
今思えば、もっと、たくさんのことを話して、
いろいろなことを聞いておくべきだった。
まさか、あの日が、レメックとの時間を過ごせる最後だったなんて、
十歳のあたしには知る由もなかった……――。