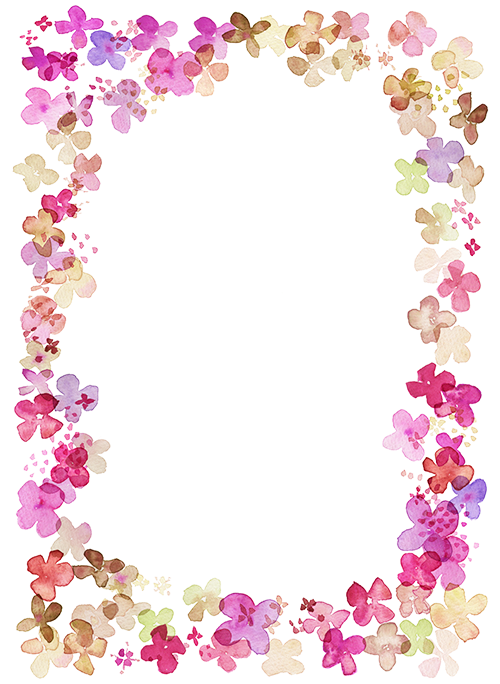「アネタ?大丈夫?」
レメックの声で、ぼんやりしていた頭の中が一気に冴えた。
彼の深い瞳と自分の目が合っただけで明るい気分になれるのに、
そんなこと言えるわけもなく、
その代わりに、ついまた言ってしまった。
「アンタのせいよ!」
いきなり理不尽なことを言われて、さすがのレメックも怒るだろう。
そう思って、見ると――
彼は、あたしの言うことなんか無視で、
目の前にあるものを指さして言った。
「アネタ、着いたよ。さあ、行こう!」
「ハア?アンタ、あたしの言ったこと聞いてた?」
「えっ、何が?もしかして、また怒ってる?」
呑気に笑う、レメック。
けれど、その笑顔を見ると、
まあいいか、と思えてしまった。
むしろ、聞かれていなくて良かったと思う、あたしだった。
「さあ、アネタ、行こう!」
レメックが、あたしの手を引いていく。
その先には、
あたしたちのお気に入りの場所―大きな野原があった。
夏の光に照らされた野原は、豊かな緑色で、
広がっている大空のように広々としていた。
あたしたちは、その緑の中へと飛び込んでいった。
その時、ちょうど風が吹き、
あたしのかぶっていた麦わら帽子が飛ばされてしまった。
「あっ!」
飛んでいく帽子を追いかけようとすると、目の前にレメックが飛び込んできた。
チラリとあたしの方を見ると、彼は言った。
「僕が取って来るよ!そこで待ってて!」
「えっ、でも、あっちには川が…!」
この野原の先には、大きな川があった。
落ちたら大変だ。
しかし、あたしの警告も聞かずに、
レメックは風と共に走っていってしまった。
あたしは、彼を追いかけた。
「レメック―!!」
次の瞬間、バッシャーンという水の弾く音が聞こえた。
レメックが飛び込んだに違いなかった。
あたしは、ゾッとして、必死に川の方へと駆け寄っていった。
けれど、そこにレメックの姿はなく―あたしの心臓は、嫌な音を立てた。
まさかと思い、彼を呼んだ。
「レメック!レメック―!」
返事は、なかった。
まさか、溺れたんじゃ…―そう思った時だった。
川の中から、少年が現れた。
あたしは驚いて、「レメック!!」と大声で叫んだ。
びしょ濡れになったレメックは、川の中から出てくると、
ニコッと笑って、ある物をあたしに差し出した。
それは、あたしの麦わら帽子だった。
「レメック…」
彼が無事で、本当に安心した。
と、同時に、怒りが込み上げてきた。
あたしは、レメックに差し出された麦わら帽子を乱暴につかんで野原の上に投げ捨てると、
大声で言った。
「何してるのっ!?頭おかしいんじゃない?
帽子を取りに行くために、川に飛び込むなんて!」
すると、レメックは、キョトンとした表情を浮かべて言った。
「当たり前だろ?この帽子、お祖母ちゃんに買ってもらった大切なものだろ。
なのに、こんな乱暴に投げ捨てたりして―」
レメックは、麦わら帽子を拾い上げると、あたしの頭の上にポンとのせた。
今度は、あたしの方がキョトンとする番だった。
「悪い子だなぁ」
濡れた髪を掻き上げながらそう言ったレメックを睨みながら、あたしは呟いた。
「悪いのは、どっちよ…」
川に飛び込む方が、よっぽど悪いに決まってる!
あたしは、たまらずレメックに向かって言い返した。
「アンタなんか、知らない!
あたしの心配も知らずに、あたしを悪い子だなんて!」
溺れたかもしれないと思って、本当に怖かったのに…。
「死んじゃったかと思った」
そう言った瞬間、涙が込み上げてきた。
レメックは、いつもあたしの思いを分かってくれない。
きっと、これからも分かってはくれない。
そう思うと、悲しかった。
大好きなのは、あたしだけなんだ…―――。
レメックは、どういう気持ちでか、じっとあたしを見た後、
こちらに背を向けて野原の上に座り込んだ。
あたしは、わめき立てることもなく、
彼とは離れた場所に腰を下ろした。
そして、心の中で、どうして、と尋ねた。
レメック、どうして分かってくれないの?
あたしは、ただ心配だっただけなのに。
ただ、好きなだけなのに。
もう、あたしのこと、嫌いなの?
ねえ、レメック…。
「アネタ」
後ろから、レメックの声があたしを呼んだ。
振り返った瞬間、あたしの頭の上に何かがのせられた。
そこで、麦わら帽子を外して見てみると――
帽子のリボンの部分に、たくさんの花や植物で作られた冠が付けられていた。
「えっ」
小さな声を上げると、
レメックが微笑んで、あたしの目の前に座った。
「それ、付けてよ。アネタ」
「え?」
言われた通りに冠の付いた帽子をかぶると、レメックはニッコリ笑った。