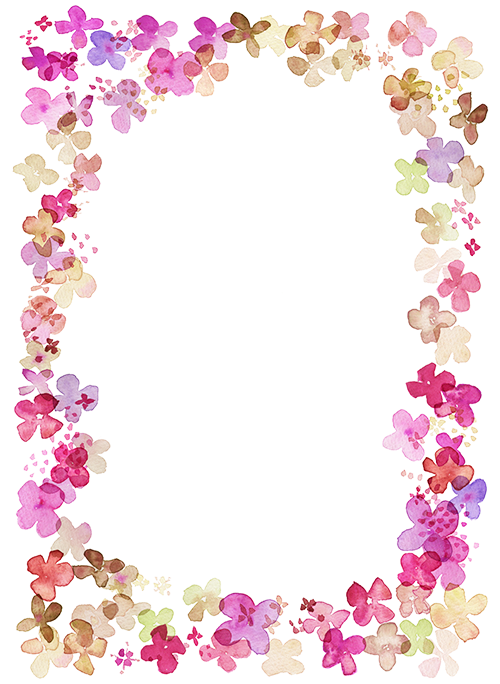それは、父の死だった。
父は、苛酷な強制労働で体力が衰え、命を落としたのだという。
母は、泣いた。
あたしは、これまで父と争ってばかりだったことを後悔した。
お互いのことをもっと理解できていれば、
もう少し仲良くできたかもしれなかった。
あたしは、
最後に「悪い子」ではないと認めてくれた父のことを、
大嫌いながらも、愛していた。
そのことを、失って初めて知った。
そして―――――今に至る。
あたしは、
レメックたちの帰りを、待ち続けている。
けれど、どんなに待っても、
彼らは帰ってこない。
一体、どうなってしまったんだろう……
心に、不安が渦巻いた。
この不安は、これまでも、いつも胸にあった。
だけど、その不安をかき消すために、自分で自分に言い聞かせる。
大丈夫だ、と。
彼らは、必ず、帰ってくると。
この六年間、ずっと、その繰り返しだった。
レメックの言葉が、あたしの生きる望みだった。
もしかすると、彼は、あたしのことを考えられる段ではなかったかもしれない。
あたしのことなんか、あまり覚えてもいないのかもしれない。
けれど、あたしにとっては、彼の言葉は救いだった。
何の希望もない地獄のような毎日を、今まで生きてこられたのは、
彼と「また、会うんだ」という望みのおかげだった。
あの別れの日から、
たとえ、辛くても、
あたしは、泣かなかった。
なぜなら、
彼が言ったからだ。
『笑って』と。
いつも、あたしの心の中には、レメックがいた。
だから、あたしは、待つ。
また、あの楽しかった日々が戻ることを信じて…
待ち続ける――――――。
今日は、
あの夏の日のように、よく晴れた日だ。
太陽が眩しいほど輝き、真っ白な雲が浮かぶ。
どこまでも続く美しい青空が、広がっている。
この空を、レメックも見ているだろうか…―――
そんなことを考えていると、
母があたしを呼んだ。
「アネタ」
「なに?」
家の中から出てきた母の表情は、
なんだか変だ。
母は、自分の後ろを指した。
そこには、
一人の少年が立っていた。
「……―レメック?」
思わず、口から彼の名が出てしまった。
けれど、その少年は、レメックではなかった。
少年は、じっと、あたしの方を見つめた。
その目は、暗く、
痛みを負っているように見える。
本能的に、手で自分の胸を押さえた。
この少年は、何かを伝えに来たに違いない―――
そう思った。