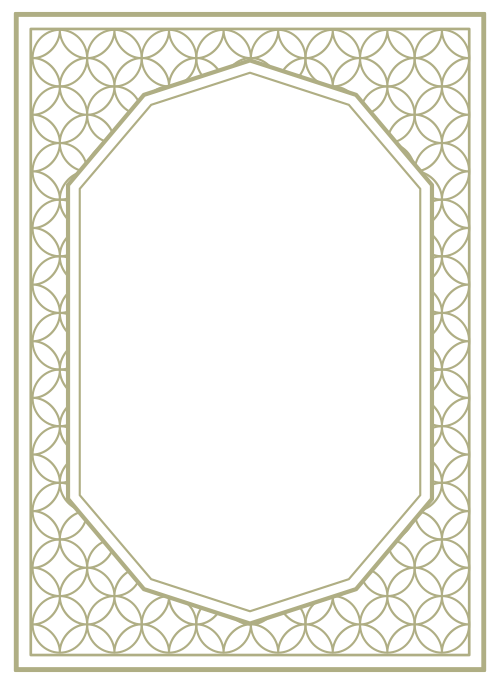*
中学に入学すると、岬は少し心の安住を得ていた。彩乃は岬が元通っていた私立のエスカレーター中学に進学し、岬は公立の中学に進んだからだった。中学では岬はその甘いルックスと優秀な成績、そして抜群の運動神経で瞬く間にその地位を高めた。屋敷に帰りさえしなければ、岬の王国は健在だった。
体育の時の成績が良かったせいで、バスケにバレーボール、サッカーにと練習試合のたびに助っ人に駆り出された。出場した試合では全て得点に絡み、応援に来ていた在校生は勿論、相手校の生徒からも注目の的だった。球技大会でも勿論クラスの皆から頼りにされたし、足も速いから体育祭でもリレーのアンカーだった。
(学校こそ、この世の天国……! 俺はこのまま天国に住みたい! あの屋敷に帰らずに!!)
そう、屋敷に帰りさえしなければ、である。
彩乃の執事をするために、好きな部活にも入れない。授業が終われば基本的に真っすぐ屋敷へと帰り、彩乃の帰りを待つ。彩乃が車で帰ってくるのを待って、まずお茶を淹れる。お茶の淹れ方なんて覚える必要もなかった筈なのに、今こうやって学校から帰ってリビングで寛ぐ彩乃の為にティーポットからカップに紅茶を注いでいる自分が嫌になる。
(しかし、こんなことまでこなせるのは、俺が器用だからだ!! まあ、天は二物も三物も与えるんだよな!!)
紅茶を注いだカップを持ちながら、悦に浸る。
リビングではマルたち親子が寛いでいて、まるで宮田家の猫のようだ。キャットフードは過去岬の家で与えていたものと同等のものを与えられ、マルたちは完全に彩乃に懐いた。動物を手懐けるのは容易い。胃袋を掴めばいいのだから。しかし岬はそうはならない、と思った。
(俺は高貴な生まれの人間だからな! 胃袋ごときでは屈しないんだ!)
岬がマルたちを眺めながらそう思っていると、彩乃が声を掛けてきた。
「岬くんの噂が私の学校まで聞こえてるわ」
優雅に紅茶を飲みながら、彩乃は微笑む。
「そうですか。どのような?」
彩乃が腰掛けるテーブルから一歩引いた壁側に立って、岬は奥歯を噛みしめながら穏やかに応えた。
「成績優秀、スポーツ万能、やさしい性格で他校生にも人気があるとか」
「そうですか」
「本当なの?」
ちょっと岬の顔色をうかがうような目。どうしてそんな目で見られなきゃいけないのか分からないが、尋ねられたからには応えないわけにはいかない。岬は、そうですね、とだけ答えた。
「ふふ。でも、そんな岬くんは、私の執事ですもの。嬉しいわ」
小鳥が歌を歌うように言われても、全然嬉しくない。むしろ、またこめかみの血管がちぎれそうになるほどに歯を食いしばってしまう。
(お前なんか、本当だったら俺の小間使いにしてやるくらいの身分だったのに……!!)
これ以上我慢していたら顔の表情筋が変に動きそうだと思って、岬は彩乃の前を辞した。廊下を歩いてあてがわれた部屋に戻る。ぱたんと後ろ手にドアを締めれば誰も……、マルたちすらいない部屋。
(あの女ああああーーーーーっ!!)
声に出すわけにはいかないので、心の中で罵倒しながら、枕を何度も殴りつける。ふかふかの枕がボスンボスンとへこんでは膨らむ。力任せに殴りつけて、気が収まる頃には肩で息をしていた。流石の岬も堪忍袋の緒が切れる。
「なんで、俺が……っ、あんな女に傅かなくちゃならないんだ……っ!」
挙句、自分のもの呼ばわりされて。
叫び出したいのを堪えて、小さな声で呟く。この屋敷に来て以来、何度繰り返したか分からない呟きを、今日も零してしまう。それほどに、今の岬の環境は、岬にとって受け入れがたいものだった。
(いつか、あの得意げな顔をぎゃふんと言わせてやる……!)
今日も今日とてそう決意する岬だった。
中学に入学すると、岬は少し心の安住を得ていた。彩乃は岬が元通っていた私立のエスカレーター中学に進学し、岬は公立の中学に進んだからだった。中学では岬はその甘いルックスと優秀な成績、そして抜群の運動神経で瞬く間にその地位を高めた。屋敷に帰りさえしなければ、岬の王国は健在だった。
体育の時の成績が良かったせいで、バスケにバレーボール、サッカーにと練習試合のたびに助っ人に駆り出された。出場した試合では全て得点に絡み、応援に来ていた在校生は勿論、相手校の生徒からも注目の的だった。球技大会でも勿論クラスの皆から頼りにされたし、足も速いから体育祭でもリレーのアンカーだった。
(学校こそ、この世の天国……! 俺はこのまま天国に住みたい! あの屋敷に帰らずに!!)
そう、屋敷に帰りさえしなければ、である。
彩乃の執事をするために、好きな部活にも入れない。授業が終われば基本的に真っすぐ屋敷へと帰り、彩乃の帰りを待つ。彩乃が車で帰ってくるのを待って、まずお茶を淹れる。お茶の淹れ方なんて覚える必要もなかった筈なのに、今こうやって学校から帰ってリビングで寛ぐ彩乃の為にティーポットからカップに紅茶を注いでいる自分が嫌になる。
(しかし、こんなことまでこなせるのは、俺が器用だからだ!! まあ、天は二物も三物も与えるんだよな!!)
紅茶を注いだカップを持ちながら、悦に浸る。
リビングではマルたち親子が寛いでいて、まるで宮田家の猫のようだ。キャットフードは過去岬の家で与えていたものと同等のものを与えられ、マルたちは完全に彩乃に懐いた。動物を手懐けるのは容易い。胃袋を掴めばいいのだから。しかし岬はそうはならない、と思った。
(俺は高貴な生まれの人間だからな! 胃袋ごときでは屈しないんだ!)
岬がマルたちを眺めながらそう思っていると、彩乃が声を掛けてきた。
「岬くんの噂が私の学校まで聞こえてるわ」
優雅に紅茶を飲みながら、彩乃は微笑む。
「そうですか。どのような?」
彩乃が腰掛けるテーブルから一歩引いた壁側に立って、岬は奥歯を噛みしめながら穏やかに応えた。
「成績優秀、スポーツ万能、やさしい性格で他校生にも人気があるとか」
「そうですか」
「本当なの?」
ちょっと岬の顔色をうかがうような目。どうしてそんな目で見られなきゃいけないのか分からないが、尋ねられたからには応えないわけにはいかない。岬は、そうですね、とだけ答えた。
「ふふ。でも、そんな岬くんは、私の執事ですもの。嬉しいわ」
小鳥が歌を歌うように言われても、全然嬉しくない。むしろ、またこめかみの血管がちぎれそうになるほどに歯を食いしばってしまう。
(お前なんか、本当だったら俺の小間使いにしてやるくらいの身分だったのに……!!)
これ以上我慢していたら顔の表情筋が変に動きそうだと思って、岬は彩乃の前を辞した。廊下を歩いてあてがわれた部屋に戻る。ぱたんと後ろ手にドアを締めれば誰も……、マルたちすらいない部屋。
(あの女ああああーーーーーっ!!)
声に出すわけにはいかないので、心の中で罵倒しながら、枕を何度も殴りつける。ふかふかの枕がボスンボスンとへこんでは膨らむ。力任せに殴りつけて、気が収まる頃には肩で息をしていた。流石の岬も堪忍袋の緒が切れる。
「なんで、俺が……っ、あんな女に傅かなくちゃならないんだ……っ!」
挙句、自分のもの呼ばわりされて。
叫び出したいのを堪えて、小さな声で呟く。この屋敷に来て以来、何度繰り返したか分からない呟きを、今日も零してしまう。それほどに、今の岬の環境は、岬にとって受け入れがたいものだった。
(いつか、あの得意げな顔をぎゃふんと言わせてやる……!)
今日も今日とてそう決意する岬だった。