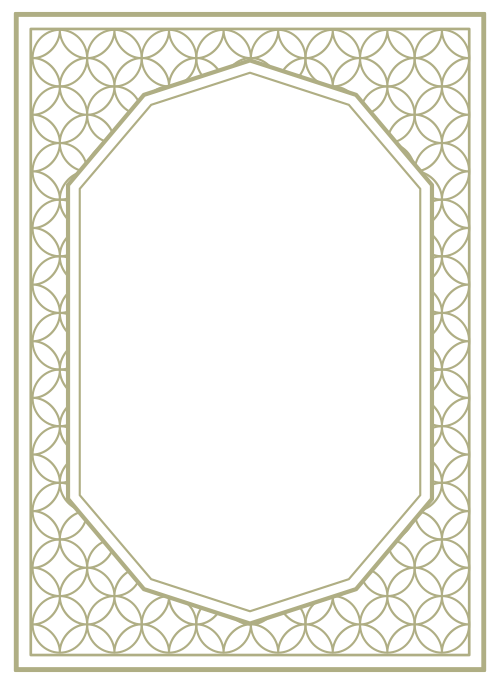*
彩乃の様子がおかしいことは、他の生徒の口からも聞こえてきた。曰く、移動教室の場所を間違える、体育のバレーボールの練習でボールを顔にぶつける、階段を踏み外す、等々。挙句の果てには期末テストで上位十位にも入れなかった。燦々たるものである。
どれも注意力散漫で起こることだったから、岬は彩乃に再度質していた。
「彩乃さん。最近彩乃さんはぼんやりしすぎです。ボールを顔にぶつけるのはまだいい……、いや、良くないですけど、階段を踏み外すなんて、怪我でもしたらどうするんですか。それにテスト! 学年総代で入学しておいて、よくもまあトップ10を逃すなんてこと出来ましたね!? それで僕を執事だと呼べるんですか!?」
彩乃が順位を落としている間に、岬はトップに返り咲いた。でもそれは彩乃が本気の時だったら喜べたことだ。こんな腑抜けた彩乃相手では、喜ぶに喜べない。岬に言われるだけ言われて、彩乃はしゅんとなっている。
「ごめんなさい……」
「この前も、ごめんなさいと言って黙りましたね? 何かあるんですか? 怪我をしそうになったことは自覚してますよね? ことと次第によっては、ご両親にお伝えしなければなりません」
岬がそう言うと、彩乃は血相を変えて、そういうことじゃないの、と首を振った。そこまで不調の理由を自覚しておきながら、隠されなきゃいけない理由はなんだ。こういう時にこそ、横柄に、これ見よがしに主人然と、これこれこういう理由で困っているから何とかして頂戴、というものではないのか?
「じゃあ、どういう理由で彩乃さんは元気なく過ごしているのですか。ご両親はそれはそれは心配されてます。貴女は僕を執事に雇ったんでしょう? その原因の根絶を、僕に頼むのが筋じゃないですか?」
「みさ……」
「おーっと、そこまで」
話に割って入って来たのは、秀星だった。今日も授業が終わり、彩乃の不調をクラスメイトから聞いて、中庭で彼女に問い質していたところを秀星が見つけたのだった。
「悩める乙女を少年漫画のように説得しようとするなよ、岬」
「なんだよ、秀星。俺の聞き方が悪いってのか?」
「イエス、イエ~ス!」
軽い奴だな。でも彩乃の悩みはそんな軽いもんじゃない筈だ。なんて言ったって入学式で岬の上を行った彩乃が学年首位を落とすくらいなんだから。
しかし秀星はまるでパーティーでエスコートするかのように彩乃の手を取って、彩乃の視界から岬を遠ざけた。
「あとは僕が聞きますよ、彩乃さん」
そう言って、秀星は彩乃を連れ去った。……何を聞き出すのか、気になった……。
彩乃の様子がおかしいことは、他の生徒の口からも聞こえてきた。曰く、移動教室の場所を間違える、体育のバレーボールの練習でボールを顔にぶつける、階段を踏み外す、等々。挙句の果てには期末テストで上位十位にも入れなかった。燦々たるものである。
どれも注意力散漫で起こることだったから、岬は彩乃に再度質していた。
「彩乃さん。最近彩乃さんはぼんやりしすぎです。ボールを顔にぶつけるのはまだいい……、いや、良くないですけど、階段を踏み外すなんて、怪我でもしたらどうするんですか。それにテスト! 学年総代で入学しておいて、よくもまあトップ10を逃すなんてこと出来ましたね!? それで僕を執事だと呼べるんですか!?」
彩乃が順位を落としている間に、岬はトップに返り咲いた。でもそれは彩乃が本気の時だったら喜べたことだ。こんな腑抜けた彩乃相手では、喜ぶに喜べない。岬に言われるだけ言われて、彩乃はしゅんとなっている。
「ごめんなさい……」
「この前も、ごめんなさいと言って黙りましたね? 何かあるんですか? 怪我をしそうになったことは自覚してますよね? ことと次第によっては、ご両親にお伝えしなければなりません」
岬がそう言うと、彩乃は血相を変えて、そういうことじゃないの、と首を振った。そこまで不調の理由を自覚しておきながら、隠されなきゃいけない理由はなんだ。こういう時にこそ、横柄に、これ見よがしに主人然と、これこれこういう理由で困っているから何とかして頂戴、というものではないのか?
「じゃあ、どういう理由で彩乃さんは元気なく過ごしているのですか。ご両親はそれはそれは心配されてます。貴女は僕を執事に雇ったんでしょう? その原因の根絶を、僕に頼むのが筋じゃないですか?」
「みさ……」
「おーっと、そこまで」
話に割って入って来たのは、秀星だった。今日も授業が終わり、彩乃の不調をクラスメイトから聞いて、中庭で彼女に問い質していたところを秀星が見つけたのだった。
「悩める乙女を少年漫画のように説得しようとするなよ、岬」
「なんだよ、秀星。俺の聞き方が悪いってのか?」
「イエス、イエ~ス!」
軽い奴だな。でも彩乃の悩みはそんな軽いもんじゃない筈だ。なんて言ったって入学式で岬の上を行った彩乃が学年首位を落とすくらいなんだから。
しかし秀星はまるでパーティーでエスコートするかのように彩乃の手を取って、彩乃の視界から岬を遠ざけた。
「あとは僕が聞きますよ、彩乃さん」
そう言って、秀星は彩乃を連れ去った。……何を聞き出すのか、気になった……。