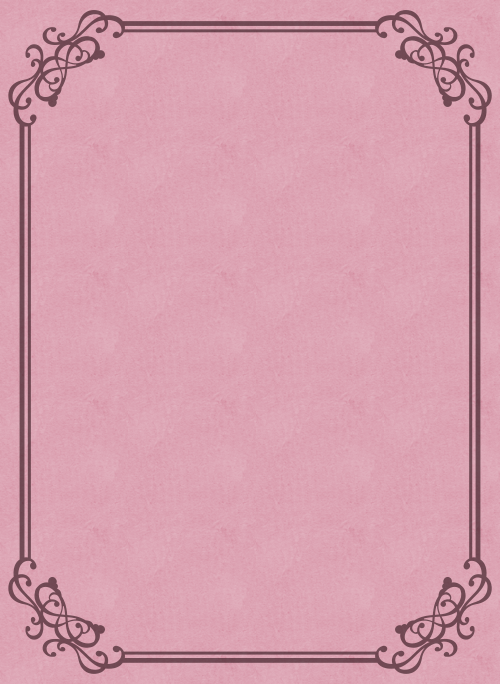「だから笑って、加恋ちゃん。加恋ちゃんには笑顔が似合うから」
いつだって加恋ちゃんには笑顔でいてほしい。
そして僕は、そんな加恋ちゃんの笑顔を見ると幸せな気持ちになる。
「優くん……」
「ねっ」
「優くん……ありがとう」
加恋ちゃんは僕にとびきりの笑顔を見せてくれた。
そして僕は、そんな加恋ちゃんのことをやさしく抱きしめた。
そのとき僕は加恋ちゃんに謝ろうと思っていることがあった。
それは、さっき僕が一方的に加恋ちゃんに……。
「……加恋ちゃん……さっきはごめんね……僕、自分の気持ちを一方的に加恋ちゃんに……」
加恋ちゃんのことを好き過ぎてのこととはいえ、急にあんなこと……。
「優くん、謝らないで。……わたし、優くんの気持ち嬉しかったよ」
「加恋ちゃん……」
「わたしの方こそ、ごめんね。優くんの気持ちを突き放すようなことをして」
「加恋ちゃん……」
「わたしは優くんとこうしているだけで幸せ」
「僕もだよ、加恋ちゃん」
「優くん……」
この後も僕と加恋ちゃんは、いろいろな話をして過ごした。