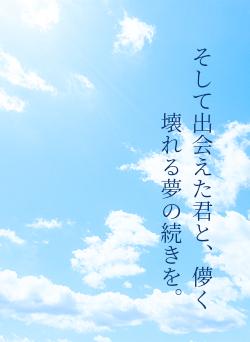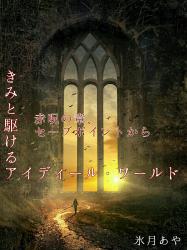帳幕の入口に垂らした布を、そっと持ち上げた。
「……何の用?」
わたしが起こすまでもなく、沖田はかすれ声でささやいた。まぶたは閉じられたままだ。
「入るよ」
「どうぞ」
わたしは沖田の布団のそばへと、膝で進んだ。布をもとに戻す。寮内のあちこちから聞こえてくる生活じみた音が、ふっと遮断された。
「熱、まだ続いてる?」
「さあね」
「息苦しそうだね。食欲は?」
「あるわけないだろう」
「飴湯、持ってきたけど、飲める?」
「ああ」
ようやく沖田はまぶたを開いた。案外、まつげが長い。熱っぽい目にまつげの影が揺れる。
沖田はゆっくりと起き上がった。わたしから湯飲みを受け取ると、浅い息を何度も湯気に吹きかけた。
「猫舌なんだね」
「江戸っ子のくせに粋じゃないって?」
「別にそんなこと思ってない。眠れてる?」
「一応ね」
御蔭寮は大小さまざまな部屋を増殖させている。沖田が居候しているのは、切石と巡野の部屋だ。広くて古い部屋で、壁の木目がとても美しい。
わたしはこの隣にある三帖間を使っている。まだ若い部屋だ。このところようやく天井が高くなり、普通に立って歩けるようになった。
沖田はここへ来た当初、相部屋を嫌がった。他人が立てる音や気配があると眠れないらしい。
わがままだ、と一蹴することはできなかった。眠りが遠いのは苦しいことだ。
剣客の研ぎ澄まされた感覚ほどではないにせよ、わたしも音や気配にぴりぴりするたちだ。自分ひとりの静かな環境でないと、寝付けない。相手が家族でさえ、神経に障ってしまってダメだ。
沖田の寝床を覆っている紗の帳幕は、結界の一種で、音と気配を遮断する。広さは畳二帖ぶんほど。わたしが日常的に使っているものを、今は沖田に貸している。
入寮してすぐのころ、不眠で悩むわたしに、当時は相部屋だった更紗さんが結界の作り方を教えてくれた。栄励気を操る、という感覚を初めて知った出来事だった。
沖田は、ごくりと喉を鳴らして飴湯を飲んだ。とがった喉仏が上下した。
「あんたが持ってくるものは喉を通るんだな」
「どういう意味?」
「寮の連中に勧められた菓子は食えなかったんだ。口に入れた途端、体が拒んで吐いちまった」
「そのへんの店で買ったお菓子でしょ。人工エレキで自動化された工場で加工されてるんだよ。そんな食べ物、きみみたいに天然の栄励気が豊富な人間は、百発百中でエレルギー反応を起こしちゃうって」
「天然じゃない栄励気があるのかい」
「あるんだよ、今の時代は。むしろ、エレキって言ったら、人工的に作ってるものを指す。天然の栄励気で技だの術だの使えるような人間はめったにいない」
沖田は飴湯をもう一口飲んで、まじまじとわたしを見た。
「あんたは本当にこの時代の人間なのか?」
「そうだよ」
「こんなものを作れるのに?」
沖田は上を指差した。紗の帳幕のことだ。
「生まれる時代を間違ったって、自分でも思うよ。きみ、こっちに来てから、本当に具合悪いでしょう? もともとわずらってる病のせいだけじゃないよ。この時代の空気が悪すぎるの」
何か言おうと口を開いた沖田が、咳をした。乾いた咳は、たちまち痰が絡んで、重たく引きずるようなものへと変わる。
わたしは沖田の手から湯飲みを奪った。沖田は両手で口元を覆い、背中を丸めて咳き込み続ける。
「大丈夫?」
とっさに、わたしは沖田の背中をさすろうとした。
ぱしん!
音と衝撃があって、それから、痛みが来た。沖田がわたしの手を振り払ったのだ。
沖田は横目でわたしを見やった。涙が目尻にたまっている。咳の合間に何かをささやいた。
「違う。ごめん」
そう聞こえた。
「……何の用?」
わたしが起こすまでもなく、沖田はかすれ声でささやいた。まぶたは閉じられたままだ。
「入るよ」
「どうぞ」
わたしは沖田の布団のそばへと、膝で進んだ。布をもとに戻す。寮内のあちこちから聞こえてくる生活じみた音が、ふっと遮断された。
「熱、まだ続いてる?」
「さあね」
「息苦しそうだね。食欲は?」
「あるわけないだろう」
「飴湯、持ってきたけど、飲める?」
「ああ」
ようやく沖田はまぶたを開いた。案外、まつげが長い。熱っぽい目にまつげの影が揺れる。
沖田はゆっくりと起き上がった。わたしから湯飲みを受け取ると、浅い息を何度も湯気に吹きかけた。
「猫舌なんだね」
「江戸っ子のくせに粋じゃないって?」
「別にそんなこと思ってない。眠れてる?」
「一応ね」
御蔭寮は大小さまざまな部屋を増殖させている。沖田が居候しているのは、切石と巡野の部屋だ。広くて古い部屋で、壁の木目がとても美しい。
わたしはこの隣にある三帖間を使っている。まだ若い部屋だ。このところようやく天井が高くなり、普通に立って歩けるようになった。
沖田はここへ来た当初、相部屋を嫌がった。他人が立てる音や気配があると眠れないらしい。
わがままだ、と一蹴することはできなかった。眠りが遠いのは苦しいことだ。
剣客の研ぎ澄まされた感覚ほどではないにせよ、わたしも音や気配にぴりぴりするたちだ。自分ひとりの静かな環境でないと、寝付けない。相手が家族でさえ、神経に障ってしまってダメだ。
沖田の寝床を覆っている紗の帳幕は、結界の一種で、音と気配を遮断する。広さは畳二帖ぶんほど。わたしが日常的に使っているものを、今は沖田に貸している。
入寮してすぐのころ、不眠で悩むわたしに、当時は相部屋だった更紗さんが結界の作り方を教えてくれた。栄励気を操る、という感覚を初めて知った出来事だった。
沖田は、ごくりと喉を鳴らして飴湯を飲んだ。とがった喉仏が上下した。
「あんたが持ってくるものは喉を通るんだな」
「どういう意味?」
「寮の連中に勧められた菓子は食えなかったんだ。口に入れた途端、体が拒んで吐いちまった」
「そのへんの店で買ったお菓子でしょ。人工エレキで自動化された工場で加工されてるんだよ。そんな食べ物、きみみたいに天然の栄励気が豊富な人間は、百発百中でエレルギー反応を起こしちゃうって」
「天然じゃない栄励気があるのかい」
「あるんだよ、今の時代は。むしろ、エレキって言ったら、人工的に作ってるものを指す。天然の栄励気で技だの術だの使えるような人間はめったにいない」
沖田は飴湯をもう一口飲んで、まじまじとわたしを見た。
「あんたは本当にこの時代の人間なのか?」
「そうだよ」
「こんなものを作れるのに?」
沖田は上を指差した。紗の帳幕のことだ。
「生まれる時代を間違ったって、自分でも思うよ。きみ、こっちに来てから、本当に具合悪いでしょう? もともとわずらってる病のせいだけじゃないよ。この時代の空気が悪すぎるの」
何か言おうと口を開いた沖田が、咳をした。乾いた咳は、たちまち痰が絡んで、重たく引きずるようなものへと変わる。
わたしは沖田の手から湯飲みを奪った。沖田は両手で口元を覆い、背中を丸めて咳き込み続ける。
「大丈夫?」
とっさに、わたしは沖田の背中をさすろうとした。
ぱしん!
音と衝撃があって、それから、痛みが来た。沖田がわたしの手を振り払ったのだ。
沖田は横目でわたしを見やった。涙が目尻にたまっている。咳の合間に何かをささやいた。
「違う。ごめん」
そう聞こえた。