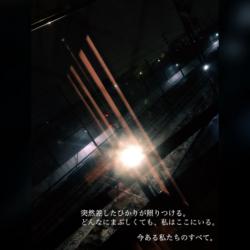七海は三時限目の講義が終わると、食品栄養学科の女子四人組と生活環境学部の一階にある第四食堂で笑い声を奏でている。『このまま帰っても暇だし』と、七海は思ったのだろう、これから築いていく四年間を充実させようと積極的に話をした。
今私たちが受けている講義は選択科目で必修ではないから受講しなくてもいい。七海は最初から、無理なスケジュールは組んでいないようだ。
バイトの面接に無事に通り、大学の勉強も忙しくなってくるだろうから、時間を気にせず話ができるのも今ぐらいだと思って、七海は四時限目の講義が終了するぐらいまで話し込んだ。
一人の女の子が『サークル活動に顔を出す』と言って立ちあがると、七海たちも自然にお開きになった。
メインストリートを歩いていく七海。地に足を確実に残しながら歩く。誰かに背中を見られていいように。
バス停の長蛇の列をすいすい追い抜かして、バスの乗車中のランプが消えて、大勢の学生を乗せたバスがのろのろと進み始めた。
吊革につかまって眠そうに窓越しから街を眺める宏紀がいた。
「宏紀だ!」
慌てて七海は宏紀に手を振るけど、宏紀の視線は七海を捉えず行方知らずになっていた。
「ああ、気付かないか」
無視された七海を置き去りしたままバスはそのまま進んでいく。理由は分かっているから気にしなくていい。宏紀は気が付かなかっただけだ。思い切って振った手を静かに戻した。
七海の視線にアパートが映る。でも今日はそのまま通り過ぎて、近くにあるスーパーに向かった。外食やコンビニに頼らず、自分で自炊を頑張ろうと意気込んでいた七海は、早くそれを実行するために足を動かす。
しばらく歩いていくと、一人の男の子の姿が入り込んだ。でも記憶は曖昧で誰かは判別できなかった。信号が赤から青に変わる。男の子の周囲にいる歩行者も同じく横断歩道を渡りはじめる。少し距離があって、七海は渡るか渡らないかを迷っていると、青信号が点滅に切り替わった。もうすぐ赤になる。七海はスニーカーのバネを弾いて黒髪を風で遊ばせながら小走りになった。横断歩道の途中で完全に赤になったけど、七海はなんとか渡り切った。
「もう少し、運動しないと」
少し荒くなった呼吸を整えながら七海はそう漏らした。
前を行っていた男の子と肩を並べると、お互いの視線を交換し合った。
「七海ちゃん」
前を行く男の子は真也だった。私たちと受けていた講義を終えて、アパートに向かう途中だった。
「園田君! 今帰り?」
呼吸が整った七海は少し声を高めて言った。
「うん。終わってすぐに出てきた。四時限目はいなかったよね?」
真也はいたかどうか分からなかったけど、とりあえず話題を振った。黙って歩いていくのは気まずいだろうから。
「私、その時間は講義取ってないの」
「そうなんだ。だからいなかったんだね」
「うん。この辺に住んでるの?」
七海は円を描いて周囲を表して言った。
「あそこに住んでる」
真也が腕を伸ばすと、七海と同じく目と鼻の先にあるアパートだった。
「近いね」
「本当に近い。でも逆に近すぎて遅刻するかもしれない」
真也は冗談のように言った。
「ああ、ギリギリまで寝ちゃうからね」
「そうそう……七海ちゃんもこの辺なの?」
二人でいるのが少し気まずいのか、真也は言葉を失っても質問を投げかけた。宏紀の隣にいた女の子っていうだけで、それ以外に接点はない。
「私もすぐ近くだよ。今からスーパーに行くの」
アパートの場所は言わなかった。微妙な関係性ではこういう風になってしまうだろう。私なら、迷わず場所を示して言っていたかもしれない。
「そうなんだ。自炊してる感じ?」
「これから頑張ろうと思って……」
七海はできるかどうか分からない不安の中を彷徨ように言った。でもどこか目には七海の決意のような瞳も据え置いている。
「頑張ってね!」
「ありがとう」
背伸びをしてお目当ての本に手を伸ばす。私は踏み台を店員さんに貸してもらって本を手にする。お礼を言って去る店員さんを横目に、ペラペラとめくって本の世界に少しだけ足を踏み入れる。
長い通学時間に何かできないかって考えてたどり着いたのが書店だった。
大学に行くときは座ることは百パーセントできないから立ちながら本を開こうと考えたけど、もみくちゃにされながら読む本はどうなんだろうって自問自答した。帰りならなんとか読めるかもしれないけど、疲れて寝ている可能性が高い。もっと言うと、この前のように宏紀と一緒に帰って会話をした方が良い。わざわざ自分の世界に入って、本と戯れる必要があるか。たぶんない。
わざわざ出してきてもらった踏み台を店員さんに返して書店を出た。
特に行くところもなくてJR京浜東北線のホームに向かう。
みんなが誰かに、何かに急かされるように歩いていく、いや、早歩きで目的地に向かっていく。誰とも目を合わさず無表情だ。怒っているのかもしれないって思って、後退りしてしまいそうだ。
その中に紛れ込んで歩く私は、とても浮いているのかもしれない。目が合うと人に笑いかけて、初対面の人でもまるで長年の友達のように接していく。でもここに紛れていると、無理やり自分を変えてでも、無表情を貫き通さないといけない空気が私を窮屈にする。
私って変なのかな……。
人々を眺めるたびに、そう感じてしまう。
大船方面のホームへとつながる階段にさしかかろうとすると、私はいきなりスピードを緩めて立ち止まった。私の至近距離を歩いていた人々が、『いきなり止まるなよ』と言わんばかりの表情を作って、私に鋭い視線を向ける。私はペコっと頭を小さく下げて、行く場所を譲った。
その場に立ち尽くして顔を上げて眺めた景色の中に、宏紀の姿があった。
手すりにつかまって階段を行くおばあちゃんの腕を優しくつかんで、階段をゆっくり上がっていく。宏紀が今、おばあちゃんに何をしているのかすぐに分かった。
この前、駅のホームで話した時の感じを思うと、おばあちゃんからお金を奪おうとかそういうことではないと思う。二人との距離ができると、私も階段をゆっくり上がっていく。まるで見えない線で私たちが繋がれているようだった。
私もだんだん大人になってきたから、それを何も言わずに眺めている。
本当言うと、私も手伝っておばあちゃんと話をしたいけど、しない。これが私の成長した部分だ。もっと言うと、誰かとのコミュニケーションが面倒な時も自ずとでてきた。
宏紀はホームまで到着すると、おばあちゃんに柔和な笑顔を見せて、何やら話している。私の荒んでいく心を正してくれるような力が、柔らかさの中にある。
おばあちゃんは頭を下げて宏紀にお礼を言っているのだろう。宏紀は手を横に振ってただ笑いかけている。口の動きでは、『全然、気にしない下さい』と読めた。
今日の疲れを取ってくれるように体が軽くなって、ふわふわした目で宏紀を見つめていると、ふと宏紀と目が合った。なんか見られている感じが、宏紀にはあったんだろうか。宏紀の視線が私を包んだ綿菓子のようなふわふわ感を取り除いて、背筋を正させた。
宏紀はすぐに視線を外して、おばあちゃんに頭を下げて奥のホームへ逃げるように歩いて行ってしまった。私は距離を詰めたけど、もう宏紀の姿はなかった。ホームには大勢の人々が電車を待つ中、おばあちゃんがぽつりと立っていた。周囲を見渡して、座る場所を探している。
「おばあちゃん、あそこにベンチありますよ」
「ありがとう」
さっきの宏紀の柔らかい笑顔に負けないぐらいの柔らかさに上品さを付け加えたような笑顔だった。それを見ていたら、私も自然に笑顔になっていた。
逃げた、いや気まずい場面を見られてしまった宏紀の心情を考えてみる。目が合って逃げられていい気分はもちろんしないけど、仕方ないかもしれない。この出来事はそこまで気にしなくてもいい。
私のことを、否定せずに話してくれた宏紀に話しかけてみよう。
まずは、磯子へ私を連れて帰ってくれる電車を待とう!
誰もいない講義室。人がいるストレスを感じなくてもいい。軽やかに足を踏み入れると、まずは密閉された窓を開けた。
朝のそよ風を全身で受けて、私は目を閉じてあるがままの私になる。髪の毛をされるままにされても、スカートがめくれても気にしない。今は誰もいない。
静かに目を開けると同時に、心地よかった風も収まって、私をもう相手にしてくれなくなった。
宏紀はもうすぐ来るかな……。
昨日の出来事を思い出すと、自然に笑顔になれる。
宏紀からしたら、恥ずかしい一面を見られてしまったのかもしれない。だから気まずくて自分のことを誰も知らないどこかを求めたのだろう。私、また余計なことしちゃったかもしれない。
でも私が言い訳をするとすれば、周囲にもたくさんの人がいたのに、なんで私に見られるのが嫌なのか。それに悪いところを見たわけではないから逃げ……恥ずかしがらなくてもいい。良いことなら誰かに伝えてあげたい。
ぼんやりと講義室を眺める。こんなにきれいな教室でこれから勉強ができる。また風が吹き始めた。まだまだ眠くて目を閉じる。立ったまま眠ることができそうだ。
私は目を開けて、視界に一人の男の子を捉えた。
静かにドアを開けて、私のはかなくて短い睡眠を破ったのは宏紀だった。
「ああ」
思わず出た言葉と同時に私は頬を緩ませた。
少しだけ作り笑いをぎこちなさそうにしている宏紀は、変なところを見られたなって、思っているのかもしれない。それでもペコっと頭を下げて私に挨拶した。私もつられて頭を動かした。
「おはよう。早いね」
私は宏紀の居心地はいい方ではないと感じたから、ぎこちなさを溶かそうと思った。
「おはよう。永井さんも早いね」
「うん……」
お互いに沈黙になった。それでも私は笑みを絶やさずに宏紀を見続けた。
宏紀は何も言わずに前の席へ足を動かした。まるで、お母さんの大事なものを壊してしまって言えずじまいの子供のように、何にも触れないように慎重に向かった。
定位置とまでは言わないけど、いつもの場所に宏紀はかばんを置いた。
私は宏紀の席の隣に座って、宏紀の横顔を見た。東京駅のホームで見た時も思ったけど、結構イケメンでいつまでも眺めていられそうだ。
「昨日……駅にいた?」
唐突に私は切り出した。このままぎこちなくしているのもだんだん面倒くさくなってきた。悪いことをしたわけじゃないから堂々としていよう。
「いたかな……でも毎日電車に乗っているから……いたかも」
目を逸らして言い訳じみた感じで宏紀は言った。毎日電車に乗るのは知っているって、私は思った。私も磯子から大学に通っているから。
「そっか……おばあちゃんと何を話していたの?」
私は核心をついて言った。もちろん笑顔で話しかけたから嫌な感じはしてないだろう。
「え、何も話してないよ……ただ……」
「ただ……」
興味津々でその言葉の後ろを待つ私。宏紀はどんな答えを用意しているんだろう。
「別に何も話してない」
「おばあちゃんのこと、助けてたんでしょ?」
「え……」
何がそんなに嫌なのかって私は少しイライラしてきた。でも宏紀の優しさには笑顔を添えてあげたいから頬のゆるみはそのままにした。
「なんでごまかすの? 宏紀君、優しいなって思ったよ」
私は宏紀の腕に軽く触れてそう言った。
「ああ……ありがとう」
恥ずかしそうに俯いて宏紀は言った。
「うん。宏紀君は、シャイなの? それなのにおばあちゃんに声をかけるってすごく勇気いるよね?」
興味津々で私は言った。宏紀の性格と行動が一致しないんだ。同じ何かを重ね合わせても違う絵が浮かび上がっている。
「いや、相手はおばあちゃんだから、あのままにはしておけないから……でも勇気が要った」
宏紀の本心が見えて、私は息を噴き出しながら笑顔になれた。胸の中にあったモヤモヤはもう消えてなくなって、隙間に余裕ができた。
「そうだよね」
「でも永井さんなら、難なくできそうだよね?」
前の私なら難なくできたと思う。でも色々な歪みが入り混じって、今は確実にできるかどうかは明言できない。でも宏紀がそんな風に言ってくれたのは、どこか嬉しかった。
「……できると思う」
「うん。なんか想像がついた」
宏紀は脳裏で私の姿を思い描いた。宏紀は私の性格と行動が一致して笑顔を見せた。
「とりあえず、ありがとうって言っておくね。宏紀君、これからも、私と仲良くしてね」
「えっ? ああ……もちろん」
目を丸くして驚きの表情を見せたものの、すぐに宏紀は表情を緩めてそう言った。
「ありがとう」
そこに七海が講義室に入ってきた。
宏紀の隣に席に向かって歩く足元を制止させた。
私と宏紀は後ろを振り返って、七海の表情を迎え入れる。七海は半笑いで私たちを見ている。『お邪魔だったかな』と言わんばかりの表情だった。まるで踏み入れてはいけない領域に何も知らず足音をさらすように。
「あ、おはよう」
宏紀は少し慌て気味で言った。彼女に言い訳するように、どこか背筋を伸ばして。
「おはよう」
そう言って七海は何事もなかったように私たちに近づいてきた。
「おはようございます。座ってください」
私はそう言って席を開けて、いつも座っている沙織との定位置に戻った。
「ああ、ありがと……」
七海は私を目で追いかけて行く。七海は気を遣ってくれたのかと思って、少し申し訳なさそうにしている。そういうことじゃない、聞きたかったことが聞けたから、体が軽くなっただけだ。
白衣を着た教授がプロジェクターに映し出された実験の概要を説明していく。各テーブルに六名がテーブルについて、後ろには非常勤講師が三人控えている。白で埋め尽くされた実験室はどこか異様な雰囲気だ。
そんな中、私は目の前に置かれたプリントに視線を落として説明を聞きながら寝てしまった。お昼の後の講義は、だいたい眠りの世界に身を置いてしまう。実験科目だから頑張って目を見開いて聞こうと思ったけど、案の定、無理だった。
私の隣に座っている七海は、私の寝息を聞きながらプリントに集中した。手でかろうじて顔が崩れ落ちるのを支えていた私を、七海は少し冷や冷やした様子でプリントに集中しながらも気にしている。
手に少しだけオイルが手に塗られたかのように、顔はテーブルに滑り落ちて着地した。私は痛みで眠りの世界から白がいくつも点在する講義室に引き戻された。
「いたっ……」
思わず声をあげてしまった私は、恐る恐る周囲を見た。幸い、誰にも気づかれなかったようだ。寝ていて、おでこの辺りをテーブルにぶつけていたなんて恥ずかしすぎる。胸を撫で下ろしていると、七海がプリントの端切れにペンを滑らせて『大丈夫?』と書いた。
無言の文字を心の中で読み上げて、私は七海を見た。
私も七海の真似をして、『大丈夫、ありがとう』と書いた。
実験概要の説明が終わると、一五分程度の休憩に入った。
すぐに私は目覚ましに目薬を目に落とした。視界がはっきりして眠気を抹殺してくれた。
少しだけ体を伸ばすと、先に七海がこう話しかけてきた。
「お昼食べた後って、眠たいよね」
私は苦笑いして「うん……寝ていちゃだめだけど」
分かっているけど、睡魔には勝てない。七海のように大学の近くに住むべきかもしれない。お母さんに真面目に検討してもらわないといけないかも。
「でも気持ちは分かるよ」
すかさず七海はフォローを入れた。それに笑顔をつけてくれたから私は居心地がよかった。
「ありがとう……宏紀君と、仲が良い子だよね?」
名前も何も知らないからそういう表現になった。初対面も同然なのに失礼かなって思ってきまりが悪かった。またやってしまった。
「えっ? ああ、そうそう。よく知ってるね」
否定せずにサラリと言いのけた七海に少し驚きながらも、私は褒められたことに対してお礼を言って、「はい……ごめんなさい、じろじろ見てたとか、そういうことじゃないんです……」
「分かっているよ。全然気にしないで」
手を横に振って七海はまたフォローを入れてくれた。
私が話すと、相手に気を遣わせてしまうから話さない方がいい。
「ありがと。名前は何ていうんですか?」
自己紹介をしていなかった。変な雰囲気を払拭してくれる話題があった。
「北川七海です」
「永井未砂です。よろしくお願いします」
改めってそう言った私は、七海に手を差し伸べた。
迷わず七海は手に取ってくれたから、私は安心して笑顔を見せた。
「宏紀ともう友達になったんだね?」
「はい。東京駅で会って、一回だけ一緒に帰ったんです」
「そうなんだ……未砂ちゃんって地元はどこなの?」
「磯子」
「そうなんだ! 私、港南台だよ!」
テンションを一気に跳ね上げて七海は言った。
「じゃあ、宏紀君と同じだね! 親近感湧くね!」
「うん。私たち、中学の同級生だから」
「そうなんだ! だから宏紀君と一緒にいたんだね」
手で口を抑えて私はそう言った。
初日から女子を話していた宏紀を、『やるな』っていう眼差しで見ていたけど、それなら納得がいった。シャイな宏紀が女子を初日から話すわけもないって感じていたから。
「そうそう。ビックリしたけどね」
学科オリエンテーションが終わった後のことを七海は思い出していた。
「そうだよね。大学も学部も学科もね……」
私は七海の笑顔に見とれてしまった。好きになってしまったわけじゃない。でも惹きつけられるような魅力がたくさんつまった笑顔だ。
私は人見知りしないし、誰とでも話ができて、よく『笑顔がかわいいね』って言われてきたけど、七海には負けたって思った。
この笑顔を迎え入れて話す宏紀の姿を思い出す。
こんな表情で話されたら、みんな好きになってしまいそうだ。
「な、なに?」
「ああ、何でもない」
別にやましいことはなかったけど、少し無理に笑顔を作って七海を見た。
「宏紀君って優しい人だね」
「うん、優しいね」
七海は否定せずにそう言った。何か聞きたそうな感じだったけど、七海はうんうんと頷いて共感してくれた。
「ね」
初めて話してくれた時、おばあちゃんに勇気を出して声をかけている姿を思い出す。私を相手するということは、優しい人じゃないと無理かもしれない。そんなことを考えていたら、気が遠くなった。
「なんで? 宏紀に優しくされた?」
七海はもう一つの壁を取り払って私に聞いてきた。聞きたそうな感じは聞きたいに変わったんだろう。
「え? あ、特に何もされてないけど、優しいんだろうなって……」
「そうなんだ……」
あたふたした私を見て、空気を読んでくれたのだろう、それ以上七海は聞かずに私の仕草を楽しんでいる。
「中学の時から、そんな感じだった?」
ごまかそうとして私は聞いたけど、宏紀は優しいに関連する内容で、墓穴を掘ってしまったと思った。それが顔に出ていると思うからすごく恥ずかしい。
「うん。そんな感じだった。みんなの前で表立ってするような優しさじゃなくて、みんなの知らないところでさりげなくする優しさって感じかな」
それならこの前の東京駅での出来事は、宏紀にとっては相当な勇気が必要だ。本人もそう言っていた。だから私から逃げるように駆け足になって姿を隠したんだろう。『さりげない優しさ』という言葉がそばにあれば、宏紀の行動は私の中で腑に落ちる。
「だから人によっては、宏紀の優しさに触れられない人もいるかも」
「どういうこと?」
「仲良くなった人はいいけど、宏紀の優しさに触れずに終わっていくこともあるかも。人と仲良くなるのに時間がかかるタイプだから。仲良くならないと自分をなかなか出さないから」
私は思わずうんうんと首を縦に振って七海の言葉に耳を傾けていた。
七海の宏紀の分析。それはきれいに宏紀と重なるような気がする。
宏紀のことをちゃんと理解している感じがして羨ましかった。中学時代のことがあるとはいえ、私と七海には、宏紀のことという点でははっきりと差があった。
なんだろうこの悔しい気持ちは。別に競っているわけじゃないのに、どうして胸の中にモヤモヤを感じるのだろう。
宏紀が七海に見せた笑顔は、自分を理解してくれるから安心して宏紀を出せるのかもしれないと思った。
「それなら、積極的に話せば、仲良くなれる感じなんだね」
「そうだと思う」
受講生たちが休憩の終了が近づいてくるにつれて、指定の席に着き始めた。
宏紀や真也も戻ってきていた。
悔しさと羨ましさが私の眠気を振り払ってくれた。
七海の隣で頑張って起きていようと、私は意気込んでいた。
今私たちが受けている講義は選択科目で必修ではないから受講しなくてもいい。七海は最初から、無理なスケジュールは組んでいないようだ。
バイトの面接に無事に通り、大学の勉強も忙しくなってくるだろうから、時間を気にせず話ができるのも今ぐらいだと思って、七海は四時限目の講義が終了するぐらいまで話し込んだ。
一人の女の子が『サークル活動に顔を出す』と言って立ちあがると、七海たちも自然にお開きになった。
メインストリートを歩いていく七海。地に足を確実に残しながら歩く。誰かに背中を見られていいように。
バス停の長蛇の列をすいすい追い抜かして、バスの乗車中のランプが消えて、大勢の学生を乗せたバスがのろのろと進み始めた。
吊革につかまって眠そうに窓越しから街を眺める宏紀がいた。
「宏紀だ!」
慌てて七海は宏紀に手を振るけど、宏紀の視線は七海を捉えず行方知らずになっていた。
「ああ、気付かないか」
無視された七海を置き去りしたままバスはそのまま進んでいく。理由は分かっているから気にしなくていい。宏紀は気が付かなかっただけだ。思い切って振った手を静かに戻した。
七海の視線にアパートが映る。でも今日はそのまま通り過ぎて、近くにあるスーパーに向かった。外食やコンビニに頼らず、自分で自炊を頑張ろうと意気込んでいた七海は、早くそれを実行するために足を動かす。
しばらく歩いていくと、一人の男の子の姿が入り込んだ。でも記憶は曖昧で誰かは判別できなかった。信号が赤から青に変わる。男の子の周囲にいる歩行者も同じく横断歩道を渡りはじめる。少し距離があって、七海は渡るか渡らないかを迷っていると、青信号が点滅に切り替わった。もうすぐ赤になる。七海はスニーカーのバネを弾いて黒髪を風で遊ばせながら小走りになった。横断歩道の途中で完全に赤になったけど、七海はなんとか渡り切った。
「もう少し、運動しないと」
少し荒くなった呼吸を整えながら七海はそう漏らした。
前を行っていた男の子と肩を並べると、お互いの視線を交換し合った。
「七海ちゃん」
前を行く男の子は真也だった。私たちと受けていた講義を終えて、アパートに向かう途中だった。
「園田君! 今帰り?」
呼吸が整った七海は少し声を高めて言った。
「うん。終わってすぐに出てきた。四時限目はいなかったよね?」
真也はいたかどうか分からなかったけど、とりあえず話題を振った。黙って歩いていくのは気まずいだろうから。
「私、その時間は講義取ってないの」
「そうなんだ。だからいなかったんだね」
「うん。この辺に住んでるの?」
七海は円を描いて周囲を表して言った。
「あそこに住んでる」
真也が腕を伸ばすと、七海と同じく目と鼻の先にあるアパートだった。
「近いね」
「本当に近い。でも逆に近すぎて遅刻するかもしれない」
真也は冗談のように言った。
「ああ、ギリギリまで寝ちゃうからね」
「そうそう……七海ちゃんもこの辺なの?」
二人でいるのが少し気まずいのか、真也は言葉を失っても質問を投げかけた。宏紀の隣にいた女の子っていうだけで、それ以外に接点はない。
「私もすぐ近くだよ。今からスーパーに行くの」
アパートの場所は言わなかった。微妙な関係性ではこういう風になってしまうだろう。私なら、迷わず場所を示して言っていたかもしれない。
「そうなんだ。自炊してる感じ?」
「これから頑張ろうと思って……」
七海はできるかどうか分からない不安の中を彷徨ように言った。でもどこか目には七海の決意のような瞳も据え置いている。
「頑張ってね!」
「ありがとう」
背伸びをしてお目当ての本に手を伸ばす。私は踏み台を店員さんに貸してもらって本を手にする。お礼を言って去る店員さんを横目に、ペラペラとめくって本の世界に少しだけ足を踏み入れる。
長い通学時間に何かできないかって考えてたどり着いたのが書店だった。
大学に行くときは座ることは百パーセントできないから立ちながら本を開こうと考えたけど、もみくちゃにされながら読む本はどうなんだろうって自問自答した。帰りならなんとか読めるかもしれないけど、疲れて寝ている可能性が高い。もっと言うと、この前のように宏紀と一緒に帰って会話をした方が良い。わざわざ自分の世界に入って、本と戯れる必要があるか。たぶんない。
わざわざ出してきてもらった踏み台を店員さんに返して書店を出た。
特に行くところもなくてJR京浜東北線のホームに向かう。
みんなが誰かに、何かに急かされるように歩いていく、いや、早歩きで目的地に向かっていく。誰とも目を合わさず無表情だ。怒っているのかもしれないって思って、後退りしてしまいそうだ。
その中に紛れ込んで歩く私は、とても浮いているのかもしれない。目が合うと人に笑いかけて、初対面の人でもまるで長年の友達のように接していく。でもここに紛れていると、無理やり自分を変えてでも、無表情を貫き通さないといけない空気が私を窮屈にする。
私って変なのかな……。
人々を眺めるたびに、そう感じてしまう。
大船方面のホームへとつながる階段にさしかかろうとすると、私はいきなりスピードを緩めて立ち止まった。私の至近距離を歩いていた人々が、『いきなり止まるなよ』と言わんばかりの表情を作って、私に鋭い視線を向ける。私はペコっと頭を小さく下げて、行く場所を譲った。
その場に立ち尽くして顔を上げて眺めた景色の中に、宏紀の姿があった。
手すりにつかまって階段を行くおばあちゃんの腕を優しくつかんで、階段をゆっくり上がっていく。宏紀が今、おばあちゃんに何をしているのかすぐに分かった。
この前、駅のホームで話した時の感じを思うと、おばあちゃんからお金を奪おうとかそういうことではないと思う。二人との距離ができると、私も階段をゆっくり上がっていく。まるで見えない線で私たちが繋がれているようだった。
私もだんだん大人になってきたから、それを何も言わずに眺めている。
本当言うと、私も手伝っておばあちゃんと話をしたいけど、しない。これが私の成長した部分だ。もっと言うと、誰かとのコミュニケーションが面倒な時も自ずとでてきた。
宏紀はホームまで到着すると、おばあちゃんに柔和な笑顔を見せて、何やら話している。私の荒んでいく心を正してくれるような力が、柔らかさの中にある。
おばあちゃんは頭を下げて宏紀にお礼を言っているのだろう。宏紀は手を横に振ってただ笑いかけている。口の動きでは、『全然、気にしない下さい』と読めた。
今日の疲れを取ってくれるように体が軽くなって、ふわふわした目で宏紀を見つめていると、ふと宏紀と目が合った。なんか見られている感じが、宏紀にはあったんだろうか。宏紀の視線が私を包んだ綿菓子のようなふわふわ感を取り除いて、背筋を正させた。
宏紀はすぐに視線を外して、おばあちゃんに頭を下げて奥のホームへ逃げるように歩いて行ってしまった。私は距離を詰めたけど、もう宏紀の姿はなかった。ホームには大勢の人々が電車を待つ中、おばあちゃんがぽつりと立っていた。周囲を見渡して、座る場所を探している。
「おばあちゃん、あそこにベンチありますよ」
「ありがとう」
さっきの宏紀の柔らかい笑顔に負けないぐらいの柔らかさに上品さを付け加えたような笑顔だった。それを見ていたら、私も自然に笑顔になっていた。
逃げた、いや気まずい場面を見られてしまった宏紀の心情を考えてみる。目が合って逃げられていい気分はもちろんしないけど、仕方ないかもしれない。この出来事はそこまで気にしなくてもいい。
私のことを、否定せずに話してくれた宏紀に話しかけてみよう。
まずは、磯子へ私を連れて帰ってくれる電車を待とう!
誰もいない講義室。人がいるストレスを感じなくてもいい。軽やかに足を踏み入れると、まずは密閉された窓を開けた。
朝のそよ風を全身で受けて、私は目を閉じてあるがままの私になる。髪の毛をされるままにされても、スカートがめくれても気にしない。今は誰もいない。
静かに目を開けると同時に、心地よかった風も収まって、私をもう相手にしてくれなくなった。
宏紀はもうすぐ来るかな……。
昨日の出来事を思い出すと、自然に笑顔になれる。
宏紀からしたら、恥ずかしい一面を見られてしまったのかもしれない。だから気まずくて自分のことを誰も知らないどこかを求めたのだろう。私、また余計なことしちゃったかもしれない。
でも私が言い訳をするとすれば、周囲にもたくさんの人がいたのに、なんで私に見られるのが嫌なのか。それに悪いところを見たわけではないから逃げ……恥ずかしがらなくてもいい。良いことなら誰かに伝えてあげたい。
ぼんやりと講義室を眺める。こんなにきれいな教室でこれから勉強ができる。また風が吹き始めた。まだまだ眠くて目を閉じる。立ったまま眠ることができそうだ。
私は目を開けて、視界に一人の男の子を捉えた。
静かにドアを開けて、私のはかなくて短い睡眠を破ったのは宏紀だった。
「ああ」
思わず出た言葉と同時に私は頬を緩ませた。
少しだけ作り笑いをぎこちなさそうにしている宏紀は、変なところを見られたなって、思っているのかもしれない。それでもペコっと頭を下げて私に挨拶した。私もつられて頭を動かした。
「おはよう。早いね」
私は宏紀の居心地はいい方ではないと感じたから、ぎこちなさを溶かそうと思った。
「おはよう。永井さんも早いね」
「うん……」
お互いに沈黙になった。それでも私は笑みを絶やさずに宏紀を見続けた。
宏紀は何も言わずに前の席へ足を動かした。まるで、お母さんの大事なものを壊してしまって言えずじまいの子供のように、何にも触れないように慎重に向かった。
定位置とまでは言わないけど、いつもの場所に宏紀はかばんを置いた。
私は宏紀の席の隣に座って、宏紀の横顔を見た。東京駅のホームで見た時も思ったけど、結構イケメンでいつまでも眺めていられそうだ。
「昨日……駅にいた?」
唐突に私は切り出した。このままぎこちなくしているのもだんだん面倒くさくなってきた。悪いことをしたわけじゃないから堂々としていよう。
「いたかな……でも毎日電車に乗っているから……いたかも」
目を逸らして言い訳じみた感じで宏紀は言った。毎日電車に乗るのは知っているって、私は思った。私も磯子から大学に通っているから。
「そっか……おばあちゃんと何を話していたの?」
私は核心をついて言った。もちろん笑顔で話しかけたから嫌な感じはしてないだろう。
「え、何も話してないよ……ただ……」
「ただ……」
興味津々でその言葉の後ろを待つ私。宏紀はどんな答えを用意しているんだろう。
「別に何も話してない」
「おばあちゃんのこと、助けてたんでしょ?」
「え……」
何がそんなに嫌なのかって私は少しイライラしてきた。でも宏紀の優しさには笑顔を添えてあげたいから頬のゆるみはそのままにした。
「なんでごまかすの? 宏紀君、優しいなって思ったよ」
私は宏紀の腕に軽く触れてそう言った。
「ああ……ありがとう」
恥ずかしそうに俯いて宏紀は言った。
「うん。宏紀君は、シャイなの? それなのにおばあちゃんに声をかけるってすごく勇気いるよね?」
興味津々で私は言った。宏紀の性格と行動が一致しないんだ。同じ何かを重ね合わせても違う絵が浮かび上がっている。
「いや、相手はおばあちゃんだから、あのままにはしておけないから……でも勇気が要った」
宏紀の本心が見えて、私は息を噴き出しながら笑顔になれた。胸の中にあったモヤモヤはもう消えてなくなって、隙間に余裕ができた。
「そうだよね」
「でも永井さんなら、難なくできそうだよね?」
前の私なら難なくできたと思う。でも色々な歪みが入り混じって、今は確実にできるかどうかは明言できない。でも宏紀がそんな風に言ってくれたのは、どこか嬉しかった。
「……できると思う」
「うん。なんか想像がついた」
宏紀は脳裏で私の姿を思い描いた。宏紀は私の性格と行動が一致して笑顔を見せた。
「とりあえず、ありがとうって言っておくね。宏紀君、これからも、私と仲良くしてね」
「えっ? ああ……もちろん」
目を丸くして驚きの表情を見せたものの、すぐに宏紀は表情を緩めてそう言った。
「ありがとう」
そこに七海が講義室に入ってきた。
宏紀の隣に席に向かって歩く足元を制止させた。
私と宏紀は後ろを振り返って、七海の表情を迎え入れる。七海は半笑いで私たちを見ている。『お邪魔だったかな』と言わんばかりの表情だった。まるで踏み入れてはいけない領域に何も知らず足音をさらすように。
「あ、おはよう」
宏紀は少し慌て気味で言った。彼女に言い訳するように、どこか背筋を伸ばして。
「おはよう」
そう言って七海は何事もなかったように私たちに近づいてきた。
「おはようございます。座ってください」
私はそう言って席を開けて、いつも座っている沙織との定位置に戻った。
「ああ、ありがと……」
七海は私を目で追いかけて行く。七海は気を遣ってくれたのかと思って、少し申し訳なさそうにしている。そういうことじゃない、聞きたかったことが聞けたから、体が軽くなっただけだ。
白衣を着た教授がプロジェクターに映し出された実験の概要を説明していく。各テーブルに六名がテーブルについて、後ろには非常勤講師が三人控えている。白で埋め尽くされた実験室はどこか異様な雰囲気だ。
そんな中、私は目の前に置かれたプリントに視線を落として説明を聞きながら寝てしまった。お昼の後の講義は、だいたい眠りの世界に身を置いてしまう。実験科目だから頑張って目を見開いて聞こうと思ったけど、案の定、無理だった。
私の隣に座っている七海は、私の寝息を聞きながらプリントに集中した。手でかろうじて顔が崩れ落ちるのを支えていた私を、七海は少し冷や冷やした様子でプリントに集中しながらも気にしている。
手に少しだけオイルが手に塗られたかのように、顔はテーブルに滑り落ちて着地した。私は痛みで眠りの世界から白がいくつも点在する講義室に引き戻された。
「いたっ……」
思わず声をあげてしまった私は、恐る恐る周囲を見た。幸い、誰にも気づかれなかったようだ。寝ていて、おでこの辺りをテーブルにぶつけていたなんて恥ずかしすぎる。胸を撫で下ろしていると、七海がプリントの端切れにペンを滑らせて『大丈夫?』と書いた。
無言の文字を心の中で読み上げて、私は七海を見た。
私も七海の真似をして、『大丈夫、ありがとう』と書いた。
実験概要の説明が終わると、一五分程度の休憩に入った。
すぐに私は目覚ましに目薬を目に落とした。視界がはっきりして眠気を抹殺してくれた。
少しだけ体を伸ばすと、先に七海がこう話しかけてきた。
「お昼食べた後って、眠たいよね」
私は苦笑いして「うん……寝ていちゃだめだけど」
分かっているけど、睡魔には勝てない。七海のように大学の近くに住むべきかもしれない。お母さんに真面目に検討してもらわないといけないかも。
「でも気持ちは分かるよ」
すかさず七海はフォローを入れた。それに笑顔をつけてくれたから私は居心地がよかった。
「ありがとう……宏紀君と、仲が良い子だよね?」
名前も何も知らないからそういう表現になった。初対面も同然なのに失礼かなって思ってきまりが悪かった。またやってしまった。
「えっ? ああ、そうそう。よく知ってるね」
否定せずにサラリと言いのけた七海に少し驚きながらも、私は褒められたことに対してお礼を言って、「はい……ごめんなさい、じろじろ見てたとか、そういうことじゃないんです……」
「分かっているよ。全然気にしないで」
手を横に振って七海はまたフォローを入れてくれた。
私が話すと、相手に気を遣わせてしまうから話さない方がいい。
「ありがと。名前は何ていうんですか?」
自己紹介をしていなかった。変な雰囲気を払拭してくれる話題があった。
「北川七海です」
「永井未砂です。よろしくお願いします」
改めってそう言った私は、七海に手を差し伸べた。
迷わず七海は手に取ってくれたから、私は安心して笑顔を見せた。
「宏紀ともう友達になったんだね?」
「はい。東京駅で会って、一回だけ一緒に帰ったんです」
「そうなんだ……未砂ちゃんって地元はどこなの?」
「磯子」
「そうなんだ! 私、港南台だよ!」
テンションを一気に跳ね上げて七海は言った。
「じゃあ、宏紀君と同じだね! 親近感湧くね!」
「うん。私たち、中学の同級生だから」
「そうなんだ! だから宏紀君と一緒にいたんだね」
手で口を抑えて私はそう言った。
初日から女子を話していた宏紀を、『やるな』っていう眼差しで見ていたけど、それなら納得がいった。シャイな宏紀が女子を初日から話すわけもないって感じていたから。
「そうそう。ビックリしたけどね」
学科オリエンテーションが終わった後のことを七海は思い出していた。
「そうだよね。大学も学部も学科もね……」
私は七海の笑顔に見とれてしまった。好きになってしまったわけじゃない。でも惹きつけられるような魅力がたくさんつまった笑顔だ。
私は人見知りしないし、誰とでも話ができて、よく『笑顔がかわいいね』って言われてきたけど、七海には負けたって思った。
この笑顔を迎え入れて話す宏紀の姿を思い出す。
こんな表情で話されたら、みんな好きになってしまいそうだ。
「な、なに?」
「ああ、何でもない」
別にやましいことはなかったけど、少し無理に笑顔を作って七海を見た。
「宏紀君って優しい人だね」
「うん、優しいね」
七海は否定せずにそう言った。何か聞きたそうな感じだったけど、七海はうんうんと頷いて共感してくれた。
「ね」
初めて話してくれた時、おばあちゃんに勇気を出して声をかけている姿を思い出す。私を相手するということは、優しい人じゃないと無理かもしれない。そんなことを考えていたら、気が遠くなった。
「なんで? 宏紀に優しくされた?」
七海はもう一つの壁を取り払って私に聞いてきた。聞きたそうな感じは聞きたいに変わったんだろう。
「え? あ、特に何もされてないけど、優しいんだろうなって……」
「そうなんだ……」
あたふたした私を見て、空気を読んでくれたのだろう、それ以上七海は聞かずに私の仕草を楽しんでいる。
「中学の時から、そんな感じだった?」
ごまかそうとして私は聞いたけど、宏紀は優しいに関連する内容で、墓穴を掘ってしまったと思った。それが顔に出ていると思うからすごく恥ずかしい。
「うん。そんな感じだった。みんなの前で表立ってするような優しさじゃなくて、みんなの知らないところでさりげなくする優しさって感じかな」
それならこの前の東京駅での出来事は、宏紀にとっては相当な勇気が必要だ。本人もそう言っていた。だから私から逃げるように駆け足になって姿を隠したんだろう。『さりげない優しさ』という言葉がそばにあれば、宏紀の行動は私の中で腑に落ちる。
「だから人によっては、宏紀の優しさに触れられない人もいるかも」
「どういうこと?」
「仲良くなった人はいいけど、宏紀の優しさに触れずに終わっていくこともあるかも。人と仲良くなるのに時間がかかるタイプだから。仲良くならないと自分をなかなか出さないから」
私は思わずうんうんと首を縦に振って七海の言葉に耳を傾けていた。
七海の宏紀の分析。それはきれいに宏紀と重なるような気がする。
宏紀のことをちゃんと理解している感じがして羨ましかった。中学時代のことがあるとはいえ、私と七海には、宏紀のことという点でははっきりと差があった。
なんだろうこの悔しい気持ちは。別に競っているわけじゃないのに、どうして胸の中にモヤモヤを感じるのだろう。
宏紀が七海に見せた笑顔は、自分を理解してくれるから安心して宏紀を出せるのかもしれないと思った。
「それなら、積極的に話せば、仲良くなれる感じなんだね」
「そうだと思う」
受講生たちが休憩の終了が近づいてくるにつれて、指定の席に着き始めた。
宏紀や真也も戻ってきていた。
悔しさと羨ましさが私の眠気を振り払ってくれた。
七海の隣で頑張って起きていようと、私は意気込んでいた。