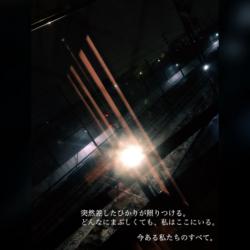雲一つない快晴の青空に挨拶するって変な人に見えるだろうか。でも今はそんなことは気にしない。何を思われてもいい。今は自分が思ったことを思いっきりやりたい。人に迷惑をかけなければいいぐらいに思っている。
今日は大学には行かず、大学の周辺を行き来している。緑が丘大学に毎日通っているけど、大学から外は出たことがないから未知の領域だった。一度、宏紀の腕を引っ張って歩いたぐらいだ。でもただバスが通っている道を二人でなぞっただけだ。
本当は家から出ないようにしようと思った。大学の近くまで行けば、大学に引き寄せられてしまいそうだったから。沙織にも会えるし、両親に悪いから頑張って勉強しようって思ってしまう。
でも気がついたら家を出ていた。一日中家に引きこもっていることは、私にはできなかった。昔から人と会うのが大好きで、どんな人でも隔てなく仲良くするのが得意だった。前にも言ったけど、友達に『目が合うと笑ってくれるから安心する』って言われたのが私の誇り。
そんな私を認めてくれた宏紀。人によっては『ただの八方美人』って言われることもあったから自分をうまく出せなくなっていった。だから頬がおかしくなるぐらい無理に笑ったことや、ハイテンションで口数が多くなることがあった。どの笑顔が自分のものなのか、分からなくなってしまうことって本当にあるんだって、唖然とした。私の好きな歌手が歌詞にそう書いていた。それが尾を引いて、自分を否定し始めた。私は変な人だって。だから人と距離を置いて、積極的にコミュニケーションを取ることを私なりに控えていった。みんなは私の変化には気づいていないと思う。
それを真っ向から否定してくれた。それが宏紀だった。むしろ、本当の私を大事にした方がいいって。目を閉じると自ずと涙があふれてしまうぐらい嬉しかった。大事なことに気付かせてくれた宏紀が大好きだ。
だから私は、ただ宏紀のそばにいたい。
昨日伝えたかった言葉はこれだった。口から飛び出すことを恐れて居座っていた言葉。
でもあの時は言えなかった。言っても意味がないって思ったんだと思う。
宏紀が苦しもうが何をしようが、私はただ目を閉じて静観していればいいのなら、そうする。
私は宏紀の今を理解しているつもりだけど、そもそも宏紀がそんな状況で苦しんでいるかもどうかも分からない。宏紀が七海を好きかも分からない。真也が七海を好きかどうかも分からない。ただの私の妄想だってすべてを片付けてしまえば、楽になれる。宏紀なんてどうでもいいって。割り切ってしまえばいい……。
でもそれができないんだ。私にはできないんだ。
宏紀のことを考えていると涙が溢れてくる。私のしていたことを『いやがらせ』と形容されると、もう何もできなくなってしまう。人なんて本当に無力だ。何もできないならおとなしくしてればいい。何もできないなら。
大学周辺を歩いていくと閑静な住宅街が広がっている。道と道の間から子供たちが飛び出して、大きな木々が揺れて私に挨拶してくれているようだ。木々の隙間から漏れた太陽光線が私を照らす。歩いていくと坂が見えてきた。今日はパンプスではなくスニーカーを履いているから坂も難なく上がれるだろう。坂を登りきると、私たちが通っている大学や新浦安駅、きれいな街並みが見える。この街を寂しい思い出にしたくない。これから四年間通うんだ。今の晴れない気持ちはどこかに置き去りにして、前を向くんだ。
言葉にすると簡単なことがどれだけ難しいか。
立派になったつもりで街を見下ろした後、坂を下っていく。
これからどんな顔して宏紀に向き合えばいいのか。そんないきなり打って変わって宏紀と距離を置くなんてあからさまで気が引ける。かといって、今まで通りに接することができるかどうか。幸い、明日と明後日は週末だから大学は休みだ。どうやって接すればいいか考える余裕はある。宏紀もきっと、こんな感じで真也の気持ちを聞いた後の週末を迎えていたんだと思う。
坂を下りて、しばらくまた歩いていくと、新浦安駅まで歩いたときに通りかかった橋が見えてきた。少しだけ駆け足になって橋に着くと、手すりに身を任せて目を閉じる。また以前と同じように水の音を拾う。今の私に必要なのは心を穏やかにしてくれる癒しだ。今日は快晴の空が川の音色を作り上げるお手伝いをしてくれる。だから夕焼けのオレンジ色じゃなくてもいい。
私は目を開けた。車が通る音に邪魔されたのか。違う。それとも誰かに声をかけられたのか。それも違う。
川の下で水しぶきがした。私の癒しの時間を取り上げられて、不満気な顔で身を乗り出すと、下で石を投げている男の子がいた。ゆるやかに流れる川に反抗するように石を投じた。
男の子は宏紀だった。
訳が分からず思わず時間を見た。今はみんなが学生で埋もれている学生食堂でお昼ご飯を食べている最中で、第三時限目がある学生は眠気を持ったまま講義室に行く時間帯だ。なんであそこに宏紀がいるんだろう。
宏紀がまた一石を投じた。力なく弾け飛んだ水はまた川のものとして流れていく。その音でさえ、私にはちゃんと聞こえている。でも音からは宏紀の感情まで分からない。
私は宏紀の背中が見える位置に移動した。ここからなら、宏紀の様子を眺めることができる。胸の動悸が内側からポンポンと叩いてくる。宏紀に近づきたいけどできない。スニーカーの裏に接着剤が塗られているかのように動かない。やっぱり昨日のことを気にしているんだ。私はここで静観して、ただ見守ってあげる方がいいんだろうか。もう私はどうしたら正解なのか分からない。答えは一体、誰が知っているんだ。
宏紀がその場でしゃがみこんだ。川のそばで太陽の光を避けるように日陰で体を丸くしている。私には宏紀が体を震わせているように見える……。
行かない方がいい。行っても何もできない。宏紀を外から暖めることができるものもないし、そんな包容力はない。まだまだ十九歳。無力さを目の当たりにするだけだ。宏紀に背を向ける。このまま会わなかったことにすればいい。どうせスニーカーは接着剤がついている。何もしない……。
目の前に広がった景色に宏紀はいない。私にできることはない……。
言い聞かせるように繰り返す。
でもなぜ宏紀はあそこにいるんだろう。私と同じように大学に行く気になれなかったのか。もう耐えられず、講義の途中でまた大学を飛び出してきたのか。ランチを買いに行くふりをしてわざわざここまで来たのか。
目をギュッとしっかり閉じる。宏紀がここに来た理由なんてどうでもいい。行くんだ。この先の道のりを行くんだ。宏紀が視界にいなければ、普通に歩いていけるはず。
宏紀のことをもう一度見てみる……変わらずしゃがみこんで震える宏紀がいる。
放っておけるはずがない。接着剤がついているなら、私がスニーカーを脱げばいい。揺るぎない決意を持って下に降りていく。もしもまた気持ちが揺らされるようならまたその場で立ち止まって考えればいい。とにかく宏紀のそばに行くんだ。
水でぬかるんだ道を行くようにゆっくりと宏紀と距離を詰める。だんだん宏紀の体が大きくなってくる。
「宏紀!」
体を回転させて宏紀は私を視界に捉えた。
宏紀の頬が濡れている。体を震わせていたのは寒かったからではなく、涙のせいだった。もう抱えきれずに宏紀の溜め込んだ気持ちは涙に変わった。取り留めもなく流れ落ちるんだ。
宏紀はすぐさまもとの姿勢に戻して涙を拭き取った。一度拭き取っただけでもとに戻るならそれでいいけど、それだけで涙は止まるのか。
「真也と……喧嘩しちゃってさ……」
宏紀が語りだした。聞き手は川ではなく私だけど、こっちを向いてくれてない。
「こんなはずじゃなかった……もっと……」
宏紀は喉に何かを詰まらしたのかひどく咳き込んだ。
「頑張ろ……」
宏紀は背中に何かを感じた。ほんの一部だけだけど温かみを感じているだろう。私が宏紀のそばで背中をさすった。気がついたらこうしていた。誰に手を引かれたかは分からない。これは私の精いっぱいの慰めだった。宏紀は少しだけ後ろをみて私を確認した。
「もういい」
「……」
「もういいから。何も言わなくていい。全部知ってるから」
「……知ってるって?」
宏紀は私を直視した。でも私は宏紀の顔が見られなかった。再び流れ出した宏紀の涙をハンカチで拭いていくことに集中する。ハンドクリームを塗っている時のように、集中できる何かがあれば私は私でいられる。
「全部知ってる」
「真也のこと?」
「うん」
「どうして?」
宏紀が瞬きをした瞬間に流れ落ちた新たな涙が宏紀の膝に落ちた。
「……宏紀が大好きだから」
ようやく目を合わせることができた私も涙が溢れ出てきた。涙ってこんなに急に出てくるものなんだろうって不思議なくらいに。
「何だよ、それ」
宏紀は小さく笑った。私はそれが嬉しくて宏紀の真似をするわけじゃないけど、少しだけ笑った。
「辛かったよね?」
宏紀は静かに頷いた。
「分かるよ……私も辛くて寂しくて。ただ……」
「ただ……」
昨日の続きをするかのように台詞が出てきた。いいところで終わったドラマのように、続きが気になって宏紀は私の言葉を繰り返した。
「ただ、宏紀のそばにいようって思ってた」
「昨日、そう言おうとしてたの?」
宏紀と目を逸らして頷いた。こんな恥ずかしいセリフ、目を見て言えなかった。
「……ごめんね、昨日は。あんな言い方して」
「ううん。私がしつこくしたのが悪かったから、気にしないで」
胸の内側を見るとまだ奥深くまで刺さった傷がある。でも宏紀に謝られると許してしまう。宏紀って、何かあればちゃんと謝ってくるから。だから私の心は最大限に温められて何も言えなくなる。
「それでこうやって慰めてもらってるんだから、嫌な男だね」
「本当だよ! 宏紀って嫌な男!」
「ごめん……」
最大限に落ちたトーンで宏紀は謝った。宏紀がそんなに真面目に返すと思わなくて私は、「冗談だよ」
涙の跡をしっかり残して宏紀は砂利石を見つめている。していいか分からなかったけど、私は勢いで宏紀を抱きしめた。
「ありがとう、未砂」
私は何も言わずに首を横に振った。
宏紀も私を受け入れてくれたのか、手を私の背中に置いた。
「手、見せて」
一時的に宏紀から離れて手を見ると、案の定、カサカサの手をしていた。背中に触れた時に乾いた皮膚の突起で分かった。
私はまたハンドクリームを取り出した。
「未砂……」
宏紀はそう言って、ポケットに身を潜めた小さいハンドクリームを私に見せた。
「おお、買ったの?」
「うん……これ、貸してくれたよね? 今度返すよ」
「うん。宏紀は大きいやつを買った方がいい。すぐになくなっちゃう」
宏紀の新品よりも、今は私のハンドクリームで潤いを与えてあげたい。
「お腹空いた……」
そう呟く宏紀に、「お昼食べてないの?」
「うん……すぐに飛び出してきたから。未砂はお腹空いてる?」
「うん」
「じゃあ、何か食べようか」
私は宏紀のハンドクリームに覆われた両手を取って立ち上がった。ぬるぬるしているけど、別に気にしない。宏紀がしっかり立てるまで、ハンドクリームの温もりを分けてほしい。
データ分析室から担当教授の声が漏れる。ということは午後からも使用中になっているから中には入れない。宏紀は細心の注意を払って少しだけドアを開けてみる。宏紀が座っていた場所にはもう別の学生が座っている。宏紀が置き去りにした荷物はなさそうだ。
もしかしたら七海たちが持っているかもしれない。
私も宏紀と同じ景色を確認すると、データ分析室の隣にある資料室のドアを開けた。中にスタッフが二人いて、遅めのランチタイムに入っていた。
「すいません」
「はい」
二人のうちの一人の女性スタッフが振り向いて、口をもぐもぐしながら振り向いた。タイミングが悪いとは思ったけど、探しものだから勘弁してほしい。スマホや財布も入っているだろうから宏紀も気が気でないと思う。宏紀もよくそんな大事なものを置いてきぼりにできたと思っているだろう。それだけ追い詰められていたということだろうか。
私が尋ねてくれているのを聞いた宏紀が、「ありがとう」と言った。それに続けて、「自分で聞くよ。隣のデータ分析室にかばんの忘れ物はなかったですか?」
「ああ」
そう言ってすぐさま立ち上がった。きっと心当たりがあるんだろう。宏紀がここを飛び出して戻ってくるまでに時間が経っていないからすぐに認知できたみたいだ。
「お願いします」
「これですか?」
「これです。ありがとうございます」
宏紀は大事そうに抱えた。
「いえいえ」
これ以上お昼休憩を邪魔するのも気が引けた私たちは、すぐに資料室を後にした。
「よかったね、見つかって」
「うん、ありがとう」
宏紀は念のため中身を確認している。スマホや財布が入っていたんだから当然だ。
「たぶん、七海たちがここに預けてくれたんだと思う」
「たぶんそうだろうね。優しいね」
今宏紀のかばんを七海たちの誰かが持っていても、宏紀の手元に戻らないっていう判断だったんだろう。
「うん……本当に……」
「ねぇ、宏紀、お腹空いたからご飯食べよう!」
「うん」
「今日はもう講義出ないでしょ? どこかに遊びに行こう!」
「そうだね。行こうか」
「うん」
こういう理由で講義を欠席するのはこれが最後にしたい。両親のお金をわざわざ誰もいない場所にばらまくことはないから。でも今日ぐらい、許してくれるだろう。
私は笑顔を見せる。宏紀も笑っている。
「もうお腹空いた!」
私たちは生活環境学部の建物を飛び出して、メインストリートにかけだしていった。
講義中だから人気は少ないから、わがもの顔でここを駆け抜けよう。
宏紀の新しい顔なのかと思った。
自分の気持ちを少なからず外に出したからか、何か吹っ切れたようにお昼ご飯、私が連れていった服屋さん、本屋さんでも見せたことのない表情だった。
お昼ご飯はお金のことを考えて、ファミリーレストランで食べた。宏紀が意外にたくさん食べることが分かった。私が頼みすぎて食べきれなかったご飯もすべて平らげてくれた。一生懸命食べている感じが微笑ましくて見とれていると、「これ食べたいの?」って宏紀に聞かれた。確かに宏紀が食べていると、美味しそうに感じた。
服屋さんは前にも沙織と一緒に行ったみなとみらいのモールに行った。最初は何も買わずにウインドウショッピングしながら楽しもうと思ったけど、夏に向けた新作も入ってきていて花柄でネイビーのワンピースの話でお店の店員さんと盛り上がった。暇そうにしていた宏紀に、私に似合う服を探してって指示を出したら、グリーンのカーディガンを持ってきた。
「宏紀ってこういうのが好きなんだ」
「違うよ。このワンピースに合うかなと思っただけ」
「照れるなよ、宏紀。私もこれ好き!」
手持ちがなかったから気に入った新作のワンピースと宏紀が選んでくれたグリーンのカーディガンを取り置きしてもらって、後日お母さんと来ることになった。
そのままの勢いで本屋さんに降りていくと、小説やビジネス本を一緒に眺めた。宏紀も通学時間を有効活用したいらしくて『本を読む』って言う選択肢が頭にあった。以前、私も本を見に来たけど、その時はあまり乗り気にならなかった。お互いに本を買って貸しあいをすればいいかなって思った。それを提案したら、宏紀も乗ってきてくれた。基本的に宏紀は否定しないから言いやすい。私は『早起き』に関する本と、宏紀は『高校生』の青春群像劇みたいな小説を持ってきた。表紙の絵柄がきれいすぎて手に取ったらしい。一人の女子高校生が教室から何かを眺めている絵柄だった。眺めている先にはいとおしい人がいるのか。
時間も気にせずに遊びまわっていたら夕食の時間になっていたから、ファストフードのハンバーガーショップに入って空腹を満たし、時間を共にした。「時間は経つのは早い」という言葉のままに次は八時ぐらい時刻を目にした。私たちは横浜駅に戻って帰ることにした。
横浜駅で大船行きの電車に乗り込んで二名がけの座席に座った。
あっという間に過ぎ去った時間。もうすぐ別れの時がやってくる。なにも永遠に別れるわけじゃない。来週の月曜日は祝日だから火曜日に大学に行けば、また宏紀に会える。
「今日はありがとう」
宏紀が唐突に小さく笑って言った。
「こちらこそ」
電車に乗ってからお互いに黙っていた私たちの沈黙を宏紀は破った。まさか宏紀がこの静けさに終止符を打つとは思わなかった。昨日の出来事に後ろめたさを感じているのかもしれない。気を遣ってくれているんだろう。ここまでしてもらっておいて、という気持ちが宏紀の行動を促している。
今見せてくれている笑顔は偽物に過ぎないのか。
現実に背を向けるかのように、不意に外の景色に視線を送る。見慣れた景色が広がってくる。ここからどこに何があるかだいたい説明できる。私の住んでいる磯子だ。
何だろう。この不安な気持ちは。
「もうすぐ磯子だね」
「うん……」
電車が速度を緩めて磯子駅の定位置に辿り着こうとしている。
本当なら座席から立ち上がって出入り口の前で待機するだろうけど、私は頑なに宏紀のそばにいる。
電車が磯子駅の定位置に着いた。プシューという音がドア開扉を知らせてくれた。でも今の私には余計な気遣いでしかない。俯いてただドアが閉まるのを待っている私。そんな私を横目で捉えても何も言わずに宏紀は同じ時を過ごしてくれている。
「未砂……」
今はそっとしておいてほしい。
次はプシューという音は完全にドアが閉まったことを伝えた。そしてまたゆっくりと速度を上げて進み始めた。
ただならぬ私の雰囲気に飲み込まれる形で「未砂……家、来る?」
私は顔を上げて宏紀を見た。
「もう磯子は過ぎちゃったし……そんな大した家じゃないけど」
表情を徐々に緩めて私は「うん」と頷いた。
「ごめんね」
港南台駅について、信号待ちをしている時に私は宏紀の横顔を見つめた。
「いいよ。気にしないで。ここから五分ぐらいだから」
「うん」
宏紀の家に行くのは初めてだから緊張するけど、宏紀の笑みがそれを緩和してくれる。宏紀の涙を見て以来、真也とのことの真相は聞かなかった。私たちが笑顔でいられるなら、聞く必要なんてないって思った。事故的ではあったけど、宏紀と距離を縮めることができた。ここはちゃんと宏紀のことを理解する必要があるような気がする。今までの私の推測ではなくて、宏紀から語られる宏紀の今を。
「未砂は、港南台に来ることあるの?」
私がまた黙ったままだったから宏紀が話しかけてくれたんだろう。
「あんまり来ないかな」
「だよね。僕も住んでいなかったら来ないと思う」
「宏紀……聞きたいことがあるの」
「何?」
宏紀の腕を掴んでその場で制止させた。歩きながら聞くのはなんか違う気がした。宏紀の言葉をちゃんと噛みしめる必要があるって勝手に思ったんだ。
「真也君と、何があったの?」
川のほとりで話して以来、一点の曇りもなかった宏紀の表情に霧がたちこめてきて、視線が足元に落ちていった。
「こうやって聞くのは、宏紀の今を知りたいの。多分、私が思っていた状況と同じだと思うけど、それにズレがあったら嫌だなって……」
私は宏紀の手を取った。宏紀のことを知っていれば私にできるは必ずあるはずだから。情報を共有しても宏紀はこれからも苦しめられるだけかもしれないけど。
「ありがとう」
「もちろん、嫌だったら言わなくていい。私も、何も言わなくていいって言ったから……」
うつむいたまま戻ってこない宏紀。受け入れがたい出来事だったことは明らかだけど、目の前に映し出すとなると恐怖で圧倒されてしまいそうだ。でも二人で分け合えばなんとかなるかもしれない。
真也と家電量販店に出かけた時に、ほのめかした真也の気持ち。まさか七海への気持ちだったとは宏紀は思いもしなかったらしい。だから宏紀は喜んで真也の役に立ちたいって思ったんだろう。
週末が開けた月曜日の朝。その日は肌寒い一日だった。朝晩は冷えるのは知っていたけど、日中でさえもう一枚羽織りたくなった。真也が生活環境学部のそばにあるベンチで、来ているジャケットのポケットに両手を忍ばせながら座っていた。重い雰囲気ではなくそれは真面目であまりにも一途な瞳が地面を断続的に打ちつけられていた。
そこに宏紀は出くわした。通学時間帯が早い宏紀を真也は待っていたのかもしれない。
まだ会って間もないだけに目にしたことがなかった真面目な眼差し。宏紀は何かに導かれるように、既定路線をただひた走るように、真也にこう尋ねた。
「どうした? 何かあった?」
真也はすぐに答えはしなかった。そう、私が沙織に宏紀への気持ちを吐露した時のように。自分の気持ちを整理するように、ひとつひとつの言葉を手に取って外に出す準備を整えた。
横を向いて真也の表情を確認した宏紀。最初に尋ねた時と変わりない、凍り付いたような真也がいた。触れれば宏紀さえも凍ってしまいそうでそっとしておいた。朝の貴重な時間が意味もなくどこかへ放浪していく。宏紀はあからさまではないけど、苛立ちを顔に張り付かせた。
「悪い……」
宏紀の仕草で苛立ちが可視化できたのか、真也はそう謝ってきた。
「いいよ。何か、大切なことなのかなって」
そう言って宏紀は顔に張り付かせた苛立ちを取り除いた。
「宏紀……」
「ん? 何? そんな大事なことなの? 何か助けられることがあったらやるけど」
「僕、七海ちゃんが好きだ……」
宏紀の柔らかい表情が警戒心に支配されたものに急変した。入ってくる言葉をすべて遮断して、かけた気遣いの言葉も真也への言葉もすべて抹殺したくなった。
真也が七海を『好きだ』って言った。
実際に宏紀の体は硬直していくけど、心の世界では小刻みに首を振る。
いや違う。きっと聞き間違いだ。このセリフを宏紀は何度も反芻した。
いや、そうであってほしい。繰り返すうちに懇願にも似たものに変わった。
「今……なんて……」
「七海ちゃんが好きだ」
二度目は書いた作文を確認するかのように、念には念を入れるように、真也は神妙な表情を崩さずに言った。
宏紀はその時、とてつもない恐怖に顔面を殴られた。これからの四年間を根底からすべてを覆されて壊されていく様子をただ単に眺めるしかできなくなった。身動きも取れずにただそこにいるだけだった。
「七海ちゃんって彼氏いるのかな? いそうだな」
そう問いかけられた宏紀は警戒心の塊になった。
七海に彼氏がいないことは知っている。もっと言うと、過去の恋愛を引きずって七海なりに今を頑張ろうとしていることも。
「そういう話はしないからな……」
宏紀はそう言ってお茶を濁した。ただ言いたくなかった。雁字搦めになった思考は止められずに心はカチカチのままだ。
この状況の中で七海や真也へのかかわり方を迫られることになった。混乱と失意のなかで七海への好意をはぎ取らざる終えない状況になった。
カチューシャのことも、缶コーヒーのことも私は聞いた。それらは私の推測ときれいに重なった。
カチューシャはやっぱり真也や七海のことが気になって、会話がまともに入ってこなかったらしい。自分を取り繕うのに精いっぱいだった。
缶コーヒーも二人から逃れるためにたまたまコンビニに行ったときに意味もなく買っただけだった。何かを買いに行っていたという口実があれば、何でもよかったのだろう。菓子パンでもガムでも。
「でも、僕が悪い……」
宏紀がつぶやいた言葉に私の胸は力いっぱい掴まれて破裂しそうになった。あともう少し。少しでも力が加われば、血が噴き出して流れ落ちただろう。
宏紀の真意は、真也と戦わずに七海への気持ちを振り払ってしまったことへの後悔だった。自分の気持ちをちゃんと伝えられなかった情けなさ。この二つの気持ちに両サイドから責められて宏紀は疲弊していった。
「未砂……聞いてくれてありがとう」
「全然いいよ。私ね……さっき電車を降りるのが怖かったんだ」
宏紀は無言で私に耳を傾けた。
「このまま帰ったら、また宏紀が宏紀じゃなくなってしまうかもって思ったら、心配でたまらなくて……私がそばにいる」
宏紀はうんうんと相槌を打った。
私は宏紀の反応が怖くて顔をすぐに見られなかった。
宏紀は少しだけ距離を詰めて、私を抱きしめてくれた。
「ありがとう……」
私は宏紀の手を握った。ハンドクリームで保湿がされていてなめらかな手だった。手に温もりに安心したのか、私は目を閉じて宏紀の胸板に身を任せた。
「未砂……もう夜遅いから帰ろうか」
「うん」
宏紀に抱きしめられて私は活力をもらったみたいだ。
「家まで送っていくよ」
「本当に?」
「うん。結局、家、行かなかったね」
「だね。でもまた今度行きたいな」
「分かった。ちゃんと掃除しておく」
宏紀は家に帰ると車のキーを手にして再び出てきた。
少しだけお母さんの声も聞こえてきた。なんだか宏紀と同じように穏やかで挨拶したくなって少し離れたドア越しで声を出した。
「こんな遅くに申し訳ありません」
「いえ、大学の方ですか?」
「はい。これからもよろしくお願います」
宏紀は恥ずかしそうに私たちのやり取りを見ていた。きっと早く会話を終わらせてほしかったんだろう。気持ちは分かるけど、これからのこともあるから。
私たちは車に乗り込んで磯子駅に向かった。
車を運転している姿でさえ、私には新鮮で宏紀をしばらく見つめてしまった。
「はぁ、なんか今日は怒ったり、泣いたり、笑ったりいろんなことがあったな」
サイドミラーを見つめながらそう呟く宏紀に私は「色々あったんだから仕方ないよ」
しばらく道なりを行くと、あっという間に磯子駅のロータリーに到着した。
「ここでいいの? 夜遅いから家の前まで行くよ」
「いいよ、ここで。もう歩いてすぐだし。ありがとう」
私は車を降りて手を振る。
「じゃあ、また来週」
「うん」
私は車から離れていく。でも歩く速度は安定しなくて立ち止まった。
「宏紀、週末って何するの?」
世間は明日から三連休だ。
「何もない。どうして?」
「じゃあさ、遠くに行こう! 何もかも忘れて楽しもうよ!」
「うん。行こうか!」
私は噛みしめるように嬉しさを体中で受け止めて、「じゃあ、明日の十二時に磯子駅に来て! 来れそう?」
「うん。大丈夫」
「じゃあまた明日」
週末も宏紀と一緒にいたい。わがままかもしれないけど一緒にいたい。宏紀の穏やかな笑顔を見ていると私も嬉しくなるから。
今日は大学には行かず、大学の周辺を行き来している。緑が丘大学に毎日通っているけど、大学から外は出たことがないから未知の領域だった。一度、宏紀の腕を引っ張って歩いたぐらいだ。でもただバスが通っている道を二人でなぞっただけだ。
本当は家から出ないようにしようと思った。大学の近くまで行けば、大学に引き寄せられてしまいそうだったから。沙織にも会えるし、両親に悪いから頑張って勉強しようって思ってしまう。
でも気がついたら家を出ていた。一日中家に引きこもっていることは、私にはできなかった。昔から人と会うのが大好きで、どんな人でも隔てなく仲良くするのが得意だった。前にも言ったけど、友達に『目が合うと笑ってくれるから安心する』って言われたのが私の誇り。
そんな私を認めてくれた宏紀。人によっては『ただの八方美人』って言われることもあったから自分をうまく出せなくなっていった。だから頬がおかしくなるぐらい無理に笑ったことや、ハイテンションで口数が多くなることがあった。どの笑顔が自分のものなのか、分からなくなってしまうことって本当にあるんだって、唖然とした。私の好きな歌手が歌詞にそう書いていた。それが尾を引いて、自分を否定し始めた。私は変な人だって。だから人と距離を置いて、積極的にコミュニケーションを取ることを私なりに控えていった。みんなは私の変化には気づいていないと思う。
それを真っ向から否定してくれた。それが宏紀だった。むしろ、本当の私を大事にした方がいいって。目を閉じると自ずと涙があふれてしまうぐらい嬉しかった。大事なことに気付かせてくれた宏紀が大好きだ。
だから私は、ただ宏紀のそばにいたい。
昨日伝えたかった言葉はこれだった。口から飛び出すことを恐れて居座っていた言葉。
でもあの時は言えなかった。言っても意味がないって思ったんだと思う。
宏紀が苦しもうが何をしようが、私はただ目を閉じて静観していればいいのなら、そうする。
私は宏紀の今を理解しているつもりだけど、そもそも宏紀がそんな状況で苦しんでいるかもどうかも分からない。宏紀が七海を好きかも分からない。真也が七海を好きかどうかも分からない。ただの私の妄想だってすべてを片付けてしまえば、楽になれる。宏紀なんてどうでもいいって。割り切ってしまえばいい……。
でもそれができないんだ。私にはできないんだ。
宏紀のことを考えていると涙が溢れてくる。私のしていたことを『いやがらせ』と形容されると、もう何もできなくなってしまう。人なんて本当に無力だ。何もできないならおとなしくしてればいい。何もできないなら。
大学周辺を歩いていくと閑静な住宅街が広がっている。道と道の間から子供たちが飛び出して、大きな木々が揺れて私に挨拶してくれているようだ。木々の隙間から漏れた太陽光線が私を照らす。歩いていくと坂が見えてきた。今日はパンプスではなくスニーカーを履いているから坂も難なく上がれるだろう。坂を登りきると、私たちが通っている大学や新浦安駅、きれいな街並みが見える。この街を寂しい思い出にしたくない。これから四年間通うんだ。今の晴れない気持ちはどこかに置き去りにして、前を向くんだ。
言葉にすると簡単なことがどれだけ難しいか。
立派になったつもりで街を見下ろした後、坂を下っていく。
これからどんな顔して宏紀に向き合えばいいのか。そんないきなり打って変わって宏紀と距離を置くなんてあからさまで気が引ける。かといって、今まで通りに接することができるかどうか。幸い、明日と明後日は週末だから大学は休みだ。どうやって接すればいいか考える余裕はある。宏紀もきっと、こんな感じで真也の気持ちを聞いた後の週末を迎えていたんだと思う。
坂を下りて、しばらくまた歩いていくと、新浦安駅まで歩いたときに通りかかった橋が見えてきた。少しだけ駆け足になって橋に着くと、手すりに身を任せて目を閉じる。また以前と同じように水の音を拾う。今の私に必要なのは心を穏やかにしてくれる癒しだ。今日は快晴の空が川の音色を作り上げるお手伝いをしてくれる。だから夕焼けのオレンジ色じゃなくてもいい。
私は目を開けた。車が通る音に邪魔されたのか。違う。それとも誰かに声をかけられたのか。それも違う。
川の下で水しぶきがした。私の癒しの時間を取り上げられて、不満気な顔で身を乗り出すと、下で石を投げている男の子がいた。ゆるやかに流れる川に反抗するように石を投じた。
男の子は宏紀だった。
訳が分からず思わず時間を見た。今はみんなが学生で埋もれている学生食堂でお昼ご飯を食べている最中で、第三時限目がある学生は眠気を持ったまま講義室に行く時間帯だ。なんであそこに宏紀がいるんだろう。
宏紀がまた一石を投じた。力なく弾け飛んだ水はまた川のものとして流れていく。その音でさえ、私にはちゃんと聞こえている。でも音からは宏紀の感情まで分からない。
私は宏紀の背中が見える位置に移動した。ここからなら、宏紀の様子を眺めることができる。胸の動悸が内側からポンポンと叩いてくる。宏紀に近づきたいけどできない。スニーカーの裏に接着剤が塗られているかのように動かない。やっぱり昨日のことを気にしているんだ。私はここで静観して、ただ見守ってあげる方がいいんだろうか。もう私はどうしたら正解なのか分からない。答えは一体、誰が知っているんだ。
宏紀がその場でしゃがみこんだ。川のそばで太陽の光を避けるように日陰で体を丸くしている。私には宏紀が体を震わせているように見える……。
行かない方がいい。行っても何もできない。宏紀を外から暖めることができるものもないし、そんな包容力はない。まだまだ十九歳。無力さを目の当たりにするだけだ。宏紀に背を向ける。このまま会わなかったことにすればいい。どうせスニーカーは接着剤がついている。何もしない……。
目の前に広がった景色に宏紀はいない。私にできることはない……。
言い聞かせるように繰り返す。
でもなぜ宏紀はあそこにいるんだろう。私と同じように大学に行く気になれなかったのか。もう耐えられず、講義の途中でまた大学を飛び出してきたのか。ランチを買いに行くふりをしてわざわざここまで来たのか。
目をギュッとしっかり閉じる。宏紀がここに来た理由なんてどうでもいい。行くんだ。この先の道のりを行くんだ。宏紀が視界にいなければ、普通に歩いていけるはず。
宏紀のことをもう一度見てみる……変わらずしゃがみこんで震える宏紀がいる。
放っておけるはずがない。接着剤がついているなら、私がスニーカーを脱げばいい。揺るぎない決意を持って下に降りていく。もしもまた気持ちが揺らされるようならまたその場で立ち止まって考えればいい。とにかく宏紀のそばに行くんだ。
水でぬかるんだ道を行くようにゆっくりと宏紀と距離を詰める。だんだん宏紀の体が大きくなってくる。
「宏紀!」
体を回転させて宏紀は私を視界に捉えた。
宏紀の頬が濡れている。体を震わせていたのは寒かったからではなく、涙のせいだった。もう抱えきれずに宏紀の溜め込んだ気持ちは涙に変わった。取り留めもなく流れ落ちるんだ。
宏紀はすぐさまもとの姿勢に戻して涙を拭き取った。一度拭き取っただけでもとに戻るならそれでいいけど、それだけで涙は止まるのか。
「真也と……喧嘩しちゃってさ……」
宏紀が語りだした。聞き手は川ではなく私だけど、こっちを向いてくれてない。
「こんなはずじゃなかった……もっと……」
宏紀は喉に何かを詰まらしたのかひどく咳き込んだ。
「頑張ろ……」
宏紀は背中に何かを感じた。ほんの一部だけだけど温かみを感じているだろう。私が宏紀のそばで背中をさすった。気がついたらこうしていた。誰に手を引かれたかは分からない。これは私の精いっぱいの慰めだった。宏紀は少しだけ後ろをみて私を確認した。
「もういい」
「……」
「もういいから。何も言わなくていい。全部知ってるから」
「……知ってるって?」
宏紀は私を直視した。でも私は宏紀の顔が見られなかった。再び流れ出した宏紀の涙をハンカチで拭いていくことに集中する。ハンドクリームを塗っている時のように、集中できる何かがあれば私は私でいられる。
「全部知ってる」
「真也のこと?」
「うん」
「どうして?」
宏紀が瞬きをした瞬間に流れ落ちた新たな涙が宏紀の膝に落ちた。
「……宏紀が大好きだから」
ようやく目を合わせることができた私も涙が溢れ出てきた。涙ってこんなに急に出てくるものなんだろうって不思議なくらいに。
「何だよ、それ」
宏紀は小さく笑った。私はそれが嬉しくて宏紀の真似をするわけじゃないけど、少しだけ笑った。
「辛かったよね?」
宏紀は静かに頷いた。
「分かるよ……私も辛くて寂しくて。ただ……」
「ただ……」
昨日の続きをするかのように台詞が出てきた。いいところで終わったドラマのように、続きが気になって宏紀は私の言葉を繰り返した。
「ただ、宏紀のそばにいようって思ってた」
「昨日、そう言おうとしてたの?」
宏紀と目を逸らして頷いた。こんな恥ずかしいセリフ、目を見て言えなかった。
「……ごめんね、昨日は。あんな言い方して」
「ううん。私がしつこくしたのが悪かったから、気にしないで」
胸の内側を見るとまだ奥深くまで刺さった傷がある。でも宏紀に謝られると許してしまう。宏紀って、何かあればちゃんと謝ってくるから。だから私の心は最大限に温められて何も言えなくなる。
「それでこうやって慰めてもらってるんだから、嫌な男だね」
「本当だよ! 宏紀って嫌な男!」
「ごめん……」
最大限に落ちたトーンで宏紀は謝った。宏紀がそんなに真面目に返すと思わなくて私は、「冗談だよ」
涙の跡をしっかり残して宏紀は砂利石を見つめている。していいか分からなかったけど、私は勢いで宏紀を抱きしめた。
「ありがとう、未砂」
私は何も言わずに首を横に振った。
宏紀も私を受け入れてくれたのか、手を私の背中に置いた。
「手、見せて」
一時的に宏紀から離れて手を見ると、案の定、カサカサの手をしていた。背中に触れた時に乾いた皮膚の突起で分かった。
私はまたハンドクリームを取り出した。
「未砂……」
宏紀はそう言って、ポケットに身を潜めた小さいハンドクリームを私に見せた。
「おお、買ったの?」
「うん……これ、貸してくれたよね? 今度返すよ」
「うん。宏紀は大きいやつを買った方がいい。すぐになくなっちゃう」
宏紀の新品よりも、今は私のハンドクリームで潤いを与えてあげたい。
「お腹空いた……」
そう呟く宏紀に、「お昼食べてないの?」
「うん……すぐに飛び出してきたから。未砂はお腹空いてる?」
「うん」
「じゃあ、何か食べようか」
私は宏紀のハンドクリームに覆われた両手を取って立ち上がった。ぬるぬるしているけど、別に気にしない。宏紀がしっかり立てるまで、ハンドクリームの温もりを分けてほしい。
データ分析室から担当教授の声が漏れる。ということは午後からも使用中になっているから中には入れない。宏紀は細心の注意を払って少しだけドアを開けてみる。宏紀が座っていた場所にはもう別の学生が座っている。宏紀が置き去りにした荷物はなさそうだ。
もしかしたら七海たちが持っているかもしれない。
私も宏紀と同じ景色を確認すると、データ分析室の隣にある資料室のドアを開けた。中にスタッフが二人いて、遅めのランチタイムに入っていた。
「すいません」
「はい」
二人のうちの一人の女性スタッフが振り向いて、口をもぐもぐしながら振り向いた。タイミングが悪いとは思ったけど、探しものだから勘弁してほしい。スマホや財布も入っているだろうから宏紀も気が気でないと思う。宏紀もよくそんな大事なものを置いてきぼりにできたと思っているだろう。それだけ追い詰められていたということだろうか。
私が尋ねてくれているのを聞いた宏紀が、「ありがとう」と言った。それに続けて、「自分で聞くよ。隣のデータ分析室にかばんの忘れ物はなかったですか?」
「ああ」
そう言ってすぐさま立ち上がった。きっと心当たりがあるんだろう。宏紀がここを飛び出して戻ってくるまでに時間が経っていないからすぐに認知できたみたいだ。
「お願いします」
「これですか?」
「これです。ありがとうございます」
宏紀は大事そうに抱えた。
「いえいえ」
これ以上お昼休憩を邪魔するのも気が引けた私たちは、すぐに資料室を後にした。
「よかったね、見つかって」
「うん、ありがとう」
宏紀は念のため中身を確認している。スマホや財布が入っていたんだから当然だ。
「たぶん、七海たちがここに預けてくれたんだと思う」
「たぶんそうだろうね。優しいね」
今宏紀のかばんを七海たちの誰かが持っていても、宏紀の手元に戻らないっていう判断だったんだろう。
「うん……本当に……」
「ねぇ、宏紀、お腹空いたからご飯食べよう!」
「うん」
「今日はもう講義出ないでしょ? どこかに遊びに行こう!」
「そうだね。行こうか」
「うん」
こういう理由で講義を欠席するのはこれが最後にしたい。両親のお金をわざわざ誰もいない場所にばらまくことはないから。でも今日ぐらい、許してくれるだろう。
私は笑顔を見せる。宏紀も笑っている。
「もうお腹空いた!」
私たちは生活環境学部の建物を飛び出して、メインストリートにかけだしていった。
講義中だから人気は少ないから、わがもの顔でここを駆け抜けよう。
宏紀の新しい顔なのかと思った。
自分の気持ちを少なからず外に出したからか、何か吹っ切れたようにお昼ご飯、私が連れていった服屋さん、本屋さんでも見せたことのない表情だった。
お昼ご飯はお金のことを考えて、ファミリーレストランで食べた。宏紀が意外にたくさん食べることが分かった。私が頼みすぎて食べきれなかったご飯もすべて平らげてくれた。一生懸命食べている感じが微笑ましくて見とれていると、「これ食べたいの?」って宏紀に聞かれた。確かに宏紀が食べていると、美味しそうに感じた。
服屋さんは前にも沙織と一緒に行ったみなとみらいのモールに行った。最初は何も買わずにウインドウショッピングしながら楽しもうと思ったけど、夏に向けた新作も入ってきていて花柄でネイビーのワンピースの話でお店の店員さんと盛り上がった。暇そうにしていた宏紀に、私に似合う服を探してって指示を出したら、グリーンのカーディガンを持ってきた。
「宏紀ってこういうのが好きなんだ」
「違うよ。このワンピースに合うかなと思っただけ」
「照れるなよ、宏紀。私もこれ好き!」
手持ちがなかったから気に入った新作のワンピースと宏紀が選んでくれたグリーンのカーディガンを取り置きしてもらって、後日お母さんと来ることになった。
そのままの勢いで本屋さんに降りていくと、小説やビジネス本を一緒に眺めた。宏紀も通学時間を有効活用したいらしくて『本を読む』って言う選択肢が頭にあった。以前、私も本を見に来たけど、その時はあまり乗り気にならなかった。お互いに本を買って貸しあいをすればいいかなって思った。それを提案したら、宏紀も乗ってきてくれた。基本的に宏紀は否定しないから言いやすい。私は『早起き』に関する本と、宏紀は『高校生』の青春群像劇みたいな小説を持ってきた。表紙の絵柄がきれいすぎて手に取ったらしい。一人の女子高校生が教室から何かを眺めている絵柄だった。眺めている先にはいとおしい人がいるのか。
時間も気にせずに遊びまわっていたら夕食の時間になっていたから、ファストフードのハンバーガーショップに入って空腹を満たし、時間を共にした。「時間は経つのは早い」という言葉のままに次は八時ぐらい時刻を目にした。私たちは横浜駅に戻って帰ることにした。
横浜駅で大船行きの電車に乗り込んで二名がけの座席に座った。
あっという間に過ぎ去った時間。もうすぐ別れの時がやってくる。なにも永遠に別れるわけじゃない。来週の月曜日は祝日だから火曜日に大学に行けば、また宏紀に会える。
「今日はありがとう」
宏紀が唐突に小さく笑って言った。
「こちらこそ」
電車に乗ってからお互いに黙っていた私たちの沈黙を宏紀は破った。まさか宏紀がこの静けさに終止符を打つとは思わなかった。昨日の出来事に後ろめたさを感じているのかもしれない。気を遣ってくれているんだろう。ここまでしてもらっておいて、という気持ちが宏紀の行動を促している。
今見せてくれている笑顔は偽物に過ぎないのか。
現実に背を向けるかのように、不意に外の景色に視線を送る。見慣れた景色が広がってくる。ここからどこに何があるかだいたい説明できる。私の住んでいる磯子だ。
何だろう。この不安な気持ちは。
「もうすぐ磯子だね」
「うん……」
電車が速度を緩めて磯子駅の定位置に辿り着こうとしている。
本当なら座席から立ち上がって出入り口の前で待機するだろうけど、私は頑なに宏紀のそばにいる。
電車が磯子駅の定位置に着いた。プシューという音がドア開扉を知らせてくれた。でも今の私には余計な気遣いでしかない。俯いてただドアが閉まるのを待っている私。そんな私を横目で捉えても何も言わずに宏紀は同じ時を過ごしてくれている。
「未砂……」
今はそっとしておいてほしい。
次はプシューという音は完全にドアが閉まったことを伝えた。そしてまたゆっくりと速度を上げて進み始めた。
ただならぬ私の雰囲気に飲み込まれる形で「未砂……家、来る?」
私は顔を上げて宏紀を見た。
「もう磯子は過ぎちゃったし……そんな大した家じゃないけど」
表情を徐々に緩めて私は「うん」と頷いた。
「ごめんね」
港南台駅について、信号待ちをしている時に私は宏紀の横顔を見つめた。
「いいよ。気にしないで。ここから五分ぐらいだから」
「うん」
宏紀の家に行くのは初めてだから緊張するけど、宏紀の笑みがそれを緩和してくれる。宏紀の涙を見て以来、真也とのことの真相は聞かなかった。私たちが笑顔でいられるなら、聞く必要なんてないって思った。事故的ではあったけど、宏紀と距離を縮めることができた。ここはちゃんと宏紀のことを理解する必要があるような気がする。今までの私の推測ではなくて、宏紀から語られる宏紀の今を。
「未砂は、港南台に来ることあるの?」
私がまた黙ったままだったから宏紀が話しかけてくれたんだろう。
「あんまり来ないかな」
「だよね。僕も住んでいなかったら来ないと思う」
「宏紀……聞きたいことがあるの」
「何?」
宏紀の腕を掴んでその場で制止させた。歩きながら聞くのはなんか違う気がした。宏紀の言葉をちゃんと噛みしめる必要があるって勝手に思ったんだ。
「真也君と、何があったの?」
川のほとりで話して以来、一点の曇りもなかった宏紀の表情に霧がたちこめてきて、視線が足元に落ちていった。
「こうやって聞くのは、宏紀の今を知りたいの。多分、私が思っていた状況と同じだと思うけど、それにズレがあったら嫌だなって……」
私は宏紀の手を取った。宏紀のことを知っていれば私にできるは必ずあるはずだから。情報を共有しても宏紀はこれからも苦しめられるだけかもしれないけど。
「ありがとう」
「もちろん、嫌だったら言わなくていい。私も、何も言わなくていいって言ったから……」
うつむいたまま戻ってこない宏紀。受け入れがたい出来事だったことは明らかだけど、目の前に映し出すとなると恐怖で圧倒されてしまいそうだ。でも二人で分け合えばなんとかなるかもしれない。
真也と家電量販店に出かけた時に、ほのめかした真也の気持ち。まさか七海への気持ちだったとは宏紀は思いもしなかったらしい。だから宏紀は喜んで真也の役に立ちたいって思ったんだろう。
週末が開けた月曜日の朝。その日は肌寒い一日だった。朝晩は冷えるのは知っていたけど、日中でさえもう一枚羽織りたくなった。真也が生活環境学部のそばにあるベンチで、来ているジャケットのポケットに両手を忍ばせながら座っていた。重い雰囲気ではなくそれは真面目であまりにも一途な瞳が地面を断続的に打ちつけられていた。
そこに宏紀は出くわした。通学時間帯が早い宏紀を真也は待っていたのかもしれない。
まだ会って間もないだけに目にしたことがなかった真面目な眼差し。宏紀は何かに導かれるように、既定路線をただひた走るように、真也にこう尋ねた。
「どうした? 何かあった?」
真也はすぐに答えはしなかった。そう、私が沙織に宏紀への気持ちを吐露した時のように。自分の気持ちを整理するように、ひとつひとつの言葉を手に取って外に出す準備を整えた。
横を向いて真也の表情を確認した宏紀。最初に尋ねた時と変わりない、凍り付いたような真也がいた。触れれば宏紀さえも凍ってしまいそうでそっとしておいた。朝の貴重な時間が意味もなくどこかへ放浪していく。宏紀はあからさまではないけど、苛立ちを顔に張り付かせた。
「悪い……」
宏紀の仕草で苛立ちが可視化できたのか、真也はそう謝ってきた。
「いいよ。何か、大切なことなのかなって」
そう言って宏紀は顔に張り付かせた苛立ちを取り除いた。
「宏紀……」
「ん? 何? そんな大事なことなの? 何か助けられることがあったらやるけど」
「僕、七海ちゃんが好きだ……」
宏紀の柔らかい表情が警戒心に支配されたものに急変した。入ってくる言葉をすべて遮断して、かけた気遣いの言葉も真也への言葉もすべて抹殺したくなった。
真也が七海を『好きだ』って言った。
実際に宏紀の体は硬直していくけど、心の世界では小刻みに首を振る。
いや違う。きっと聞き間違いだ。このセリフを宏紀は何度も反芻した。
いや、そうであってほしい。繰り返すうちに懇願にも似たものに変わった。
「今……なんて……」
「七海ちゃんが好きだ」
二度目は書いた作文を確認するかのように、念には念を入れるように、真也は神妙な表情を崩さずに言った。
宏紀はその時、とてつもない恐怖に顔面を殴られた。これからの四年間を根底からすべてを覆されて壊されていく様子をただ単に眺めるしかできなくなった。身動きも取れずにただそこにいるだけだった。
「七海ちゃんって彼氏いるのかな? いそうだな」
そう問いかけられた宏紀は警戒心の塊になった。
七海に彼氏がいないことは知っている。もっと言うと、過去の恋愛を引きずって七海なりに今を頑張ろうとしていることも。
「そういう話はしないからな……」
宏紀はそう言ってお茶を濁した。ただ言いたくなかった。雁字搦めになった思考は止められずに心はカチカチのままだ。
この状況の中で七海や真也へのかかわり方を迫られることになった。混乱と失意のなかで七海への好意をはぎ取らざる終えない状況になった。
カチューシャのことも、缶コーヒーのことも私は聞いた。それらは私の推測ときれいに重なった。
カチューシャはやっぱり真也や七海のことが気になって、会話がまともに入ってこなかったらしい。自分を取り繕うのに精いっぱいだった。
缶コーヒーも二人から逃れるためにたまたまコンビニに行ったときに意味もなく買っただけだった。何かを買いに行っていたという口実があれば、何でもよかったのだろう。菓子パンでもガムでも。
「でも、僕が悪い……」
宏紀がつぶやいた言葉に私の胸は力いっぱい掴まれて破裂しそうになった。あともう少し。少しでも力が加われば、血が噴き出して流れ落ちただろう。
宏紀の真意は、真也と戦わずに七海への気持ちを振り払ってしまったことへの後悔だった。自分の気持ちをちゃんと伝えられなかった情けなさ。この二つの気持ちに両サイドから責められて宏紀は疲弊していった。
「未砂……聞いてくれてありがとう」
「全然いいよ。私ね……さっき電車を降りるのが怖かったんだ」
宏紀は無言で私に耳を傾けた。
「このまま帰ったら、また宏紀が宏紀じゃなくなってしまうかもって思ったら、心配でたまらなくて……私がそばにいる」
宏紀はうんうんと相槌を打った。
私は宏紀の反応が怖くて顔をすぐに見られなかった。
宏紀は少しだけ距離を詰めて、私を抱きしめてくれた。
「ありがとう……」
私は宏紀の手を握った。ハンドクリームで保湿がされていてなめらかな手だった。手に温もりに安心したのか、私は目を閉じて宏紀の胸板に身を任せた。
「未砂……もう夜遅いから帰ろうか」
「うん」
宏紀に抱きしめられて私は活力をもらったみたいだ。
「家まで送っていくよ」
「本当に?」
「うん。結局、家、行かなかったね」
「だね。でもまた今度行きたいな」
「分かった。ちゃんと掃除しておく」
宏紀は家に帰ると車のキーを手にして再び出てきた。
少しだけお母さんの声も聞こえてきた。なんだか宏紀と同じように穏やかで挨拶したくなって少し離れたドア越しで声を出した。
「こんな遅くに申し訳ありません」
「いえ、大学の方ですか?」
「はい。これからもよろしくお願います」
宏紀は恥ずかしそうに私たちのやり取りを見ていた。きっと早く会話を終わらせてほしかったんだろう。気持ちは分かるけど、これからのこともあるから。
私たちは車に乗り込んで磯子駅に向かった。
車を運転している姿でさえ、私には新鮮で宏紀をしばらく見つめてしまった。
「はぁ、なんか今日は怒ったり、泣いたり、笑ったりいろんなことがあったな」
サイドミラーを見つめながらそう呟く宏紀に私は「色々あったんだから仕方ないよ」
しばらく道なりを行くと、あっという間に磯子駅のロータリーに到着した。
「ここでいいの? 夜遅いから家の前まで行くよ」
「いいよ、ここで。もう歩いてすぐだし。ありがとう」
私は車を降りて手を振る。
「じゃあ、また来週」
「うん」
私は車から離れていく。でも歩く速度は安定しなくて立ち止まった。
「宏紀、週末って何するの?」
世間は明日から三連休だ。
「何もない。どうして?」
「じゃあさ、遠くに行こう! 何もかも忘れて楽しもうよ!」
「うん。行こうか!」
私は噛みしめるように嬉しさを体中で受け止めて、「じゃあ、明日の十二時に磯子駅に来て! 来れそう?」
「うん。大丈夫」
「じゃあまた明日」
週末も宏紀と一緒にいたい。わがままかもしれないけど一緒にいたい。宏紀の穏やかな笑顔を見ていると私も嬉しくなるから。