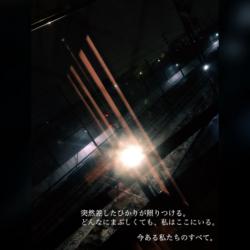トイレで今の私を写し出す。眼鏡がくっついている。イメチェンじゃない。今朝は時間がなくて出発時刻になったと同時にワンデーのコンタクトを掴んで家を出た。
スマホが揺れる。講義前だからきっと沙織だろう。
「今日用事があって一限目の講義に行けないからプリントがあったらお願いします! ごめんね」
コンタクト姿で講義室に向かう足取りが止まった。まるで通路に信号でもあるように。青に変わったとしても次の一歩を出す勇気があるだろうか。
今日は一人になる。
宏紀たちがいる。でもそこには七海もいる。二人の姿を近くで眺めることになるっていうことだ。
七海のことは大好きだ。実験科目の時に初対面でも普通に話してくれたし、真面目な性格でも固さはなく、人を包み込む笑顔はまさに天使だ。でも時折、嫉妬心で心を掻き乱すことも事実だった。当然、意図してのことじゃない。それにまた缶コーヒーが置いてあったら嫌だ。それも意図したことじゃない。宏紀の立場なら、同様にコーヒーを好きになろうとしたかもしれない。
仕方ない。そんな稚拙な理由で講義をサボるわけにもいかない。沙織にプリントも頼まれている。
講義室のドアを俯きながら開けた。いじめられていて足取りの重い女の子のように、ただ誰にも気づかれないようにひっそりと。
私と沙織がいつも座っている席は空きになっている。みんな律儀なのか、席に各学生の名前入りの紙が置いてあるかのように、だいたいみんな同じ席に座る。あそこに一人で座るのも寂しい。でも宏紀たちに近づいて行くのも怖い。
どうしたらいいんだろう。答えがないままいつもの指定席に吸い込まれていった。
前方を向くと、七海、真也、宏紀は席についていた。前の席に七海が、そのすぐ後ろに宏紀と真也が並んで座っている。三人で談笑している感じだ。その三人だけ妙に輝いて見える。華のあるアーティストがスポットライトに照らされているようだった。みんな心から笑っているように見えるし、何よりも大好きな宏紀がそばにいる。
目が虚ろになって霧が立ち込めてくる。コンタクトがズレているわけじゃない。ただの羨望の眼差しだった。しかしそれも束の間、霧が徐々に吸い取られて光が差し込む。七海と目が合った。その瞬間に私は頬を吊り上げて奇妙な笑みを浮かべる。小さく手を振る七海は立ち上がって近づいて来る。
体を小刻みに揺らしながら七海の受け入れ態勢を作る。急造の笑顔はさらに進化して顔の筋肉がヒクヒクする。
「未砂ちゃん、おはよう」
「おはよう……」
話しかけられるのは楽だ。ただ相手の話に耳を傾ければいいから。でも今は例外。
「沙織ちゃんいないの?」
「あ、一限目は来られないんだって。だから……今日はぼっちなんだ」
「前においでよ。私の隣、空いてるから」
基本的に誘われて断らない。前に行くのは嫌だけど、七海を断る気になれない。一人ぼっちの私に気付いて、わざわざ声をかけてくれるなんてすごく優しい。宏紀が七海に惹かれる理由は十二分に理解できる。
「ありがとう」
誘ってくれたのは素直に嬉しい。私は立ち上がって前に向かった。
「永井さん、おはよう」
真也がそうやって迎え入れてくれた。
「未砂……遅かったね」
宏紀がそうやって真也の言葉に続けた。寝不足なのか宏紀の目元にクマができている。
「おはよう」
宏紀の目元を気にしながら真也と宏紀の出迎えに応える。
私は空席になっている七海の隣に座った。
宏紀に声をかけたくなる。眠れているのか。それと比べて真也の瞳は恍惚としている。特に何かに照らされるわけでもないのに眩い光のような視線は七海に注がれている。思わず身を引いてしまった。見えないテープがひかれているようだった。あまりにもまっすぐな眼差しがある。これを見たら、私じゃなくても自分の居場所はないと感じたかもしれない。
そして宏紀は、特に何も話すことなくポツンと座っている。居場所を失っているようだった。
七海は真也に任せておいて、私は宏紀に選別した映画のラインナップを見せようと思った瞬間だった……今までばらついていたものが一つの線になってはっきり見えるようになった。知らぬ間に何かに辿り着いた。きれいに整えられた線を動かすのは気が引ける。だから慎重に、崩れないように歩いてみよう。
周囲には百人近くの学生がいるのに何も聞こえない。
私は真也と宏紀を同時に見つめる。
嫌な静寂が私を包んだ。
部屋のベッドの上に寝転がって私は天井を見つめている。
考え事をしていたせいで五、六人のLINEの返信が滞っていた。私ってこんなに人気があったかなって思った。今はそんなことどうでもいい。
七海に誘われていった前の席。集中して講義は受けられたけど、胸の痛みを聞くのが嫌で一人になってまで傷を隠した。前に行くのが怖かった。でもそのおかげで、今の宏紀をうまく描写できるようになった。今の宏紀を理解する過程では、必要なことだったんだ。
真也の光輝く視線に身を引いた。真也が作り出す七海との世界。誰も寄せ付けることのない強固な敷居が引かれていた。そんな雰囲気を感じた。
あの眼差しに、真也の気持ちを見たような気がした。
要するに真也も七海が好きなんだ。私じゃなくても、誰が見ても真也の気持ちは丸裸だった。そして何も言わず、視線を落としたままで居場所のない宏紀がいた。
宏紀も七海が好きだと思う。真也のように七海と相まみえたいと思っているのにそれができないでいる。なぜなら真也がいる。こんなにも近くに真也がいるんだ。
会話を真也に譲っていると、最初はそう思った。
でも宏紀の七海への気持ちはそんな軽いものではない。おそらく中学生の時から抱えている気持ち。たまたま同じ大学、同じ学部、同じ学科に所属することになって、秘めてきた想いが蘇ってきたんだ。きっと再会を喜んで、七海に想いを伝えようとしていたんだ。アパートにも出入りできるような間柄だ。
真也に気を遣っているのか。
どこかのタイミングで、宏紀は真也の気持ちを聞かされたのかもしれない。それで真也に気を遣って話さないようにしているのか。
いや、譲る、気遣うということじゃない。
宏紀は自分の気持ちが自由に表出することができなくなったんだ。真也は知らず知らずのうちに宏紀の気持ちに釘を強く打ち付けてしまった。身動きが取れなくなり、おとなしくポツンと座っていたんだ。真也の視界に、あの時の宏紀の姿は映っていただろうか。おそらくそうじゃない。
この前、分析室で青ざめた宏紀の表情を見た時から様子が変だと感じた。宏紀に嫌われてしまったと勝手な妄想を脳裏で展開し恐怖で体をなぞられた。でも打って変わって、カチューシャを髪の毛から消し去ってしまったことを謝ってきた。
最初にカチューシャの感想を尋ねられた時、宏紀の周囲には当然、真也や七海がいた。きっと、二人のことが気になってまともな返事ができなかったのかもしれない。もしかしたら、質問の意味でさえ、分かっていなかったのかもしれない。いつも肯定的な宏紀だから、人を否定するようなことは言わないと思う。
そしてあの缶コーヒー。
講義のギリギリになって、宏紀はひょっこり現れた。誰にも何も告げることなく、宏紀はコーヒーを買いに行った。でも宏紀はコーヒーが好きじゃない。目的はコーヒーではなかったんだろう。二人と距離を置きたくて、買いたくもないコーヒーを手にして、「最近、飲めるようになった」と嘘を言ったんだ。
きっとそうだ。
どこかで真也の気持ちを知ってしまった。それでどんな態度を取ればいいのか分からなくなってしまった。七海と仲良くする姿は、真也を刺激してしまうかもしれない。真也の気持ちも分かった。応援したい気持ちもあった。
でも溢れかえる七海への気持ちは消せない。そう考えれば、宏紀の表情、張りのない声、虚ろな目が理解できる。私の相手なんてしている暇がないっていうのが本音だったんだろう。それでも嫌々ながらも新浦安駅まで歩いてくれたり、映画の約束もしてくれていたんだ。宏紀の気持ちに寄り添えなかった自分が嫌になった。
そしてこの答えに導かれた時、宏紀は猛烈な嫉妬の気持ちに苛まれていると思う。今の私のように。
あの缶コーヒーも私の視界から二度と映らないようにしてほしいとさえ思った。コーヒーにとりわけ恨みなんてあるはずがないのに。アパートで食べた野菜炒めの話。七海を気遣う宏紀の優しさ。すべてが私を強く揺さぶってぐちゃぐちゃにする。
宏紀も身動きが取れない中で、真也と七海が仲を深めていくさまをあんなにも近くで見ているんだ。俯いていたのはそれに必死で抵抗していたんだ。宏紀の気持ちは中学生の時からのものだ。突然、真也のことがあるからと言って断ち切ることは難しい。
きっとそうだ。
私は一人で身を震わした。
この推測が宏紀の取り巻く現実ときれいに重なれば、表現しようのない恐怖に襲われることになる。自分の気持ちを伝えたくても伝えられない苦しさは、想像するだけでも涙が出てきそうだ。好きなのに好きと言えない。好きなのに、何もできない。
私はただ首を振って、描き出された苦悩を振り払った。
宏紀は、このままでいいんだろうか。
せっかく七海と再会できたのに、このままでいいんだろうか。
真也と七海が仲良くなったとしても、まだ宏紀に分があると思う。これまで秘めてきた想いを伝えるチャンスなのに、何もせずに終わっていくのだろうか。
その一方で、この状況は私にとって好都合であることも事実だった。
七海への気持ちを伝えられないとなれば、これ以上、宏紀と七海の関係の進展はないだろう。七海という最強のライバルはここで姿を消すんだ。真也が宏紀の恋心に釘を刺している間に、宏紀の今を理解し、傷を癒してあげればいい。そして弱みにつけこんで宏紀の気持ちを掴むんだ。
背筋に溶けた氷のしずくが落ちた。そんなメリットを導き出していた。宏紀を苦しめる過程で、宏紀の気持ちを掴もうとするあざとさ。私はただただ最低だった。
これがたどり着いた宏紀の今だった。
スマホが揺れる。講義前だからきっと沙織だろう。
「今日用事があって一限目の講義に行けないからプリントがあったらお願いします! ごめんね」
コンタクト姿で講義室に向かう足取りが止まった。まるで通路に信号でもあるように。青に変わったとしても次の一歩を出す勇気があるだろうか。
今日は一人になる。
宏紀たちがいる。でもそこには七海もいる。二人の姿を近くで眺めることになるっていうことだ。
七海のことは大好きだ。実験科目の時に初対面でも普通に話してくれたし、真面目な性格でも固さはなく、人を包み込む笑顔はまさに天使だ。でも時折、嫉妬心で心を掻き乱すことも事実だった。当然、意図してのことじゃない。それにまた缶コーヒーが置いてあったら嫌だ。それも意図したことじゃない。宏紀の立場なら、同様にコーヒーを好きになろうとしたかもしれない。
仕方ない。そんな稚拙な理由で講義をサボるわけにもいかない。沙織にプリントも頼まれている。
講義室のドアを俯きながら開けた。いじめられていて足取りの重い女の子のように、ただ誰にも気づかれないようにひっそりと。
私と沙織がいつも座っている席は空きになっている。みんな律儀なのか、席に各学生の名前入りの紙が置いてあるかのように、だいたいみんな同じ席に座る。あそこに一人で座るのも寂しい。でも宏紀たちに近づいて行くのも怖い。
どうしたらいいんだろう。答えがないままいつもの指定席に吸い込まれていった。
前方を向くと、七海、真也、宏紀は席についていた。前の席に七海が、そのすぐ後ろに宏紀と真也が並んで座っている。三人で談笑している感じだ。その三人だけ妙に輝いて見える。華のあるアーティストがスポットライトに照らされているようだった。みんな心から笑っているように見えるし、何よりも大好きな宏紀がそばにいる。
目が虚ろになって霧が立ち込めてくる。コンタクトがズレているわけじゃない。ただの羨望の眼差しだった。しかしそれも束の間、霧が徐々に吸い取られて光が差し込む。七海と目が合った。その瞬間に私は頬を吊り上げて奇妙な笑みを浮かべる。小さく手を振る七海は立ち上がって近づいて来る。
体を小刻みに揺らしながら七海の受け入れ態勢を作る。急造の笑顔はさらに進化して顔の筋肉がヒクヒクする。
「未砂ちゃん、おはよう」
「おはよう……」
話しかけられるのは楽だ。ただ相手の話に耳を傾ければいいから。でも今は例外。
「沙織ちゃんいないの?」
「あ、一限目は来られないんだって。だから……今日はぼっちなんだ」
「前においでよ。私の隣、空いてるから」
基本的に誘われて断らない。前に行くのは嫌だけど、七海を断る気になれない。一人ぼっちの私に気付いて、わざわざ声をかけてくれるなんてすごく優しい。宏紀が七海に惹かれる理由は十二分に理解できる。
「ありがとう」
誘ってくれたのは素直に嬉しい。私は立ち上がって前に向かった。
「永井さん、おはよう」
真也がそうやって迎え入れてくれた。
「未砂……遅かったね」
宏紀がそうやって真也の言葉に続けた。寝不足なのか宏紀の目元にクマができている。
「おはよう」
宏紀の目元を気にしながら真也と宏紀の出迎えに応える。
私は空席になっている七海の隣に座った。
宏紀に声をかけたくなる。眠れているのか。それと比べて真也の瞳は恍惚としている。特に何かに照らされるわけでもないのに眩い光のような視線は七海に注がれている。思わず身を引いてしまった。見えないテープがひかれているようだった。あまりにもまっすぐな眼差しがある。これを見たら、私じゃなくても自分の居場所はないと感じたかもしれない。
そして宏紀は、特に何も話すことなくポツンと座っている。居場所を失っているようだった。
七海は真也に任せておいて、私は宏紀に選別した映画のラインナップを見せようと思った瞬間だった……今までばらついていたものが一つの線になってはっきり見えるようになった。知らぬ間に何かに辿り着いた。きれいに整えられた線を動かすのは気が引ける。だから慎重に、崩れないように歩いてみよう。
周囲には百人近くの学生がいるのに何も聞こえない。
私は真也と宏紀を同時に見つめる。
嫌な静寂が私を包んだ。
部屋のベッドの上に寝転がって私は天井を見つめている。
考え事をしていたせいで五、六人のLINEの返信が滞っていた。私ってこんなに人気があったかなって思った。今はそんなことどうでもいい。
七海に誘われていった前の席。集中して講義は受けられたけど、胸の痛みを聞くのが嫌で一人になってまで傷を隠した。前に行くのが怖かった。でもそのおかげで、今の宏紀をうまく描写できるようになった。今の宏紀を理解する過程では、必要なことだったんだ。
真也の光輝く視線に身を引いた。真也が作り出す七海との世界。誰も寄せ付けることのない強固な敷居が引かれていた。そんな雰囲気を感じた。
あの眼差しに、真也の気持ちを見たような気がした。
要するに真也も七海が好きなんだ。私じゃなくても、誰が見ても真也の気持ちは丸裸だった。そして何も言わず、視線を落としたままで居場所のない宏紀がいた。
宏紀も七海が好きだと思う。真也のように七海と相まみえたいと思っているのにそれができないでいる。なぜなら真也がいる。こんなにも近くに真也がいるんだ。
会話を真也に譲っていると、最初はそう思った。
でも宏紀の七海への気持ちはそんな軽いものではない。おそらく中学生の時から抱えている気持ち。たまたま同じ大学、同じ学部、同じ学科に所属することになって、秘めてきた想いが蘇ってきたんだ。きっと再会を喜んで、七海に想いを伝えようとしていたんだ。アパートにも出入りできるような間柄だ。
真也に気を遣っているのか。
どこかのタイミングで、宏紀は真也の気持ちを聞かされたのかもしれない。それで真也に気を遣って話さないようにしているのか。
いや、譲る、気遣うということじゃない。
宏紀は自分の気持ちが自由に表出することができなくなったんだ。真也は知らず知らずのうちに宏紀の気持ちに釘を強く打ち付けてしまった。身動きが取れなくなり、おとなしくポツンと座っていたんだ。真也の視界に、あの時の宏紀の姿は映っていただろうか。おそらくそうじゃない。
この前、分析室で青ざめた宏紀の表情を見た時から様子が変だと感じた。宏紀に嫌われてしまったと勝手な妄想を脳裏で展開し恐怖で体をなぞられた。でも打って変わって、カチューシャを髪の毛から消し去ってしまったことを謝ってきた。
最初にカチューシャの感想を尋ねられた時、宏紀の周囲には当然、真也や七海がいた。きっと、二人のことが気になってまともな返事ができなかったのかもしれない。もしかしたら、質問の意味でさえ、分かっていなかったのかもしれない。いつも肯定的な宏紀だから、人を否定するようなことは言わないと思う。
そしてあの缶コーヒー。
講義のギリギリになって、宏紀はひょっこり現れた。誰にも何も告げることなく、宏紀はコーヒーを買いに行った。でも宏紀はコーヒーが好きじゃない。目的はコーヒーではなかったんだろう。二人と距離を置きたくて、買いたくもないコーヒーを手にして、「最近、飲めるようになった」と嘘を言ったんだ。
きっとそうだ。
どこかで真也の気持ちを知ってしまった。それでどんな態度を取ればいいのか分からなくなってしまった。七海と仲良くする姿は、真也を刺激してしまうかもしれない。真也の気持ちも分かった。応援したい気持ちもあった。
でも溢れかえる七海への気持ちは消せない。そう考えれば、宏紀の表情、張りのない声、虚ろな目が理解できる。私の相手なんてしている暇がないっていうのが本音だったんだろう。それでも嫌々ながらも新浦安駅まで歩いてくれたり、映画の約束もしてくれていたんだ。宏紀の気持ちに寄り添えなかった自分が嫌になった。
そしてこの答えに導かれた時、宏紀は猛烈な嫉妬の気持ちに苛まれていると思う。今の私のように。
あの缶コーヒーも私の視界から二度と映らないようにしてほしいとさえ思った。コーヒーにとりわけ恨みなんてあるはずがないのに。アパートで食べた野菜炒めの話。七海を気遣う宏紀の優しさ。すべてが私を強く揺さぶってぐちゃぐちゃにする。
宏紀も身動きが取れない中で、真也と七海が仲を深めていくさまをあんなにも近くで見ているんだ。俯いていたのはそれに必死で抵抗していたんだ。宏紀の気持ちは中学生の時からのものだ。突然、真也のことがあるからと言って断ち切ることは難しい。
きっとそうだ。
私は一人で身を震わした。
この推測が宏紀の取り巻く現実ときれいに重なれば、表現しようのない恐怖に襲われることになる。自分の気持ちを伝えたくても伝えられない苦しさは、想像するだけでも涙が出てきそうだ。好きなのに好きと言えない。好きなのに、何もできない。
私はただ首を振って、描き出された苦悩を振り払った。
宏紀は、このままでいいんだろうか。
せっかく七海と再会できたのに、このままでいいんだろうか。
真也と七海が仲良くなったとしても、まだ宏紀に分があると思う。これまで秘めてきた想いを伝えるチャンスなのに、何もせずに終わっていくのだろうか。
その一方で、この状況は私にとって好都合であることも事実だった。
七海への気持ちを伝えられないとなれば、これ以上、宏紀と七海の関係の進展はないだろう。七海という最強のライバルはここで姿を消すんだ。真也が宏紀の恋心に釘を刺している間に、宏紀の今を理解し、傷を癒してあげればいい。そして弱みにつけこんで宏紀の気持ちを掴むんだ。
背筋に溶けた氷のしずくが落ちた。そんなメリットを導き出していた。宏紀を苦しめる過程で、宏紀の気持ちを掴もうとするあざとさ。私はただただ最低だった。
これがたどり着いた宏紀の今だった。