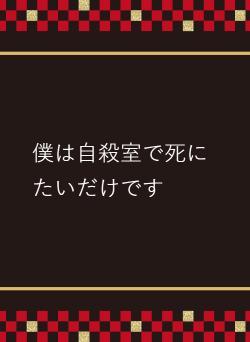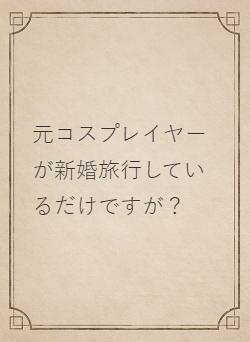・
・【促されるまま廊下へ】
・
僕たちはイッチンに促されるまま廊下へ出てきた。
イッチンが先頭を歩いていたその時だった。
「イタぁ、足挫いたかもしれんわぁ」
その場にへたり込んだイッチン。
いや全然挫くような要素無かったけども、と思った刹那、博士が震えながらこう言った。
「おんぶの、シーンで、ヤンス……」
いや!
「何で急にヤンス口調! 説明するモブ感を出したんだ!」
いやでも確かにその通りのようで、座りながらこっちを振り向いたイッチンは痛そうにしつつもニコニコしている。
こんなラブコメを試されるようなことがあるなんて! いやイッチンも結構ノリノリだ!
するとまず真っ先に手を挙げたのが、トールだった。
そして、
「何だよっ、だらしがないなっ、しゃーねぇなぁっ、俺がおんぶしてやるよっ」
と、もう役に入ってやり始めた。
いやもはや役ではなくて、これが本当のトールなのか? ついに覚醒したのか?
そう思って見ていると、トールはイッチンの前でしゃがみ込み、おんぶさせたその時だった。
「おっ、おぉっ、ハハッ、ハハッ、ハハッ」
立ち上がりすらせず、その場であのかすれた笑い声を出し始めたので、僕は
「トール? どうしたの? 逆にトールがマジで挫いたの?」
「いやっ、そうじゃないっ、ガチのおんぶってっ、感触がっ、ハハッ」
と言った時にイッチンがすぐさまプフーと吹き出しながら、
「アタシのおっぱいに興奮しすぎやーん!」
で、トールが慌ててイッチンから離れてから、
「止めろっ! おっぱいって言うなっ! 意識するだろっ!」
と叫んだ。
いやもう完全に意識していたけども。
やっぱりトールは覚醒していなかった。
そして練習は結局練習で、本番には使えないんだな、と思ってしまった。
いやでも実際、ここでハッキリおっぱいという単語を聞いてしまったら、うかつにもう「次のおんぶは僕だ」とか言えなくなったな、とか思っていると、博士がメガネを上げながらこう言った。
「おっぱいに、耐える、練習、させて、下さい」
いや!
「おっぱいを意識した状態でよく言い出せるね! せめておっぱいは関係無い感じで言い出しなよ!」
しかしイッチンは首を横に振り、
「ええねん、理央。アタシはアンタら三人にならいくらでもおっぱい貸し出せんねん」
と言って笑った。
それに強く反応したのは博士で、その場に前屈みで倒れ込み、
「小生は、笛、担当、でした」
と言って俯いた。
いや!
「そんなことないよ! 笛担当なんて人は主審以外いないよ! 主審のある部活動じゃないからこれ!」
「いや、これは、主審のある、スポーツだ」
「スポーツでは全然無いよ! 今日も今日とてバカな部活動だよ!」
ここでイッチンが割って入って来た。
「で、アタシの傷んだ足を助けて、教室まで運んでくれる人は誰やねん」
というか教室に行くんだ、と思いつつ、僕はイッチンの前でしゃがんだ。
「おっ、理央が運んでくれるんやな、でも理央は女子みたいに線細いけども大丈夫やんかな?」
また女子みたいに、とか言って……僕は男子だ! できる!
「大丈夫! イッチンのことちゃんと運ぶから!」
「ええ気合いやん! じゃぁよろしゅー!」
そう言って僕の背中に乗ってきたイッチン。
いや! 確かに! 何か! すごい!
でもここで、おっぱいおっぱい言ってもしょうがないので、僕は歩き出した。
というかおっぱいのことは考えない! 考えたら、何か、すごくなっちゃうから……!
「乗り心地ええやん! ええやん!」
そう言いながら僕の背中の上で揺れ始めたイッチン。
いや、背中の上でおっぱいがバウンドするせいで、その感覚が一定じゃなくて、揺れるごとに触れる感じが……わざとなのか! これはわざとなのか!
なんて悪魔的な女子なんだ、イッチンは! でも! でも!
≪≪!悪くない!≫≫
そんなことを考えながら、僕はイッチンを近くにあった教室まで運びきり、またしゃがんで、イッチンが降りやすそうにしたその時、僕はちょっとバランスを崩してしまい、手を前について倒れそうになった。
「あっ! イッチン大丈夫!」
そう言って僕がすぐさま振り返ると、イッチンの顔が僕の顔の近くにあって、あわやほっぺたにキスしてしまいになったので、僕はあわあわ慌てると、
「さすがにキスはまだ早いでー!」
と僕のおでこを突いて笑った。
それを見ていた博士は笛を勢いよく二回吹いて、
「得点、連続、奪取」
トールも手を叩きながら、
「やったなっ! 理央っ!」
いや!
「別にやってはいないよ! 事故だよ! 事故!」
と僕がツッコむと、一瞬イッチンは切なげな顔で、
「事故ねぇ……」
事故という言葉に何か反応した……一体何なのだろうか……いやまあいいや、そんなことよりも、イッチンは教室で何をする気なんだろうか?
・【促されるまま廊下へ】
・
僕たちはイッチンに促されるまま廊下へ出てきた。
イッチンが先頭を歩いていたその時だった。
「イタぁ、足挫いたかもしれんわぁ」
その場にへたり込んだイッチン。
いや全然挫くような要素無かったけども、と思った刹那、博士が震えながらこう言った。
「おんぶの、シーンで、ヤンス……」
いや!
「何で急にヤンス口調! 説明するモブ感を出したんだ!」
いやでも確かにその通りのようで、座りながらこっちを振り向いたイッチンは痛そうにしつつもニコニコしている。
こんなラブコメを試されるようなことがあるなんて! いやイッチンも結構ノリノリだ!
するとまず真っ先に手を挙げたのが、トールだった。
そして、
「何だよっ、だらしがないなっ、しゃーねぇなぁっ、俺がおんぶしてやるよっ」
と、もう役に入ってやり始めた。
いやもはや役ではなくて、これが本当のトールなのか? ついに覚醒したのか?
そう思って見ていると、トールはイッチンの前でしゃがみ込み、おんぶさせたその時だった。
「おっ、おぉっ、ハハッ、ハハッ、ハハッ」
立ち上がりすらせず、その場であのかすれた笑い声を出し始めたので、僕は
「トール? どうしたの? 逆にトールがマジで挫いたの?」
「いやっ、そうじゃないっ、ガチのおんぶってっ、感触がっ、ハハッ」
と言った時にイッチンがすぐさまプフーと吹き出しながら、
「アタシのおっぱいに興奮しすぎやーん!」
で、トールが慌ててイッチンから離れてから、
「止めろっ! おっぱいって言うなっ! 意識するだろっ!」
と叫んだ。
いやもう完全に意識していたけども。
やっぱりトールは覚醒していなかった。
そして練習は結局練習で、本番には使えないんだな、と思ってしまった。
いやでも実際、ここでハッキリおっぱいという単語を聞いてしまったら、うかつにもう「次のおんぶは僕だ」とか言えなくなったな、とか思っていると、博士がメガネを上げながらこう言った。
「おっぱいに、耐える、練習、させて、下さい」
いや!
「おっぱいを意識した状態でよく言い出せるね! せめておっぱいは関係無い感じで言い出しなよ!」
しかしイッチンは首を横に振り、
「ええねん、理央。アタシはアンタら三人にならいくらでもおっぱい貸し出せんねん」
と言って笑った。
それに強く反応したのは博士で、その場に前屈みで倒れ込み、
「小生は、笛、担当、でした」
と言って俯いた。
いや!
「そんなことないよ! 笛担当なんて人は主審以外いないよ! 主審のある部活動じゃないからこれ!」
「いや、これは、主審のある、スポーツだ」
「スポーツでは全然無いよ! 今日も今日とてバカな部活動だよ!」
ここでイッチンが割って入って来た。
「で、アタシの傷んだ足を助けて、教室まで運んでくれる人は誰やねん」
というか教室に行くんだ、と思いつつ、僕はイッチンの前でしゃがんだ。
「おっ、理央が運んでくれるんやな、でも理央は女子みたいに線細いけども大丈夫やんかな?」
また女子みたいに、とか言って……僕は男子だ! できる!
「大丈夫! イッチンのことちゃんと運ぶから!」
「ええ気合いやん! じゃぁよろしゅー!」
そう言って僕の背中に乗ってきたイッチン。
いや! 確かに! 何か! すごい!
でもここで、おっぱいおっぱい言ってもしょうがないので、僕は歩き出した。
というかおっぱいのことは考えない! 考えたら、何か、すごくなっちゃうから……!
「乗り心地ええやん! ええやん!」
そう言いながら僕の背中の上で揺れ始めたイッチン。
いや、背中の上でおっぱいがバウンドするせいで、その感覚が一定じゃなくて、揺れるごとに触れる感じが……わざとなのか! これはわざとなのか!
なんて悪魔的な女子なんだ、イッチンは! でも! でも!
≪≪!悪くない!≫≫
そんなことを考えながら、僕はイッチンを近くにあった教室まで運びきり、またしゃがんで、イッチンが降りやすそうにしたその時、僕はちょっとバランスを崩してしまい、手を前について倒れそうになった。
「あっ! イッチン大丈夫!」
そう言って僕がすぐさま振り返ると、イッチンの顔が僕の顔の近くにあって、あわやほっぺたにキスしてしまいになったので、僕はあわあわ慌てると、
「さすがにキスはまだ早いでー!」
と僕のおでこを突いて笑った。
それを見ていた博士は笛を勢いよく二回吹いて、
「得点、連続、奪取」
トールも手を叩きながら、
「やったなっ! 理央っ!」
いや!
「別にやってはいないよ! 事故だよ! 事故!」
と僕がツッコむと、一瞬イッチンは切なげな顔で、
「事故ねぇ……」
事故という言葉に何か反応した……一体何なのだろうか……いやまあいいや、そんなことよりも、イッチンは教室で何をする気なんだろうか?