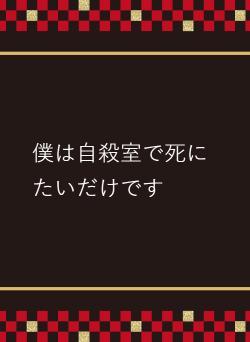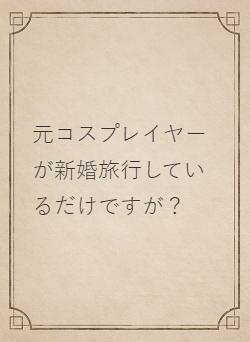・
・【男子だけのラブコメ部】
・
「そんなつれない態度ばっかりとるんじゃねぇよっ」
トールは髪をかき上げながら”僕”……じゃなくて、私のことを睨んだ。
「あの……ぼ……私……」
「なぁっ、俺のことっ、好きなんだろっ?」
そう言ったトールは私のアゴを掴み、クイっと上にあげた。
その手は力強さもあるんだけども、優しい包容力もあって、私はその手を払わず、受け入れた……ところで、博士はいつも所持しているホイッスルを吹いてから、
「カット、これは、良い、ラブコメ、でしたね」
ここで博士の止めが入った。
すぐさま博士のほうを見たトール、かなり自信満々の眼差しだ、果たして。
「トール、今回の演技、ほぼ百点だ、もう誰にでも、アゴクイ、できるだろう」
「やったぜっ! やっぱやってると俺たちっ、どんどんラブコメが上手くなるなぁっ!」
確かにトールの演技力はもう完璧で、本番でも大活躍だろうなとは思ったけども、思ったけども!
「僕にも男役やらせてよ!」
「いやでも理央は中性的な猫顔でっ、もうほぼ女じゃんかっ。俺は顔が昭和の男前だしっ、博士は典型的な塩顔じゃんかっ。名前もめちゃくちゃ女っぽいしっ」
「名前のことは言わないでよ! 僕、気にしているんだからね!」
と僕が少しムッとすると、トールが僕の頭をくしゃくしゃ撫でながら、
「悪いっ、ゴメンなっ、赤く膨れ上がった理央の可愛い顔が見たくなったんだよっ」
それに博士が唸りながら、
「それも、ポイントが、高いな、もう、トールは、ほぼ現代のイケメン、だな」
と満足げに笑った。
いや!
「僕にも成長するチャンスを与えてよ!」
でも全然僕の意見は通らなくて。
そんなに僕を無視するならば、いっそのことこのラブコメ部、辞めたっていいんだから!
いやまあどうせ帰宅部に戻るだけで、暇だから、三人と遊んでいたほうが面白いけどさ。
とか思っていると、トールがこんなことを言い出した。
「そろそろ女をラブコメ部に入れたいなっ!」
いやでも
「女って言ってる時点で何か見込みが低いよ、女性って言うべきだよ、女子とかさ」
ここに博士が反応する。
「確かに、一理ある、ただし、トールは、オラオラ系、だから、女でも、合ってるかもしれない」
「だよなーっ! 俺はガチガチの硬派だから女で合ってるよなーっ!」
でも
「そういうキャラは僕たちにしか見せないから、クラスの女子とかは分かんないだろうねぇ」
と何気なく言った言葉にトールは一気に肩を落として、
「女子とはっ、話せないからなっ……理央以外っ……っ」
そう言って僕のほうを睨んだ。
さっきの演技の力強い眼差しじゃなくて、マジの妬みのヤツだ。
いやでも!
「僕はほら! 何か可愛いとか言われてさ! でも不本意ではあるんだからね! トールみたいにカッコ良くありたいと思っているんだから!」
そんな僕の慌てて絞り出した声にトールは納得するように頷きながら、
「まあ俺ってカッコイイからなっ」
博士は鼻で笑ってから、
「単純だな、女性に、言われた、みたいに、言うな」
「うるせぇっ! 理央はもうほぼ女だよっ!」
「いや違うけどもね! 僕は男だから!」
そう言ってから三人で笑い合った。
深く考えると、かなり悲しい部活動だけども、僕はこの三人でいることが本当に好きだ。大好きだ。
女子の役ばかりやらされるので、少し男子の役もやりたくなるけども、実際は正直そんなにしなくてもいいと思っている。
だって僕は女子に興味が無いから。それよりも男子のトールと博士と一緒にいれればそれでいい。
それに、何か女子って僕の見た目を「可愛い」「可愛い」言ってきて、ちょっと腹が立つんだ。
小学生の低学年なら可愛いでも嬉しかったかもしれないけども、中学一年生になって可愛いは何かイライラしちゃう。
だから僕はこの三人で、と思いながら、部室に戻った。
廊下を歩いているとトールが、
「というか今週の週刊少年アガジン読んだっ? ドキュアイでめちゃくちゃエロいラッキースケベのシーンがあったんだぜっ!」
その一言に博士がコホンと一息ついてから、
「その略し方、してるの、トールだけだよな、普通に、同級生は俺の愛人って、言えよ」
「いやもうドキュアイだろっ! 心臓がドキュドキュするみたいで良い略し方だろっ!」
いや
「心臓がドキュドキュするって何? ちょっとドクドク血が漏れていそうじゃないか」
「いやっ! 理央の発想グロテスクだなっ! ドキュドキュとドリルみたいだろっ!」
いやいや
「ドリルだったらなおさら心臓に穴空きそうじゃないか!」
「そんなことないだろっ! 理央が妙にグロテスクで困っていますっ!」
「いや急に、ですます口調! 何か漫画のタイトルみたいになった!」
博士は頷きながら、
「まあ実際、小生たちは、表向きは、漫画部な、わけだから、漫画みたいな、タイトル、言うことは、いいことだな」
そう、僕たちは一応漫画部ということで通っている。
実際は人気のいない廊下でラブコメのシーンの練習をする部活動なんだけども。
一応、地方のマンガ・コンテストに四コマ漫画を投稿したりして、漫画部らしい体面を保っている。
でもそんなコンテストもいっぱいあるわけではないので、あとは大体練習に疲れたら、部室に戻って漫画を読むだけだ。
練習に疲れたらって何か、野球部がタイヤを引きずって走っているみたいな感じだけども、漫画部は遊んでいるだけだ。
「とりまさっ! ドキュアイ見ろってっ! 今日持ってきたからっ!」
そう言いながら部室の扉を開けたトールは驚愕の表情をした。
もう目ん玉飛び出るくらいに驚いている。
一体どうしたんだろうと思い、僕と博士も部室の中を見ると、なんとそこにはショートカットの女子の後ろ姿が。
誰かいる……僕は立ちすくむ博士とトールをかわして、部室の中に入っていった。
「おいっ! 理央っ! 危険だっ!」
一体何が、と思いつつ、トールの言葉は無視して、その女子に話し掛けた。
「ここは漫画部の部室ですよ、これから部活をするので帰って下さい」
するとその女子は振り向いてこう言った。
「ええやん! ええやん! アタシも漫画好きやし、いさせてやー!」
・【男子だけのラブコメ部】
・
「そんなつれない態度ばっかりとるんじゃねぇよっ」
トールは髪をかき上げながら”僕”……じゃなくて、私のことを睨んだ。
「あの……ぼ……私……」
「なぁっ、俺のことっ、好きなんだろっ?」
そう言ったトールは私のアゴを掴み、クイっと上にあげた。
その手は力強さもあるんだけども、優しい包容力もあって、私はその手を払わず、受け入れた……ところで、博士はいつも所持しているホイッスルを吹いてから、
「カット、これは、良い、ラブコメ、でしたね」
ここで博士の止めが入った。
すぐさま博士のほうを見たトール、かなり自信満々の眼差しだ、果たして。
「トール、今回の演技、ほぼ百点だ、もう誰にでも、アゴクイ、できるだろう」
「やったぜっ! やっぱやってると俺たちっ、どんどんラブコメが上手くなるなぁっ!」
確かにトールの演技力はもう完璧で、本番でも大活躍だろうなとは思ったけども、思ったけども!
「僕にも男役やらせてよ!」
「いやでも理央は中性的な猫顔でっ、もうほぼ女じゃんかっ。俺は顔が昭和の男前だしっ、博士は典型的な塩顔じゃんかっ。名前もめちゃくちゃ女っぽいしっ」
「名前のことは言わないでよ! 僕、気にしているんだからね!」
と僕が少しムッとすると、トールが僕の頭をくしゃくしゃ撫でながら、
「悪いっ、ゴメンなっ、赤く膨れ上がった理央の可愛い顔が見たくなったんだよっ」
それに博士が唸りながら、
「それも、ポイントが、高いな、もう、トールは、ほぼ現代のイケメン、だな」
と満足げに笑った。
いや!
「僕にも成長するチャンスを与えてよ!」
でも全然僕の意見は通らなくて。
そんなに僕を無視するならば、いっそのことこのラブコメ部、辞めたっていいんだから!
いやまあどうせ帰宅部に戻るだけで、暇だから、三人と遊んでいたほうが面白いけどさ。
とか思っていると、トールがこんなことを言い出した。
「そろそろ女をラブコメ部に入れたいなっ!」
いやでも
「女って言ってる時点で何か見込みが低いよ、女性って言うべきだよ、女子とかさ」
ここに博士が反応する。
「確かに、一理ある、ただし、トールは、オラオラ系、だから、女でも、合ってるかもしれない」
「だよなーっ! 俺はガチガチの硬派だから女で合ってるよなーっ!」
でも
「そういうキャラは僕たちにしか見せないから、クラスの女子とかは分かんないだろうねぇ」
と何気なく言った言葉にトールは一気に肩を落として、
「女子とはっ、話せないからなっ……理央以外っ……っ」
そう言って僕のほうを睨んだ。
さっきの演技の力強い眼差しじゃなくて、マジの妬みのヤツだ。
いやでも!
「僕はほら! 何か可愛いとか言われてさ! でも不本意ではあるんだからね! トールみたいにカッコ良くありたいと思っているんだから!」
そんな僕の慌てて絞り出した声にトールは納得するように頷きながら、
「まあ俺ってカッコイイからなっ」
博士は鼻で笑ってから、
「単純だな、女性に、言われた、みたいに、言うな」
「うるせぇっ! 理央はもうほぼ女だよっ!」
「いや違うけどもね! 僕は男だから!」
そう言ってから三人で笑い合った。
深く考えると、かなり悲しい部活動だけども、僕はこの三人でいることが本当に好きだ。大好きだ。
女子の役ばかりやらされるので、少し男子の役もやりたくなるけども、実際は正直そんなにしなくてもいいと思っている。
だって僕は女子に興味が無いから。それよりも男子のトールと博士と一緒にいれればそれでいい。
それに、何か女子って僕の見た目を「可愛い」「可愛い」言ってきて、ちょっと腹が立つんだ。
小学生の低学年なら可愛いでも嬉しかったかもしれないけども、中学一年生になって可愛いは何かイライラしちゃう。
だから僕はこの三人で、と思いながら、部室に戻った。
廊下を歩いているとトールが、
「というか今週の週刊少年アガジン読んだっ? ドキュアイでめちゃくちゃエロいラッキースケベのシーンがあったんだぜっ!」
その一言に博士がコホンと一息ついてから、
「その略し方、してるの、トールだけだよな、普通に、同級生は俺の愛人って、言えよ」
「いやもうドキュアイだろっ! 心臓がドキュドキュするみたいで良い略し方だろっ!」
いや
「心臓がドキュドキュするって何? ちょっとドクドク血が漏れていそうじゃないか」
「いやっ! 理央の発想グロテスクだなっ! ドキュドキュとドリルみたいだろっ!」
いやいや
「ドリルだったらなおさら心臓に穴空きそうじゃないか!」
「そんなことないだろっ! 理央が妙にグロテスクで困っていますっ!」
「いや急に、ですます口調! 何か漫画のタイトルみたいになった!」
博士は頷きながら、
「まあ実際、小生たちは、表向きは、漫画部な、わけだから、漫画みたいな、タイトル、言うことは、いいことだな」
そう、僕たちは一応漫画部ということで通っている。
実際は人気のいない廊下でラブコメのシーンの練習をする部活動なんだけども。
一応、地方のマンガ・コンテストに四コマ漫画を投稿したりして、漫画部らしい体面を保っている。
でもそんなコンテストもいっぱいあるわけではないので、あとは大体練習に疲れたら、部室に戻って漫画を読むだけだ。
練習に疲れたらって何か、野球部がタイヤを引きずって走っているみたいな感じだけども、漫画部は遊んでいるだけだ。
「とりまさっ! ドキュアイ見ろってっ! 今日持ってきたからっ!」
そう言いながら部室の扉を開けたトールは驚愕の表情をした。
もう目ん玉飛び出るくらいに驚いている。
一体どうしたんだろうと思い、僕と博士も部室の中を見ると、なんとそこにはショートカットの女子の後ろ姿が。
誰かいる……僕は立ちすくむ博士とトールをかわして、部室の中に入っていった。
「おいっ! 理央っ! 危険だっ!」
一体何が、と思いつつ、トールの言葉は無視して、その女子に話し掛けた。
「ここは漫画部の部室ですよ、これから部活をするので帰って下さい」
するとその女子は振り向いてこう言った。
「ええやん! ええやん! アタシも漫画好きやし、いさせてやー!」