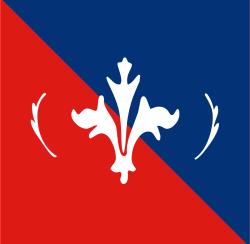「……ただいま」
リビングの扉を開けて、顔だけを覗かせて中を見た。台所にいるお母さん、ソファに座ってテレビを見ている妹、テーブルでお酒を飲みながら新聞を読むお父さん。
どこにでもある、ごく普通の一般家庭だ。
「ご飯、もうみんな食べちゃったけど、アンタどうする?外で食べてきたの?」
「……うん。今日の夕飯は明日の朝食べるから、冷蔵庫に入れといて。ごめん」
本当は食べてないし、お腹もすいていた。だけど、そんなことも気にならないくらい胸がいっぱいで、今は少しでも早く自分の部屋に行きたかった。
二階に上がって、自分の部屋に入ってから、適当にカバンを床に置いて、棚を開けた。
画用紙サイズの紙を用意して、水彩絵の具をばらばらと出していく。パレットとバケツも取り出すと、バケツを持って階段を駆け降りた。
洗面台でバケツに水を汲むと、こぼれない程度に急いでまた階段を上がった。
部屋に戻ってバケツを置いて、早々に紙を手に取った。
何も考えず、ただただ衝動に任せてシャーペンを動かす。
ーー描かなきゃ。
そう、思った。星空の下、笑う颯を見て。