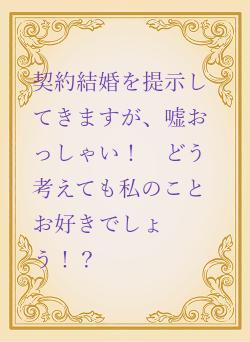幸い、太一さんのお祓いは翌日に終わり、太一さんは執筆を終わらせるために慌てて帰っていきましたが、随分身体が軽くなったようで、翼が生えたように軽やかに帰っていきました。お祓いの代金は、嶋神社よりも安い額だったと思いますが、太一さんはお礼といって大きな額を払っていってくれたので、わたくしたちは呆気にとられてしまったのですが、喜助さんはわたくしたちに受け取るように丁寧に言って、太一さんを連れて帰っていきました。
舞をやると言ったのは良いのですが、さて、舞は誰が何をすればいいのか。そしてどうやって舞を見に来てもらうか、が重要になるでしょうか。幸い、太一さんが作家仲間に蘿月様のお祓いの評判を伝えてくれたようで、作家を職業とする人たちが、鎌倉へ取材がてら蘭麝神社を覗いてくれるようになったり、大事な用事や何かあった時の後にお祓いをお願いしてくれるようになったりしたので、今すぐ経営が危機、というわけではなくなったのですが、はやり神社合祀の心配もありますので、やはり地域の皆から愛される神社に作らなくてはなりません。太一さんの作家仲間は東京にいる人が多いので、鎌倉に住む人に愛されるには、やはり何かしなくてはならないようでした。
舞は教わったことがありませんが、やはり神秘性というものを表わし、またお客様に体験してもらうのなら、舞が一番であるように思います。わたくしは華族の生まれでありながら、華道も茶道もお琴も習わせてもらえなかった身なので、当然、舞踊というものもさせてもらったこともありません。十四から習い始めるには遅いかもしれませんが、遅いからと言って、やらないという選択肢はありませんでした。
「舞を習えるところ、あったかな」
朝食の際に舞を習いたいと言うと、蘿月様と躑躅さんは首を傾げましたが、二人ともまだ明治に変わって以降、街を何度も散策したわけではないようですので、すぐに思いつくところはないようでした。
「街に出ても、良いでしょうか」
どうして聞くんだい、と蘿月様が首を傾げました。ただすぐに、わたくしが萩原の家でほとんど軟禁状態にあったことを思い出したようで、ほんの一瞬、険しい顔をしました。
「そうだな、まだ、志貴が生きているから、一人で行って良いとは言えないが。ただ躑躅か俺のどちらかがつこう、だからお前は、出かけたい、と言えばいいのだよ」
「そうよぉ。必ず琥珀の行きたい時に合わせてあげられるわけじゃないけど。でもそんな、出かけたらだめなんて言わないから」
幸い、今日はお祓いの約束もない。一緒に行こうか。蘿月様にそう微笑まれて、わたくしは頷きました。彼と一緒に出掛けられるのだと思うと、嬉しくてたまりません。家のことがある程度済んだ後、わたくしは髪を英吉利結びという髪型にして、鎌倉の街に出ました。結界、というものの外に出ると、わたくしはどうやら、志貴様は志貴様の手下の目につきやすくなるそうなので、姿隠しのお守りを懐に忍ばせながらになりましたが、街を歩く人は皆、わたくしの存在を気が付いているのに見ないといった風に、視線が合ったり、服を観察したりすることもないのに、ぶつかられることすらありませんでした。
「舞って、どこで習えるのでしょうか」
「俺も分からないのだ」
二人で顔を見合わせて、それから吹き出します。街は十年でも変わりますから、百年二百年と経てば、もっと変わっていくのでしょう。蘿月様もきょろきょろと辺りを見渡しながら進んでいきますので、ほどほどに散策したら、街行く人に聞いてみようかと思ったところ、道の向こうから、太一さんと喜助さんが走ってきます。
「俺の物語は要らなくても、俺の人脈は要るのではないかと」
「えっと、作家はあれこれ取材に行っているから、少し詳しいとのことだ」
「東京から、わざわざ来てくださったのですか」
驚いた声を上げるわたくしに、太一さんは頷きます。喜助さんは相変わらず付き添いのようでしたが、不思議と、二人とも目が輝いているように見えました。
「祓ってもらったら、どれだけ自分が辛かったか分かっちまってな。これはもう、お金だけでお礼は出来ないと、そう思ったわけでさァ」
「十分、大金は、頂いてますのに」
「お嬢さん、もしや人間の縁が金以外で出来てることを知らねぇな」
喜助さんは軽い冗談のつもりで、笑って言ったようですが、わたくしの胸に、何か刃が刺さったような気がしました。
どうやら、生家がわたくしをお金で売ったこと、彼らに、援助金をさらにせしめるために志貴様に気に入られるように言われたことが、わたくしの中で存外深い傷になっているようでした。政略結婚が当たり前の時分ですから、上流階級の間では、自由恋愛を楽しもうとすれば、駆け落ちするのがほとんどになりましょうか。お父様とお義母様のように、恋愛関係にある人を妾にすることはできますが、やはり人というものは、売られるようにして結婚するものです。女の場合、外で働くと家の名誉を傷つけることがありますので、嫁入り前の奉公を除いては、家の仕事以外許されないこともしばしばあります。そうなるとどうしても、女は結婚先の家に飼われる他なくなります。また、より上の身分の者やお金のある者と結ばれることで家は富を得ますから、お金のために結婚することは珍しくはないのですが、援助金以外のことは一つもお父様とお義母様に期待されたことはなく、気晴らしに叩かれたり怒鳴られたりすることばかりだったのに、わたくしを通して援助金を得られることになったら、搾り取れるだけ搾り取ろうとする、彼らの魂胆を醜く思ったものですが、わたくしはそれを、あまり気にしないようにしていました。まったく平気だったわけではありませんが、女はこういうものだから仕方ないと、諦めていました。きっとほたるも、もっと位の上の殿方と嫁ぐために、今頃花嫁修業に精を出しているはずですから、彼女も売られるようにして結婚するのだろうと、思っていました。
「お嬢さん、あのな、この旦那さんがお前さんに心底惚れ込んでるみたいに、人間、案外縁とか恩で生きてるのさ」
ああ、そうか。小さな声が零れました。わたくしは、お金のためにかろうじて生家で食べさせられていたのでした。売られるために育てられたのでした。売られるように嫁ぐ女たちですが、親がその娘のためを思って相手を選ぶか、育てるかによって、天と地ほどの差がありましょう。わたくしのことを冷遇しながらも、わたくしと母を、母の実家に帰しはしなかったのは、成長したわたくしを売るためだったのだと気が付いて、心底吐き気がしました。そうして、喜助さんや太一さんは、お金のためではなく、縁や恩を大事にしていると聞いて、人にはうつくしい人もいるのだと、わたくしの周りにいたほとんどの人間が、汚く、醜い者ばかりだったのだと、やっと気が付いたのでした。
お母様が可哀そうだわ。ぽつりとそう呟きました。そんな呟きは蘿月様にしか聞こえなかったようで、はっとしたような顔をしたのも、彼だけでした。
「今度あんたらの神社を小説に出させてもらうからな。良いネタになるから、まあ、そのお礼料でもあるさね」
ついでにうまい店を教えるからな、と喜助さんが言い、わたくしと蘿月様は、二人について歩きます。そうして、二人には聞こえないような声で、蘿月様にそっと耳打ちしました。
「人には、これほど綺麗な人がいるのですね」
「そうさ。きっとお前は、これからたくさんの心の澄んだ人に出会うよ。性根の腐った者もいくらでもいるが、きっとお前の周りには、優しい人が集まるに違いない」
そうでしょうか、と呟くと、彼は頷いて、わたくしの頭を撫でてくれます。そうされている間になんだか安心して、いつか優しい人に囲まれるようになれば良いと思いました。それと同時に、もう随分、萩原の家から連れ出されて以降優しくしてもらっていますから、これ以上を望んでいいのか、不安に思いました。
舞をやると言ったのは良いのですが、さて、舞は誰が何をすればいいのか。そしてどうやって舞を見に来てもらうか、が重要になるでしょうか。幸い、太一さんが作家仲間に蘿月様のお祓いの評判を伝えてくれたようで、作家を職業とする人たちが、鎌倉へ取材がてら蘭麝神社を覗いてくれるようになったり、大事な用事や何かあった時の後にお祓いをお願いしてくれるようになったりしたので、今すぐ経営が危機、というわけではなくなったのですが、はやり神社合祀の心配もありますので、やはり地域の皆から愛される神社に作らなくてはなりません。太一さんの作家仲間は東京にいる人が多いので、鎌倉に住む人に愛されるには、やはり何かしなくてはならないようでした。
舞は教わったことがありませんが、やはり神秘性というものを表わし、またお客様に体験してもらうのなら、舞が一番であるように思います。わたくしは華族の生まれでありながら、華道も茶道もお琴も習わせてもらえなかった身なので、当然、舞踊というものもさせてもらったこともありません。十四から習い始めるには遅いかもしれませんが、遅いからと言って、やらないという選択肢はありませんでした。
「舞を習えるところ、あったかな」
朝食の際に舞を習いたいと言うと、蘿月様と躑躅さんは首を傾げましたが、二人ともまだ明治に変わって以降、街を何度も散策したわけではないようですので、すぐに思いつくところはないようでした。
「街に出ても、良いでしょうか」
どうして聞くんだい、と蘿月様が首を傾げました。ただすぐに、わたくしが萩原の家でほとんど軟禁状態にあったことを思い出したようで、ほんの一瞬、険しい顔をしました。
「そうだな、まだ、志貴が生きているから、一人で行って良いとは言えないが。ただ躑躅か俺のどちらかがつこう、だからお前は、出かけたい、と言えばいいのだよ」
「そうよぉ。必ず琥珀の行きたい時に合わせてあげられるわけじゃないけど。でもそんな、出かけたらだめなんて言わないから」
幸い、今日はお祓いの約束もない。一緒に行こうか。蘿月様にそう微笑まれて、わたくしは頷きました。彼と一緒に出掛けられるのだと思うと、嬉しくてたまりません。家のことがある程度済んだ後、わたくしは髪を英吉利結びという髪型にして、鎌倉の街に出ました。結界、というものの外に出ると、わたくしはどうやら、志貴様は志貴様の手下の目につきやすくなるそうなので、姿隠しのお守りを懐に忍ばせながらになりましたが、街を歩く人は皆、わたくしの存在を気が付いているのに見ないといった風に、視線が合ったり、服を観察したりすることもないのに、ぶつかられることすらありませんでした。
「舞って、どこで習えるのでしょうか」
「俺も分からないのだ」
二人で顔を見合わせて、それから吹き出します。街は十年でも変わりますから、百年二百年と経てば、もっと変わっていくのでしょう。蘿月様もきょろきょろと辺りを見渡しながら進んでいきますので、ほどほどに散策したら、街行く人に聞いてみようかと思ったところ、道の向こうから、太一さんと喜助さんが走ってきます。
「俺の物語は要らなくても、俺の人脈は要るのではないかと」
「えっと、作家はあれこれ取材に行っているから、少し詳しいとのことだ」
「東京から、わざわざ来てくださったのですか」
驚いた声を上げるわたくしに、太一さんは頷きます。喜助さんは相変わらず付き添いのようでしたが、不思議と、二人とも目が輝いているように見えました。
「祓ってもらったら、どれだけ自分が辛かったか分かっちまってな。これはもう、お金だけでお礼は出来ないと、そう思ったわけでさァ」
「十分、大金は、頂いてますのに」
「お嬢さん、もしや人間の縁が金以外で出来てることを知らねぇな」
喜助さんは軽い冗談のつもりで、笑って言ったようですが、わたくしの胸に、何か刃が刺さったような気がしました。
どうやら、生家がわたくしをお金で売ったこと、彼らに、援助金をさらにせしめるために志貴様に気に入られるように言われたことが、わたくしの中で存外深い傷になっているようでした。政略結婚が当たり前の時分ですから、上流階級の間では、自由恋愛を楽しもうとすれば、駆け落ちするのがほとんどになりましょうか。お父様とお義母様のように、恋愛関係にある人を妾にすることはできますが、やはり人というものは、売られるようにして結婚するものです。女の場合、外で働くと家の名誉を傷つけることがありますので、嫁入り前の奉公を除いては、家の仕事以外許されないこともしばしばあります。そうなるとどうしても、女は結婚先の家に飼われる他なくなります。また、より上の身分の者やお金のある者と結ばれることで家は富を得ますから、お金のために結婚することは珍しくはないのですが、援助金以外のことは一つもお父様とお義母様に期待されたことはなく、気晴らしに叩かれたり怒鳴られたりすることばかりだったのに、わたくしを通して援助金を得られることになったら、搾り取れるだけ搾り取ろうとする、彼らの魂胆を醜く思ったものですが、わたくしはそれを、あまり気にしないようにしていました。まったく平気だったわけではありませんが、女はこういうものだから仕方ないと、諦めていました。きっとほたるも、もっと位の上の殿方と嫁ぐために、今頃花嫁修業に精を出しているはずですから、彼女も売られるようにして結婚するのだろうと、思っていました。
「お嬢さん、あのな、この旦那さんがお前さんに心底惚れ込んでるみたいに、人間、案外縁とか恩で生きてるのさ」
ああ、そうか。小さな声が零れました。わたくしは、お金のためにかろうじて生家で食べさせられていたのでした。売られるために育てられたのでした。売られるように嫁ぐ女たちですが、親がその娘のためを思って相手を選ぶか、育てるかによって、天と地ほどの差がありましょう。わたくしのことを冷遇しながらも、わたくしと母を、母の実家に帰しはしなかったのは、成長したわたくしを売るためだったのだと気が付いて、心底吐き気がしました。そうして、喜助さんや太一さんは、お金のためではなく、縁や恩を大事にしていると聞いて、人にはうつくしい人もいるのだと、わたくしの周りにいたほとんどの人間が、汚く、醜い者ばかりだったのだと、やっと気が付いたのでした。
お母様が可哀そうだわ。ぽつりとそう呟きました。そんな呟きは蘿月様にしか聞こえなかったようで、はっとしたような顔をしたのも、彼だけでした。
「今度あんたらの神社を小説に出させてもらうからな。良いネタになるから、まあ、そのお礼料でもあるさね」
ついでにうまい店を教えるからな、と喜助さんが言い、わたくしと蘿月様は、二人について歩きます。そうして、二人には聞こえないような声で、蘿月様にそっと耳打ちしました。
「人には、これほど綺麗な人がいるのですね」
「そうさ。きっとお前は、これからたくさんの心の澄んだ人に出会うよ。性根の腐った者もいくらでもいるが、きっとお前の周りには、優しい人が集まるに違いない」
そうでしょうか、と呟くと、彼は頷いて、わたくしの頭を撫でてくれます。そうされている間になんだか安心して、いつか優しい人に囲まれるようになれば良いと思いました。それと同時に、もう随分、萩原の家から連れ出されて以降優しくしてもらっていますから、これ以上を望んでいいのか、不安に思いました。