講堂の中は、死に絶えたような静寂が横たわっていた。
地下ライブハウスに特有の重低音の唸りも、開演を待つファンの熱っぽい私語もない。
安っぽいワックスの匂いの底に、拭き残された血の鉄臭さと、長年蓄積された囚人たちの不潔な体臭がまで再現されている。
鼻を突く鉄臭さも、『監獄』という作品の一部に思えた。ここまでリアリティに固執する地下ライブが、かつてあっただろうか。
藍田は、指定された三列目の椅子に深く腰を下ろした。周囲を見渡すと、そこに集まった『面会人』たちは、一様に奇妙なほど大人しかった。
三十代から五十代の、社会の片隅にへばりついて生きているような男たち。彼らはペンライトを持つ代わりに、膝の上で両手を固く握りしめ、前方の暗がりを凝視している。
不意に、舞台袖から乾いた音が響いた。
軍靴の音だ。
スーツ姿の男たちとは明らかに違う、深い紺色の制服を纏った刑務官たちが、二人一組で左右から現れた。手には、警棒ではなく、太い麻縄の端が握られている。
縄の先には、四人の少女たちが繋がれていた。
腰縄を回され、一列に数珠繋ぎにされた姿は、かつての江戸時代の刑場へ向かう罪人の行列を彷彿とさせた。手元は、鈍色の金属が光る手錠で固定されている。
刑務官たちは彼女らを見ることなく、客席に座る藍田たちの喉元を、害獣でも見るような冷徹な眼差しでなぞっていた。
般若の面を被った彼女たちが、重い足取りでステージ中央に立つ。照明が、暴力的なまでの白さで彼女たちを射抜いた。
音楽が始まった。
激しいビートではない。震えるようなピアノの旋律が、講堂の冷たい空気を震わせる。
一曲目は、バラードだった。
彼女たちは、面を被ったまま歌い始めた。
マイクもスピーカーもない剥き出しの空間に、生々しい歌声が響き渡る。それは、明日をも知れぬ命が絞り出す、最後の一呼吸のような切実さを孕んでいた。
「ううっ……」
隣に座っていた中年男が、こらえきれずに嗚咽を漏らした。感動ではない。圧倒的な死の気配に当てられた、生存本能の悲鳴に近かった。
男たちの啜り泣きが、読経のように講堂を浸食していく。
歌が終わると、伴奏が止まった。
静寂が戻る。だが、それは先ほどよりも重く、粘り気のある沈黙だった。
舞台中央に、番号四〇二番・沙希がゆっくりと進んだ。
他の三人は影のように後方へ下がり、膝をついてハミングを続けている。低く、地這うような和音が、講堂の冷えた空気を震わせる。
沙希がゆっくりと顔を上げた。
般若の面を外したその素顔は、暴力的なまでに整っていた。だが、瞳には光がない。

深い、底なしの暗渠《あんきょ》を覗き込んでいるような錯覚に、藍田は眩暈《めまい》を覚えた。
頭上のスクリーンに、無機質な明朝体の文字が映し出される。
【令和五年(わ)第〇〇号 殺人被告事件】
東京地方裁判所 刑事第五部
主文
被告人を死刑に処する――。
『死刑』という二文字が、白く、冷たく、藍田の網膜を刺した。
「……私の主文が読み上げられた時、法廷が静まり返りました」
沙希の口から漏れたのは、歌声ではなく、氷の破片のような言葉だ。
「裁判長の声は、とても優しかった。まるで、これ以上汚れないようにと、私を箱に閉じ込める約束をしてくれているみたいに」
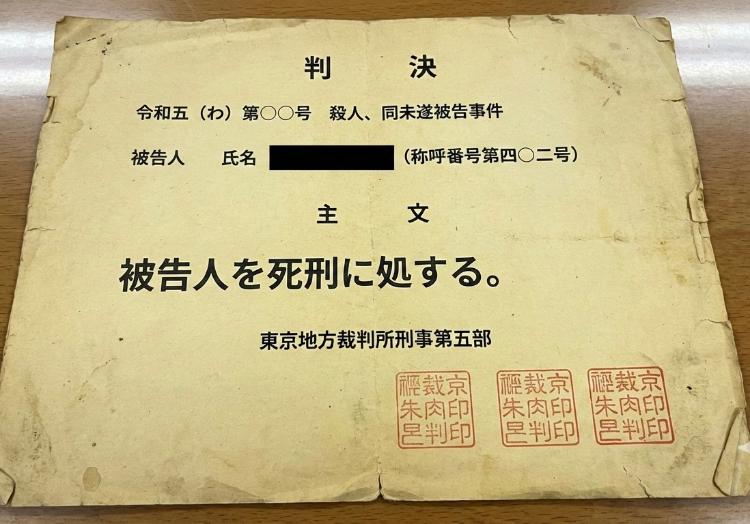
彼女が歌い始めた。
一曲目のバラードとは打って変わった、美しくも歪なメロディ。
歌詞は、彼女がワインに毒を落とした瞬間の、泡立つ心音を綴ったものだった。
「披露宴、白いドレス、高いシャンパン。みんなが幸福の絶頂にいて、これからの輝かしい未来を信じて疑わない。その無防備な喉元に、私が選んだ『無』を滑り込ませる」
沙希の手首が動く。手錠がチャリ、と無機質な音を立て、リズムを刻む。
「十二人が崩れ落ちました。泡を吹き、白目を剥いて、最高の幸福から一瞬で地獄へ。その瞬間、会場で一番美しく哀れだったのは、誰でもない、私でした」
藍田は震える手で、パイプ椅子の端を掴んだ。
彼女の告白に合わせて、スクリーンには当時の「現場証拠」が次々と投影される。
・【証拠番号12:割れたワイングラスと吐瀉物の付着した絨毯】
・【証拠番号45:証拠番号45:被告人の自撮り写真。微笑む彼女の背後で、這い蹲る新婦が純白のドレスに『毒の泡』を吐き出している。その白い飛沫が、まるで精緻な刺繍のように沙希のスカートの裾を汚していた】
・【精神鑑定書:『自己愛性パーソナリティ障害の傾向があるが、責任能力は完全に認められる』】
それらは、ファンがアイドルの『成長記録』を眺めるのとは真逆の、死へのカウントダウンだった。
沙希は、独白を終えると、再び般若の面を顔に当てた。面の奥から漏れる、深い溜息。
「……次は、七一五番」
沙希が静かに退く。
藍田の脳裏には、先ほどの『主文』の二文字が、焦げ付いたように消えずに残っていた。
一人の美しい女性を公開処刑するための手続き。
自分はその一端を、支援という名目で、たった今買い支えたのだ。
次の瞬間、講堂の照明が血のように赤く染まった。
七一五番。
莉央の番が来る――。
地下ライブハウスに特有の重低音の唸りも、開演を待つファンの熱っぽい私語もない。
安っぽいワックスの匂いの底に、拭き残された血の鉄臭さと、長年蓄積された囚人たちの不潔な体臭がまで再現されている。
鼻を突く鉄臭さも、『監獄』という作品の一部に思えた。ここまでリアリティに固執する地下ライブが、かつてあっただろうか。
藍田は、指定された三列目の椅子に深く腰を下ろした。周囲を見渡すと、そこに集まった『面会人』たちは、一様に奇妙なほど大人しかった。
三十代から五十代の、社会の片隅にへばりついて生きているような男たち。彼らはペンライトを持つ代わりに、膝の上で両手を固く握りしめ、前方の暗がりを凝視している。
不意に、舞台袖から乾いた音が響いた。
軍靴の音だ。
スーツ姿の男たちとは明らかに違う、深い紺色の制服を纏った刑務官たちが、二人一組で左右から現れた。手には、警棒ではなく、太い麻縄の端が握られている。
縄の先には、四人の少女たちが繋がれていた。
腰縄を回され、一列に数珠繋ぎにされた姿は、かつての江戸時代の刑場へ向かう罪人の行列を彷彿とさせた。手元は、鈍色の金属が光る手錠で固定されている。
刑務官たちは彼女らを見ることなく、客席に座る藍田たちの喉元を、害獣でも見るような冷徹な眼差しでなぞっていた。
般若の面を被った彼女たちが、重い足取りでステージ中央に立つ。照明が、暴力的なまでの白さで彼女たちを射抜いた。
音楽が始まった。
激しいビートではない。震えるようなピアノの旋律が、講堂の冷たい空気を震わせる。
一曲目は、バラードだった。
彼女たちは、面を被ったまま歌い始めた。
マイクもスピーカーもない剥き出しの空間に、生々しい歌声が響き渡る。それは、明日をも知れぬ命が絞り出す、最後の一呼吸のような切実さを孕んでいた。
「ううっ……」
隣に座っていた中年男が、こらえきれずに嗚咽を漏らした。感動ではない。圧倒的な死の気配に当てられた、生存本能の悲鳴に近かった。
男たちの啜り泣きが、読経のように講堂を浸食していく。
歌が終わると、伴奏が止まった。
静寂が戻る。だが、それは先ほどよりも重く、粘り気のある沈黙だった。
舞台中央に、番号四〇二番・沙希がゆっくりと進んだ。
他の三人は影のように後方へ下がり、膝をついてハミングを続けている。低く、地這うような和音が、講堂の冷えた空気を震わせる。
沙希がゆっくりと顔を上げた。
般若の面を外したその素顔は、暴力的なまでに整っていた。だが、瞳には光がない。

深い、底なしの暗渠《あんきょ》を覗き込んでいるような錯覚に、藍田は眩暈《めまい》を覚えた。
頭上のスクリーンに、無機質な明朝体の文字が映し出される。
【令和五年(わ)第〇〇号 殺人被告事件】
東京地方裁判所 刑事第五部
主文
被告人を死刑に処する――。
『死刑』という二文字が、白く、冷たく、藍田の網膜を刺した。
「……私の主文が読み上げられた時、法廷が静まり返りました」
沙希の口から漏れたのは、歌声ではなく、氷の破片のような言葉だ。
「裁判長の声は、とても優しかった。まるで、これ以上汚れないようにと、私を箱に閉じ込める約束をしてくれているみたいに」
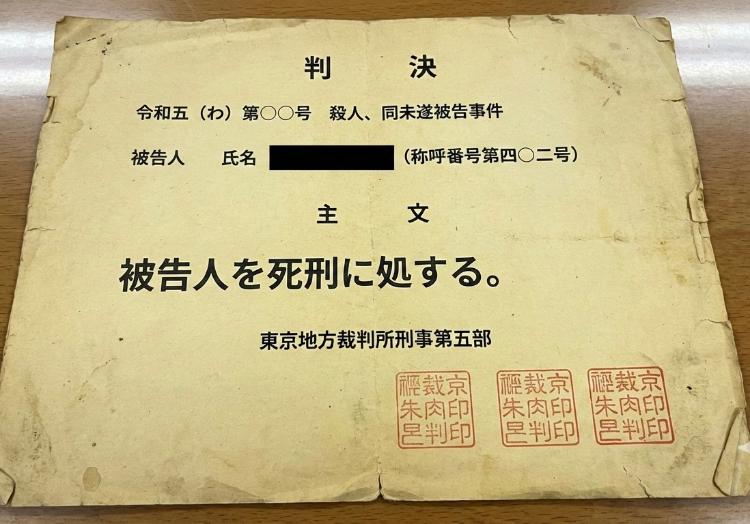
彼女が歌い始めた。
一曲目のバラードとは打って変わった、美しくも歪なメロディ。
歌詞は、彼女がワインに毒を落とした瞬間の、泡立つ心音を綴ったものだった。
「披露宴、白いドレス、高いシャンパン。みんなが幸福の絶頂にいて、これからの輝かしい未来を信じて疑わない。その無防備な喉元に、私が選んだ『無』を滑り込ませる」
沙希の手首が動く。手錠がチャリ、と無機質な音を立て、リズムを刻む。
「十二人が崩れ落ちました。泡を吹き、白目を剥いて、最高の幸福から一瞬で地獄へ。その瞬間、会場で一番美しく哀れだったのは、誰でもない、私でした」
藍田は震える手で、パイプ椅子の端を掴んだ。
彼女の告白に合わせて、スクリーンには当時の「現場証拠」が次々と投影される。
・【証拠番号12:割れたワイングラスと吐瀉物の付着した絨毯】
・【証拠番号45:証拠番号45:被告人の自撮り写真。微笑む彼女の背後で、這い蹲る新婦が純白のドレスに『毒の泡』を吐き出している。その白い飛沫が、まるで精緻な刺繍のように沙希のスカートの裾を汚していた】
・【精神鑑定書:『自己愛性パーソナリティ障害の傾向があるが、責任能力は完全に認められる』】
それらは、ファンがアイドルの『成長記録』を眺めるのとは真逆の、死へのカウントダウンだった。
沙希は、独白を終えると、再び般若の面を顔に当てた。面の奥から漏れる、深い溜息。
「……次は、七一五番」
沙希が静かに退く。
藍田の脳裏には、先ほどの『主文』の二文字が、焦げ付いたように消えずに残っていた。
一人の美しい女性を公開処刑するための手続き。
自分はその一端を、支援という名目で、たった今買い支えたのだ。
次の瞬間、講堂の照明が血のように赤く染まった。
七一五番。
莉央の番が来る――。





