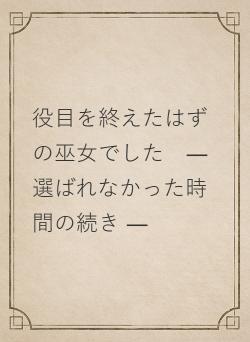アディスが騎士となったのは、選択というより、ほとんど宿命に近かった。
生まれつき魔力量がずば抜けていたため、
騎士となることが最初から定められていたかのようだった。
もともと責任感も強く、
魔力も戦闘センスも突出していた。
剣を握れば、どう動けばよいかが自然と分かる。
状況を見渡せば、どこに立てば被害を最小限に抑えられるかが分かる。
だから、いつの間にか――
自分が先陣を切れば、被害は最小限に済む、
という考えが当たり前になっていた。
国を守るという、騎士としての大義はあった。
それ以上のものは、特に必要としていなかった。
危険な場所に立つことも、
命を賭ける判断も、
すべて「役目」だった。
――少なくとも、あの時までは。
ダリアという存在を、
はっきりと意識するようになってから、
彼の中で、何かが少しずつずれていった。
最初は、取るに足らない変化だった。
彼女が癒しの力を使う場面を、何度か目にしただけだ。
あの力は、確かに人を救う。
だが同時に、使うたびに彼女自身を削っていく。
アディスにとっては今もあの時の恐怖を忘れることはできない。
――――――――
戦争が終わった直後、
この町は最前線となり、異様な光景に包まれていた。
病院も、集会所も、神殿も、
傷ついた騎士や住民で埋め尽くされている。
たくさんのけが人たちの傍を、
医師や看護人、衛生兵が忙しく動き回っていた。
アディス自身も、
右肩と左わき腹に負傷していた。
痛みはあるが、動けないわけではない。
そして、休める立場でもなかった。
戦後の残務に追われながら、
状況を整理し、指示を出し続けていた。
その最中だった。
「団長、ダリア様が、マイア神殿へ入られました」
バサラ第一師団長と話しているところへ、
騎士がそう報告に来る。
「わかった」
団長が短く答えると、
騎士は持ち場へと戻っていった。
「アディス、ダリア様のところへ顔を見せに行ってこい」
それは、命令に近い口調だった。
ダリアがアディスに懸想していることは、
貴族や騎士たちの間では暗黙の了解となっていた。
暗黙の了解で済んでいるのは、
ダリアが一度も、そういう想いを言葉にしたことがないからだ。
とはいえ、
そのことが周知の事実となっている理由は単純だった。
ダリアは、思っていることが態度に出やすい。
それだけのことだ。
ダリアが望めば、
アディスの妻となることは、そう難しい話ではない。
もちろん、アディスに婚約者でもいれば話は別だが、
断る正当な理由がなければ、
王族からの降嫁の申し入れを断るのは容易ではないのが実情だった。
「……わかりました」
そう返事をし、
アディスは神殿へと向かった。
胸の奥には、嫌な予感があった。
この実情を目の当たりにして、
あの姫は、
通常の癒しの歌を歌うだけで済ませるとは思えなかった。
神殿の広場で、
ダリアは深い悲しみをたたえた表情を浮かべ、立っていた。
「お久しぶりです」
アディスがきれいな礼をして声をかけると、
ダリアは少しだけ嬉しそうな表情を浮かべた。
「えぇ、久しぶりですね。ご無事でなによりです」
公式の場であることから、
挨拶はどこか堅苦しい。
「姫様。ご準備はよろしいですか?」
ミルゲラ大臣が声をかける。
「えぇ、大丈夫です」
「姫、まさか……」
思わず、声が漏れた。
その言葉に、
ダリアは振り返り、ふわりと笑顔を浮かべた。
アディスは、
痛いほどに手を握り締める。
そして、ダリアは癒しの歌を紡いだ。
体に、癒しの力が少しずつ流れてくる。
それは同時に、
ダリアが体力を削られている証拠でもあった。
アディスにとって、
それは苦痛でしかなかった。
それでも、
彼女の歌う姿から目を離せない。
どこまでも清楚で、
純潔で、
神々しさすら感じさせる。
ひどく、彼女を遠く感じる瞬間だった。
ダリア自身は知らないが、
彼女は国民から「癒し姫」と呼ばれている。
特に庶民の間では、
王家の中で一番人気のある姫であり、
巫女になることを望む声すらある。
癒しの歌が終わると、
ダリアはアディスのもとへ近づいた。
「もし、倒れてしまったら……その時は、お願いできますか?」
「ダリア様、お願いです、もう……」
その言葉を遮るように、
ダリアは微笑んだ。
「大丈夫です。無理はしませんから」
そう言って、
再び広場へと戻る。
そして――
今までこの国の人々が耳にしたことのない、
圧倒的な効力を持つ癒しの歌を紡ぎ始めた。
ダリアの体が、
少しずつ光り始める。
そして、
彼女は倒れた。
その後、
ダリアは三日間、床から起き上がれなかった。
意識はあったが、
食事もほとんど取れず、
指先ひとつ動かすのも辛そうで。
あの三日間は、
生きた心地がしなかった。
それ以来――
アディスの中で、
気づかないうちに基準が増えていた。
どれだけ国を守れたか。
どれだけ被害を減らせたか。
それに加えて、
もう一つ。
――ダリアに、力を使わせずに済んだか。
それは誓いでも、
使命でもなかった。
ただ、
いつの間にか考えてしまうようになった項目だった。
自分が前に出る。
自分が危険を引き受ける。
自分が血を流す。
それで、
彼女が歌わずに済むなら。
彼女が、
あの力を使わずに済むなら。
それもまた、
守れたということになるのではないか。
彼女を失うかもしれない恐怖は2度と味わいたくはなかった。
生まれつき魔力量がずば抜けていたため、
騎士となることが最初から定められていたかのようだった。
もともと責任感も強く、
魔力も戦闘センスも突出していた。
剣を握れば、どう動けばよいかが自然と分かる。
状況を見渡せば、どこに立てば被害を最小限に抑えられるかが分かる。
だから、いつの間にか――
自分が先陣を切れば、被害は最小限に済む、
という考えが当たり前になっていた。
国を守るという、騎士としての大義はあった。
それ以上のものは、特に必要としていなかった。
危険な場所に立つことも、
命を賭ける判断も、
すべて「役目」だった。
――少なくとも、あの時までは。
ダリアという存在を、
はっきりと意識するようになってから、
彼の中で、何かが少しずつずれていった。
最初は、取るに足らない変化だった。
彼女が癒しの力を使う場面を、何度か目にしただけだ。
あの力は、確かに人を救う。
だが同時に、使うたびに彼女自身を削っていく。
アディスにとっては今もあの時の恐怖を忘れることはできない。
――――――――
戦争が終わった直後、
この町は最前線となり、異様な光景に包まれていた。
病院も、集会所も、神殿も、
傷ついた騎士や住民で埋め尽くされている。
たくさんのけが人たちの傍を、
医師や看護人、衛生兵が忙しく動き回っていた。
アディス自身も、
右肩と左わき腹に負傷していた。
痛みはあるが、動けないわけではない。
そして、休める立場でもなかった。
戦後の残務に追われながら、
状況を整理し、指示を出し続けていた。
その最中だった。
「団長、ダリア様が、マイア神殿へ入られました」
バサラ第一師団長と話しているところへ、
騎士がそう報告に来る。
「わかった」
団長が短く答えると、
騎士は持ち場へと戻っていった。
「アディス、ダリア様のところへ顔を見せに行ってこい」
それは、命令に近い口調だった。
ダリアがアディスに懸想していることは、
貴族や騎士たちの間では暗黙の了解となっていた。
暗黙の了解で済んでいるのは、
ダリアが一度も、そういう想いを言葉にしたことがないからだ。
とはいえ、
そのことが周知の事実となっている理由は単純だった。
ダリアは、思っていることが態度に出やすい。
それだけのことだ。
ダリアが望めば、
アディスの妻となることは、そう難しい話ではない。
もちろん、アディスに婚約者でもいれば話は別だが、
断る正当な理由がなければ、
王族からの降嫁の申し入れを断るのは容易ではないのが実情だった。
「……わかりました」
そう返事をし、
アディスは神殿へと向かった。
胸の奥には、嫌な予感があった。
この実情を目の当たりにして、
あの姫は、
通常の癒しの歌を歌うだけで済ませるとは思えなかった。
神殿の広場で、
ダリアは深い悲しみをたたえた表情を浮かべ、立っていた。
「お久しぶりです」
アディスがきれいな礼をして声をかけると、
ダリアは少しだけ嬉しそうな表情を浮かべた。
「えぇ、久しぶりですね。ご無事でなによりです」
公式の場であることから、
挨拶はどこか堅苦しい。
「姫様。ご準備はよろしいですか?」
ミルゲラ大臣が声をかける。
「えぇ、大丈夫です」
「姫、まさか……」
思わず、声が漏れた。
その言葉に、
ダリアは振り返り、ふわりと笑顔を浮かべた。
アディスは、
痛いほどに手を握り締める。
そして、ダリアは癒しの歌を紡いだ。
体に、癒しの力が少しずつ流れてくる。
それは同時に、
ダリアが体力を削られている証拠でもあった。
アディスにとって、
それは苦痛でしかなかった。
それでも、
彼女の歌う姿から目を離せない。
どこまでも清楚で、
純潔で、
神々しさすら感じさせる。
ひどく、彼女を遠く感じる瞬間だった。
ダリア自身は知らないが、
彼女は国民から「癒し姫」と呼ばれている。
特に庶民の間では、
王家の中で一番人気のある姫であり、
巫女になることを望む声すらある。
癒しの歌が終わると、
ダリアはアディスのもとへ近づいた。
「もし、倒れてしまったら……その時は、お願いできますか?」
「ダリア様、お願いです、もう……」
その言葉を遮るように、
ダリアは微笑んだ。
「大丈夫です。無理はしませんから」
そう言って、
再び広場へと戻る。
そして――
今までこの国の人々が耳にしたことのない、
圧倒的な効力を持つ癒しの歌を紡ぎ始めた。
ダリアの体が、
少しずつ光り始める。
そして、
彼女は倒れた。
その後、
ダリアは三日間、床から起き上がれなかった。
意識はあったが、
食事もほとんど取れず、
指先ひとつ動かすのも辛そうで。
あの三日間は、
生きた心地がしなかった。
それ以来――
アディスの中で、
気づかないうちに基準が増えていた。
どれだけ国を守れたか。
どれだけ被害を減らせたか。
それに加えて、
もう一つ。
――ダリアに、力を使わせずに済んだか。
それは誓いでも、
使命でもなかった。
ただ、
いつの間にか考えてしまうようになった項目だった。
自分が前に出る。
自分が危険を引き受ける。
自分が血を流す。
それで、
彼女が歌わずに済むなら。
彼女が、
あの力を使わずに済むなら。
それもまた、
守れたということになるのではないか。
彼女を失うかもしれない恐怖は2度と味わいたくはなかった。