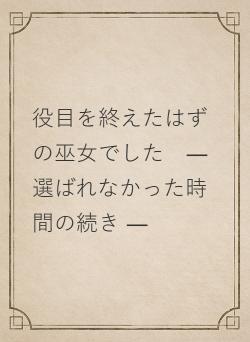「はぁ……」
思わず漏れたため息は、もう何度目だろう。
この三日間、私は数えきれないほど同じ息を吐いていた。
「ダリア様……」
付き侍女のレイラが、心配そうに私の顔を覗き込む。
その視線に気づきながらも、
私はぼんやりと彼女の顔を見つめたまま、
つい口にしてしまった。
「せめて、レイラくらい綺麗だったらよかったのになあ」
レイラはぴたりと動きを止め、
すぐに眉をひそめる。
「何をおっしゃっているのですか。
ダリア様には、ダリア様の可愛らしさがあります。
ご自分を卑下するのはおやめください」
きっぱりとした声。
いつも通りで、変わらない。
「ありがとう。
レイラは相変わらず優しいね」
そう言うと、
レイラは少し困ったように笑った。
――いつもなら、
その優しさに少し救われる。
けれど、
今の私には、
その言葉が少しだけ痛かった。
どうしても、
先日のことを思い出してしまう。
謁見の間で告げられた、
一ヶ月という期限。
お父様の、
あまりにも冷静な声。
……もう少し、
やり方があったのではないかと
思わないわけではない。
けれど、
分かってもいる。
お父様は、
私がアディスを
どれほど想っているか、
きっと最初から知っていた。
むしろ私の気持ちは、
近しい人なら誰でも
知っていると思う。
アディスの前に出ると、
どうしても顔が熱くなる。
言葉がぎこちなくなり、
視線も定まらない。
――たぶん、
本人にだって
気づかれていると思う。
私なんかに惚れられたばかりに。
彼は、
とんでもない貧乏くじを
引かされそうになっている。
王女が降嫁することは、
家にとっては
確かに利益になる。
けれど、
ナファバル家にはすでに、
王の第二王女である
リーア姉さまが嫁いでいる。
今さら私が行ったところで、
彼自身にとっての
メリットはない。
好意も持っていない、
不美人な女を妻にする。
それは、
彼にとって不幸でしかないだろう、
もうただの嫌がらせではないかと
まで思う。
私は、
本当に、
顔を見るだけで
満足だった。
ここ五年ほど、
私の護衛に彼が
つくこともなくなり、
時々すれ違ったり、
少し言葉を交わしたり――
それだけで、
十分に幸福だった。
……十分、だった。
そう言い切れないから、
今、
こんなにも苦しい。
私は慌てて頭を振った。
だめだ。
なにを一瞬でも、
結婚なんて考えているの。
順当に考えれば、
答えなど
最初から決まっている。
私の選択肢は、
巫女になることだ。
姉さまたちが
あまりにも派手で、
私は最初から
“そういう話”の外側にいた。
仮に縁談が来たとしても、
王族とのつながり目当てか、
あるいは、
0能力者としての
癒しの力を
利用したいだけ。
……そう考えると、
最低だけれど。
アディスにとっても、
私が役に立つ場面は、
あるのかもしれない。
彼は騎士だ。
命を落とすほどの
怪我を負う可能性もある。
その時、
私の力は――
「……いや」
私は小さく首を振った。
そんなふうに考えるなんて、
本当に最低だ。
「ため息をつく暇があったら、
アディス様のために
花嫁修業をしましょう」
レイラはそう言って、
私の腕を掴むと、
そのまま料理部屋へ
引っ張っていった。
王族である私は、
料理も洗濯も、
ほとんどしたことがない。
昨日から、
レイラがとにかく
基礎を仕込もうとしている。
編み物や繕い物だけは
趣味でそれなりにできるのだけれど、
それは別らしい。
レイラは、
私がアディスを
選ぶと思っている。
たぶん、
城の人間のほとんどが
そうだ。
けれど、
お父様だけは違う。
あの場で
アディスの名を出したのは、
私にきちんと
吹っ切らせるため。
思い残すことなく、
巫女になれるように。
――長い長い、
叶うことのない
片思いをしてきた娘への、
お父様なりの
最後通告。
それから、
私は時々
アディスを食事に
誘うようになった。
もちろん、
昼食の時間に
三十分ほどだけ。
迷惑だということは
分かっている。
それでも――
ほんの少しだけ、
婚約者のような気分を
味わってもいいのではないかと、
そんな私欲が、
どうしても
顔を出してしまった。
きっと私は
臆病なのだ。
一ヶ月後に、
血迷ったことを
言わないために。
その前に、
この気持ちを
使い切ってしまいたかった。
アディスだって、
私を妻に
娶らなければならないかもしれない
という状況に、
内心では
追い詰められているはずだ。
好きな人には、
幸せでいてほしい。
それは、
昔から変わらない。
アディスは、
自分のことを
大切にしない人だ。
だからこそ――
彼自身が、
簡単に命を
投げ出せなくなるような女性が、
そばに
必要なのだと思う。
……例えば、
アリア。
それか、
セリア家の
レイラさん。
以前、
祝賀祭で
二人が踊っているのを見た。
本当に、
お似合いだった。
あの頃は、
アディスは
レイラさんと
結婚するのではないか、
という噂もあった。
そうなるべきだ、と。
それが
正しい未来だと、
私は思っていた。
だから今、
こうして
昼食を共にし、
何気ない会話を
交わしている
この時間は――
たぶん、
もう分不相応なのだ。
それでも。
「あの……どうかな」
焼き上がった
パンケーキを差し出しながら、
私はアディスの表情を、
ついちらちらと
窺ってしまう。
彼は一口食べ、
きちんと飲み込んでから
言った。
「美味しいですよ」
「本当に?
本当のこと言っていいのよ?」
念を押すと、
彼は少しだけ
苦笑する。
「本当です。
それに、
嘘が苦手なのは
姫もご存じでしょう」
「そうだったわね」
昔のことを思い出して、
私はくすくす笑った。
そこから、
久々にたくさん話をした。
昔の思い出。
城の外の話。
少しだけ、
騎士たちの裏話。
最初は
心臓がうるさすぎて
どうしようかと思ったのに、
話しているうちに、
その鼓動が
心地よくなっていく。
この時間が、
ずっと続けばいいのに。
けれど、
楽しい時間は
あっという間だった。
「では、私はこれで。
夜勤がありますので。
お招き、ありがとうございました」
アディスは椅子から立ち上がり、
騎士らしく頭を下げる。
「えぇ……
こちらこそ。
あの、もしよかったら、また。
上手に出来たら、
食べに来てね」
言ってから、
自分の願望が
そのまま声になっていたことに
気づき、
胸が詰まった。
「分かりました。
では、楽しみにしています」
そつのない返事。
それでも、
その言葉だけで、
私は救われてしまう。
彼が部屋を
出て行ったあと、
甘い匂いだけが
残された。
私は静かに息を吐く。
これは、
幸せのため息ではない。
でも、
苦しいだけのため息でもなかった。
――偽りだと
分かっていても。
この時間は、
確かに
私のものだった。
宣言された期限内に、
きちんと終わらせるために。
私は今日も、
この偽りの時間に
身を置く。
思わず漏れたため息は、もう何度目だろう。
この三日間、私は数えきれないほど同じ息を吐いていた。
「ダリア様……」
付き侍女のレイラが、心配そうに私の顔を覗き込む。
その視線に気づきながらも、
私はぼんやりと彼女の顔を見つめたまま、
つい口にしてしまった。
「せめて、レイラくらい綺麗だったらよかったのになあ」
レイラはぴたりと動きを止め、
すぐに眉をひそめる。
「何をおっしゃっているのですか。
ダリア様には、ダリア様の可愛らしさがあります。
ご自分を卑下するのはおやめください」
きっぱりとした声。
いつも通りで、変わらない。
「ありがとう。
レイラは相変わらず優しいね」
そう言うと、
レイラは少し困ったように笑った。
――いつもなら、
その優しさに少し救われる。
けれど、
今の私には、
その言葉が少しだけ痛かった。
どうしても、
先日のことを思い出してしまう。
謁見の間で告げられた、
一ヶ月という期限。
お父様の、
あまりにも冷静な声。
……もう少し、
やり方があったのではないかと
思わないわけではない。
けれど、
分かってもいる。
お父様は、
私がアディスを
どれほど想っているか、
きっと最初から知っていた。
むしろ私の気持ちは、
近しい人なら誰でも
知っていると思う。
アディスの前に出ると、
どうしても顔が熱くなる。
言葉がぎこちなくなり、
視線も定まらない。
――たぶん、
本人にだって
気づかれていると思う。
私なんかに惚れられたばかりに。
彼は、
とんでもない貧乏くじを
引かされそうになっている。
王女が降嫁することは、
家にとっては
確かに利益になる。
けれど、
ナファバル家にはすでに、
王の第二王女である
リーア姉さまが嫁いでいる。
今さら私が行ったところで、
彼自身にとっての
メリットはない。
好意も持っていない、
不美人な女を妻にする。
それは、
彼にとって不幸でしかないだろう、
もうただの嫌がらせではないかと
まで思う。
私は、
本当に、
顔を見るだけで
満足だった。
ここ五年ほど、
私の護衛に彼が
つくこともなくなり、
時々すれ違ったり、
少し言葉を交わしたり――
それだけで、
十分に幸福だった。
……十分、だった。
そう言い切れないから、
今、
こんなにも苦しい。
私は慌てて頭を振った。
だめだ。
なにを一瞬でも、
結婚なんて考えているの。
順当に考えれば、
答えなど
最初から決まっている。
私の選択肢は、
巫女になることだ。
姉さまたちが
あまりにも派手で、
私は最初から
“そういう話”の外側にいた。
仮に縁談が来たとしても、
王族とのつながり目当てか、
あるいは、
0能力者としての
癒しの力を
利用したいだけ。
……そう考えると、
最低だけれど。
アディスにとっても、
私が役に立つ場面は、
あるのかもしれない。
彼は騎士だ。
命を落とすほどの
怪我を負う可能性もある。
その時、
私の力は――
「……いや」
私は小さく首を振った。
そんなふうに考えるなんて、
本当に最低だ。
「ため息をつく暇があったら、
アディス様のために
花嫁修業をしましょう」
レイラはそう言って、
私の腕を掴むと、
そのまま料理部屋へ
引っ張っていった。
王族である私は、
料理も洗濯も、
ほとんどしたことがない。
昨日から、
レイラがとにかく
基礎を仕込もうとしている。
編み物や繕い物だけは
趣味でそれなりにできるのだけれど、
それは別らしい。
レイラは、
私がアディスを
選ぶと思っている。
たぶん、
城の人間のほとんどが
そうだ。
けれど、
お父様だけは違う。
あの場で
アディスの名を出したのは、
私にきちんと
吹っ切らせるため。
思い残すことなく、
巫女になれるように。
――長い長い、
叶うことのない
片思いをしてきた娘への、
お父様なりの
最後通告。
それから、
私は時々
アディスを食事に
誘うようになった。
もちろん、
昼食の時間に
三十分ほどだけ。
迷惑だということは
分かっている。
それでも――
ほんの少しだけ、
婚約者のような気分を
味わってもいいのではないかと、
そんな私欲が、
どうしても
顔を出してしまった。
きっと私は
臆病なのだ。
一ヶ月後に、
血迷ったことを
言わないために。
その前に、
この気持ちを
使い切ってしまいたかった。
アディスだって、
私を妻に
娶らなければならないかもしれない
という状況に、
内心では
追い詰められているはずだ。
好きな人には、
幸せでいてほしい。
それは、
昔から変わらない。
アディスは、
自分のことを
大切にしない人だ。
だからこそ――
彼自身が、
簡単に命を
投げ出せなくなるような女性が、
そばに
必要なのだと思う。
……例えば、
アリア。
それか、
セリア家の
レイラさん。
以前、
祝賀祭で
二人が踊っているのを見た。
本当に、
お似合いだった。
あの頃は、
アディスは
レイラさんと
結婚するのではないか、
という噂もあった。
そうなるべきだ、と。
それが
正しい未来だと、
私は思っていた。
だから今、
こうして
昼食を共にし、
何気ない会話を
交わしている
この時間は――
たぶん、
もう分不相応なのだ。
それでも。
「あの……どうかな」
焼き上がった
パンケーキを差し出しながら、
私はアディスの表情を、
ついちらちらと
窺ってしまう。
彼は一口食べ、
きちんと飲み込んでから
言った。
「美味しいですよ」
「本当に?
本当のこと言っていいのよ?」
念を押すと、
彼は少しだけ
苦笑する。
「本当です。
それに、
嘘が苦手なのは
姫もご存じでしょう」
「そうだったわね」
昔のことを思い出して、
私はくすくす笑った。
そこから、
久々にたくさん話をした。
昔の思い出。
城の外の話。
少しだけ、
騎士たちの裏話。
最初は
心臓がうるさすぎて
どうしようかと思ったのに、
話しているうちに、
その鼓動が
心地よくなっていく。
この時間が、
ずっと続けばいいのに。
けれど、
楽しい時間は
あっという間だった。
「では、私はこれで。
夜勤がありますので。
お招き、ありがとうございました」
アディスは椅子から立ち上がり、
騎士らしく頭を下げる。
「えぇ……
こちらこそ。
あの、もしよかったら、また。
上手に出来たら、
食べに来てね」
言ってから、
自分の願望が
そのまま声になっていたことに
気づき、
胸が詰まった。
「分かりました。
では、楽しみにしています」
そつのない返事。
それでも、
その言葉だけで、
私は救われてしまう。
彼が部屋を
出て行ったあと、
甘い匂いだけが
残された。
私は静かに息を吐く。
これは、
幸せのため息ではない。
でも、
苦しいだけのため息でもなかった。
――偽りだと
分かっていても。
この時間は、
確かに
私のものだった。
宣言された期限内に、
きちんと終わらせるために。
私は今日も、
この偽りの時間に
身を置く。