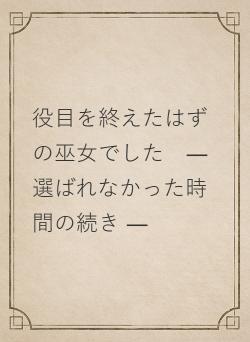けれど――
私は知っている。
思い返してしまうのだ。
あの夜のことを。
その距離が、
決して縮まらなかった理由を。
「ダリア様、またそちらのドレスですか?」
私が指差したドレスを手に取りながら、
レイラはため息をついた。
「私はこのドレス、気に入っているのだからいいじゃない」
最近、何かイベントがあると選んでしまう
紫の地味なドレスを手に取り、
冗談めかしてすねたふりをする。
「私は、こっちの青のドレスのほうが
ダリア様にはお似合いだと思います。
せっかくの国王様の誕生祭なのですよ。
たまには私の言うことも聞いてください」
そう言って、
レイラは青のドレスを私に差し出した。
「それに……」
にっこりと笑ってから、
メイド仲間から聞いた話だと言わんばかりに
声をひそめる。
「めずらしく、
ナファバル家のご兄弟も
そろって出席されるそうですよ」
完全に人参をぶら下げられた。
「え、アディスが……っ」
思わず食いついてしまってから、
慌てて顔が熱くなる。
レイラをにらみつけると、
彼女は楽しそうに肩をすくめた。
「とにかく、私は……」
そう言いかけたところで、
「今回は譲りませんよ。
めずらしくアディス様が出席されるのに、
ダリア様を売り込むチャンスを
逃すわけにはいきません。
それに、最近は
あまりお会いできていないのですよね?」
さらに痛いところを突いてくる。
私は勢いに押されながら、
苦笑いで答えた。
「お会いも何も、
アディスにとって私は
もう護衛対象ですらないのだから、
仕方がないわ。
それにね、
私がちょっと着飾ったぐらいで、
アディスの目にとまるとは
思えないけど」
我ながら、
自分のことをよく分かっている
発言だと思った。
「そんなことありません。
大体、アディス様は
もう何年も浮いた話を聞かないですし、
絶対ダリア様にも
チャンスはあると思います」
レイラは意味もなく
胸をそり返らせる。
一体、どこから来るのだろう、
この根拠のない自信。
アディス=ナファバルは、
公爵家の次男。
それに、ナファバル家といえば、
家族全員どこから集めてきたのかと
思うほどの美形ぞろいだ。
金髪に、
透き通るような深緑の瞳。
均整の取れた体格。
名門の家柄に、
若くして第一師団副師団長となるほどの実力。
早い話が、
結婚相手として
この国の姫たちの憧れの的の一人。
本人は
そういうのが嫌いみたいだけど。
きれいな人には、
きれいな人なりの悩みが
あるのかもしれない。
私にとっては、
うらやましい限りの悩みだけど。
つまり、
私とアディスの容姿は、
月とすっぽんほど
釣り合っていない。
アディスを恋愛対象として
意識してから、
初めて鏡に映った私と彼の
あまりの不釣り合いさに衝撃を受け、
しばらく鏡を見られなくなったこともあった。
今となっては、
笑い話だけど。
所作も、立ち居振る舞いも、
私は他の姉妹姫たちより
かなり劣っている。
むしろ、
アディスのほうがよほど
所作もきれいで、品格もある。
――長い時間をかけて、
嫌というほど思い知らされた真実だ。
彼は、
絶対に手の届かない
お月様のような存在。
たぶん、
彼が誰かと結婚したとしても、
落ち込んだり泣いたりはするだろうけれど、
最後には笑って結婚式に参加して、
心から祝福できると思っていた。
まあ、結局のところ、
レイラの熱意に負けて
青のドレスを着ることに
なったのだけど……。
■国王の誕生祭
こういうパーティーでは、
私はいつも
アルフレッドおじ様とペアで
会場に入る。
妹のアリアやお兄様は
申し込み相手に事欠かないけれど、
私にはそういう相手がいない。
十年前に奥様を亡くしたおじ様が、
私が恥をかかないようにと
気を遣ってくださっているのだ。
ちなみにこの日、
アリアはアディスと
ペアを組んでいた。
二人とも申し込みに
うんざりしていたらしく、
思惑が一致したらしい。
「私だったら安心でしょ」
そう言って、
アリアは私に気を遣って
教えてくれた。
「よく似合っているよ」
おじ様にそう言われて、
私は照れくさく笑った。
「ありがとうございます。
……レイラに押し切られてしまって」
そのとき、
扉が開き、
会場がわずかにざわめく。
「これは……」
おじ様が目を見張り、
私もつられて振り向いた。
扉の向こうから、
アディスとアリアが姿を現す。
二人並ぶと、
どこか神話の世界の住人のようで、
思わず息をのんだ。
――本当に、
お似合いだと思った。
身分的にも問題はなく、
性格も合っている。
アリアは可憐な見た目に反して、
明るくさっぱりした性格だ。
私の気持ちを知っているから、
私が巫女にならない限り、
そういう話には
ならないのだろうけれど。
それでも、
アリアも案外
アディスのことを
気に入っているのではないか、
そんなことを考えてしまった。
私が巫女になり、
この不毛な片思いに
早く区切りをつけられたら、
何もかもうまくいくのかもしれない。
そう思いながら、
私は遠くのアディスを見つめていた。
アリアだけは、
アディスの視線が
無意識にダリアの方へと
向いていることに気づいている。
それは、
ほんの少し彼に
憧れていたからかもしれないし、
人の目を引くという
似たような境遇の中で、
互いに利用し合ううちに
多少親しくなったからかもしれない。
「あまり見惚れていると、
根も葉もある噂を
立てられるかもしれませんわよ」
アディスは慌てて視線を逸らし、
珍しく動揺した様子で
顔を赤くする。
「今日だって、
お姉さまのお相手をできる
良い機会でしたのに」
からかうような笑みを浮かべる
アリアに、
アディスはちらりと
ダリアの方を見てから、
視線を床に落とした。
「あの方は、
どこまでも癒し姫ですから。
私とは、あまりにも違う」
それは、
線を引くための言葉だった。
パーティーも終盤に差しかかり、
私は人の多さに疲れて
ベランダに出た。
「はぁ……」
小さく息を吐いたところで、
聞き覚えのある声がした。
「疲れましたか?」
振り向くと、
そこにいたのは
アディスだった。
近距離で話すことに
胸が高鳴りつつ、
思わず笑ってしまう。
「貴方こそ、
げんなりした顔をしているわよ」
「そのドレス、
よく似合っていますね」
社交辞令だと分かっていても、
顔が熱くなる。
「ありがとう」
「もしよろしければ、
しばらくお相手を
させていただけませんか?」
驚いている私に、
彼は続けた。
「……私を女性避けに使うなんて、
高くつくわよ」
「そのつもりはありません。
ただ……
お願いを聞いていただくのですから、
ダリア様もご希望をおっしゃってください。
何でも聞きます」
少し考えてから、
私は答えた。
「怪我なく、
元気でいてくれれば、
それでいいわ」
その後、
パーティーが終わるまで、
アディスは私の傍を離れなかった。
ほんの三十分ほど。
けれど、
私にとっては
何年ぶりかの、
幸せな時間だった。
その後、
私が王女の権利をかざして
アディスを傍に置いたのではないか、
という噂が、
しばらく貴族の女性たちの間で
流れたらしい。
ほんの三十分。
けれど、
私が「まだいいか」と
思ってしまうには、
十分すぎる夜だった。
そして今――
私は、
一ヶ月の期限を与えられている。
私は知っている。
思い返してしまうのだ。
あの夜のことを。
その距離が、
決して縮まらなかった理由を。
「ダリア様、またそちらのドレスですか?」
私が指差したドレスを手に取りながら、
レイラはため息をついた。
「私はこのドレス、気に入っているのだからいいじゃない」
最近、何かイベントがあると選んでしまう
紫の地味なドレスを手に取り、
冗談めかしてすねたふりをする。
「私は、こっちの青のドレスのほうが
ダリア様にはお似合いだと思います。
せっかくの国王様の誕生祭なのですよ。
たまには私の言うことも聞いてください」
そう言って、
レイラは青のドレスを私に差し出した。
「それに……」
にっこりと笑ってから、
メイド仲間から聞いた話だと言わんばかりに
声をひそめる。
「めずらしく、
ナファバル家のご兄弟も
そろって出席されるそうですよ」
完全に人参をぶら下げられた。
「え、アディスが……っ」
思わず食いついてしまってから、
慌てて顔が熱くなる。
レイラをにらみつけると、
彼女は楽しそうに肩をすくめた。
「とにかく、私は……」
そう言いかけたところで、
「今回は譲りませんよ。
めずらしくアディス様が出席されるのに、
ダリア様を売り込むチャンスを
逃すわけにはいきません。
それに、最近は
あまりお会いできていないのですよね?」
さらに痛いところを突いてくる。
私は勢いに押されながら、
苦笑いで答えた。
「お会いも何も、
アディスにとって私は
もう護衛対象ですらないのだから、
仕方がないわ。
それにね、
私がちょっと着飾ったぐらいで、
アディスの目にとまるとは
思えないけど」
我ながら、
自分のことをよく分かっている
発言だと思った。
「そんなことありません。
大体、アディス様は
もう何年も浮いた話を聞かないですし、
絶対ダリア様にも
チャンスはあると思います」
レイラは意味もなく
胸をそり返らせる。
一体、どこから来るのだろう、
この根拠のない自信。
アディス=ナファバルは、
公爵家の次男。
それに、ナファバル家といえば、
家族全員どこから集めてきたのかと
思うほどの美形ぞろいだ。
金髪に、
透き通るような深緑の瞳。
均整の取れた体格。
名門の家柄に、
若くして第一師団副師団長となるほどの実力。
早い話が、
結婚相手として
この国の姫たちの憧れの的の一人。
本人は
そういうのが嫌いみたいだけど。
きれいな人には、
きれいな人なりの悩みが
あるのかもしれない。
私にとっては、
うらやましい限りの悩みだけど。
つまり、
私とアディスの容姿は、
月とすっぽんほど
釣り合っていない。
アディスを恋愛対象として
意識してから、
初めて鏡に映った私と彼の
あまりの不釣り合いさに衝撃を受け、
しばらく鏡を見られなくなったこともあった。
今となっては、
笑い話だけど。
所作も、立ち居振る舞いも、
私は他の姉妹姫たちより
かなり劣っている。
むしろ、
アディスのほうがよほど
所作もきれいで、品格もある。
――長い時間をかけて、
嫌というほど思い知らされた真実だ。
彼は、
絶対に手の届かない
お月様のような存在。
たぶん、
彼が誰かと結婚したとしても、
落ち込んだり泣いたりはするだろうけれど、
最後には笑って結婚式に参加して、
心から祝福できると思っていた。
まあ、結局のところ、
レイラの熱意に負けて
青のドレスを着ることに
なったのだけど……。
■国王の誕生祭
こういうパーティーでは、
私はいつも
アルフレッドおじ様とペアで
会場に入る。
妹のアリアやお兄様は
申し込み相手に事欠かないけれど、
私にはそういう相手がいない。
十年前に奥様を亡くしたおじ様が、
私が恥をかかないようにと
気を遣ってくださっているのだ。
ちなみにこの日、
アリアはアディスと
ペアを組んでいた。
二人とも申し込みに
うんざりしていたらしく、
思惑が一致したらしい。
「私だったら安心でしょ」
そう言って、
アリアは私に気を遣って
教えてくれた。
「よく似合っているよ」
おじ様にそう言われて、
私は照れくさく笑った。
「ありがとうございます。
……レイラに押し切られてしまって」
そのとき、
扉が開き、
会場がわずかにざわめく。
「これは……」
おじ様が目を見張り、
私もつられて振り向いた。
扉の向こうから、
アディスとアリアが姿を現す。
二人並ぶと、
どこか神話の世界の住人のようで、
思わず息をのんだ。
――本当に、
お似合いだと思った。
身分的にも問題はなく、
性格も合っている。
アリアは可憐な見た目に反して、
明るくさっぱりした性格だ。
私の気持ちを知っているから、
私が巫女にならない限り、
そういう話には
ならないのだろうけれど。
それでも、
アリアも案外
アディスのことを
気に入っているのではないか、
そんなことを考えてしまった。
私が巫女になり、
この不毛な片思いに
早く区切りをつけられたら、
何もかもうまくいくのかもしれない。
そう思いながら、
私は遠くのアディスを見つめていた。
アリアだけは、
アディスの視線が
無意識にダリアの方へと
向いていることに気づいている。
それは、
ほんの少し彼に
憧れていたからかもしれないし、
人の目を引くという
似たような境遇の中で、
互いに利用し合ううちに
多少親しくなったからかもしれない。
「あまり見惚れていると、
根も葉もある噂を
立てられるかもしれませんわよ」
アディスは慌てて視線を逸らし、
珍しく動揺した様子で
顔を赤くする。
「今日だって、
お姉さまのお相手をできる
良い機会でしたのに」
からかうような笑みを浮かべる
アリアに、
アディスはちらりと
ダリアの方を見てから、
視線を床に落とした。
「あの方は、
どこまでも癒し姫ですから。
私とは、あまりにも違う」
それは、
線を引くための言葉だった。
パーティーも終盤に差しかかり、
私は人の多さに疲れて
ベランダに出た。
「はぁ……」
小さく息を吐いたところで、
聞き覚えのある声がした。
「疲れましたか?」
振り向くと、
そこにいたのは
アディスだった。
近距離で話すことに
胸が高鳴りつつ、
思わず笑ってしまう。
「貴方こそ、
げんなりした顔をしているわよ」
「そのドレス、
よく似合っていますね」
社交辞令だと分かっていても、
顔が熱くなる。
「ありがとう」
「もしよろしければ、
しばらくお相手を
させていただけませんか?」
驚いている私に、
彼は続けた。
「……私を女性避けに使うなんて、
高くつくわよ」
「そのつもりはありません。
ただ……
お願いを聞いていただくのですから、
ダリア様もご希望をおっしゃってください。
何でも聞きます」
少し考えてから、
私は答えた。
「怪我なく、
元気でいてくれれば、
それでいいわ」
その後、
パーティーが終わるまで、
アディスは私の傍を離れなかった。
ほんの三十分ほど。
けれど、
私にとっては
何年ぶりかの、
幸せな時間だった。
その後、
私が王女の権利をかざして
アディスを傍に置いたのではないか、
という噂が、
しばらく貴族の女性たちの間で
流れたらしい。
ほんの三十分。
けれど、
私が「まだいいか」と
思ってしまうには、
十分すぎる夜だった。
そして今――
私は、
一ヶ月の期限を与えられている。