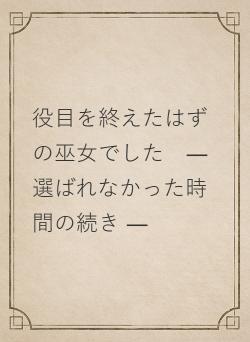私はダリア=ルートビッヒ、二十五歳。
ルートビッヒ国の現国王の第三王女だ。
私の家族は、分かりやすく容姿端麗でそろっている。
私以外は、全員が碧眼で、
彫りの深い顔立ちをしている。
この世界では、それがごく普通だ。
――そして、私だけが違う。
黒髪に、黒い目。
彫りの浅い顔立ち。
誰にも似ていない、と自分でも思う。
それには理由がある。
私は、0能力者として生まれた。
0能力者として生まれると、
家族の誰にも似ない顔立ちになり、
彫りの浅い顔と、黒い目を持つ。
それは、この世界では例外なく共通している。
もっとも、
彫りが浅いからといって、
容姿が劣ると決まっているわけではない。
だから私の顔立ちも、
本当は大きな問題ではないのだと思う。
ただ――
私はその中で、
やや不細工寄りだっただけだ。
それだけの話だ。
きれいな家族に囲まれて育ったおかげで、
同じ土俵に立とうなどという考えは、
物心ついた頃には自然と消えていた。
そんなわけで、
私には浮いた話ひとつなく、今に至る。
0能力者は、能力として魔力を持たない。
人数としては少ないが、
珍しい存在というほどではない。
この世界の人々のほとんどは魔力を持っている。
能力に差はあっても、魔力石を使えば、
簡単な防御陣くらいなら誰でも張れる。
けれど、0能力者にはそれができない。
代わりに、
癒しの力を持つ者がいる。
私も、その一人だ。
癒しの力は、
特別な能力というほど珍しくはない。
ただし、その代償は大きい。
自分の生命力を削って、他人を癒す。
軽い怪我でも、一日は動けなくなる。
理論上は、
自分の命を媒体にすれば、
死の淵にいる人さえ癒すことができる。
けれど、だからこそ――
自己犠牲を前提にしてまで、
その力を使い続ける人は多くない。
使えないのではなく、使わない。
私は、自分が特別だとは思っていない。
ただ、目の前で困っている人がいれば、
使わずにいられなかっただけだ。
この国で王族の女性は、
十八歳を過ぎて結婚していなければ、
姫としての公務のほかに、仕事を持つことになる。
私は、親を亡くした子供たちの支援に関わる仕事を選んだ。
各施設を回り、状況を確認し、対応を考える。
地味で、派手さのない仕事だ。
でも、子供が好きだったから、
この仕事は気に入っている。
ただ、この仕事を始めてから、
強く思うようになったことがある。
――戦争がなければ。
こんな現実を知る子供は、
もっと少なかったはずなのに。
ルートビッヒ国は、中規模国家だ。
三つの国に囲まれている。
二国とは友好関係を保っている。
そして、かつて敵対していた大国――
マルギノ国とも、今は関係が変わりつつある。
三年前の大きな戦争で、
マルギノ国の国王は戦死した。
それを境に、
あの国は大きく方針を転じたらしい。
現在は、各国との友好関係を築こうとする動きが見られ、
少なくとも、以前のような侵略の気配はない。
まだ、完全に信頼できるわけではない。
けれど、
剣を構え続けるだけの関係ではなくなった。
それでも、この国が持ちこたえられたのは、
騎士たちの日頃の訓練のおかげだと思う。
この国の騎士団は、
第1師団から第10師団まで分かれている。
中でも、第1師団の戦闘能力は、
周囲の国々にも知られている。
――そして。
その第1師団の副師団長が、
今、私のすぐ後ろに立っている。
ルートビッヒ国の現国王の第三王女だ。
私の家族は、分かりやすく容姿端麗でそろっている。
私以外は、全員が碧眼で、
彫りの深い顔立ちをしている。
この世界では、それがごく普通だ。
――そして、私だけが違う。
黒髪に、黒い目。
彫りの浅い顔立ち。
誰にも似ていない、と自分でも思う。
それには理由がある。
私は、0能力者として生まれた。
0能力者として生まれると、
家族の誰にも似ない顔立ちになり、
彫りの浅い顔と、黒い目を持つ。
それは、この世界では例外なく共通している。
もっとも、
彫りが浅いからといって、
容姿が劣ると決まっているわけではない。
だから私の顔立ちも、
本当は大きな問題ではないのだと思う。
ただ――
私はその中で、
やや不細工寄りだっただけだ。
それだけの話だ。
きれいな家族に囲まれて育ったおかげで、
同じ土俵に立とうなどという考えは、
物心ついた頃には自然と消えていた。
そんなわけで、
私には浮いた話ひとつなく、今に至る。
0能力者は、能力として魔力を持たない。
人数としては少ないが、
珍しい存在というほどではない。
この世界の人々のほとんどは魔力を持っている。
能力に差はあっても、魔力石を使えば、
簡単な防御陣くらいなら誰でも張れる。
けれど、0能力者にはそれができない。
代わりに、
癒しの力を持つ者がいる。
私も、その一人だ。
癒しの力は、
特別な能力というほど珍しくはない。
ただし、その代償は大きい。
自分の生命力を削って、他人を癒す。
軽い怪我でも、一日は動けなくなる。
理論上は、
自分の命を媒体にすれば、
死の淵にいる人さえ癒すことができる。
けれど、だからこそ――
自己犠牲を前提にしてまで、
その力を使い続ける人は多くない。
使えないのではなく、使わない。
私は、自分が特別だとは思っていない。
ただ、目の前で困っている人がいれば、
使わずにいられなかっただけだ。
この国で王族の女性は、
十八歳を過ぎて結婚していなければ、
姫としての公務のほかに、仕事を持つことになる。
私は、親を亡くした子供たちの支援に関わる仕事を選んだ。
各施設を回り、状況を確認し、対応を考える。
地味で、派手さのない仕事だ。
でも、子供が好きだったから、
この仕事は気に入っている。
ただ、この仕事を始めてから、
強く思うようになったことがある。
――戦争がなければ。
こんな現実を知る子供は、
もっと少なかったはずなのに。
ルートビッヒ国は、中規模国家だ。
三つの国に囲まれている。
二国とは友好関係を保っている。
そして、かつて敵対していた大国――
マルギノ国とも、今は関係が変わりつつある。
三年前の大きな戦争で、
マルギノ国の国王は戦死した。
それを境に、
あの国は大きく方針を転じたらしい。
現在は、各国との友好関係を築こうとする動きが見られ、
少なくとも、以前のような侵略の気配はない。
まだ、完全に信頼できるわけではない。
けれど、
剣を構え続けるだけの関係ではなくなった。
それでも、この国が持ちこたえられたのは、
騎士たちの日頃の訓練のおかげだと思う。
この国の騎士団は、
第1師団から第10師団まで分かれている。
中でも、第1師団の戦闘能力は、
周囲の国々にも知られている。
――そして。
その第1師団の副師団長が、
今、私のすぐ後ろに立っている。