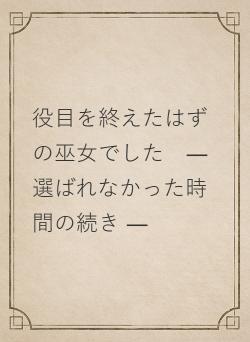謁見の間は、張りつめた静けさに包まれていた。
玉座の前に立つ私の背後には、
宰相、軍務卿、神殿長――
この国の中枢を担う重臣たちが並んでいる。
視線はすべて父へ向けられ、
私に向けられるものはほとんどない。
ほんの数歩後ろ。
右斜め後方に、はっきりと分かる気配があった。
第1師団副師団長、アディス=ナファバル。
「ダリア」
父――ルートビッヒ国王の声が、
低く謁見の間に響いた。
「一ヶ月以内に決めなさい」
一瞬、言葉の意味を取りこぼした。
「そこにいる、アディス=ナファバル。
第1師団副師団長への降嫁か――」
わずかな間が置かれる。
「それとも、神殿の巫女となるか」
「……はい?」
思わず、素の声が漏れた。
しまった、と思う。
けれど、その場の誰も私を咎めなかった。
この言葉が、冗談でも、思いつきでもないことを、
ここにいる全員が理解していたからだ。
「これは、決定事項だ」
父は感情の起伏を感じさせない声で言い切った。
怒りでも、苛立ちでもない。
あまりにも冷静な判断の声。
だからこそ、胸の奥がひどく痛んだ。
喉の奥が、きゅっと締め付けられる。
私は小さく息を吸い、視線を前に戻した。
……違う。
これは、叱責ではない。
でも、優しさとも少し違う。
それが分かってしまうから、
逃げ場がなかった。
背後に立つ彼の存在が、
どうしても意識に入り込んでくる。
アディス=ナファバル。
金髪に、深い緑の瞳。
第1師団の副師団長として、常に最前線に立つ騎士。
名門ナファバル公爵家の次男で、
実力も家柄も申し分ない。
本来なら、すでに結婚していても
おかしくない年齢でもある。
……私がいなければ。
そんな考えが、頭をよぎって、
すぐに打ち消した。
私は、アディスと出会ってから、
ずっと、あきらめきれずにきた。
言葉にしたことはない。
選ばれるはずがないと、分かっていたからだ。
私は、美人姉妹に囲まれて育った。
自分が「選ばれる側」ではないことは、
特別な出来事がなくても、
自然と理解していた。
好きでもない人に嫁ぐという選択肢は、
最初からなかった。
政略結婚も、側室という形も、
考える以前に、心が動かなかった。
だから結婚というもの自体を、
どこかで人生から外していたのだと思う。
……思う、だけだ。
本当は、そんなふうに
きっぱり割り切れていたわけじゃない。
選ばれないと分かっていても、
完全に期待を捨てられたかと言われれば、
たぶん、そうではなかった。
アディスが誰かと結婚してくれたら。
その時には、きっと区切りがつく。
そう思っていた。
でも、
それが今日である必要も、
明日である必要もなかった。
まだいいか、と。
そんなふうに思いながら、
何も決めない時間が、
いつの間にか長くなっていただけだ。
ほんの一瞬、
背後の空気が揺れた気がした。
視線を向けなくても分かる。
彼もまた、この通告を
予期していなかったのだ。
「……お父様」
何か言わなければならない。
そう思ったのに、言葉が出てこない。
お父様の視線は、
背後に立つアディスへと向けられた。
「アディス=ナファバル。
ダリア次第とはなるが、異論はないな?」
私は、その言葉に
思わず心の中で舌打ちした。
この国の国王を前にして、
異論など言えるわけがないじゃない。
思わず、お父様をにらみつける。
案の定、
アディスはいつも通りの
落ち着いた声で答えた。
「異論など、恐れ多いことです。
謹んで、お受けいたします」
その言葉は丁寧で、正しくて、
そして――
あまりにも逃げ場がなかった。
お父様はアディスの言葉を受けて、
まるで私だけでなく、
もう一人の存在にも
区切りをつけるかのように言う。
「時間は与えた。よく考えなさい」
それだけだった。
冷たい言葉に聞こえたかもしれない。
けれど――
私は、なぜか分かってしまった。
お父様は、
私が何も選ばないまま、
このまま日々を重ねていくことを、
見過ごせなかったのだ。
それが、
娘として幸せかどうかは、分からない。
でも、
少なくとも「決めないまま終わる」未来だけは、
許さなかった。
私は、0能力者だ。
癒しの力を持っているが、
それを特別な力だと思ったことはない。
同じ力を持つ人はいる。
ただ、その力は自分の生命力を削る。
だから、多くの人は使わない。
使えないのではなく、使わないのだ。
私は、ただ使っているだけだった。
目の前で困っている人がいれば、
使わずにいられなかっただけ。
それが評価されているとも、
必要とされているとも、
正直、考えたことはなかった。
ただ――
結婚の話をされることは、ほとんどなく、
代わりに、
「いつかは巫女になられるのですよね」
そんなふうに言われることが、
時々あった。
断定でも、期待でもない。
ただの前提のような口調で。
だから私も、
そういうものなのだろう、と
深く考えずに受け止めていた。
残された時間は、一ヶ月。
私が選ぶべき道は、
最初から決まっているはずだった。
それでも。
ほんの一瞬だけ、
背後に立つ彼の存在を、
強く意識してしまう。
彼は、きっと、
私のことなど考えていない。
ただ、騎士として、
そこに立っているだけだ。
――選ばれるはずがない。
これは、
そう思うことで、
胸の奥に残った期待を、
静かに押し込めた。
私が終わらせるための一ヶ月。
そう、自分に言い聞かせながら。
玉座の前に立つ私の背後には、
宰相、軍務卿、神殿長――
この国の中枢を担う重臣たちが並んでいる。
視線はすべて父へ向けられ、
私に向けられるものはほとんどない。
ほんの数歩後ろ。
右斜め後方に、はっきりと分かる気配があった。
第1師団副師団長、アディス=ナファバル。
「ダリア」
父――ルートビッヒ国王の声が、
低く謁見の間に響いた。
「一ヶ月以内に決めなさい」
一瞬、言葉の意味を取りこぼした。
「そこにいる、アディス=ナファバル。
第1師団副師団長への降嫁か――」
わずかな間が置かれる。
「それとも、神殿の巫女となるか」
「……はい?」
思わず、素の声が漏れた。
しまった、と思う。
けれど、その場の誰も私を咎めなかった。
この言葉が、冗談でも、思いつきでもないことを、
ここにいる全員が理解していたからだ。
「これは、決定事項だ」
父は感情の起伏を感じさせない声で言い切った。
怒りでも、苛立ちでもない。
あまりにも冷静な判断の声。
だからこそ、胸の奥がひどく痛んだ。
喉の奥が、きゅっと締め付けられる。
私は小さく息を吸い、視線を前に戻した。
……違う。
これは、叱責ではない。
でも、優しさとも少し違う。
それが分かってしまうから、
逃げ場がなかった。
背後に立つ彼の存在が、
どうしても意識に入り込んでくる。
アディス=ナファバル。
金髪に、深い緑の瞳。
第1師団の副師団長として、常に最前線に立つ騎士。
名門ナファバル公爵家の次男で、
実力も家柄も申し分ない。
本来なら、すでに結婚していても
おかしくない年齢でもある。
……私がいなければ。
そんな考えが、頭をよぎって、
すぐに打ち消した。
私は、アディスと出会ってから、
ずっと、あきらめきれずにきた。
言葉にしたことはない。
選ばれるはずがないと、分かっていたからだ。
私は、美人姉妹に囲まれて育った。
自分が「選ばれる側」ではないことは、
特別な出来事がなくても、
自然と理解していた。
好きでもない人に嫁ぐという選択肢は、
最初からなかった。
政略結婚も、側室という形も、
考える以前に、心が動かなかった。
だから結婚というもの自体を、
どこかで人生から外していたのだと思う。
……思う、だけだ。
本当は、そんなふうに
きっぱり割り切れていたわけじゃない。
選ばれないと分かっていても、
完全に期待を捨てられたかと言われれば、
たぶん、そうではなかった。
アディスが誰かと結婚してくれたら。
その時には、きっと区切りがつく。
そう思っていた。
でも、
それが今日である必要も、
明日である必要もなかった。
まだいいか、と。
そんなふうに思いながら、
何も決めない時間が、
いつの間にか長くなっていただけだ。
ほんの一瞬、
背後の空気が揺れた気がした。
視線を向けなくても分かる。
彼もまた、この通告を
予期していなかったのだ。
「……お父様」
何か言わなければならない。
そう思ったのに、言葉が出てこない。
お父様の視線は、
背後に立つアディスへと向けられた。
「アディス=ナファバル。
ダリア次第とはなるが、異論はないな?」
私は、その言葉に
思わず心の中で舌打ちした。
この国の国王を前にして、
異論など言えるわけがないじゃない。
思わず、お父様をにらみつける。
案の定、
アディスはいつも通りの
落ち着いた声で答えた。
「異論など、恐れ多いことです。
謹んで、お受けいたします」
その言葉は丁寧で、正しくて、
そして――
あまりにも逃げ場がなかった。
お父様はアディスの言葉を受けて、
まるで私だけでなく、
もう一人の存在にも
区切りをつけるかのように言う。
「時間は与えた。よく考えなさい」
それだけだった。
冷たい言葉に聞こえたかもしれない。
けれど――
私は、なぜか分かってしまった。
お父様は、
私が何も選ばないまま、
このまま日々を重ねていくことを、
見過ごせなかったのだ。
それが、
娘として幸せかどうかは、分からない。
でも、
少なくとも「決めないまま終わる」未来だけは、
許さなかった。
私は、0能力者だ。
癒しの力を持っているが、
それを特別な力だと思ったことはない。
同じ力を持つ人はいる。
ただ、その力は自分の生命力を削る。
だから、多くの人は使わない。
使えないのではなく、使わないのだ。
私は、ただ使っているだけだった。
目の前で困っている人がいれば、
使わずにいられなかっただけ。
それが評価されているとも、
必要とされているとも、
正直、考えたことはなかった。
ただ――
結婚の話をされることは、ほとんどなく、
代わりに、
「いつかは巫女になられるのですよね」
そんなふうに言われることが、
時々あった。
断定でも、期待でもない。
ただの前提のような口調で。
だから私も、
そういうものなのだろう、と
深く考えずに受け止めていた。
残された時間は、一ヶ月。
私が選ぶべき道は、
最初から決まっているはずだった。
それでも。
ほんの一瞬だけ、
背後に立つ彼の存在を、
強く意識してしまう。
彼は、きっと、
私のことなど考えていない。
ただ、騎士として、
そこに立っているだけだ。
――選ばれるはずがない。
これは、
そう思うことで、
胸の奥に残った期待を、
静かに押し込めた。
私が終わらせるための一ヶ月。
そう、自分に言い聞かせながら。