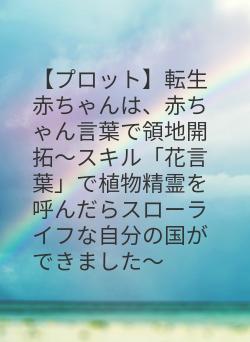「のりとハサミでございます」
鑑定士は厳かに宣言した。しかしかなり焦っているのか、しきりにハンカチで冷や汗を拭いている。
侯爵家の居間で彼と向き合い、ソファに座る僕は紫水晶に右手をかざしていた。鑑定士はこの水晶で生来持っている【ギフト】を鑑定する。
【ギフト】は四大元素、火水風土を冠した能力だ。
例えば、『水の騎士』や『火の賢者』など、とにかく響きが良い。
そのはずなのだが、気の毒な鑑定士は汗を拭き拭き先程からずっと困惑顔だ。
「何だと……?」
「私にも意味はわかりません」
鑑定士と、父である侯爵は混乱しているが僕にはわかる。
ギフトには、僕の前世が関係しているのだ。
「わ、わけがわからん。役に立ちそうにないギフトを授かりおったということか」
「し、しかしこのような不可思議なギフトは長い鑑定歴の中でも見たことがありません。世に二つとはないこのギフト。五男様は神に祝福された天才ではないかと……」
「そんなわけないだろう!」
初老の鑑定士は揉み手をしがらお世辞を言ったが父上はとうとう激怒してしまう。
「ゼクス、お前には失望した。今日の鑑定を楽しみにしておったがまったくの期待外れであった」
え、この流れはまさか……?
「能力次第では裕福な所領を誕生日の祝いにくれてやろうと考えていたが、無能なお前にはもったいない!役立たずの五男坊など、辺境の荒れ地アヴェリアに追放してくれるわ!」
「やったーーー!!追放だあぁーーー!!」
5歳になったばかりの僕は、嬉しさのあまりソファによじ登ってぴょんぴょん飛び跳ねた。
その僕を父上と鑑定士はただただ呆然と見守っていた。
「そうだ、こうしちゃいられない!」
気が済むまで喜んだ僕は放心状態の大人たちを尻目に、自室に駆け込む。
早速旅立ちの準備をしなくちゃね!
「ぼ、坊ちゃまあぁーーー!!」
「うわあっ!?」
いそいそと旅行鞄に衣類を詰め込んでいると、メイドのリリーが開いたドアから飛び込んできた。
そして体当たりするようにして、僕をぎゅっと両手で抱きしめる。
「旦那様はあんまりです!お誕生日にいきなり追放だなんて!いくら『ごうつくばり侯爵』とはいえ悪鬼のごとき所業です!!」
リリーは興奮し過ぎて雇い主にすごいことを言っている。
「く、苦しいよう……」
抱きしめられた胸から、もぞもぞともがき出すと、やっとリリーは離してくれた。
「申し訳ありません、あまりに坊ちゃまがお可哀想で……。それにまだケーキとごちそうも用意していないのに……」
『ごうつくばり侯爵』と社交界からも噂される父上のことだ。
鑑定の結果次第では、今日の誕生日パーティーを開く気は最初からなかったのだろう。
「平気さ。だって父上は最高の誕生日プレゼントをくれたじゃない?」
「え?」
「この家からの自由だよ!」
ベッドに腰かけ直して、足をぶらぶらさせてる僕をリリーは驚いて見つめた。
「ずっとこの家から出たかったんだ、僕」
そう言って笑いかけると、リリーは眉を八の字にして泣きそうな顔をする。
無理もない。僕の家族はとにかく仲が悪い。
父上は『ごうつくばり侯爵』とあだ名されるほどお金に汚い。領民が飢饉や疫病に苦しんでいる時でさえ、重税を課して金目のものなら、取って取って取りまくる。それこそ病人の布団まで家来に命じてはぎ取ってくるのだ。
母上と結婚したのも大商人の娘で実家の財力目当てだった。
母上はそんな夫を嫌い、僕を生んですぐに館を出て別荘で暮らしている。
だから僕は母の顔も知らない。
加えて4人の兄たちも父親に似て、性格が悪く仲も悪い。
兄たちと仲良く遊んだ記憶はなく、いじめられるか無視されるかの思い出しかない。
だから今日の僕の5歳の誕生日にも、父上以外の家族は館にいない。
そして今朝いきなり父上は鑑定士を呼びつけ、僕のギフトを鑑定させたのだ。
そして気に入らないからと追放した。
いくら期待されていない五男坊とはいえ、あまりといえばあまりの扱いである。
それにみんなには内緒だが僕には前世の記憶があった。
4歳の時、積木で遊んでいたらふと頭に浮かんだ。
【雑誌の組み立て付録が作りたい!!】と――――。
前世では子供の頃はもちろん、大人になっても甥っ子や姪っ子のためにと児童誌の付録を作っていた。
車や怪獣、ロボットを平面図からハサミで切り取りのりでくっつけ、立体化する。
そして苦労して完成した付録が動き出した時の感動と達成感は格別だった。
この世界には雑誌はあるにはある。だが一般国民の識字率は低い。
従って発行部数は極めて少なく、付録付きの雑誌に至っては皆無なのだ。
大好きな雑誌の付録が作りたい!
それも大人でも手こずるような、精緻な組み立て付録がいい!!
その願望は小さな僕の中で、日に日に高まってゆく。
だが現実は、大好きな付録が作りたくて作りたくてたまらないのに、この世界では作れない。
この膨れ上がった欲求不満が、前代未聞のギフトを僕がもらった理由ではないだろうか――――。
「ギフト【のりとハサミ】を授かるなんて、本当に僕らしいよ。きっとこれから先も、僕にぴったりの素敵な事が起きるよ!」
自信満々に胸を張るとリリーもやっと少しだけ笑ってくれた。
「ご心配には及びません。このリリーも坊ちゃまと一緒に辺境だろうと地獄だろうと、どこへでもお供いたしますからね」
そう言って彼女は今度は優しく、僕を抱きしめてくれた。
それなのに……。
「え、御者がいないの?」
「はい、旦那様が御者も護衛の騎士も、五男坊には分不相応だからと……」
午前中に支度を済ませ、さあ領地に行こうと張り切っていたら、何と父上が御者を出し惜しみしたらしい。
「御者は何とかわたくしがやりますが、こんなボロボロの馬車だなんてあんまりです……」
確かに馬車にはシュヴァイツァー侯爵家の家紋も入っていないし、馬車も外装が至る所剥がれてかなりの年代ものだ。
走り始めた途端、バラバラに分解しないだろうか。
「平気だよ。父上はきっと僕の追放を大袈裟にしたくなくて、護衛と家紋を外したんだよ」
「ですがこれでは、まるで夜逃げです」
リリーはそう言って涙ぐむ。
僕だって本当はわかっていた。
父上は当てが外れた五男坊に、余計なお金を使いたくないだけだよね。
だけどその事実を口にすれば、心優しいリリーは僕以上に悲しむだろう。
赤ちゃんの時から僕を見守ってくれている彼女をこれ以上傷つけたくはない。
「リリー、何をしている。使用人が主に気を使わせるとは何事だ」
そんな僕ら2人の元に、老執事ハルベリがやってきた。
「お話は伺いました。ゼクス様、今からでも遅くありません。旦那様にお許しいただけるように、お詫びしてはいかがでしょうか」
黒い燕尾服を優雅に着こなしたハルベリは、父上より貴族らしく威厳がある。
「何をおっしゃるんです!坊ちゃまは謝らなくてはいけないことなんて何も……!」
「待って、リリー」
顔を真っ赤にして食ってかかる彼女を僕は手で制する。
「父上に許しを請う気はないよ、僕は」
「ほう、なぜですかな?」
ハルベリは眼鏡の奥から眼光鋭く睨む。
「能なし五男坊にも意地がある。勝手に期待をかけて当てが外れたら飽きた玩具みたいに我が子を捨てる。そんな身勝手な父親に下げる頭はない」
これは本心だった。
家族にも館にも今さら何の未練もない。辺境とはいえ自分の領地を持てるのなら、こんな家に用はない。
ハルベリはそんな僕の言い分を無表情に聞いていた。
「まあ、それは建前で、本当は嫌な家族から解放されてのんびり過ごしたいだけなんだ」
僕はえへへっと照れ笑いをした。
嫌な家族のいない場所で伸び伸びと、この世界には存在しない『付録』を自分の手で一から作りたい。
これもまた、本心には違いないのだ。
するとハルベリはふっと含み笑いを浮かべる。
「なるほど、のんびり過ごすためですか。ではこの年寄りが余生を送るにもおあつらえ向きのお話ですな」
「え……?」
「このハルベリもお供いたします」
「ええ!?筆頭執事が!?その地位を捨てて?何で……?」
シュヴァイツァー侯爵家筆頭執事にして、元国王軍第一騎士団騎士団長。
剣術と体術においては王国最強と謳われたこの人が僕についてくるって?
「年のせいか最近、寝ても疲れがとれません。そろそろ後進に道を譲って楽隠居しようと思い立ちまして」
「いや、何が疲れだよ。今朝も腕立て伏せを100回もやってただろう!?僕も一緒に30回もやらされたもん」
「若い頃は1000回できました」
ハルベリは体育会系執事だった。
幼い頃から今に至るまで、基礎訓練から体術剣術までみっちりと叩き込まれたのだ。
まさか辺境の地まで着いてきて僕をしごく気じゃないだろうな!?
「それに僕が赴任する領地は厳しい辺境の荒れ地だよ。苦労するだけだよ」
「嫌とは言わせませんぞ、ゼクス様。その廃車寸前のおんぼろ馬車ではとても辺境地アヴェリアまでたどり着けません。その点」
ハルベリはそこまで話すと自身の背後を振り返る。
僕とリリーもつられて同じ方向を見た。
そして僕ら2人は驚きに目を見張った。
そこにはシュヴァイツァー侯爵家の家紋である『向かい合う2頭の獅子が葡萄を抱える』図案が描かれた、6頭立ての立派な馬車が停まっていたのだ。
「わたくしが旦那様から退職金代わりに分捕ってきた、この高級馬車なら10日の行程を4日に短縮できますぞ」
「何だって?4日に短縮!?よし、ともに行こう!ハルベリ!!」
僕は即座に老執事の手を両手でガッチリと握った。
ハルベリもまた会心の笑みを浮かべる。
「坊ちゃまぁ!本当にいいんですか!?この馬車を分捕ってきたと言ってましたよ、執事さん」
リリーは悲鳴を上げたがその時には、僕はいそいそと高級馬車に乗り込み、ハルベリも上機嫌で御者台に上っていた。
「あのケチな父上のことだよ。まともに交渉して退職金を払うと思う?」
「さすがゼクス様。よくわかっていらっしゃる。リリーも細かいことは気にするな。それより旦那様の追っ手が来る前に急げ」
可哀想に、真面目なリリーは僕とハルベリを交互に見上げて半泣きであった。
「ほらね、言った通りだろう?」
僕は馬車の中からリリーに手を差し出しながら笑った。
「きっとこれから先も、僕にぴったりの素敵な事が起きるって。リリーの他にも仲間が増えたよ!」
「侯爵家の若様と我々が仲間などとは畏れ多い。口を挟むようで恐縮ですが、わたくしどもはゼクス様の使用人にございます」
リリーが答えるより早く、ハルベリがやんわりと釘を刺す。
「うん、そうだね。じゃあ、仲間がダメなら僕の付録じゃどうかな?」
「ふろく……とは?」
ハルベリとリリーは顔を見合わせ不思議がる。
「雑誌に付いているおまけさ。なのに、肝心な雑誌より面白くってさ。どうしても欲しくなるんだ!」
「なるほど、我々はゼクス様のおまけですか」
なぜかハルベリの声は嬉しそうに弾んでいた。
「それも面白くってどうしても欲しくなるおまけなんですって!」
リリーは御者台に座るハルベリを見上げて笑った。
「だから2人とも僕にくっ付いてきてよ。付録みたいにさ」
僕が差し出した右手をリリーが力強く握る。
そしてステップに足を乗せると素早く馬車に乗り込んだ。
「行くよ、みんな!僕らの新天地アヴェリアに出発だ!!」
手にしたステッキで馬車の天井を軽く突く。
それを合図に6頭の黒馬たちは、艶やかなたてがみをなびかせて駆け出した。
僕らの馬車は風のように音もなく滑り出してゆく。
遠くからは、『待てぇ~!』『馬車泥棒ぉ~!』『わしの特注高級馬車を返せぇ~!』と家来たちと父上の声が聞こえてくるが気にしない。
この旅立ちが、僕の輝かしい付録付きライフの始まりなのだ。
鑑定士は厳かに宣言した。しかしかなり焦っているのか、しきりにハンカチで冷や汗を拭いている。
侯爵家の居間で彼と向き合い、ソファに座る僕は紫水晶に右手をかざしていた。鑑定士はこの水晶で生来持っている【ギフト】を鑑定する。
【ギフト】は四大元素、火水風土を冠した能力だ。
例えば、『水の騎士』や『火の賢者』など、とにかく響きが良い。
そのはずなのだが、気の毒な鑑定士は汗を拭き拭き先程からずっと困惑顔だ。
「何だと……?」
「私にも意味はわかりません」
鑑定士と、父である侯爵は混乱しているが僕にはわかる。
ギフトには、僕の前世が関係しているのだ。
「わ、わけがわからん。役に立ちそうにないギフトを授かりおったということか」
「し、しかしこのような不可思議なギフトは長い鑑定歴の中でも見たことがありません。世に二つとはないこのギフト。五男様は神に祝福された天才ではないかと……」
「そんなわけないだろう!」
初老の鑑定士は揉み手をしがらお世辞を言ったが父上はとうとう激怒してしまう。
「ゼクス、お前には失望した。今日の鑑定を楽しみにしておったがまったくの期待外れであった」
え、この流れはまさか……?
「能力次第では裕福な所領を誕生日の祝いにくれてやろうと考えていたが、無能なお前にはもったいない!役立たずの五男坊など、辺境の荒れ地アヴェリアに追放してくれるわ!」
「やったーーー!!追放だあぁーーー!!」
5歳になったばかりの僕は、嬉しさのあまりソファによじ登ってぴょんぴょん飛び跳ねた。
その僕を父上と鑑定士はただただ呆然と見守っていた。
「そうだ、こうしちゃいられない!」
気が済むまで喜んだ僕は放心状態の大人たちを尻目に、自室に駆け込む。
早速旅立ちの準備をしなくちゃね!
「ぼ、坊ちゃまあぁーーー!!」
「うわあっ!?」
いそいそと旅行鞄に衣類を詰め込んでいると、メイドのリリーが開いたドアから飛び込んできた。
そして体当たりするようにして、僕をぎゅっと両手で抱きしめる。
「旦那様はあんまりです!お誕生日にいきなり追放だなんて!いくら『ごうつくばり侯爵』とはいえ悪鬼のごとき所業です!!」
リリーは興奮し過ぎて雇い主にすごいことを言っている。
「く、苦しいよう……」
抱きしめられた胸から、もぞもぞともがき出すと、やっとリリーは離してくれた。
「申し訳ありません、あまりに坊ちゃまがお可哀想で……。それにまだケーキとごちそうも用意していないのに……」
『ごうつくばり侯爵』と社交界からも噂される父上のことだ。
鑑定の結果次第では、今日の誕生日パーティーを開く気は最初からなかったのだろう。
「平気さ。だって父上は最高の誕生日プレゼントをくれたじゃない?」
「え?」
「この家からの自由だよ!」
ベッドに腰かけ直して、足をぶらぶらさせてる僕をリリーは驚いて見つめた。
「ずっとこの家から出たかったんだ、僕」
そう言って笑いかけると、リリーは眉を八の字にして泣きそうな顔をする。
無理もない。僕の家族はとにかく仲が悪い。
父上は『ごうつくばり侯爵』とあだ名されるほどお金に汚い。領民が飢饉や疫病に苦しんでいる時でさえ、重税を課して金目のものなら、取って取って取りまくる。それこそ病人の布団まで家来に命じてはぎ取ってくるのだ。
母上と結婚したのも大商人の娘で実家の財力目当てだった。
母上はそんな夫を嫌い、僕を生んですぐに館を出て別荘で暮らしている。
だから僕は母の顔も知らない。
加えて4人の兄たちも父親に似て、性格が悪く仲も悪い。
兄たちと仲良く遊んだ記憶はなく、いじめられるか無視されるかの思い出しかない。
だから今日の僕の5歳の誕生日にも、父上以外の家族は館にいない。
そして今朝いきなり父上は鑑定士を呼びつけ、僕のギフトを鑑定させたのだ。
そして気に入らないからと追放した。
いくら期待されていない五男坊とはいえ、あまりといえばあまりの扱いである。
それにみんなには内緒だが僕には前世の記憶があった。
4歳の時、積木で遊んでいたらふと頭に浮かんだ。
【雑誌の組み立て付録が作りたい!!】と――――。
前世では子供の頃はもちろん、大人になっても甥っ子や姪っ子のためにと児童誌の付録を作っていた。
車や怪獣、ロボットを平面図からハサミで切り取りのりでくっつけ、立体化する。
そして苦労して完成した付録が動き出した時の感動と達成感は格別だった。
この世界には雑誌はあるにはある。だが一般国民の識字率は低い。
従って発行部数は極めて少なく、付録付きの雑誌に至っては皆無なのだ。
大好きな雑誌の付録が作りたい!
それも大人でも手こずるような、精緻な組み立て付録がいい!!
その願望は小さな僕の中で、日に日に高まってゆく。
だが現実は、大好きな付録が作りたくて作りたくてたまらないのに、この世界では作れない。
この膨れ上がった欲求不満が、前代未聞のギフトを僕がもらった理由ではないだろうか――――。
「ギフト【のりとハサミ】を授かるなんて、本当に僕らしいよ。きっとこれから先も、僕にぴったりの素敵な事が起きるよ!」
自信満々に胸を張るとリリーもやっと少しだけ笑ってくれた。
「ご心配には及びません。このリリーも坊ちゃまと一緒に辺境だろうと地獄だろうと、どこへでもお供いたしますからね」
そう言って彼女は今度は優しく、僕を抱きしめてくれた。
それなのに……。
「え、御者がいないの?」
「はい、旦那様が御者も護衛の騎士も、五男坊には分不相応だからと……」
午前中に支度を済ませ、さあ領地に行こうと張り切っていたら、何と父上が御者を出し惜しみしたらしい。
「御者は何とかわたくしがやりますが、こんなボロボロの馬車だなんてあんまりです……」
確かに馬車にはシュヴァイツァー侯爵家の家紋も入っていないし、馬車も外装が至る所剥がれてかなりの年代ものだ。
走り始めた途端、バラバラに分解しないだろうか。
「平気だよ。父上はきっと僕の追放を大袈裟にしたくなくて、護衛と家紋を外したんだよ」
「ですがこれでは、まるで夜逃げです」
リリーはそう言って涙ぐむ。
僕だって本当はわかっていた。
父上は当てが外れた五男坊に、余計なお金を使いたくないだけだよね。
だけどその事実を口にすれば、心優しいリリーは僕以上に悲しむだろう。
赤ちゃんの時から僕を見守ってくれている彼女をこれ以上傷つけたくはない。
「リリー、何をしている。使用人が主に気を使わせるとは何事だ」
そんな僕ら2人の元に、老執事ハルベリがやってきた。
「お話は伺いました。ゼクス様、今からでも遅くありません。旦那様にお許しいただけるように、お詫びしてはいかがでしょうか」
黒い燕尾服を優雅に着こなしたハルベリは、父上より貴族らしく威厳がある。
「何をおっしゃるんです!坊ちゃまは謝らなくてはいけないことなんて何も……!」
「待って、リリー」
顔を真っ赤にして食ってかかる彼女を僕は手で制する。
「父上に許しを請う気はないよ、僕は」
「ほう、なぜですかな?」
ハルベリは眼鏡の奥から眼光鋭く睨む。
「能なし五男坊にも意地がある。勝手に期待をかけて当てが外れたら飽きた玩具みたいに我が子を捨てる。そんな身勝手な父親に下げる頭はない」
これは本心だった。
家族にも館にも今さら何の未練もない。辺境とはいえ自分の領地を持てるのなら、こんな家に用はない。
ハルベリはそんな僕の言い分を無表情に聞いていた。
「まあ、それは建前で、本当は嫌な家族から解放されてのんびり過ごしたいだけなんだ」
僕はえへへっと照れ笑いをした。
嫌な家族のいない場所で伸び伸びと、この世界には存在しない『付録』を自分の手で一から作りたい。
これもまた、本心には違いないのだ。
するとハルベリはふっと含み笑いを浮かべる。
「なるほど、のんびり過ごすためですか。ではこの年寄りが余生を送るにもおあつらえ向きのお話ですな」
「え……?」
「このハルベリもお供いたします」
「ええ!?筆頭執事が!?その地位を捨てて?何で……?」
シュヴァイツァー侯爵家筆頭執事にして、元国王軍第一騎士団騎士団長。
剣術と体術においては王国最強と謳われたこの人が僕についてくるって?
「年のせいか最近、寝ても疲れがとれません。そろそろ後進に道を譲って楽隠居しようと思い立ちまして」
「いや、何が疲れだよ。今朝も腕立て伏せを100回もやってただろう!?僕も一緒に30回もやらされたもん」
「若い頃は1000回できました」
ハルベリは体育会系執事だった。
幼い頃から今に至るまで、基礎訓練から体術剣術までみっちりと叩き込まれたのだ。
まさか辺境の地まで着いてきて僕をしごく気じゃないだろうな!?
「それに僕が赴任する領地は厳しい辺境の荒れ地だよ。苦労するだけだよ」
「嫌とは言わせませんぞ、ゼクス様。その廃車寸前のおんぼろ馬車ではとても辺境地アヴェリアまでたどり着けません。その点」
ハルベリはそこまで話すと自身の背後を振り返る。
僕とリリーもつられて同じ方向を見た。
そして僕ら2人は驚きに目を見張った。
そこにはシュヴァイツァー侯爵家の家紋である『向かい合う2頭の獅子が葡萄を抱える』図案が描かれた、6頭立ての立派な馬車が停まっていたのだ。
「わたくしが旦那様から退職金代わりに分捕ってきた、この高級馬車なら10日の行程を4日に短縮できますぞ」
「何だって?4日に短縮!?よし、ともに行こう!ハルベリ!!」
僕は即座に老執事の手を両手でガッチリと握った。
ハルベリもまた会心の笑みを浮かべる。
「坊ちゃまぁ!本当にいいんですか!?この馬車を分捕ってきたと言ってましたよ、執事さん」
リリーは悲鳴を上げたがその時には、僕はいそいそと高級馬車に乗り込み、ハルベリも上機嫌で御者台に上っていた。
「あのケチな父上のことだよ。まともに交渉して退職金を払うと思う?」
「さすがゼクス様。よくわかっていらっしゃる。リリーも細かいことは気にするな。それより旦那様の追っ手が来る前に急げ」
可哀想に、真面目なリリーは僕とハルベリを交互に見上げて半泣きであった。
「ほらね、言った通りだろう?」
僕は馬車の中からリリーに手を差し出しながら笑った。
「きっとこれから先も、僕にぴったりの素敵な事が起きるって。リリーの他にも仲間が増えたよ!」
「侯爵家の若様と我々が仲間などとは畏れ多い。口を挟むようで恐縮ですが、わたくしどもはゼクス様の使用人にございます」
リリーが答えるより早く、ハルベリがやんわりと釘を刺す。
「うん、そうだね。じゃあ、仲間がダメなら僕の付録じゃどうかな?」
「ふろく……とは?」
ハルベリとリリーは顔を見合わせ不思議がる。
「雑誌に付いているおまけさ。なのに、肝心な雑誌より面白くってさ。どうしても欲しくなるんだ!」
「なるほど、我々はゼクス様のおまけですか」
なぜかハルベリの声は嬉しそうに弾んでいた。
「それも面白くってどうしても欲しくなるおまけなんですって!」
リリーは御者台に座るハルベリを見上げて笑った。
「だから2人とも僕にくっ付いてきてよ。付録みたいにさ」
僕が差し出した右手をリリーが力強く握る。
そしてステップに足を乗せると素早く馬車に乗り込んだ。
「行くよ、みんな!僕らの新天地アヴェリアに出発だ!!」
手にしたステッキで馬車の天井を軽く突く。
それを合図に6頭の黒馬たちは、艶やかなたてがみをなびかせて駆け出した。
僕らの馬車は風のように音もなく滑り出してゆく。
遠くからは、『待てぇ~!』『馬車泥棒ぉ~!』『わしの特注高級馬車を返せぇ~!』と家来たちと父上の声が聞こえてくるが気にしない。
この旅立ちが、僕の輝かしい付録付きライフの始まりなのだ。