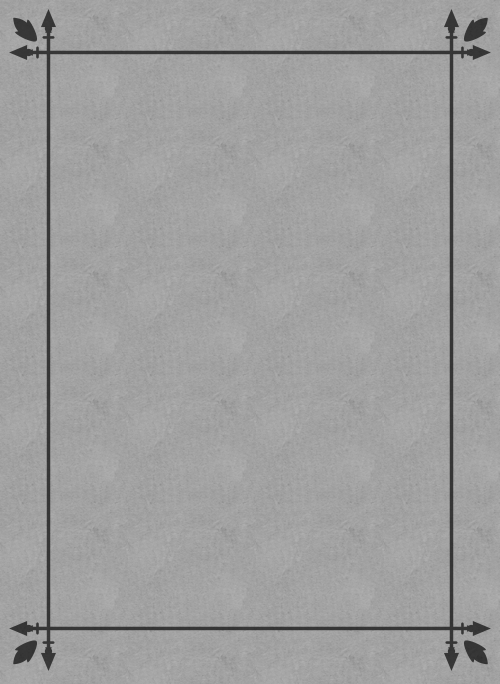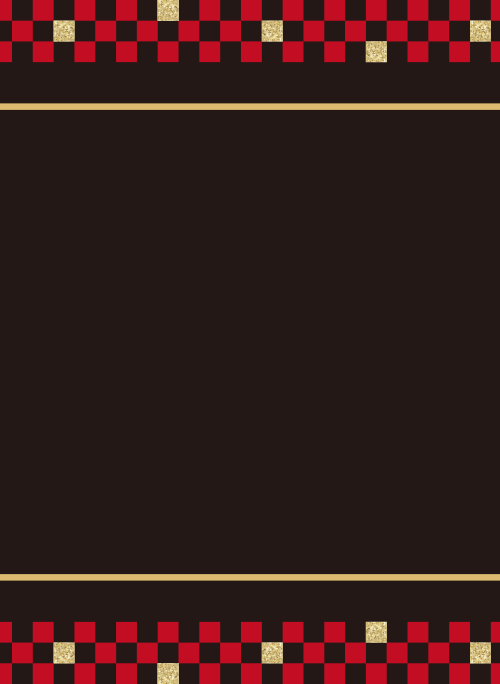「紬(つむぎ)さん。コハクちゃん、お入りください」
受付のお姉さんの声がやけに明るくて、逆に胸がきゅっと縮む。
動物病院の待合室のテレビでは、動物番組の犬が芸をしていて、周りのおばさんたちが「かわいいねぇ」って笑ってる。
かわいい。うん、かわいい。犬はかわいい。世界はそれを知ってる。
だったら、なんで——。
母がキャリーケースをそっと持ち上げる。いつもなら「重いから私が持つ」って言い張るのに、今日は言えなかった。
中のコハクは、もう重さがないみたいだった。ふわっと軽い。軽すぎる。
診察室のドアが閉まる音が、妙に大きい。
先生はいつもの白衣、いつもの無表情、いつものペン。
それなのに机の上の紙だけが、今日だけ別の種類みたいに見える。
「検査結果ですけど……」
先生がモニターを指さす。数字とかグラフとか、私にはほとんど外国語だ。
でも、先生の声のトーンだけは理解できる。
やさしく、丁寧に、でも逃げ道を用意しない声。
「腎臓の数値が、かなり悪いです。前回より進行していますね。体重も落ちていますし、食欲も戻らない」
「……薬、増やせますか?」
私の声が、自分のものじゃないみたいに震えた。
増やせるはずだ。薬ってそういうものでしょ。増やしたら効くでしょ。
私は数字の意味は分からなくても、増やせるって言葉なら知ってる。
先生は一瞬だけ目を伏せた。
その一瞬が、すでに答えだった。
「これ以上の投薬は、身体に負担になります」
「じゃあ……じゃあ、せめて。せめて栄養のある流動食とか……。何か、こう、家でできること——」
私は言いながら、言葉を探していた。
家でできることなんて、無限にあってほしかった。
温めるとか、撫でるとか、祈るとか。
全部でもいい。全部やる。私がやる。
でも先生は、ペンを置いた。
「紬さん……いえ、飼い主さんとして、つらいと思うんですが」
飼い主さん。
そう呼ばれた瞬間だけ、私は紬じゃなくなって、ただの犬を飼ってる人になった気がした。
クラスの名前のないモブみたいに。
「この状態だと、治療で回復する見込みは……正直、ありません。何をしても、苦しい時間を延ばすだけになる可能性が高い」
母が息を呑む音がした。
私はその音に腹が立った。
息を呑むくらいなら、何か言ってよ。反論してよ。先生に噛みついてよ。
でも母は、ただ黙って、手を膝の上で握りしめている。
「……手遅れ、ってことですか」
自分で言って、自分の言葉が耳に刺さった。
手遅れ。遅れ。
何に遅れた?私はどこで間に合わなくなった?
先生は、はっきりと頷いた。
「はい。残念ですが……」
残念。
残念って、何?
失敗したテストの点数みたいに言わないで。
先生が、机の引き出しから一枚の紙を出した。
白い紙。文字がいっぱい。
たぶん、あれが「それ」だって、分かった。
「安楽死という選択肢も、現実的に考える段階です。痛みや苦しみを——」
「だめ!」
声が出るより先に、喉が熱くなった。
胸の奥で何かが暴れて、言葉の形になって飛び出した。
「だめです!だめ!やめてください!」
先生が、少しだけ眉を寄せる。
母が「紬……」と私の袖を掴もうとする。
でも私は母の手を振りほどいて、診察台に身を乗り出した。
「目の前で殺さないで!ずっと一緒にいたのに!私の目の前で——」
殺すって言った自分の言葉が、先生の顔にぶつかって跳ね返ってくる。
先生は冷静に、「殺す、ではなく」と言いかけた。
でも、私には同じだった。
注射だろうが薬だろうが、同意書だろうが、呼び方がどうであろうが。
その後に来るのは、コハクがいなくなる現実だ。
「私、頑張ります。看病だってする。寝ないでもいい。学校だって——」
「紬」
母の声が、低い。
その低さが、怖い。
母が現実の方へ歩いていこうとしているのが分かるから。
「現実見なさい」って言われるのが怖い。
だって現実って、いつも私の大事なものを奪う。
「……紬さん」
先生も、私の名前を呼んだ。
その一言が、妙に優しくて、余計に腹が立った。
「コハクちゃんは、もうかなり——」
「分かってます!」
分かってない。分かりたくない。
分かってしまったら、私はここで崩れる。
そのときだった。
診察台の上で横たわっていたコハクが、ほんの少しだけ首を動かした。
いつもなら「どうしたの?」って笑える程度の動き。
でも今日は違う。今日は、奇跡みたいに見えた。
「……コハク?」
私は名前を呼びながら、息を止めていた。
呼吸したら壊れそうだった。
コハクは、震える前足をゆっくりと伸ばした。
爪が診察台のシートに引っかかって、かすかな音がする。
ザリ、ザリ。
それが、やけに生々しい。
「待って……無理しないで……」
止めたいのに、止められない。
コハクは、必死にどこかへ移動しようとしている。
方向は——私。
「コハク、こっち来なくていい。いいから、寝てて……」
私がしゃべると、涙が勝手に落ちる。
涙が落ちると、視界が歪む。
歪んだ視界の向こうで、コハクが、私の方へ顔を寄せた。
……寄せた、というより、運んだみたいだった。
身体の全部を使って、残ってる力を全部、前足に集めて。
そして、私の膝に、鼻先が触れた。
ちょん。
たったそれだけ。
なのに胸の奥が、熱くなって、苦しくて、息ができなくなる。
「……っ、コハク……」
私の口から出たのは、謝罪だった。
「ごめんね……ごめん……ごめんなさい……」
何に対して謝ってるのか、自分でも分からない。
病院に連れてきたこと?もっと早く気づけなかったこと?
学校行ってたこと?スマホ見て笑ってたこと?
普通に生きてたこと?
コハクの尻尾が、かすかに動いた。
ぶぶ、ぶぶ、と小さく震えるみたいに。
「……しっぽ、動いた……」
私が言うと、母が泣きそうな声で「うん……」と言った。
先生はその尻尾を見て、何も言わなかった。
言えなかったのかもしれない。
だってそれは、医学の範囲外の、気持ちだったから。
先生が、紙をそっと机の上に置いた。
押しつけるでもなく、引っ込めるでもなく。
「すぐ決めろとは言いません。ただ……コハクちゃんの負担が増える前に、話し合ってください」
話し合う。
誰と?母と?先生と?
コハクと?
コハクは今、私の膝に鼻をつけて、ただ静かに目を開けている。
その目が、「大丈夫」って言ってる気がした。
いや、言っててほしかった。
私の都合で、そう聞こえるだけかもしれないのに。
「……帰ります」
私が立ち上がると、足が少しふらついた。
母がキャリーを抱え直す。
私はコハクを抱き上げたかった。でも先生が「無理に動かさないで」と言ったから、抱けなかった。
抱けないのが悔しくて、また涙が出た。
診察室を出るとき、待合室のテレビがまだ犬を映していた。
芸をして、褒められて、しっぽを振って。
みんなが笑ってる。
私の中で何かがひび割れた。
——コハクは、芸なんかしなくても一番えらいのに。
——ただ生きてるだけで、ずっと、えらいのに。
外に出た瞬間、冷たい雨が顔に当たった。
息を吸うと、雨の匂いとアスファルトの匂いと、病院の消毒液が混ざって、気持ちが悪くなる。
「紬、車乗りなさい」
母はそう言ったけれど、声に力がなかった。
母の腕の中のキャリーケースが、雨に濡れないように傾けられている。
「……私、歩く」
「こんな雨なのに?」
「歩く。頭冷やす」
本当は逆だった。
頭を冷やしたら、冷たすぎて壊れそうだった。
でも車に乗ったら、母の隣で、現実の話をしなきゃいけない。
同意書。苦しみ。手遅れ。
そんな単語を、車内の狭い空間で、逃げ場なく聞きたくなかった。
「紬……」
母が私の名前を呼ぶ。
でも私は、聞こえないふりをして傘を開いた。
傘の骨が、カチン、と鳴る。
その音が、妙に終わりみたいだった。
「家で待ってるから、早く帰ってきて」
母の声が背中に落ちた。
私は返事をしなかった。
返事をしたら、泣き声が混ざるから。
雨の中を歩き出すと、制服がすぐに湿って、スカートが脚に張り付いた。
靴の中も冷たい。
でもそれでよかった。
身体が不快だと、心の痛みが少しだけ薄まる気がする。
スマホが震えた。
母からの着信。
私は画面を伏せて、ポケットに押し込んだ。
——私が出たら、母は言う。
——「紬、現実を見なさい」
——「コハクのために」
——「苦しませたくないでしょ」
コハクのため。
その言葉、ずるい。
コハクを盾にするのは、ずるい。
でも、私も同じくらいずるい。
コハクを理由にして、決断から逃げてる。
川沿いの道は、雨の日は誰もいない。
濡れた草の匂いがする。
川の水は増えていて、流れが速い。
遠くで電車の音がした。鉄橋を渡る、ゴゴゴ、という低い音。
私は昔から、その音が好きだった。
どこかへ行ける音だから。
——どこかへ行きたい。
——今のここじゃない、どこかへ。
でも、どこへ行けばいいんだろう。
「……コハク」
声に出して名前を呼ぶと、胸がぎゅっと痛む。
呼べば呼ぶほど、現実になる。
コハクが弱ってること。
もう長くないこと。
選択を迫られていること。
私は何度も自分に言い聞かせる。
私は悪くない。
私はちゃんと病院に連れてきた。
薬も飲ませた。
夜だって起きて、水を飲ませた。
あったかい毛布も用意した。
撫でた。話しかけた。
写真も撮った。
誕生日にはケーキ(犬用)も買った。
散歩も——散歩も……。
歩きながら、頭の中で言い訳が増えていく。
言い訳って、こんなに増えるんだ。
増えるほど、苦しくなるのに。
ふと、昔の光景が浮かんだ。
小学生の頃。
私が泣きながら家を飛び出した日。
理由は覚えてない。たぶん、どうでもいい。
でも、玄関を飛び出した私の服の袖をぐいぐい引っ張った存在がいた。
『行かないで』って、言うみたいに。
振り返ったら、子犬のコハクが、必死に私の袖を咥えていた。
まだ耳が大きくて、足が短くて、目だけが真剣で。
私はそれで笑ってしまって、泣くのをやめた。
袖がよだれでべちゃべちゃになったのに、嬉しかった。
——あの時から、コハクは私を引き戻すのが得意だ。
——私がどこかへ行きそうになると、ちゃんと引っ張ってくる。
だから、今日も。
今日も引っ張って。
私を決断の地獄から、どこか別の場所へ連れてって。
「……なんで、こんなことになるの」
私は、誰にも聞こえないように呟いた。
雨に紛れて、声が消える。
「どうしたらいいの。ねえ、コハク。私、どうしたら——」
川の水音が、答えみたいに大きい。
ザアアア、と流れて、何も残さない。
私は立ち止まって、ガードレールに手をついた。
冷たい。
冷たすぎて、手がしびれる。
でもその冷たさが、現実みたいで、怖い。
——もし、同意書にサインしたら。
——コハクは、私の目の前で眠って、二度と起きない。
——私が、決める。
——私が、終わらせる。
「……無理」
声が漏れた。
無理。無理無理無理。
なのに、“無理”って言う自分に腹が立つ。
じゃあ、どうするの?
ずっと苦しませるの?
それはコハクのため?
それとも私のため?
雨が強くなって、視界が白くなる。
前髪から滴が落ちて、目に入って痛い。
そのとき、足元の土が、ずるりと滑った。
「——っ!」
一瞬、時間が止まったみたいだった。
次の瞬間、身体が傾いて、傘が風を受けて、バランスが崩れて。
ガードレールを掴もうとした手が、濡れて滑る。
指が、空を掴む。
「うそ——!」
世界が回転して、川の水面が迫ってくる。
黒い。冷たい。重たい。
落ちる、と理解した時にはもう遅かった。
——手遅れ。
先生の声が頭の中で響く。
やめて。今それ言わないで。
水に叩きつけられた瞬間、息が全部抜けた。
冷たさが身体の中に突き刺さって、肺がぎゅっと縮む。
「——っ、……!」
叫ぼうとして、口から水が入る。
苦い。泥の味。雨の味。
制服が水を吸って、急に重くなる。
脚が持っていかれる。
私は必死に腕を動かした。
水面がどこか分からない。
目を開けると、雨の泡が視界を埋めて、何も見えない。
閉じても、同じ。
——死ぬ。
——私、死ぬ。
その言葉が浮かんだ瞬間、怖さより先に、別の感情が来た。
——コハク。
——コハク、置いていくの?
——私が先に?
——そんなの、だめ。
母の顔が浮かぶ。
泣いてる母。
キャリーケースの中のコハク。
同意書。白い紙。
「……ごめ、……」
水の中で謝っても、誰にも届かない。
謝罪って、こういうとき役に立たない。
息もできないのに、私はごめんなさいしか言えない。
そのときだった。
制服の袖が、ぐい、と引かれた。
最初は、水の流れだと思った。
でも違う。
水の流れは、こんなふうに意志を持って引っ張らない。
ぐい。
もう一度。
今度ははっきりと、私の腕を上へ引き上げる力。
——誰?
私は反射的に目線を動かした。
水の中で、必死に顔を上げようとして。
濁った水の向こう、私の袖を咥える影。
小さくて、しなやかで、真剣な目。
その瞬間、私は理解してしまった。
袖を引く力に顔を上げると、そこにいたのは――。
受付のお姉さんの声がやけに明るくて、逆に胸がきゅっと縮む。
動物病院の待合室のテレビでは、動物番組の犬が芸をしていて、周りのおばさんたちが「かわいいねぇ」って笑ってる。
かわいい。うん、かわいい。犬はかわいい。世界はそれを知ってる。
だったら、なんで——。
母がキャリーケースをそっと持ち上げる。いつもなら「重いから私が持つ」って言い張るのに、今日は言えなかった。
中のコハクは、もう重さがないみたいだった。ふわっと軽い。軽すぎる。
診察室のドアが閉まる音が、妙に大きい。
先生はいつもの白衣、いつもの無表情、いつものペン。
それなのに机の上の紙だけが、今日だけ別の種類みたいに見える。
「検査結果ですけど……」
先生がモニターを指さす。数字とかグラフとか、私にはほとんど外国語だ。
でも、先生の声のトーンだけは理解できる。
やさしく、丁寧に、でも逃げ道を用意しない声。
「腎臓の数値が、かなり悪いです。前回より進行していますね。体重も落ちていますし、食欲も戻らない」
「……薬、増やせますか?」
私の声が、自分のものじゃないみたいに震えた。
増やせるはずだ。薬ってそういうものでしょ。増やしたら効くでしょ。
私は数字の意味は分からなくても、増やせるって言葉なら知ってる。
先生は一瞬だけ目を伏せた。
その一瞬が、すでに答えだった。
「これ以上の投薬は、身体に負担になります」
「じゃあ……じゃあ、せめて。せめて栄養のある流動食とか……。何か、こう、家でできること——」
私は言いながら、言葉を探していた。
家でできることなんて、無限にあってほしかった。
温めるとか、撫でるとか、祈るとか。
全部でもいい。全部やる。私がやる。
でも先生は、ペンを置いた。
「紬さん……いえ、飼い主さんとして、つらいと思うんですが」
飼い主さん。
そう呼ばれた瞬間だけ、私は紬じゃなくなって、ただの犬を飼ってる人になった気がした。
クラスの名前のないモブみたいに。
「この状態だと、治療で回復する見込みは……正直、ありません。何をしても、苦しい時間を延ばすだけになる可能性が高い」
母が息を呑む音がした。
私はその音に腹が立った。
息を呑むくらいなら、何か言ってよ。反論してよ。先生に噛みついてよ。
でも母は、ただ黙って、手を膝の上で握りしめている。
「……手遅れ、ってことですか」
自分で言って、自分の言葉が耳に刺さった。
手遅れ。遅れ。
何に遅れた?私はどこで間に合わなくなった?
先生は、はっきりと頷いた。
「はい。残念ですが……」
残念。
残念って、何?
失敗したテストの点数みたいに言わないで。
先生が、机の引き出しから一枚の紙を出した。
白い紙。文字がいっぱい。
たぶん、あれが「それ」だって、分かった。
「安楽死という選択肢も、現実的に考える段階です。痛みや苦しみを——」
「だめ!」
声が出るより先に、喉が熱くなった。
胸の奥で何かが暴れて、言葉の形になって飛び出した。
「だめです!だめ!やめてください!」
先生が、少しだけ眉を寄せる。
母が「紬……」と私の袖を掴もうとする。
でも私は母の手を振りほどいて、診察台に身を乗り出した。
「目の前で殺さないで!ずっと一緒にいたのに!私の目の前で——」
殺すって言った自分の言葉が、先生の顔にぶつかって跳ね返ってくる。
先生は冷静に、「殺す、ではなく」と言いかけた。
でも、私には同じだった。
注射だろうが薬だろうが、同意書だろうが、呼び方がどうであろうが。
その後に来るのは、コハクがいなくなる現実だ。
「私、頑張ります。看病だってする。寝ないでもいい。学校だって——」
「紬」
母の声が、低い。
その低さが、怖い。
母が現実の方へ歩いていこうとしているのが分かるから。
「現実見なさい」って言われるのが怖い。
だって現実って、いつも私の大事なものを奪う。
「……紬さん」
先生も、私の名前を呼んだ。
その一言が、妙に優しくて、余計に腹が立った。
「コハクちゃんは、もうかなり——」
「分かってます!」
分かってない。分かりたくない。
分かってしまったら、私はここで崩れる。
そのときだった。
診察台の上で横たわっていたコハクが、ほんの少しだけ首を動かした。
いつもなら「どうしたの?」って笑える程度の動き。
でも今日は違う。今日は、奇跡みたいに見えた。
「……コハク?」
私は名前を呼びながら、息を止めていた。
呼吸したら壊れそうだった。
コハクは、震える前足をゆっくりと伸ばした。
爪が診察台のシートに引っかかって、かすかな音がする。
ザリ、ザリ。
それが、やけに生々しい。
「待って……無理しないで……」
止めたいのに、止められない。
コハクは、必死にどこかへ移動しようとしている。
方向は——私。
「コハク、こっち来なくていい。いいから、寝てて……」
私がしゃべると、涙が勝手に落ちる。
涙が落ちると、視界が歪む。
歪んだ視界の向こうで、コハクが、私の方へ顔を寄せた。
……寄せた、というより、運んだみたいだった。
身体の全部を使って、残ってる力を全部、前足に集めて。
そして、私の膝に、鼻先が触れた。
ちょん。
たったそれだけ。
なのに胸の奥が、熱くなって、苦しくて、息ができなくなる。
「……っ、コハク……」
私の口から出たのは、謝罪だった。
「ごめんね……ごめん……ごめんなさい……」
何に対して謝ってるのか、自分でも分からない。
病院に連れてきたこと?もっと早く気づけなかったこと?
学校行ってたこと?スマホ見て笑ってたこと?
普通に生きてたこと?
コハクの尻尾が、かすかに動いた。
ぶぶ、ぶぶ、と小さく震えるみたいに。
「……しっぽ、動いた……」
私が言うと、母が泣きそうな声で「うん……」と言った。
先生はその尻尾を見て、何も言わなかった。
言えなかったのかもしれない。
だってそれは、医学の範囲外の、気持ちだったから。
先生が、紙をそっと机の上に置いた。
押しつけるでもなく、引っ込めるでもなく。
「すぐ決めろとは言いません。ただ……コハクちゃんの負担が増える前に、話し合ってください」
話し合う。
誰と?母と?先生と?
コハクと?
コハクは今、私の膝に鼻をつけて、ただ静かに目を開けている。
その目が、「大丈夫」って言ってる気がした。
いや、言っててほしかった。
私の都合で、そう聞こえるだけかもしれないのに。
「……帰ります」
私が立ち上がると、足が少しふらついた。
母がキャリーを抱え直す。
私はコハクを抱き上げたかった。でも先生が「無理に動かさないで」と言ったから、抱けなかった。
抱けないのが悔しくて、また涙が出た。
診察室を出るとき、待合室のテレビがまだ犬を映していた。
芸をして、褒められて、しっぽを振って。
みんなが笑ってる。
私の中で何かがひび割れた。
——コハクは、芸なんかしなくても一番えらいのに。
——ただ生きてるだけで、ずっと、えらいのに。
外に出た瞬間、冷たい雨が顔に当たった。
息を吸うと、雨の匂いとアスファルトの匂いと、病院の消毒液が混ざって、気持ちが悪くなる。
「紬、車乗りなさい」
母はそう言ったけれど、声に力がなかった。
母の腕の中のキャリーケースが、雨に濡れないように傾けられている。
「……私、歩く」
「こんな雨なのに?」
「歩く。頭冷やす」
本当は逆だった。
頭を冷やしたら、冷たすぎて壊れそうだった。
でも車に乗ったら、母の隣で、現実の話をしなきゃいけない。
同意書。苦しみ。手遅れ。
そんな単語を、車内の狭い空間で、逃げ場なく聞きたくなかった。
「紬……」
母が私の名前を呼ぶ。
でも私は、聞こえないふりをして傘を開いた。
傘の骨が、カチン、と鳴る。
その音が、妙に終わりみたいだった。
「家で待ってるから、早く帰ってきて」
母の声が背中に落ちた。
私は返事をしなかった。
返事をしたら、泣き声が混ざるから。
雨の中を歩き出すと、制服がすぐに湿って、スカートが脚に張り付いた。
靴の中も冷たい。
でもそれでよかった。
身体が不快だと、心の痛みが少しだけ薄まる気がする。
スマホが震えた。
母からの着信。
私は画面を伏せて、ポケットに押し込んだ。
——私が出たら、母は言う。
——「紬、現実を見なさい」
——「コハクのために」
——「苦しませたくないでしょ」
コハクのため。
その言葉、ずるい。
コハクを盾にするのは、ずるい。
でも、私も同じくらいずるい。
コハクを理由にして、決断から逃げてる。
川沿いの道は、雨の日は誰もいない。
濡れた草の匂いがする。
川の水は増えていて、流れが速い。
遠くで電車の音がした。鉄橋を渡る、ゴゴゴ、という低い音。
私は昔から、その音が好きだった。
どこかへ行ける音だから。
——どこかへ行きたい。
——今のここじゃない、どこかへ。
でも、どこへ行けばいいんだろう。
「……コハク」
声に出して名前を呼ぶと、胸がぎゅっと痛む。
呼べば呼ぶほど、現実になる。
コハクが弱ってること。
もう長くないこと。
選択を迫られていること。
私は何度も自分に言い聞かせる。
私は悪くない。
私はちゃんと病院に連れてきた。
薬も飲ませた。
夜だって起きて、水を飲ませた。
あったかい毛布も用意した。
撫でた。話しかけた。
写真も撮った。
誕生日にはケーキ(犬用)も買った。
散歩も——散歩も……。
歩きながら、頭の中で言い訳が増えていく。
言い訳って、こんなに増えるんだ。
増えるほど、苦しくなるのに。
ふと、昔の光景が浮かんだ。
小学生の頃。
私が泣きながら家を飛び出した日。
理由は覚えてない。たぶん、どうでもいい。
でも、玄関を飛び出した私の服の袖をぐいぐい引っ張った存在がいた。
『行かないで』って、言うみたいに。
振り返ったら、子犬のコハクが、必死に私の袖を咥えていた。
まだ耳が大きくて、足が短くて、目だけが真剣で。
私はそれで笑ってしまって、泣くのをやめた。
袖がよだれでべちゃべちゃになったのに、嬉しかった。
——あの時から、コハクは私を引き戻すのが得意だ。
——私がどこかへ行きそうになると、ちゃんと引っ張ってくる。
だから、今日も。
今日も引っ張って。
私を決断の地獄から、どこか別の場所へ連れてって。
「……なんで、こんなことになるの」
私は、誰にも聞こえないように呟いた。
雨に紛れて、声が消える。
「どうしたらいいの。ねえ、コハク。私、どうしたら——」
川の水音が、答えみたいに大きい。
ザアアア、と流れて、何も残さない。
私は立ち止まって、ガードレールに手をついた。
冷たい。
冷たすぎて、手がしびれる。
でもその冷たさが、現実みたいで、怖い。
——もし、同意書にサインしたら。
——コハクは、私の目の前で眠って、二度と起きない。
——私が、決める。
——私が、終わらせる。
「……無理」
声が漏れた。
無理。無理無理無理。
なのに、“無理”って言う自分に腹が立つ。
じゃあ、どうするの?
ずっと苦しませるの?
それはコハクのため?
それとも私のため?
雨が強くなって、視界が白くなる。
前髪から滴が落ちて、目に入って痛い。
そのとき、足元の土が、ずるりと滑った。
「——っ!」
一瞬、時間が止まったみたいだった。
次の瞬間、身体が傾いて、傘が風を受けて、バランスが崩れて。
ガードレールを掴もうとした手が、濡れて滑る。
指が、空を掴む。
「うそ——!」
世界が回転して、川の水面が迫ってくる。
黒い。冷たい。重たい。
落ちる、と理解した時にはもう遅かった。
——手遅れ。
先生の声が頭の中で響く。
やめて。今それ言わないで。
水に叩きつけられた瞬間、息が全部抜けた。
冷たさが身体の中に突き刺さって、肺がぎゅっと縮む。
「——っ、……!」
叫ぼうとして、口から水が入る。
苦い。泥の味。雨の味。
制服が水を吸って、急に重くなる。
脚が持っていかれる。
私は必死に腕を動かした。
水面がどこか分からない。
目を開けると、雨の泡が視界を埋めて、何も見えない。
閉じても、同じ。
——死ぬ。
——私、死ぬ。
その言葉が浮かんだ瞬間、怖さより先に、別の感情が来た。
——コハク。
——コハク、置いていくの?
——私が先に?
——そんなの、だめ。
母の顔が浮かぶ。
泣いてる母。
キャリーケースの中のコハク。
同意書。白い紙。
「……ごめ、……」
水の中で謝っても、誰にも届かない。
謝罪って、こういうとき役に立たない。
息もできないのに、私はごめんなさいしか言えない。
そのときだった。
制服の袖が、ぐい、と引かれた。
最初は、水の流れだと思った。
でも違う。
水の流れは、こんなふうに意志を持って引っ張らない。
ぐい。
もう一度。
今度ははっきりと、私の腕を上へ引き上げる力。
——誰?
私は反射的に目線を動かした。
水の中で、必死に顔を上げようとして。
濁った水の向こう、私の袖を咥える影。
小さくて、しなやかで、真剣な目。
その瞬間、私は理解してしまった。
袖を引く力に顔を上げると、そこにいたのは――。