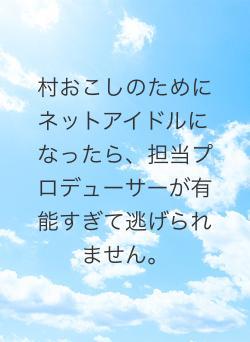ずっと好きだった幼馴染が女性と結婚した夜に見た僕の夢
──それは幼馴染と僕が結婚するもしもの世界。
想うだけなら許されるかな。
誰にも言わない、僕だけの秘密にするから。
自分で想うだけにとどめるから。
◇◇◇
「おはよう」
って君は僕を抱き寄せたままベッドで囁くんだ。いつもみたいに甘くて、優しい声で。
他の人にはそんな声出さないのに。
君はどちらかといえばやんちゃなほうで、引っ込み思案の僕とは正反対。
なのに惹かれ合うのは不思議だね。
僕だけには、甘えてきてくれる。ツンデレな猫みたいな君のことが子どもの頃から大好きだった。
君が僕の頬に軽く口付ける。
僕は心の底から嬉しくてたまらなくて、素直に見えないしっぽを振って君にくっつく。
「おはよう」
と僕が返せば君は愛おしそうに僕の前髪をごつごつした骨ばった細い指で梳いてくれる。
熱を帯びた指先に触れられると、まるで心までもぽかぽかと温まるのだ。
「なぁに? 目、にこにこさんでご機嫌じゃん」
「……うん。毎日、朝から一緒のベッドでおはようって言えるの、幸せだなーって」
「へえ」
君はにやにや口端を引いて枕に頬杖をついて笑う。
不意に、ぷにぷにと僕の頬っぺたに人差し指を押し付けてくる。
あ、遊ばれてる。
僕は少しむすっとした顔をして君を見上げた。
「んー?」
君はどこ吹く風といったように知らんぷりしている。
こういう可愛いいじわるも、嫌じゃない。
幼い頃から一緒に過ごしてきたからかな。
お互い言いたいことは面と向かって言うし、喧嘩も仲直りもたくさんしてきた。
なんでだろう。昔から君の笑った顔を見ると胸が痛いんだ。
いつかその笑顔を僕以外の人にも向けるんじゃないかって思ったら、怖くて、怖くて。
僕だけを見ていてよ。
他の人なんて視界に入れないで。
僕だけのために怒ってよ。
僕だけのために笑ってよ。
僕だけのために──泣いてよ。
いつしか君のすべては僕のすべてになった。
だから離れないで。僕を離さないで。
こんなにも君にとろけている僕を手放したりなんかしないで。
僕には君がいればいいんだから。
君以外のものは何もいらない。
君といれるならどんなことだってやる。
高校受験も大学受験も死にものぐるいでやって、君と同じ学校に入ったよ。
君は
「お。学校同じじゃん」
って笑うだけだったけど。
それでいいんだ。それでいいんだよ。
僕だけが知っていればいい。
君の背中を追いかけて、雨の日も雪の日もうしろをくっついていったこと。
「愛してる」
そう言って、僕と結婚してから毎朝おはようのキスをしてくれたね。
おやすみのキスは朝よりも長くて甘かったね。
「愛してるよ」
って僕が呟けば、君は照れくさそうに目線を合わせて僕の指を恋人繋ぎで君の指に絡めてくれたね。
「おやすみ」
「愛してる」と囁いてから君の唇が僕の唇に重なる。何度も首の角度を変えながらついばむように軽くキスをした。
そのままベッドのシーツに両手を縫いつけられて沈められる。
君との甘い夜は永遠みたいに長く感じたんだ。
恋愛映画のエンドロールみたいに長くて、甘くて、余韻が残って。
僕の世界の中で君しか見えなくなる。
「おー! これ美味いな。やっぱお前の飯最高。仕事の疲れが吹っ飛ぶ」
とある日の週末、午後9時。
繁忙期ゆえに残業からへとへとで帰ってきた君に身体が温まるご飯を食べて欲しくて、一生懸命レシピ本を片手に晩ご飯を作ったよ。
鶏団子としょうがのぽかぽか中華スープ。身体の芯から温まるように、隠し味ですりおろしたニンニクも入れた。
君とだったらニンニクを食べた後でもキスしたい。匂いなんて気にしない。
君には炊きたての麦ご飯を大盛り。僕は普通盛り。食物繊維たっぷりで、ぷちぷちとした食感がアクセント。腹持ちもいいんだって、レシピ本に書いてあった。
サバの塩焼きはよく皮を焼いてパリパリに。身はふっくらしていてご飯とよく合うらしい。
僕は今日の仕事を終えてから即座に帰宅し、すぐさま夕飯の仕度を始めた。一口の味見くらいしかしてない。
だって。夜ご飯は君と一緒に食べたい。
「いただきます」
って君はちゃんと言った?
よっぽどお腹が空いてるみたいで勢いよく食べてるけど、後でお腹痛くならないかな?
僕は缶ビールをおいしそうに飲む君を見て、「ああ。この人と結婚してよかった」と思い直す。
だって、仕事で疲れていてもこんなにも笑顔で僕の作ったご飯を食べてくれる。
こういう生活にずっと憧れていた。
君を手に入れてから、誰かに奪われないかと心配になって秘密の宝箱にこの瞬間を隠したくなる。
君はそんな僕のことを
『俺のこと好き好き病』
って言ってからかうんだ。
そんな病気があるんなら一生治らなくていいよ。
不意に視界がゆっくりと白い霧に包まれていく。ホワイトリリーの微かな匂い。
昨日、君が『結婚して半年記念日だから』と言って贈ってくれた白い花束の匂いがたゆたうように僕を包んだ。
「待って。行かないで──」
君は僕を置いて光の中へ歩いていく。その後ろ姿が見慣れていて、大きくて、逞しくて。
涙がぽろぽろ止まらなかった。
──それは幼馴染と僕が結婚するもしもの世界。
想うだけなら許されるかな。
誰にも言わない、僕だけの秘密にするから。
自分で想うだけにとどめるから。
◇◇◇
「おはよう」
って君は僕を抱き寄せたままベッドで囁くんだ。いつもみたいに甘くて、優しい声で。
他の人にはそんな声出さないのに。
君はどちらかといえばやんちゃなほうで、引っ込み思案の僕とは正反対。
なのに惹かれ合うのは不思議だね。
僕だけには、甘えてきてくれる。ツンデレな猫みたいな君のことが子どもの頃から大好きだった。
君が僕の頬に軽く口付ける。
僕は心の底から嬉しくてたまらなくて、素直に見えないしっぽを振って君にくっつく。
「おはよう」
と僕が返せば君は愛おしそうに僕の前髪をごつごつした骨ばった細い指で梳いてくれる。
熱を帯びた指先に触れられると、まるで心までもぽかぽかと温まるのだ。
「なぁに? 目、にこにこさんでご機嫌じゃん」
「……うん。毎日、朝から一緒のベッドでおはようって言えるの、幸せだなーって」
「へえ」
君はにやにや口端を引いて枕に頬杖をついて笑う。
不意に、ぷにぷにと僕の頬っぺたに人差し指を押し付けてくる。
あ、遊ばれてる。
僕は少しむすっとした顔をして君を見上げた。
「んー?」
君はどこ吹く風といったように知らんぷりしている。
こういう可愛いいじわるも、嫌じゃない。
幼い頃から一緒に過ごしてきたからかな。
お互い言いたいことは面と向かって言うし、喧嘩も仲直りもたくさんしてきた。
なんでだろう。昔から君の笑った顔を見ると胸が痛いんだ。
いつかその笑顔を僕以外の人にも向けるんじゃないかって思ったら、怖くて、怖くて。
僕だけを見ていてよ。
他の人なんて視界に入れないで。
僕だけのために怒ってよ。
僕だけのために笑ってよ。
僕だけのために──泣いてよ。
いつしか君のすべては僕のすべてになった。
だから離れないで。僕を離さないで。
こんなにも君にとろけている僕を手放したりなんかしないで。
僕には君がいればいいんだから。
君以外のものは何もいらない。
君といれるならどんなことだってやる。
高校受験も大学受験も死にものぐるいでやって、君と同じ学校に入ったよ。
君は
「お。学校同じじゃん」
って笑うだけだったけど。
それでいいんだ。それでいいんだよ。
僕だけが知っていればいい。
君の背中を追いかけて、雨の日も雪の日もうしろをくっついていったこと。
「愛してる」
そう言って、僕と結婚してから毎朝おはようのキスをしてくれたね。
おやすみのキスは朝よりも長くて甘かったね。
「愛してるよ」
って僕が呟けば、君は照れくさそうに目線を合わせて僕の指を恋人繋ぎで君の指に絡めてくれたね。
「おやすみ」
「愛してる」と囁いてから君の唇が僕の唇に重なる。何度も首の角度を変えながらついばむように軽くキスをした。
そのままベッドのシーツに両手を縫いつけられて沈められる。
君との甘い夜は永遠みたいに長く感じたんだ。
恋愛映画のエンドロールみたいに長くて、甘くて、余韻が残って。
僕の世界の中で君しか見えなくなる。
「おー! これ美味いな。やっぱお前の飯最高。仕事の疲れが吹っ飛ぶ」
とある日の週末、午後9時。
繁忙期ゆえに残業からへとへとで帰ってきた君に身体が温まるご飯を食べて欲しくて、一生懸命レシピ本を片手に晩ご飯を作ったよ。
鶏団子としょうがのぽかぽか中華スープ。身体の芯から温まるように、隠し味ですりおろしたニンニクも入れた。
君とだったらニンニクを食べた後でもキスしたい。匂いなんて気にしない。
君には炊きたての麦ご飯を大盛り。僕は普通盛り。食物繊維たっぷりで、ぷちぷちとした食感がアクセント。腹持ちもいいんだって、レシピ本に書いてあった。
サバの塩焼きはよく皮を焼いてパリパリに。身はふっくらしていてご飯とよく合うらしい。
僕は今日の仕事を終えてから即座に帰宅し、すぐさま夕飯の仕度を始めた。一口の味見くらいしかしてない。
だって。夜ご飯は君と一緒に食べたい。
「いただきます」
って君はちゃんと言った?
よっぽどお腹が空いてるみたいで勢いよく食べてるけど、後でお腹痛くならないかな?
僕は缶ビールをおいしそうに飲む君を見て、「ああ。この人と結婚してよかった」と思い直す。
だって、仕事で疲れていてもこんなにも笑顔で僕の作ったご飯を食べてくれる。
こういう生活にずっと憧れていた。
君を手に入れてから、誰かに奪われないかと心配になって秘密の宝箱にこの瞬間を隠したくなる。
君はそんな僕のことを
『俺のこと好き好き病』
って言ってからかうんだ。
そんな病気があるんなら一生治らなくていいよ。
不意に視界がゆっくりと白い霧に包まれていく。ホワイトリリーの微かな匂い。
昨日、君が『結婚して半年記念日だから』と言って贈ってくれた白い花束の匂いがたゆたうように僕を包んだ。
「待って。行かないで──」
君は僕を置いて光の中へ歩いていく。その後ろ姿が見慣れていて、大きくて、逞しくて。
涙がぽろぽろ止まらなかった。