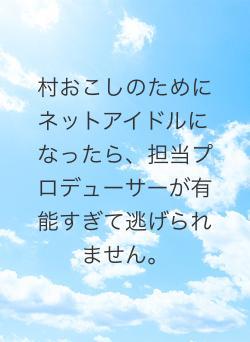校内に響き渡るチャイムの音に、僕はふうっと大きく伸びをして椅子の背もたれに腰掛けた。
苦手な物理の授業は、一生懸命黒板と先生の話にかじりつくけど言葉がすべて呪文みたいに聞こえてしまって、右耳から左耳へと通り抜けてしまう。
なんで理系に進んじゃったんだろ。
後悔先に立たず、とはよく言うもので。
本当は自分の数少ない長所を見るなら、文系のほうがいいかもなあ、なんて思ってたのにとある理由で理系を志願してしまった。
実際のところ、国立大学を目指しているから無駄な道ではないし、遠回りでもないんだけどね。
水筒からひんやりとした麦茶をこくんと口に含み、飲み干す。7月の夏休み直前。
教室にはクーラーがあるけど、僕のいる席にはあまり冷たい風があたらないから少し不満はある。
だけど、この席になってからは僕にとっては良いこと尽くめでしかなくて──。
「吹雪ー。チョコちょーだい」
あっ。今日は少し機嫌がいいみたい。
僕は名前を呼んだ前の席の子に一口チョコレートの包みを手渡す。彼は後ろを振り向くかわりに、ぐてっと椅子の背もたれに背中を押し付け、首を僕のほうへ倒してきた。
だらしのない姿勢なのに、なんか様になるのがずるい。
彼は僕を下から見上げるかたちで舌をべっ、と突き出した。紅く、肉厚な舌が真っ白い歯に映えて綺麗だ。思わず見とれてしまう。それと、シルバーの舌ピがきらっと教室の照明に反射して光った。
たぶん、舌ピってうちの学校だと校則違反だと思うんだけど……。
「あーん、は?」
「っ……わかった。あーん」
彼がむすっとしてイラつきだしたので慌ててチョコレートの包みを広げて、チョコレートを彼の舌の上に乗せた。すると彼は器用にチョコレートを口に含むと、もぐもぐと頬っぺを動かし始める。
「どろどろに溶けててなんか変な味する」
あーもう。変なこと言わないでよ。ここ、教室だよ。周りに聞こえたら恥ずかしいよ。
「仕方ないでしょ。夏だもん。そりゃチョコレートも溶けるよ」
「ふうん」
彼はつまらなそうに姿勢を正すと、僕の机に頬杖をついて向かいあわせで座り直す。その距離、約30センチ。不意の至近距離に思わず、ごくんと唾を飲み込んだ。
前の席の彼──宮家葵は、僕──笹川吹雪の恋人だ。
決して誰にもバレてはいけない、内緒の恋人。
僕と葵が出会ったのは、小学生1年生の頃。町内で開催されている月に2回の子ども食堂に行った時だった。
初めて葵を見た時に、目が釘付けになった。大きな二重に、凛とした大人っぽい表情を浮かべてカレーを淡々と食べていた。僕はたまたま隣の席が空いていたので座ることにした。
葵はもぐもぐとカレーを口に運んでおかわりをもらいにいっていた。僕はその日、お母さんが遅くまでパートで忙しかったので子ども食堂で夕食を食べるように言われていた。
綺麗な子だな。
それが葵の第一印象だった。ただ、葵の着ているTシャツは首元のボタンがひとつ無くなっていたり、履いているハーフパンツはしわくちゃなしわができているのが、子どもながらに少し気になった。
葵から自分と似た匂いがすると勘づいたからだ。だから、勇気を出して声をかけてみることにした。その時、僕は葵がカレーを食べ終えたところで「ねえ」と声をかけてみた。手には汗がじんわりと浮かび、喉の奥がからからだ。声を出すのもやっとで、掠れた声しか出なかった。けど、葵は「何?」と僕の声を聞きとってくれた。
「あの、はじめましてだよね? 僕、吹雪。それ、Tシャツのボタン無くしちゃったの?」
簡単な自己紹介と共にそう聞いてみると、葵は先程までの大人っぽい表情から一点、赤ちゃんみたく顔を真っ赤にさせて泣きそうな顔を浮かべた。僕は何か嫌なことを言ってしまったんだと思い、慌てて謝る。
「ごめん。あの、よかったら僕、Tシャツのボタン付けようか?」
「は? 何? 俺に同情でもしてんの? 他の大人たちみたいに」
泣きそうな顔のまま、葵が早口でまくし立てるのを僕は目を瞬かせて見張った。
なんでだろう。嫌な態度なのに、なんか寂しそうな子だな……。
それが僕が葵に初めて話しかけた時の印象。負けず嫌いなのか、勝気なのか。自分の弱いところを隠すように毛を逆立てている野良猫みたいな子。
僕はそんな葵の固く結ばれた心を開いてみたいと思った。本当はこの子はどんな性格で、どんな食べ物が好きで、どんなことが苦手なんだろう。
「僕、同情してないよ。ただ、友達になれたらなって、思ったんだけど……」
言えた。すごく、緊張したけど。僕はなるべく笑顔を作ろうとして頬を引き攣った。不意に、葵がそんな僕の頬をぷにっと右手の指でつまむ。
「笑えないのに無理して笑うなよ」
「……え?」
「お前、表情固すぎ。いつか地蔵になっても知らねえからな」
じ、地蔵?
僕は頭の中で自分が地蔵になっているのを想像してみて、ふっと笑い声が洩れてしまった。
なんだろう。この子、すごく面白い人な気がする。
「じゃあ僕が地蔵にならないためにも、君のボタン縫わせてよ」
葵は数秒固まった後に、ゆっくりこくんと頷いた。
これが僕と葵の最悪で最愛の出逢い──。
「じゃあ、今度会う時ボタンと裁縫セット持っていくね。名前はなんていうの?」
「……宮家葵。葵でいいよ。お前、子どもなのにボタン縫えるの?」
少し疑うような視線で葵が僕を見つめた。初めて、やっと目を合わせてくれた。葵はなんだか野良猫みたいに、警戒心が強いからその時すごく嬉しかったのを今でも覚えている。
子ども食堂が閉店し、子どもたちが家に帰りはじめる。僕も家の鍵を確認してから家へ向かおうとした。けれど──。
「待って。おいてかないで」
「っ」
ぎゅっ、と葵が僕の腕を掴んできた。その手はぷるぷる震えてて産まれたての小鹿みたいに見えた。僕はひとまず、今にも泣き出しそうな葵と手を繋いで近くの公園に向かうことにした。
ラッコ公園についた。遊具のラッコが置いてある公園だから、お母さんがそう呼んでいた。僕らはそれぞれブランコに座って、互いのことを質問しあった。
「ねえ、なんで葵は泣きそうなの? いっつも泣いてるの?」
「ちがうっ……! 子ども食堂のカレーが美味しすぎたせいだ。俺のお父さんの作るカレーと味が全然違うから」
ぐったりしているへなへなのスニーカーのつま先で砂を弄りながら、小さな声で呟く。その言葉に僕はピンときたのだ。やっぱり、葵と僕は何か似ていると。
「そうなんだ。僕は泣きはしないけど、うちのお母さんのカレーとは味が違うから好きだよ。野菜もごろごろ入ってるし。ヤングコーンなんて、うちのお母さんが買ってるとこ見たことないもん」
「……ぶっ」
すると、僕の話を聞いてツボにハマってしまったのか葵がお腹を抱えて笑いだしてしまった。
僕は今の話にそんなに笑うところ無かったと思うんだけど。
と、少し頬を膨らませた。
「ごめんごめん。貧乏自慢っていうの? それなら俺も負けないから、面白くてさ」
泣き顔から一転、少し気持ちの晴れたような笑顔を見せる葵は申し訳なさそうに肩をすくめた。
「貧乏自慢じゃないけど、まあうちお母さんしかいないし」
葵になら、話してもいいかな。
そんなふうに思ったのは、葵が初めてだった。
初対面の人に、うち、お母さんしかいない『シングルマザー』ってことを言うのは嫌だったのに。葵になら何でも話せる気がした。それが不思議と心地よかった。
僕の話を聞いてから葵は笑うのをやめて、ふぅん、と軽く呟いた。数分、お互い黙ったまま。ゆっくり、葵が口を開いた。
「俺んちは、お父さんしかいないから。シングルファーザーってやつらしい。料理下手くそだから、給食のほうが断然美味いし」
後半は目を伏せてもごもごと小さな声で呟いていたので、なんとか聞き取れるくらいのボリュームだった。
僕もわかるよ。その気持ち。
気づけば、ブランコから立ち上がって葵に身体を向けていた。
「僕もっ……! お母さん、パートが忙しくて手料理なんてほとんど出ないし。冷凍食品とか、お湯入れるだけのカップ麺とかだし……学校の給食美味しいよね。僕、たくさんおかわりしちゃうんだ……」
僕も、後半のほうは尻すぼみで葵が聞き取れたかはわからなかった。けど、葵はそんな僕の話を真剣な顔をして頷いてくれた。
「わかるよ。お前の気持ち。……似てるな、俺たち」
「……うん。片親同士だから」
「違う。そこじゃない」
「え?」
てっきり、僕は葵も片親だから似ていると思ったのに。葵はブランコから立ち上がると僕の肩にそっと両手を乗せた。
「俺たちのハングリー精神が、似てるんだよ。俺たちはご飯食べるの、好きだろ?」
くしゃっと、初めて葵が見せる素直な笑顔だった。片親ということがネガティブなだけじゃない、むしろポジティブな言葉に言い換えられる葵の心が強いと思った。
そして、翌日小学校の下駄箱でばったり葵と出会った。僕らの通う学校はクラスが4つあったから、お互いの存在を知らなかったようだ。それに、これは後から本人に聞いた話なのだが葵は当時あまり学校に登校していなかったらしい。
それもあって、僕と葵が初めて会ったのは子ども食堂になったというわけだ。
「ボタン、直すから明日Tシャツ持ってきて」
葵は少し目を見張ってから、くすっと笑う。
「わかった。明日、約束な」
その時交わした指切りを僕は忘れた日はない。
そんなこんなで小学生の頃から共に成長してきた葵と僕。
同じ地区の中学校へ入学し、部活も一緒。そして、家が近所というのもありずっと一緒にいたのを鮮明に覚えている。
そんな中、僕は葵に告白された。
「俺、吹雪が好きだ」
ベタな展開の放課後の校舎裏。呼び出しを受けた僕は何も予想してないまま、葵の告白を受けて思わずその場で俯いてしまった。
え、好き? 葵が僕を?
「……返事聞かせろよ」
「あっ」
僕が微動だにしないのを見て痺れを切らしたのか、葵が僕の顎に指先を添えて上に持ち上げた。
「……なんつう顔してんの。ゆでダコじゃん」
なぜだか僕の顔を見た葵も照れて、目線を逸らされた。僕は不意に急接近した距離に心臓がばくばくと鳴り止まない。
「その顔はいーってこと? 俺の恋人になってよ」
葵の顔をおずおずと見つめれば、その目は真剣そのものでそこにからかいの色は見えなかった。
ずっと言いたかったことを先に言われてしまったな。
僕は嬉しくてぽろぽろ涙がこぼれてきた。泣き出した僕を葵がいつもの彼らしく不器用にあやしてくれる。とんとん、と葵に肩をさすられると安心するのだ。
「僕もっ、好きだよ……ずっとずっと、初めて葵と出会ったあの日から大好きだったよ」
思い切り想いをぶつけたら、葵は首の下から額まで真っ赤にさせて僕を抱き寄せて肩に顎を埋めてきた。
葵なりの照れ隠しだった。
「……ばーか。俺のほうが先に好きだった」
その時の葵、本当にかわいかった。
ふと、そんな葵と付き合うに至る経緯を思い返していると、前の席の葵がくるりと振り返って僕の机の下に足を入れてきた。
彼はにやにやと意地悪に笑うと机の下で、僕の閉じた足の膝をすりすりと彼の膝で押し付けてくる。まるで、「足を開け」と命令されているみたいに、目にはドSの炎がめらめらと燃えているのが見えた。
「っ」
僕は絶対に死守しなきゃと思い、がっちり膝と膝を合わせているのだが彼の膝の力が強すぎて、ちょっとだけ隙間が生まれてしまった。そこに目ざとく反応して、僕の膝の間に彼の膝が押し入ってきた。ぐぐぐ、と彼の膝と膝に僕の右太ももが挟まれる。
こういう密着を彼は恥ずかしげもなく皆が見ているところでやるから、いつ他のクラスメイトにバレるかとヒヤヒヤする。そんな僕の焦った顔を面白がるのが彼のマイブームらしい。
「ねえ、吹雪。そんなに拗ねんなよ。こっち見ろって」
僕が静かになったのを見て、彼は拗ねたと思ったらしい。急に猫撫で声になって僕を油断させようとしてくる。
だけど、その手には乗らないから。いつも彼の好き勝手にされていたら、心臓がいくつあってももたない。それくらい毎日ドキドキさせてくるし、不意打ちもたくさんあるし、彼といると気が抜けないのだ。
「別に、拗ねてない。ほら、あと休憩5分しかないって。次の授業の準備しないと」
「はあ。次、生物かー。めんどくせえな」
僕が急かすと彼は渋々自分の机の上に置いていたバイク雑誌を自分の机の中にしまった。
あーもう。物理の時、またサボってたんだ。
僕はお母さんみたいな気持ちで彼を見つめてしまう。
だって、彼と僕は小学生の頃からの幼馴染。家もお隣さん。一軒家同士、庭を挟んで共に成長してきた。
彼は昔からリーダーシップに恵まれていて、自然と人が集まってくるタイプ。まさにENFJって感じ。
僕とは正反対だ。INFJの僕は引っ込み思案で些細なことで悩みがち。友達は少なく、気を遣いがちで疲れやすい。
そんな僕が彼と仲良くなったのは少し不思議だ。お互い、自分に持ってないものを持っているから惹かれ合うのかな?
休憩時間残り2分。生物の先生が教室に入ってきた。のそのそ、熊さんみたいに大柄な男の先生。白髪と白ひげの似合う紳士なおじさま先生。
僕は生物の教科書とノートを机に置いて準備万端。また、大きく伸びをして気持ちを切替える。この授業が終わったらお昼休みだ。
今日の学食どれにしようかな。鯖の味噌煮定食、トンテキ定食もいいな。あ、でも野菜も食べなきゃだからコールスローサラダも付けてもらおうか。デザートは生みたてたまごのプリンにしよう。
お昼ご飯のメニューばかり考えていたら、ぐーっとお腹が鳴ってしまった。慌ててお腹を手で隠す。すると、前の席にいた彼が笑いを堪えきれなかったみたいで「ぶっ」と吹き出すのが聞こえて恥ずかしくなる。
彼が僕を振り返る。不意に、生物の教科書を横向きにして僕と自身の顔を隠した。僕らは一番窓際の席だから左には窓、右にはその他のクラスメイトがいる。
彼は他のクラスメイトに見えないように僕の顔を教科書で隠してから
「さっきのお返し。これでも食って昼休みまで我慢しとけ」
そう言って、唇を押し付けてきた。
「っん」
そのまま数秒くっついたあと、急に上唇を彼の舌でめくられて舌が入ってくる。それと同時に感じるメロンソーダの味。舌の上でぱちぱちと弾ける。
「先生にバレないように食えよ」
生物の教科書を机に戻してから、彼はそう不敵に笑った。
あーもう。なんなの、これ。もしかして、お腹空かせた僕のこと心配して、餌付けしてくれてる?
口移しでもらったメロンソーダ味の飴玉。たぶん、さっき僕が渡したチョコレートのお返しだと思うんだけど。渡し方がずるいよ。
こんなのもう、皆に見られたら付き合ってるって一瞬でバレちゃうじゃんか。
僕は口元を隠すように手を当ててひとり悶えていた。
そう。僕の初彼氏は彼で、付き合って1年経つ。理系のクラスに進んだのは彼と同じクラスになりたかったから。晴れて同じクラスになれたのが嬉しすぎて、家に帰ったら部屋でガッツポーズとっちゃったくらい。
それくらい、好きなんだよ。
こうやって内緒の恋人として学校で過ごすのも悪くないかも。
そう思った夏のはじまり。
苦手な物理の授業は、一生懸命黒板と先生の話にかじりつくけど言葉がすべて呪文みたいに聞こえてしまって、右耳から左耳へと通り抜けてしまう。
なんで理系に進んじゃったんだろ。
後悔先に立たず、とはよく言うもので。
本当は自分の数少ない長所を見るなら、文系のほうがいいかもなあ、なんて思ってたのにとある理由で理系を志願してしまった。
実際のところ、国立大学を目指しているから無駄な道ではないし、遠回りでもないんだけどね。
水筒からひんやりとした麦茶をこくんと口に含み、飲み干す。7月の夏休み直前。
教室にはクーラーがあるけど、僕のいる席にはあまり冷たい風があたらないから少し不満はある。
だけど、この席になってからは僕にとっては良いこと尽くめでしかなくて──。
「吹雪ー。チョコちょーだい」
あっ。今日は少し機嫌がいいみたい。
僕は名前を呼んだ前の席の子に一口チョコレートの包みを手渡す。彼は後ろを振り向くかわりに、ぐてっと椅子の背もたれに背中を押し付け、首を僕のほうへ倒してきた。
だらしのない姿勢なのに、なんか様になるのがずるい。
彼は僕を下から見上げるかたちで舌をべっ、と突き出した。紅く、肉厚な舌が真っ白い歯に映えて綺麗だ。思わず見とれてしまう。それと、シルバーの舌ピがきらっと教室の照明に反射して光った。
たぶん、舌ピってうちの学校だと校則違反だと思うんだけど……。
「あーん、は?」
「っ……わかった。あーん」
彼がむすっとしてイラつきだしたので慌ててチョコレートの包みを広げて、チョコレートを彼の舌の上に乗せた。すると彼は器用にチョコレートを口に含むと、もぐもぐと頬っぺを動かし始める。
「どろどろに溶けててなんか変な味する」
あーもう。変なこと言わないでよ。ここ、教室だよ。周りに聞こえたら恥ずかしいよ。
「仕方ないでしょ。夏だもん。そりゃチョコレートも溶けるよ」
「ふうん」
彼はつまらなそうに姿勢を正すと、僕の机に頬杖をついて向かいあわせで座り直す。その距離、約30センチ。不意の至近距離に思わず、ごくんと唾を飲み込んだ。
前の席の彼──宮家葵は、僕──笹川吹雪の恋人だ。
決して誰にもバレてはいけない、内緒の恋人。
僕と葵が出会ったのは、小学生1年生の頃。町内で開催されている月に2回の子ども食堂に行った時だった。
初めて葵を見た時に、目が釘付けになった。大きな二重に、凛とした大人っぽい表情を浮かべてカレーを淡々と食べていた。僕はたまたま隣の席が空いていたので座ることにした。
葵はもぐもぐとカレーを口に運んでおかわりをもらいにいっていた。僕はその日、お母さんが遅くまでパートで忙しかったので子ども食堂で夕食を食べるように言われていた。
綺麗な子だな。
それが葵の第一印象だった。ただ、葵の着ているTシャツは首元のボタンがひとつ無くなっていたり、履いているハーフパンツはしわくちゃなしわができているのが、子どもながらに少し気になった。
葵から自分と似た匂いがすると勘づいたからだ。だから、勇気を出して声をかけてみることにした。その時、僕は葵がカレーを食べ終えたところで「ねえ」と声をかけてみた。手には汗がじんわりと浮かび、喉の奥がからからだ。声を出すのもやっとで、掠れた声しか出なかった。けど、葵は「何?」と僕の声を聞きとってくれた。
「あの、はじめましてだよね? 僕、吹雪。それ、Tシャツのボタン無くしちゃったの?」
簡単な自己紹介と共にそう聞いてみると、葵は先程までの大人っぽい表情から一点、赤ちゃんみたく顔を真っ赤にさせて泣きそうな顔を浮かべた。僕は何か嫌なことを言ってしまったんだと思い、慌てて謝る。
「ごめん。あの、よかったら僕、Tシャツのボタン付けようか?」
「は? 何? 俺に同情でもしてんの? 他の大人たちみたいに」
泣きそうな顔のまま、葵が早口でまくし立てるのを僕は目を瞬かせて見張った。
なんでだろう。嫌な態度なのに、なんか寂しそうな子だな……。
それが僕が葵に初めて話しかけた時の印象。負けず嫌いなのか、勝気なのか。自分の弱いところを隠すように毛を逆立てている野良猫みたいな子。
僕はそんな葵の固く結ばれた心を開いてみたいと思った。本当はこの子はどんな性格で、どんな食べ物が好きで、どんなことが苦手なんだろう。
「僕、同情してないよ。ただ、友達になれたらなって、思ったんだけど……」
言えた。すごく、緊張したけど。僕はなるべく笑顔を作ろうとして頬を引き攣った。不意に、葵がそんな僕の頬をぷにっと右手の指でつまむ。
「笑えないのに無理して笑うなよ」
「……え?」
「お前、表情固すぎ。いつか地蔵になっても知らねえからな」
じ、地蔵?
僕は頭の中で自分が地蔵になっているのを想像してみて、ふっと笑い声が洩れてしまった。
なんだろう。この子、すごく面白い人な気がする。
「じゃあ僕が地蔵にならないためにも、君のボタン縫わせてよ」
葵は数秒固まった後に、ゆっくりこくんと頷いた。
これが僕と葵の最悪で最愛の出逢い──。
「じゃあ、今度会う時ボタンと裁縫セット持っていくね。名前はなんていうの?」
「……宮家葵。葵でいいよ。お前、子どもなのにボタン縫えるの?」
少し疑うような視線で葵が僕を見つめた。初めて、やっと目を合わせてくれた。葵はなんだか野良猫みたいに、警戒心が強いからその時すごく嬉しかったのを今でも覚えている。
子ども食堂が閉店し、子どもたちが家に帰りはじめる。僕も家の鍵を確認してから家へ向かおうとした。けれど──。
「待って。おいてかないで」
「っ」
ぎゅっ、と葵が僕の腕を掴んできた。その手はぷるぷる震えてて産まれたての小鹿みたいに見えた。僕はひとまず、今にも泣き出しそうな葵と手を繋いで近くの公園に向かうことにした。
ラッコ公園についた。遊具のラッコが置いてある公園だから、お母さんがそう呼んでいた。僕らはそれぞれブランコに座って、互いのことを質問しあった。
「ねえ、なんで葵は泣きそうなの? いっつも泣いてるの?」
「ちがうっ……! 子ども食堂のカレーが美味しすぎたせいだ。俺のお父さんの作るカレーと味が全然違うから」
ぐったりしているへなへなのスニーカーのつま先で砂を弄りながら、小さな声で呟く。その言葉に僕はピンときたのだ。やっぱり、葵と僕は何か似ていると。
「そうなんだ。僕は泣きはしないけど、うちのお母さんのカレーとは味が違うから好きだよ。野菜もごろごろ入ってるし。ヤングコーンなんて、うちのお母さんが買ってるとこ見たことないもん」
「……ぶっ」
すると、僕の話を聞いてツボにハマってしまったのか葵がお腹を抱えて笑いだしてしまった。
僕は今の話にそんなに笑うところ無かったと思うんだけど。
と、少し頬を膨らませた。
「ごめんごめん。貧乏自慢っていうの? それなら俺も負けないから、面白くてさ」
泣き顔から一転、少し気持ちの晴れたような笑顔を見せる葵は申し訳なさそうに肩をすくめた。
「貧乏自慢じゃないけど、まあうちお母さんしかいないし」
葵になら、話してもいいかな。
そんなふうに思ったのは、葵が初めてだった。
初対面の人に、うち、お母さんしかいない『シングルマザー』ってことを言うのは嫌だったのに。葵になら何でも話せる気がした。それが不思議と心地よかった。
僕の話を聞いてから葵は笑うのをやめて、ふぅん、と軽く呟いた。数分、お互い黙ったまま。ゆっくり、葵が口を開いた。
「俺んちは、お父さんしかいないから。シングルファーザーってやつらしい。料理下手くそだから、給食のほうが断然美味いし」
後半は目を伏せてもごもごと小さな声で呟いていたので、なんとか聞き取れるくらいのボリュームだった。
僕もわかるよ。その気持ち。
気づけば、ブランコから立ち上がって葵に身体を向けていた。
「僕もっ……! お母さん、パートが忙しくて手料理なんてほとんど出ないし。冷凍食品とか、お湯入れるだけのカップ麺とかだし……学校の給食美味しいよね。僕、たくさんおかわりしちゃうんだ……」
僕も、後半のほうは尻すぼみで葵が聞き取れたかはわからなかった。けど、葵はそんな僕の話を真剣な顔をして頷いてくれた。
「わかるよ。お前の気持ち。……似てるな、俺たち」
「……うん。片親同士だから」
「違う。そこじゃない」
「え?」
てっきり、僕は葵も片親だから似ていると思ったのに。葵はブランコから立ち上がると僕の肩にそっと両手を乗せた。
「俺たちのハングリー精神が、似てるんだよ。俺たちはご飯食べるの、好きだろ?」
くしゃっと、初めて葵が見せる素直な笑顔だった。片親ということがネガティブなだけじゃない、むしろポジティブな言葉に言い換えられる葵の心が強いと思った。
そして、翌日小学校の下駄箱でばったり葵と出会った。僕らの通う学校はクラスが4つあったから、お互いの存在を知らなかったようだ。それに、これは後から本人に聞いた話なのだが葵は当時あまり学校に登校していなかったらしい。
それもあって、僕と葵が初めて会ったのは子ども食堂になったというわけだ。
「ボタン、直すから明日Tシャツ持ってきて」
葵は少し目を見張ってから、くすっと笑う。
「わかった。明日、約束な」
その時交わした指切りを僕は忘れた日はない。
そんなこんなで小学生の頃から共に成長してきた葵と僕。
同じ地区の中学校へ入学し、部活も一緒。そして、家が近所というのもありずっと一緒にいたのを鮮明に覚えている。
そんな中、僕は葵に告白された。
「俺、吹雪が好きだ」
ベタな展開の放課後の校舎裏。呼び出しを受けた僕は何も予想してないまま、葵の告白を受けて思わずその場で俯いてしまった。
え、好き? 葵が僕を?
「……返事聞かせろよ」
「あっ」
僕が微動だにしないのを見て痺れを切らしたのか、葵が僕の顎に指先を添えて上に持ち上げた。
「……なんつう顔してんの。ゆでダコじゃん」
なぜだか僕の顔を見た葵も照れて、目線を逸らされた。僕は不意に急接近した距離に心臓がばくばくと鳴り止まない。
「その顔はいーってこと? 俺の恋人になってよ」
葵の顔をおずおずと見つめれば、その目は真剣そのものでそこにからかいの色は見えなかった。
ずっと言いたかったことを先に言われてしまったな。
僕は嬉しくてぽろぽろ涙がこぼれてきた。泣き出した僕を葵がいつもの彼らしく不器用にあやしてくれる。とんとん、と葵に肩をさすられると安心するのだ。
「僕もっ、好きだよ……ずっとずっと、初めて葵と出会ったあの日から大好きだったよ」
思い切り想いをぶつけたら、葵は首の下から額まで真っ赤にさせて僕を抱き寄せて肩に顎を埋めてきた。
葵なりの照れ隠しだった。
「……ばーか。俺のほうが先に好きだった」
その時の葵、本当にかわいかった。
ふと、そんな葵と付き合うに至る経緯を思い返していると、前の席の葵がくるりと振り返って僕の机の下に足を入れてきた。
彼はにやにやと意地悪に笑うと机の下で、僕の閉じた足の膝をすりすりと彼の膝で押し付けてくる。まるで、「足を開け」と命令されているみたいに、目にはドSの炎がめらめらと燃えているのが見えた。
「っ」
僕は絶対に死守しなきゃと思い、がっちり膝と膝を合わせているのだが彼の膝の力が強すぎて、ちょっとだけ隙間が生まれてしまった。そこに目ざとく反応して、僕の膝の間に彼の膝が押し入ってきた。ぐぐぐ、と彼の膝と膝に僕の右太ももが挟まれる。
こういう密着を彼は恥ずかしげもなく皆が見ているところでやるから、いつ他のクラスメイトにバレるかとヒヤヒヤする。そんな僕の焦った顔を面白がるのが彼のマイブームらしい。
「ねえ、吹雪。そんなに拗ねんなよ。こっち見ろって」
僕が静かになったのを見て、彼は拗ねたと思ったらしい。急に猫撫で声になって僕を油断させようとしてくる。
だけど、その手には乗らないから。いつも彼の好き勝手にされていたら、心臓がいくつあってももたない。それくらい毎日ドキドキさせてくるし、不意打ちもたくさんあるし、彼といると気が抜けないのだ。
「別に、拗ねてない。ほら、あと休憩5分しかないって。次の授業の準備しないと」
「はあ。次、生物かー。めんどくせえな」
僕が急かすと彼は渋々自分の机の上に置いていたバイク雑誌を自分の机の中にしまった。
あーもう。物理の時、またサボってたんだ。
僕はお母さんみたいな気持ちで彼を見つめてしまう。
だって、彼と僕は小学生の頃からの幼馴染。家もお隣さん。一軒家同士、庭を挟んで共に成長してきた。
彼は昔からリーダーシップに恵まれていて、自然と人が集まってくるタイプ。まさにENFJって感じ。
僕とは正反対だ。INFJの僕は引っ込み思案で些細なことで悩みがち。友達は少なく、気を遣いがちで疲れやすい。
そんな僕が彼と仲良くなったのは少し不思議だ。お互い、自分に持ってないものを持っているから惹かれ合うのかな?
休憩時間残り2分。生物の先生が教室に入ってきた。のそのそ、熊さんみたいに大柄な男の先生。白髪と白ひげの似合う紳士なおじさま先生。
僕は生物の教科書とノートを机に置いて準備万端。また、大きく伸びをして気持ちを切替える。この授業が終わったらお昼休みだ。
今日の学食どれにしようかな。鯖の味噌煮定食、トンテキ定食もいいな。あ、でも野菜も食べなきゃだからコールスローサラダも付けてもらおうか。デザートは生みたてたまごのプリンにしよう。
お昼ご飯のメニューばかり考えていたら、ぐーっとお腹が鳴ってしまった。慌ててお腹を手で隠す。すると、前の席にいた彼が笑いを堪えきれなかったみたいで「ぶっ」と吹き出すのが聞こえて恥ずかしくなる。
彼が僕を振り返る。不意に、生物の教科書を横向きにして僕と自身の顔を隠した。僕らは一番窓際の席だから左には窓、右にはその他のクラスメイトがいる。
彼は他のクラスメイトに見えないように僕の顔を教科書で隠してから
「さっきのお返し。これでも食って昼休みまで我慢しとけ」
そう言って、唇を押し付けてきた。
「っん」
そのまま数秒くっついたあと、急に上唇を彼の舌でめくられて舌が入ってくる。それと同時に感じるメロンソーダの味。舌の上でぱちぱちと弾ける。
「先生にバレないように食えよ」
生物の教科書を机に戻してから、彼はそう不敵に笑った。
あーもう。なんなの、これ。もしかして、お腹空かせた僕のこと心配して、餌付けしてくれてる?
口移しでもらったメロンソーダ味の飴玉。たぶん、さっき僕が渡したチョコレートのお返しだと思うんだけど。渡し方がずるいよ。
こんなのもう、皆に見られたら付き合ってるって一瞬でバレちゃうじゃんか。
僕は口元を隠すように手を当ててひとり悶えていた。
そう。僕の初彼氏は彼で、付き合って1年経つ。理系のクラスに進んだのは彼と同じクラスになりたかったから。晴れて同じクラスになれたのが嬉しすぎて、家に帰ったら部屋でガッツポーズとっちゃったくらい。
それくらい、好きなんだよ。
こうやって内緒の恋人として学校で過ごすのも悪くないかも。
そう思った夏のはじまり。