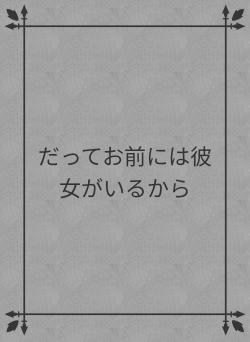恋をした。ぴしゃり、と雷が落ちたような衝撃だった。可愛くて、人に丁寧に接しているあの子と付き合いたいと思った。それなのに。
「理玖! 聞いてくれ! 振られた!!」
「へえ」
おい。興味ない顔で本に戻るな。親友が泣いているんだから、慰めろ。そう思いながら、肩に寄りかかったり、本を見つめる目の前で手を振ってみたりしたが、返答はない。
仕方がないので、前の席に座って泣いたふりをしてみる。本当に泣きたいのだから、嘘泣きではない。
しかし、理玖はしばらく本を読んでいて、こちらなんて見る素振りも見せない。ひどい。
「酷い……」
「だって、陽癸。今年に入ってから、何度目だよ」
「うっ……」
思わず言葉に詰まった。痛いところを突かれた俺は、目を逸らしなが言う。
「ええっと……。6人目、です」
「違う。8人はいってた」
「ええ……」
俺はちゃんと覚えていなかったのに、理玖はしっかりと訂正までしてくる。何で覚えているんだよ。
やっと本を閉じた理玖が、呆れたような顔をしながら、淡々と言う。
「1人目は、恋の応援をしてって言われて? 2人目はお兄ちゃんみたいって言われて? 3人目は普通に断られて、4人目は恋人いますって言われて……」
「もう、やめてくれ……」
俺にクリティカルヒットだ。記憶の底に埋めておいたというのに、掘り起こさないでほしい。俺が呻いていると、理玖がふっと笑った。
「まあ、別にそこはいい。それで? カラオケでも行くか?」
「……行く。ありがと」
俺が失恋をするたびに、理玖はカラオケに誘ってくれる。本当に、良い奴なのだ。
◆
「あいーしてましたー」
やばい。歌いながら、涙が出てきた。
カラオケで歌うのは失恋ソングのことが多い。だって、俺の気持ちを鏡で映しているかのように共感できるから。女々しいとか言われても、知らない。理玖からは特に何も言われたことがない。理玖も歌いたい曲を勝手に歌っているだけだ。
そのお陰で気が楽だ。心置きなく大声で歌を歌い、失恋の苦しさや自分に何が足りなかったのかという後悔を追い払ってくれる気がするから。
しばらくして、少し気分が落ち着いた。俺は理玖へと向き直る。
「いつも、カラオケに付き合ってくれて、ありがとな」
失恋しても、理玖がカラオケに付き合ってくれることでどれほど気持ちが軽くなっているか。本当に有り難い。
俺が理玖に礼を言うと、ジュースを飲んでいた理玖が、コップから口を離した。理玖は軽く首を傾げてから、ゆっくりと口を開いた。
「お前が人に好きって言ったり、振られたって落ち込んだりするたびに、すごいなって思うよ」
「……はあ? 馬鹿にしているのか?」
「違う、違う」
褒められているのか良く分からないことを理玖から言われ、俺が眉をひそめていると、理玖は慌てたように首を振った。
じゃあ、どういう意味なのか。俺が理玖を見ていると、俺から目を逸らした理玖が空中を見ながら言う。
「顔だとしても、性格だとしても、お前は人の良い所を見つけられる。本気で好きになれる。そんなお前には、きっとお前の良さを分かってくれる人間がいるはずだ」
「……」
「しかも、人の良さを見つけるだけじゃなくて、告白するという行動まで移せるだろう。それはきっと、一種の才能だ」
こんなことを言われたのは初めてかもしれない。
「恋に恋している」とか「彼女欲しいだけだろ」とか言われることは多かった。それなのに、理玖はそれを俺の「才能だ」と言ってくれる。
やばい。嬉しいかも。俺の友達は、思っていた以上に俺のことを知っていたらしい。急に恥ずかしいような気持ちになってきて、俺は理玖に照れ隠しで言う。
「お前、俺と付き合えよー」
「はあ? 今からお前の失恋記録を伸ばしてほしいのか?」
「冗談だって」
もちろん冗談だ。これ以上、失恋記録を伸ばしたくない。
失恋はした。それでも、俺のことを理解してくれている友人はいる。それで、今は十分かもしれない。
「よし、まだまだ歌うぞ!」
「おー」
声が枯れそうになるまで歌い続けたあと、俺はやっと満足をした。振られた直後とは比べものにならないほど、気持ちが軽い。
「また失恋したら、カラオケ付き合ってくれよ」
「そろそろ成功しろよ」
「俺だってしたいよ」
俺はきっと、また人を好きになって、告白をするだろう。また失恋をするかもしれないし、今度は上手くいくかもしれない。それは分からないけれど、俺は人を好きになることを恐れないし、気持ちを伝えることに怯えないのだろう。
失恋は悲しいが、また、恋をできたら良い。そんなことを考えながら、俺は理玖と並んで帰路へとついた。
「理玖! 聞いてくれ! 振られた!!」
「へえ」
おい。興味ない顔で本に戻るな。親友が泣いているんだから、慰めろ。そう思いながら、肩に寄りかかったり、本を見つめる目の前で手を振ってみたりしたが、返答はない。
仕方がないので、前の席に座って泣いたふりをしてみる。本当に泣きたいのだから、嘘泣きではない。
しかし、理玖はしばらく本を読んでいて、こちらなんて見る素振りも見せない。ひどい。
「酷い……」
「だって、陽癸。今年に入ってから、何度目だよ」
「うっ……」
思わず言葉に詰まった。痛いところを突かれた俺は、目を逸らしなが言う。
「ええっと……。6人目、です」
「違う。8人はいってた」
「ええ……」
俺はちゃんと覚えていなかったのに、理玖はしっかりと訂正までしてくる。何で覚えているんだよ。
やっと本を閉じた理玖が、呆れたような顔をしながら、淡々と言う。
「1人目は、恋の応援をしてって言われて? 2人目はお兄ちゃんみたいって言われて? 3人目は普通に断られて、4人目は恋人いますって言われて……」
「もう、やめてくれ……」
俺にクリティカルヒットだ。記憶の底に埋めておいたというのに、掘り起こさないでほしい。俺が呻いていると、理玖がふっと笑った。
「まあ、別にそこはいい。それで? カラオケでも行くか?」
「……行く。ありがと」
俺が失恋をするたびに、理玖はカラオケに誘ってくれる。本当に、良い奴なのだ。
◆
「あいーしてましたー」
やばい。歌いながら、涙が出てきた。
カラオケで歌うのは失恋ソングのことが多い。だって、俺の気持ちを鏡で映しているかのように共感できるから。女々しいとか言われても、知らない。理玖からは特に何も言われたことがない。理玖も歌いたい曲を勝手に歌っているだけだ。
そのお陰で気が楽だ。心置きなく大声で歌を歌い、失恋の苦しさや自分に何が足りなかったのかという後悔を追い払ってくれる気がするから。
しばらくして、少し気分が落ち着いた。俺は理玖へと向き直る。
「いつも、カラオケに付き合ってくれて、ありがとな」
失恋しても、理玖がカラオケに付き合ってくれることでどれほど気持ちが軽くなっているか。本当に有り難い。
俺が理玖に礼を言うと、ジュースを飲んでいた理玖が、コップから口を離した。理玖は軽く首を傾げてから、ゆっくりと口を開いた。
「お前が人に好きって言ったり、振られたって落ち込んだりするたびに、すごいなって思うよ」
「……はあ? 馬鹿にしているのか?」
「違う、違う」
褒められているのか良く分からないことを理玖から言われ、俺が眉をひそめていると、理玖は慌てたように首を振った。
じゃあ、どういう意味なのか。俺が理玖を見ていると、俺から目を逸らした理玖が空中を見ながら言う。
「顔だとしても、性格だとしても、お前は人の良い所を見つけられる。本気で好きになれる。そんなお前には、きっとお前の良さを分かってくれる人間がいるはずだ」
「……」
「しかも、人の良さを見つけるだけじゃなくて、告白するという行動まで移せるだろう。それはきっと、一種の才能だ」
こんなことを言われたのは初めてかもしれない。
「恋に恋している」とか「彼女欲しいだけだろ」とか言われることは多かった。それなのに、理玖はそれを俺の「才能だ」と言ってくれる。
やばい。嬉しいかも。俺の友達は、思っていた以上に俺のことを知っていたらしい。急に恥ずかしいような気持ちになってきて、俺は理玖に照れ隠しで言う。
「お前、俺と付き合えよー」
「はあ? 今からお前の失恋記録を伸ばしてほしいのか?」
「冗談だって」
もちろん冗談だ。これ以上、失恋記録を伸ばしたくない。
失恋はした。それでも、俺のことを理解してくれている友人はいる。それで、今は十分かもしれない。
「よし、まだまだ歌うぞ!」
「おー」
声が枯れそうになるまで歌い続けたあと、俺はやっと満足をした。振られた直後とは比べものにならないほど、気持ちが軽い。
「また失恋したら、カラオケ付き合ってくれよ」
「そろそろ成功しろよ」
「俺だってしたいよ」
俺はきっと、また人を好きになって、告白をするだろう。また失恋をするかもしれないし、今度は上手くいくかもしれない。それは分からないけれど、俺は人を好きになることを恐れないし、気持ちを伝えることに怯えないのだろう。
失恋は悲しいが、また、恋をできたら良い。そんなことを考えながら、俺は理玖と並んで帰路へとついた。