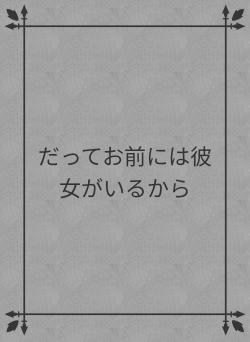学校を出ても、千隼は歩くスピードを落とさなかった。俺がついていけるくらいのスピードだから、少しは気を遣ってくれているのだろうが、そろそろゆっくり歩きたい。
「千隼」
「……」
「千隼。歩くの速えよ」
「……ごめん」
やっと掴んでいた俺の腕を放した千隼が、立ち止まって俯いた。俺はそんな千隼の顔をのぞきこんだが、よく顔が見えない。
「千隼。どうした?」
「ごめん」
「まあ、いいけど」
別に腕が痛いわけでも、疲れたわけでもないから構わないけれど。それでも、この千隼の態度がどうも不思議だ。
完全に立ち止まってしまっている千隼に、また聞いてみた。
「それでどうしたんだよ」
「……」
「言いたくないならいいけど」
そう言うと、急に千隼がまじまじとこちらを見てきた。その焦茶色の瞳を眺めていると、千隼がため息をついた。
「だってー、僕だけだもんなー」
「何が?」
口調は軽いものの、その焦茶の目はゆらゆらと揺れているように見える。冗談めかしながらも、それが千隼の本音だと気づき、真剣に聞くことにした。
「……怜くんに友達たくさんいるのが寂しい」
「ああ。なんだ。そんなことか」
千隼の言ったことに拍子抜けした気分だ。そう言うと、少しむっとしたように千隼が睨み付けてきた。
「そんなことって……」
「別にお前だけじゃない。俺もちょっと寂しいからな」
むしろ、俺の方が寂しさは感じているのではないか。だって、千隼の方が人気者で、人と共にいる時間は長いはず。幼馴染が人気者なのは嬉しいが、それでも少しは寂しくなる。
すると、なぜか急に顔を輝かせた千隼が、俺の顔を覗き込んできた。
「……え? 怜くん、もう1回」
「え? いや、お前が人気者なのは少し寂しいって……」
「えへへ」
さっきまでのどこか不満げな表情とは全然違い、満面の笑み。この一瞬で、何があったのか。俺は千隼の肩を小突いた。
「お前、なんで少し嬉しそうなんだよ」
「だってー、怜くんも僕と同じなのが嬉しくて」
千隼の言うことがよく分からなくて、首を傾げる。
「なんだよ。それ」
「だって、怜くんにそう思ってほしかったから」
「……は?」
本当に千隼の言っていることが分からない。返事ができずにいると、こてんとかわいらしく首を傾げた千隼が言う。
「昔、言ってたよ?『いろんな人と仲良くしてほしいけれど、それはそれで寂しいかもなあ』って」
「そんなこと言ったか?」
「うん」
本当に言った記憶がない。俺にしてみれば何気なく言ったことなんだろうが……。なんでそれを千隼は覚えているのか。
千隼が俺の頬に手を伸ばしてきた。少し冷たい手が触れる。驚いて千隼を見ると、彼は焦茶の目をゆっくりと細めた。
「だから、僕、待ってたんだよ。怜くんが人気者になったねって言ってくれる瞬間を」
「……」
「怜くんが僕以外の人に話しかけられるのが嫌なのと同じように、僕が人気者だから寂しいって思ってくれる日をずーっと待ってたんだ」
「それは、なんで……」
別に寂しいなんて思わせる必要はないだろう? そう言おうとしたとき、それを遮るように、千隼が口を開いた。
「ねえ、怜くん」
その真剣でありながらも、どこか縋っているようにも聞こえる。こんな余裕のなさそうな千隼の表情は見たことがあっただろうか。
千隼がふわりと微笑んだ。幼馴染の千隼のそんな笑い方は見たことがなく、目線を外せなくなった。
「大好きだよ。ずっと、ずっと」
「……ああ」
どくどく、と自分の心臓の音がうるさい。きっと、それは千隼が珍しい表情をしているせいだ。そうに違いない。自分にそう言い聞かせていると、千隼の顔が不満げに見えた。
「……意味、分かってる?」
「大好きなんだろう?」
「そうじゃなくてー」
千隼が思案するように視線を落としたあと、こちらを真っ直ぐに見つめてきた。千隼の言葉を待っていると、千隼は手をぎゅっと握ってきた。
「付き合うなら、竹村さんじゃなくて、僕と付き合おうってこと」
「は……」
いきなり何を言い出したのか。言葉が音として認識できても、その意味が理解できない。
「付き合う……? なんでそんな話に? 竹村さんは友達になろうって話だろう?」
竹村紬は話をしたい、と言っていただけで、別に付き合いたいとは言われていない。それなのに、なぜそこまで話が飛んでいるのか。
理解ができていない俺とは違い、千隼はなぜか確信をしているようで、頬を膨らませた。
「ええー、絶対そうでしょう」
「いや、俺は千隼みたいな人気者とは違うんだから」
すると、目を伏せた千隼がぼそりと呟いた。
「違わないけど……まあ、知らない分にはいいか」
「え?」
一瞬、暗い表情を浮かべたように見えたが、瞬きをすると太陽のように眩しい笑顔が目に入ったから、見間違いだったのだろう。
俺の手を握る力を強めてきながら、千隼がさらに言う。
「ねえ、怜くん。愛しているよ。本当に。だから、僕と付き合って」
「……は? いや、え?」
聞き間違えたかと思った。
すきー、という言葉はたまに言われるものの、今みたいな真剣さはなかった。それに付き合って、と言われるのは初めてだ。
付き合う、というのはいわゆる交際ということだろうか。それを自分と?
よく分からないままでいると、千隼が上目遣いでこちらを見ながら言う。
「竹村さんと付き合うのなら、僕と付き合ってよ。絶対、ぜーったいに僕の方が怜くんのこと好きだかし、怜くんは僕のことが好きなんだから」
「その自信は、どこから来るんだ……」
俺自身が、自分の気持ちを分かっていないのに。思わず聞くと、千隼はきょとんとした顔で答えた。
「どこからって……。だって、怜くん、僕がいろんな人と仲良くて寂しかったんでしょう? それって僕のことが好きでしょう?」
「そう、か……?」
たしかに。千隼以外が人気でも何も思わない。友人の律音だって人気だが、それを気にしたことはなかった。
俺が気にしていたのは、千隼だけだ。それが何を表すか。
「そうか、俺は千隼のこと、が……」
思わず言葉を零すと、千隼の焦げ茶色の瞳がじっとこちらを見ていた。それに気がついて動きを止めると、千隼は甘えるような口調でいう。
「つづき。ねえ、続きを言って」
「え……。ちょっと心の準備が」
「いいから、お願い!」
千隼の目に、期待と必死さが滲んでいるのを、ちょっとかわいいなと思った。その感情は、自分の気持ちを認識するのに十分だった。
この、年下の幼馴染が愛おしい。
「好きだよ。千隼。お前が人気者なのが寂しいくらいには」
そう言うと、千隼は焦げ茶色の瞳を大きく見開いた後で、ゆるゆると口元を緩めた。どこか噛みしめるように下を見たあと、花よりもかわいらしい笑みを浮かべて笑う。
「やった。やった!」
がばっと抱きつかれて、慌ててそれを受け止める。ぎゅうぎゅうと抱きついてきたのを受け止めていたが、しばらくして離れた千隼が顔を覗き込んできた。その距離は先ほどまでより圧倒的に近い。
「じゃあ、付き合うってことで良いよね? 良いよね?」
「……ああ」
「やった。えへへ」
歌い出しそうなほど上機嫌な千隼が、俺の手を握る。少し恥ずかしいが、振りほどくこともしたくがないのでそのままにしていると、千隼が空いている手で頬に触れてきた。
「じゃあ、キスしていい?」
「どこでする気だよ。テストが近いんだ。帰るぞ」
「えー」
ばしっと軽く頭を叩き、手を離す。テストが近い、という現実を思い出して、浮かれそうな気持ちを落ち着けた。
千隼は不満げな声をしているが、知らない。赤点をとったら不味いのは千隼の方のくせに。さっさと歩き始めると、早足で千隼が追いついてきた。そのまま、耳元で言う。
「じゃあ、テスト終わったら、キスしてね。人前じゃなかったら、良いんでしょう?」
「……もう帰るぞ」
「怜くん、耳まで真っ赤。かわいいー」
「うるさい」
そう言いながらも、俺の頬が緩んでいるのは自覚していた。これからも、この人気者に振り回されるのだろう。それも、悪くはない気がする。
俺だけのことを振り回すなら、それで良い。
「千隼」
「……」
「千隼。歩くの速えよ」
「……ごめん」
やっと掴んでいた俺の腕を放した千隼が、立ち止まって俯いた。俺はそんな千隼の顔をのぞきこんだが、よく顔が見えない。
「千隼。どうした?」
「ごめん」
「まあ、いいけど」
別に腕が痛いわけでも、疲れたわけでもないから構わないけれど。それでも、この千隼の態度がどうも不思議だ。
完全に立ち止まってしまっている千隼に、また聞いてみた。
「それでどうしたんだよ」
「……」
「言いたくないならいいけど」
そう言うと、急に千隼がまじまじとこちらを見てきた。その焦茶色の瞳を眺めていると、千隼がため息をついた。
「だってー、僕だけだもんなー」
「何が?」
口調は軽いものの、その焦茶の目はゆらゆらと揺れているように見える。冗談めかしながらも、それが千隼の本音だと気づき、真剣に聞くことにした。
「……怜くんに友達たくさんいるのが寂しい」
「ああ。なんだ。そんなことか」
千隼の言ったことに拍子抜けした気分だ。そう言うと、少しむっとしたように千隼が睨み付けてきた。
「そんなことって……」
「別にお前だけじゃない。俺もちょっと寂しいからな」
むしろ、俺の方が寂しさは感じているのではないか。だって、千隼の方が人気者で、人と共にいる時間は長いはず。幼馴染が人気者なのは嬉しいが、それでも少しは寂しくなる。
すると、なぜか急に顔を輝かせた千隼が、俺の顔を覗き込んできた。
「……え? 怜くん、もう1回」
「え? いや、お前が人気者なのは少し寂しいって……」
「えへへ」
さっきまでのどこか不満げな表情とは全然違い、満面の笑み。この一瞬で、何があったのか。俺は千隼の肩を小突いた。
「お前、なんで少し嬉しそうなんだよ」
「だってー、怜くんも僕と同じなのが嬉しくて」
千隼の言うことがよく分からなくて、首を傾げる。
「なんだよ。それ」
「だって、怜くんにそう思ってほしかったから」
「……は?」
本当に千隼の言っていることが分からない。返事ができずにいると、こてんとかわいらしく首を傾げた千隼が言う。
「昔、言ってたよ?『いろんな人と仲良くしてほしいけれど、それはそれで寂しいかもなあ』って」
「そんなこと言ったか?」
「うん」
本当に言った記憶がない。俺にしてみれば何気なく言ったことなんだろうが……。なんでそれを千隼は覚えているのか。
千隼が俺の頬に手を伸ばしてきた。少し冷たい手が触れる。驚いて千隼を見ると、彼は焦茶の目をゆっくりと細めた。
「だから、僕、待ってたんだよ。怜くんが人気者になったねって言ってくれる瞬間を」
「……」
「怜くんが僕以外の人に話しかけられるのが嫌なのと同じように、僕が人気者だから寂しいって思ってくれる日をずーっと待ってたんだ」
「それは、なんで……」
別に寂しいなんて思わせる必要はないだろう? そう言おうとしたとき、それを遮るように、千隼が口を開いた。
「ねえ、怜くん」
その真剣でありながらも、どこか縋っているようにも聞こえる。こんな余裕のなさそうな千隼の表情は見たことがあっただろうか。
千隼がふわりと微笑んだ。幼馴染の千隼のそんな笑い方は見たことがなく、目線を外せなくなった。
「大好きだよ。ずっと、ずっと」
「……ああ」
どくどく、と自分の心臓の音がうるさい。きっと、それは千隼が珍しい表情をしているせいだ。そうに違いない。自分にそう言い聞かせていると、千隼の顔が不満げに見えた。
「……意味、分かってる?」
「大好きなんだろう?」
「そうじゃなくてー」
千隼が思案するように視線を落としたあと、こちらを真っ直ぐに見つめてきた。千隼の言葉を待っていると、千隼は手をぎゅっと握ってきた。
「付き合うなら、竹村さんじゃなくて、僕と付き合おうってこと」
「は……」
いきなり何を言い出したのか。言葉が音として認識できても、その意味が理解できない。
「付き合う……? なんでそんな話に? 竹村さんは友達になろうって話だろう?」
竹村紬は話をしたい、と言っていただけで、別に付き合いたいとは言われていない。それなのに、なぜそこまで話が飛んでいるのか。
理解ができていない俺とは違い、千隼はなぜか確信をしているようで、頬を膨らませた。
「ええー、絶対そうでしょう」
「いや、俺は千隼みたいな人気者とは違うんだから」
すると、目を伏せた千隼がぼそりと呟いた。
「違わないけど……まあ、知らない分にはいいか」
「え?」
一瞬、暗い表情を浮かべたように見えたが、瞬きをすると太陽のように眩しい笑顔が目に入ったから、見間違いだったのだろう。
俺の手を握る力を強めてきながら、千隼がさらに言う。
「ねえ、怜くん。愛しているよ。本当に。だから、僕と付き合って」
「……は? いや、え?」
聞き間違えたかと思った。
すきー、という言葉はたまに言われるものの、今みたいな真剣さはなかった。それに付き合って、と言われるのは初めてだ。
付き合う、というのはいわゆる交際ということだろうか。それを自分と?
よく分からないままでいると、千隼が上目遣いでこちらを見ながら言う。
「竹村さんと付き合うのなら、僕と付き合ってよ。絶対、ぜーったいに僕の方が怜くんのこと好きだかし、怜くんは僕のことが好きなんだから」
「その自信は、どこから来るんだ……」
俺自身が、自分の気持ちを分かっていないのに。思わず聞くと、千隼はきょとんとした顔で答えた。
「どこからって……。だって、怜くん、僕がいろんな人と仲良くて寂しかったんでしょう? それって僕のことが好きでしょう?」
「そう、か……?」
たしかに。千隼以外が人気でも何も思わない。友人の律音だって人気だが、それを気にしたことはなかった。
俺が気にしていたのは、千隼だけだ。それが何を表すか。
「そうか、俺は千隼のこと、が……」
思わず言葉を零すと、千隼の焦げ茶色の瞳がじっとこちらを見ていた。それに気がついて動きを止めると、千隼は甘えるような口調でいう。
「つづき。ねえ、続きを言って」
「え……。ちょっと心の準備が」
「いいから、お願い!」
千隼の目に、期待と必死さが滲んでいるのを、ちょっとかわいいなと思った。その感情は、自分の気持ちを認識するのに十分だった。
この、年下の幼馴染が愛おしい。
「好きだよ。千隼。お前が人気者なのが寂しいくらいには」
そう言うと、千隼は焦げ茶色の瞳を大きく見開いた後で、ゆるゆると口元を緩めた。どこか噛みしめるように下を見たあと、花よりもかわいらしい笑みを浮かべて笑う。
「やった。やった!」
がばっと抱きつかれて、慌ててそれを受け止める。ぎゅうぎゅうと抱きついてきたのを受け止めていたが、しばらくして離れた千隼が顔を覗き込んできた。その距離は先ほどまでより圧倒的に近い。
「じゃあ、付き合うってことで良いよね? 良いよね?」
「……ああ」
「やった。えへへ」
歌い出しそうなほど上機嫌な千隼が、俺の手を握る。少し恥ずかしいが、振りほどくこともしたくがないのでそのままにしていると、千隼が空いている手で頬に触れてきた。
「じゃあ、キスしていい?」
「どこでする気だよ。テストが近いんだ。帰るぞ」
「えー」
ばしっと軽く頭を叩き、手を離す。テストが近い、という現実を思い出して、浮かれそうな気持ちを落ち着けた。
千隼は不満げな声をしているが、知らない。赤点をとったら不味いのは千隼の方のくせに。さっさと歩き始めると、早足で千隼が追いついてきた。そのまま、耳元で言う。
「じゃあ、テスト終わったら、キスしてね。人前じゃなかったら、良いんでしょう?」
「……もう帰るぞ」
「怜くん、耳まで真っ赤。かわいいー」
「うるさい」
そう言いながらも、俺の頬が緩んでいるのは自覚していた。これからも、この人気者に振り回されるのだろう。それも、悪くはない気がする。
俺だけのことを振り回すなら、それで良い。