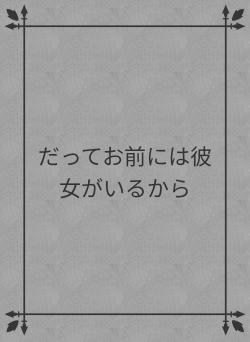「奥村怜先輩、ですよね?」
「……俺に用事ですか?」
ある日の放課後。教室で帰る時間の相談のためにスマホを取り出して千隼に連絡をしていると、急に声をかけられて動きを止めた。自分の名前を呼ばれた気がするも、後輩の知り合いは千隼しかいないはずだ。訝しみながら問い返すと、その少女はにこりと微笑んだ。
「はじめまして。竹内紬です」
「……どうも」
にこり、と微笑む彼女の名前はどこかで聞いたことがあった。確か、千隼と同じ学年の女の子。千隼と同じくらい学校で人気があるようだ。
そんな彼女が、俺に笑顔で声をかけてきている。
「私、お話してみたくって」
「……千隼に用事があるのなら、直接話しかけてください」
千隼に話しかけたくて、俺を通そうとするのはよくあることだ。今まで、何人の人がそうしてきたことか。男女問わず、まるで俺が千隼の窓口かのように声をかけられることが多くあった。俺には慣れたことであるため、淡々と返事をした。
すると、きょとんと首を傾げた彼女がふわりと笑う。
「違いますよ。私は、奥村先輩とお話がしたかったんです」
「俺と?」
千隼への窓口ではなく、俺自身に用事がある人、というのがよく分からなくて、まじまじと竹内紬という少女を見つめた。ほんのりと頬をピンクに染めた彼女がにこりと微笑む。なるほど。確かにかわいらしいかもしれない。
そんなことを考えていると、不意に右肩が重くなった。それはよくあることで、俺がちらりと目を動かすと、真っ黒でふわふわな髪が視界に入る。
「なにしてんの、怜くん」
「ああ。千隼……って重いし、くすぐったい」
「あはは。ごめんごめん」
千隼が肩から離れたようで、右肩から重さが消える。俺の顔を覗き込んできた千隼が、にこやかに尋ねてきた。
「連絡来なかったから来ちゃったけど……。用事?」
ちらりとスマホに目を向けると、確かに千隼からメッセージが来ていた。それを確認してから、俺は説明に困った。
「いや。用事というか……」
いきなり彼女から声をかけられていただけだ。説明に困った俺は竹内紬の方を見る。俺と千隼からの視線に、相変わらず彼女の笑みは消えない。
「中尾くん。私も、奥村先輩とお話したくて」
「……ああ、なるほど。そういう」
千隼が低い声で何かを呟いたようだったが、よく聞こえてこない。千隼の方を見ると、彼は誤魔化すように笑った。そんな千隼の顔はあまり見たことがないため、少し驚いた。
「怜くん。そんなことより、帰ろう」
「え。でも……」
折角、来にくいであろう先輩の教室に来てくれているのだから、少しは会話をしようと思っていたのに。
どうするか悩んでいると、後ろから千隼が腕を掴んできた。いつも優しくて子犬みたいにかわいらしい彼にしては珍しい行動。驚いてそちらを見ると、チョコレートのような焦茶色の瞳が揺れていた。
「一緒に勉強するって約束でしょう? 宿題を教えてくれるんじゃなかったの?」
「……そうだったな」
確かに中間試験が近いから、一緒に勉強をしようという話をした。昼休みは外で遊んでいたのに、勉強する気になったのだなあ、と若干安堵しながら、竹村紬に軽く頭を下げた。
「ごめんなさい。竹村さん。この後、用事があるので」
顔を上げると、竹村紬はやはり笑みを浮かべていた。ずっと微笑んでいるのは凄いと純粋に尊敬していると、彼女が頷きながら言う。
「分かりました。それでは、連絡先だけでも交換してくださいませんか?」
「まあ、はい。それなら」
俺はスマホを取り出して、連絡先を交換した。千隼からの視線がぐさぐさと刺さっていたが、何も言ってこない。
交換し終わった瞬間、千隼が俺の腕を掴んできた。
「帰ろう」
「あ、おい」
俺は慌てて鞄を持ち上げて、千隼の歩くスピードについていった。
「……俺に用事ですか?」
ある日の放課後。教室で帰る時間の相談のためにスマホを取り出して千隼に連絡をしていると、急に声をかけられて動きを止めた。自分の名前を呼ばれた気がするも、後輩の知り合いは千隼しかいないはずだ。訝しみながら問い返すと、その少女はにこりと微笑んだ。
「はじめまして。竹内紬です」
「……どうも」
にこり、と微笑む彼女の名前はどこかで聞いたことがあった。確か、千隼と同じ学年の女の子。千隼と同じくらい学校で人気があるようだ。
そんな彼女が、俺に笑顔で声をかけてきている。
「私、お話してみたくって」
「……千隼に用事があるのなら、直接話しかけてください」
千隼に話しかけたくて、俺を通そうとするのはよくあることだ。今まで、何人の人がそうしてきたことか。男女問わず、まるで俺が千隼の窓口かのように声をかけられることが多くあった。俺には慣れたことであるため、淡々と返事をした。
すると、きょとんと首を傾げた彼女がふわりと笑う。
「違いますよ。私は、奥村先輩とお話がしたかったんです」
「俺と?」
千隼への窓口ではなく、俺自身に用事がある人、というのがよく分からなくて、まじまじと竹内紬という少女を見つめた。ほんのりと頬をピンクに染めた彼女がにこりと微笑む。なるほど。確かにかわいらしいかもしれない。
そんなことを考えていると、不意に右肩が重くなった。それはよくあることで、俺がちらりと目を動かすと、真っ黒でふわふわな髪が視界に入る。
「なにしてんの、怜くん」
「ああ。千隼……って重いし、くすぐったい」
「あはは。ごめんごめん」
千隼が肩から離れたようで、右肩から重さが消える。俺の顔を覗き込んできた千隼が、にこやかに尋ねてきた。
「連絡来なかったから来ちゃったけど……。用事?」
ちらりとスマホに目を向けると、確かに千隼からメッセージが来ていた。それを確認してから、俺は説明に困った。
「いや。用事というか……」
いきなり彼女から声をかけられていただけだ。説明に困った俺は竹内紬の方を見る。俺と千隼からの視線に、相変わらず彼女の笑みは消えない。
「中尾くん。私も、奥村先輩とお話したくて」
「……ああ、なるほど。そういう」
千隼が低い声で何かを呟いたようだったが、よく聞こえてこない。千隼の方を見ると、彼は誤魔化すように笑った。そんな千隼の顔はあまり見たことがないため、少し驚いた。
「怜くん。そんなことより、帰ろう」
「え。でも……」
折角、来にくいであろう先輩の教室に来てくれているのだから、少しは会話をしようと思っていたのに。
どうするか悩んでいると、後ろから千隼が腕を掴んできた。いつも優しくて子犬みたいにかわいらしい彼にしては珍しい行動。驚いてそちらを見ると、チョコレートのような焦茶色の瞳が揺れていた。
「一緒に勉強するって約束でしょう? 宿題を教えてくれるんじゃなかったの?」
「……そうだったな」
確かに中間試験が近いから、一緒に勉強をしようという話をした。昼休みは外で遊んでいたのに、勉強する気になったのだなあ、と若干安堵しながら、竹村紬に軽く頭を下げた。
「ごめんなさい。竹村さん。この後、用事があるので」
顔を上げると、竹村紬はやはり笑みを浮かべていた。ずっと微笑んでいるのは凄いと純粋に尊敬していると、彼女が頷きながら言う。
「分かりました。それでは、連絡先だけでも交換してくださいませんか?」
「まあ、はい。それなら」
俺はスマホを取り出して、連絡先を交換した。千隼からの視線がぐさぐさと刺さっていたが、何も言ってこない。
交換し終わった瞬間、千隼が俺の腕を掴んできた。
「帰ろう」
「あ、おい」
俺は慌てて鞄を持ち上げて、千隼の歩くスピードについていった。