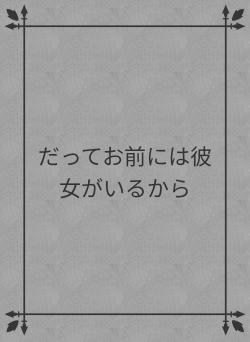「おはよう、千隼」
「おう、おはよう!」
「おはよう、中尾くん」
「先輩、おはようございます!」
ざわざわしている校舎に足を踏み入れると、まるでそこだけが照らされているかのような人気者がいる。残念ながら挨拶をされているのは俺ではない。隣を歩く、1つ年下の幼馴染を見ながら、思わず苦笑した。
「千隼。相変わらず、お前は大人気だな」
「そう?」
こてんと首を傾げる幼馴染、中尾千隼は、自分が人気者であることを自覚していないのだろうか。
少し癖のあるふわふわとした黒髪。くりっとした目に、愛嬌のある笑み。
行き交う人の視線を奪っていることを、千隼は気づいていないようだ。きょとんとした表情を浮かべた彼が尋ねてきた。
「怜くん、僕がいろんな人から声をかけられているの、気になる?」
「何が? お前が人気なのはいいことだろう?」
「そう?」
また、すれ違う人に声をかけられ始め、それに返事をしている千隼をこっそりと見ながら息を吐いた。
嘘をついた。大事な幼馴染が、俺の元から離れていくのは少し寂しい。しかし、そんな身勝手な気持ちはのみ込んだ。伝える必要のない言葉だ。
隣を歩く千隼を見ながら考える。昔は今と全く違ったのにな、と考えてしまうのはきっと弟離れができない兄なのだ。
◆
千隼とは家が近所だった。知り合った年齢さえ覚えていないくらいから遊んでいる。最初、千隼は俺のことを「お兄ちゃん」と呼んでくれていた。
頼ってくる千隼が可愛くてしかたがなかった。千隼といると、ついお兄さんぶりたくなって、ちょっと背伸びをして、難しいことを言ってみたり、外に連れ出したりしていた。俺が間違えていたことも、大袈裟だったこともあれば、迷子になって近所の人に家まで連れて帰ってもらえったこともある。
俺はそんな頼りない「兄」だった。それでも、千隼は呆れるどころか俺のことを頼り、目を輝かせながらついてきてくれていた。
中学に上がったくらいだろうか。千隼はぐんと大人びた。引っ込み思案で、俺の後ろに隠れていたはずだった彼は、気づけば社交的になっていた。友達がたくさんでき、クラスどころか、学校の人気者になった。
このまま、彼は自分の元から離れていくのだろう。千隼が自分の意思で動けるようになったということは喜ばしいはずなのに、少し寂しい気持ちがした。「今日から登下校は別にしよう」と言われる日がいつ来るのかと身構えていた。
しかし。千隼は俺のことを忘れることもしなかった。まるで子犬のように顔を輝かせて近寄ってくる。それが少し嬉しいとともに、いつか来るだろう別れを考えて、寂しい心地がしていることは、千隼には内緒だ。
「おう、おはよう!」
「おはよう、中尾くん」
「先輩、おはようございます!」
ざわざわしている校舎に足を踏み入れると、まるでそこだけが照らされているかのような人気者がいる。残念ながら挨拶をされているのは俺ではない。隣を歩く、1つ年下の幼馴染を見ながら、思わず苦笑した。
「千隼。相変わらず、お前は大人気だな」
「そう?」
こてんと首を傾げる幼馴染、中尾千隼は、自分が人気者であることを自覚していないのだろうか。
少し癖のあるふわふわとした黒髪。くりっとした目に、愛嬌のある笑み。
行き交う人の視線を奪っていることを、千隼は気づいていないようだ。きょとんとした表情を浮かべた彼が尋ねてきた。
「怜くん、僕がいろんな人から声をかけられているの、気になる?」
「何が? お前が人気なのはいいことだろう?」
「そう?」
また、すれ違う人に声をかけられ始め、それに返事をしている千隼をこっそりと見ながら息を吐いた。
嘘をついた。大事な幼馴染が、俺の元から離れていくのは少し寂しい。しかし、そんな身勝手な気持ちはのみ込んだ。伝える必要のない言葉だ。
隣を歩く千隼を見ながら考える。昔は今と全く違ったのにな、と考えてしまうのはきっと弟離れができない兄なのだ。
◆
千隼とは家が近所だった。知り合った年齢さえ覚えていないくらいから遊んでいる。最初、千隼は俺のことを「お兄ちゃん」と呼んでくれていた。
頼ってくる千隼が可愛くてしかたがなかった。千隼といると、ついお兄さんぶりたくなって、ちょっと背伸びをして、難しいことを言ってみたり、外に連れ出したりしていた。俺が間違えていたことも、大袈裟だったこともあれば、迷子になって近所の人に家まで連れて帰ってもらえったこともある。
俺はそんな頼りない「兄」だった。それでも、千隼は呆れるどころか俺のことを頼り、目を輝かせながらついてきてくれていた。
中学に上がったくらいだろうか。千隼はぐんと大人びた。引っ込み思案で、俺の後ろに隠れていたはずだった彼は、気づけば社交的になっていた。友達がたくさんでき、クラスどころか、学校の人気者になった。
このまま、彼は自分の元から離れていくのだろう。千隼が自分の意思で動けるようになったということは喜ばしいはずなのに、少し寂しい気持ちがした。「今日から登下校は別にしよう」と言われる日がいつ来るのかと身構えていた。
しかし。千隼は俺のことを忘れることもしなかった。まるで子犬のように顔を輝かせて近寄ってくる。それが少し嬉しいとともに、いつか来るだろう別れを考えて、寂しい心地がしていることは、千隼には内緒だ。