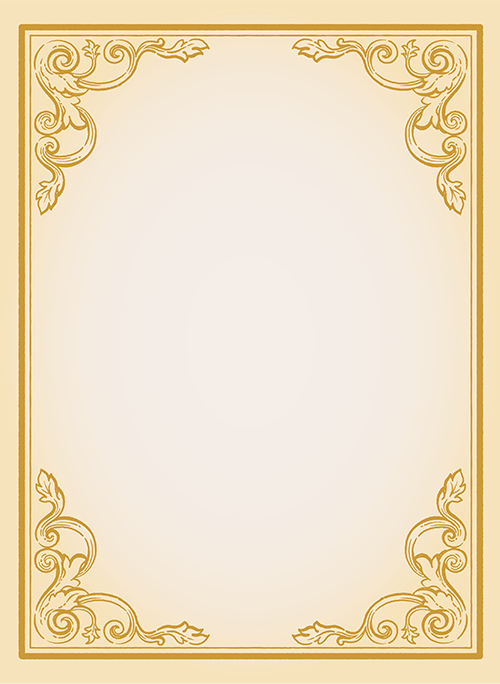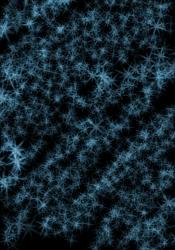さーと雨の音がする。
その昔、六月は「青水無月」と呼ばれていた。
誰もいない図書館の隅で知りえた情報をなぜ「悲しい」と思ったのか。
青がふわりと消え、じわりと滲む青になる。
梅雨明けの日々を過ごしているわたし。
青水無月という存在を、わたしはまだ何も知らない。
ーー
梅雨入りは遅かれ早かれだいたい六月からと決まっている。
二年前、雨上がりの七月下旬。
梅雨明けの朝、学校に向かうため紫陽花の咲いた屋根つきのバス停に向かうと、バス停のベンチに座り、一人で泣いている男の子を見つけた。
歳は当時のわたしと同じ十六歳に見えた。
彼は堪えきれなかった一粒の涙をこぼして、無表情のままで、バスに乗るために恐る恐る近づいたわたしの姿を見るわけではなく、座って俯いたままただ静かに泣いていて、わたしははっとする。
『どうしましたか?』
すぐにかけよって声をかけられたらよかったけど、彼にとっては初対面のわたしが声をかけたところで、よけいに彼のことを傷つけてしまいそうで、バスの到着時間までわたしはただその場で静かにしていることにした。
五分後、予定時刻丁度にバスはやってきた。
結局、彼はバスに乗らなかった。
わたしは来たバスに乗り席に座って、彼をちらりと見たあとで、出発した車内から彼のいなくなった住宅街の景色をぼんやりと見ていた。
理由はよく分からないけど、私は彼のことがずっと忘れられない。
それは彼が綺麗な顔だったからなのかと納得づけてみたけど、実際のところ、よく分からない。
時を経て
雨が上がった一年前の七月下旬。
梅雨明けの朝、最寄りの紫陽花の咲いたバス停のベンチに座り、一人泣いている男の子を見つけた。
一度しか会ったことがなかったのに、去年もここで泣いていた人だとすぐに分かった。
彼は去年と同じで堪えきれなかった涙をこぼして、無表情のままで、バスに乗るために恐る恐るバス停に近づいたわたしの姿をやはり気に留めることなく、ただ静かに泣いていて、わたしはどきりとする。
『どうしましたか?』
勇気を持って声をかけられたらよかったけど、彼にとってはわたしはやっぱり知らない人だからやはり声はかけられなくて、結局何もないまま、わたしは予定時刻丁度に到着したバスに乗った。
去年と同じで、結局彼はやってきたバスに乗らなかった。
わたしはバスに乗り、席でぼんやりと流れる景色を見た。わたしはやはり何故か彼のことを忘れることはなかった。理由はよく分からなかった。けど少ししてぼんやりと、去年の彼と今の彼に共通点があることに気づいた。
やたら綺麗な顔つきの彼は、あのバス停で決まって泣いている。
彼はなんでこの日にこの場所で泣いているのだろう?
二回目の彼に会ってから季節は巡り、六月の上旬の梅雨入り前。
学校の窓から曇り空を眺めて思う。
梅雨が明けたら三度目がやってくる。
変に思われるかもしれない。
けど、理由もなく、わたしは彼のことがやたら気になる。
好きとかそういう感情では今のところないのだけど、理由もないまま、私は……。
梅雨入りして梅雨が明けて、あのバス停のベンチに座って彼がまた泣いてたら、訳を聞こう。
会いに行くんだ、彼に。
わたしは自分の席で窓の外を見ながら静かに決意した。
「翠《すい》、帰ろう?」
クラスメートの飛倉紗那《ひくらさな》はいつの間にかわたしの目の前に立っていた。
「わ……」
「え、なに驚いてるの?」
紗那ちゃんの長いストレート髪は緩やかな風にゆれていた。女子の中でも背は高めだし、大きな目は若干つり上がっているから一見怖そうに見えるけど、紗那ちゃんはフレンドリーな性格をしている。
「ちょっと考えてごとしてたから、いきなり紗那ちゃんがいてびっくりして」
「考えごと? なに考えたの?」
ふふふと笑い、紗那は首を捻る。
「いいの、帰ろう」
わたしが立ち上がると急いで鞄を持つと、紗那ちゃんは苦笑した。
二人で一階に降りると、雨が上がっていた。
わたしと紗那は持ってきた傘を忘れずに持ち、一緒に歩き出す。
「そういえばさ、この辺最近物騒らしいよ、痴漢とか通り魔とか多いらしいんだよね」
「え……そうなんだ」
「翠、立ち向かわないでよ。まず逃げてね!」
「もちろん逃げるが前提だよ」
「でもね、翠って傘の持ち方変なんだよね。反対向きに握ってるというかいつでもその傘で戦闘態勢というか」
「なんか癖でね」
「剣道部だから?」
「んー、関係なさそうだけど」
「危ないから持ち直して」
「そうだね」
傘の持ち方を変えてふふとわたしが笑うと、紗那もにこりとした。
道は十字路にさしかかる。
クレープ屋さんでバイトする紗那ちゃんはバイト前に一度家に帰るため、わたしに手を振る。
「翠ばいばーい。また明日」
「うん、また明日」
紗那ちゃんに手を振り返し、わたしはバス停に向かって歩き出す。
紫陽花の咲くバス停でバスを待ち、五分後に到着時間ぴったりのバスに乗り、窓の景色をぼんやりと眺めて、空いているバスに揺られていた。
ぼんやりしているだけで、家からの最寄り駅であるバス停に到着した。
バスを降りると、紫陽花の咲くバス停のベンチを見る。
あの泣いている彼に、一年に一度、合計で二回しか会ったことはない。
でもバスに乗るときも降りるときも何故か探してしまう。
毎年梅雨明けに一日だけ会える彼は、梅雨の始まりそうな現在じゃ、どこにもいない。
ーー
「おねえちゃん、お帰りー」
最寄りのバス停から坂道を上がって、小さな公園を通りすぎ、徒歩15分。
家の玄関の扉をあけると、奏太が小走りで駆け寄ってきた。
「ただいま、奏太」
「お土産はー?」
「学校にお土産売り場ないの」
「……ちぇっ」
奏太は口を尖らせて行ってしまった。
「もう、学校をなんだと思ってるのよ」
はあとため息をついてから靴を脱ぎリビングに行くと、畳んだ洗濯物を抱えたお母さんと目が合う。
「あ、おかえり、涼くん来てるけど?」
「は?」
「お母さん二階にお父さんの洗濯物置いてくる」
「え?」
お母さんは二階へ行った。
「翠」
ソファーに座っていた幼なじみの涼くんは振り向き、片手を軽くあげにこりとした。
会うのは……小6の時、つまり五年前以来か。
突然両親の仕事の都合でアメリカに飛び立ち、なにも言わずに帰ってきたらしい。
「随分久しぶりだね。わたしのいないところで勝手に家入らないでよね」
「おばさんの許可もらったから」
わたしははあとまたため息をつく。
奏太はテレビの前で正座して画面を見るのに神経を走らせていたので、何を見ているのかなと近づくと、テレビでは天気予報が始まった。
『今日の近畿は曇り空。遅れている梅雨入りの発表は明日にもありそうです』
わたしは奏太を背中から抱え込み、後ろに下げソファーに座らせた。
「あ。何するんだよー」
「近くで見すぎ、目悪くなるでしょ?」
「ちぇっ」
奏太は口を尖らせたが、すぐににこりとして画面を指差す。
「明日梅雨入りなんだね」
「そうみたいだね。というか奏太は難しい言葉知ってるね?」
「梅雨入り、か」
奏太はぱっと顔を明るくしてわたしに微笑む。
「ようやく、明日会えるね」
わたしは首をかしげた。
「会える? 誰に?」
「青くんだよ」
「青くん……?」
思い返してみるが、何も思い出せないわたしに奏太はきょとんとした。
「忘れたの?」
「え、と……誰だっけ?」
記憶を辿る。奏太の声のボリュームが少し上がる。
「紫陽花の青くんだよ?」
「……え? なに紫陽花って」
「紫陽花は紫陽花だよ。目の下にほくろがある、青くんのことだよ? ほら思い出せた?」
奏太は自分の目の下を指でちょんちょんと触ってわたしにアピールした。
「紫陽花? ほくろ?」
「去年も一昨年も会ってるじゃん、梅雨の日に」
「梅雨の日……?」
「今年は僕も喋れるようになったし、今年は青くんとおねえちゃんの二人きりの中に僕を入れてね。二人でデートしないでね?」
「……はあ?」
眉を寄せるしかない。
でも奏太はわたしににこりとしている。
わたしは考える。
一体誰の話なんだろう? と。
「なんの話してるの?」
涼くんが戻ってきて、見知らぬ誰かの話といいかけたところで、お母さんも二階から戻ってきて口を開く。
「奏太、涼くん、今日ハンバーグ作るよ」
「え、やったー手伝うー」
ソファーを勢いよく降りた奏太は行ってしまった。
「俺もー」
涼くんも行ってしまった。
なんだか涼くんのはしゃぎかたは奏太と同じだ。
二歳の奏太はアメリカから帰国したばかりの涼くんと今日が初めて会ったはずなのにすっかりなついていた。
はあとため息をついたあとで
……そういえば、と思う。
バス停。
紫陽花の咲いたベンチ。
梅雨明けに一日しか会えない彼には、
目の下にほくろがある。
ーー
次の日。
日曜日だったが、早くに目が覚めた。
隣では布団をひいて涼くんが寝ていた。
まったくわたしの部屋にいつ侵入してきたのか。
ぼんやりとした頭でなんとなく
自分の部屋でテレビをつける。
『本日梅雨入りが発表されました』
「梅雨入り、か」
たまたま見ていたニュースを見つめる。
梅雨入りの今日、家族はまだ誰も起きていない中で、わたしは自分の部屋を出て顔を洗って歯を磨いてリビングのソファーに座った。
先程のテレビを消して、ぼんやりしていると涼くんが起きてきた。
「翠」
「……なんで泊まってるわけ?」
「おばさんがいいっていったから」
お母さん、そんなあっさり決めないでくれとため息をついていると、涼くんはわたしの隣に座る。
「翠、考えてくれた?」
「何を?」
眉を潜めると、涼ちゃんはそっとわたしの顔を覗く。
「五年前に言ったでしょ、俺は翠のことが好きだって」
「え……」
「だから答えを聞くために、アメリカから戻ってきた」
「……待って、あれ、本気だったの?」
「当たり前だろ」
真剣に話すが、よく考えてみて涼くんに聞かずにいられなかった。
「なんでわたしのこと好きなの?」
「わかんねーよ」
「はあ?」
「でも俺は顔もよくて頭もよくて学歴もある、翠とは小さい頃から一緒にいて翠のだいたいのことは理解してあげられる。翠は俺と付き合うのになにか問題ある?」
確かに彼の言うことは正しいのかもしれない。
でも。
「めっちゃ自信家だね」
「全部翠のためだよ」
「……ごめんなさい、本気なら涼くんの気持ちには答えられない」
「なんで」
「なんでって……」
「俺のこと嫌い?」
「まあめちゃくちゃ嫌いってわけじゃないけど」
「ならいいじゃん」
「よくないよ」
「なんで」
「なんでって」
「翠」
「なに」
「……他に好きな人いるだろ?」
「え?」
少し固まってしまう。
好きな人?
そんな人はいない。
ただ、気になる人はいるかもしれない。
あのバス停の、男の子。
でもあれは……好きなんだろうか?
「いないよ」
「だったら俺と付き合ってくれるはずだ」
「だからどこからの自信……?」
「幼なじみとしての自信だよ」
「はあ?」
「翠の好きな人って誰?」
その時、さーと雨が降る。
その時、わたしの頭の中に何かがにじみ出るような感覚を覚えた。
「あ……れ?」
何かはわからないけど、寝起きのまま三角座りをして、その感覚に集中する。
「な、に」
一つ一つ、何かが鮮明になっていく。
一つ一つ、何かを思い出してくる。
それは、少しずつ……そう、少しずつ。
わたしはばっと顔をあげた。
思い出せたのは、
涼くんに『好きな人って誰?』と聞かれたからじゃない。
今日、梅雨入りしたからだ。
さーと雨の音がする。
全部全部、思い出した。
「……青、くん」
「え?」
「青くん」
「あおくん……?」
「……ごめん涼くん、わたし行かなきゃ」
私はソファーから立ち上がる。
「は、おい翠!」
「ごめん」
「こんな朝早くにどこ行くんだよ、おい、翠!?」
家を飛び出して、傘をさして、雨の中を走り出す。
最寄り駅の紫陽花の咲くバス停まで。
走りながら思い出した記憶を整理した。
梅雨明けのバス停のベンチで泣いている男の子の名前は青くん。
他人が聞いたら信じられない話だが彼は紫陽花の妖精で、毎年梅雨入りから梅雨明けの間だけ何故か人間になれる。
二年前の梅雨の日、青くんは綺麗な顔すぎたからなのか、太った見知らぬ男から痴漢にあっていた。その痴漢を目撃したわたしは痴漢するその男が許せなくて、わたしは男を傘で撃退したということは今なら鮮明に思い出せる。
青くんと仲良くなって、わたしが恋に落ちるのに時間はかからなかった。
青くんは綺麗な人で、優しくて、誰よりもわたしの存在を肯定してくれる。
わたしの初めての恋だ。
どういう理由かはわからないが、
紫陽花の青くんは梅雨明けでも
種になり、また花を咲かせながら
わたしとの思い出を毎年上書きすることができ、わたしのことを忘れることはない。
わたしは梅雨明けの瞬間に彼との記憶が消え、
紫陽花をみかけても、次の梅雨入りまで青くんの記憶は封印され、つまりは忘れてしまう。
梅雨入りしたこの瞬間に思うのだ。
聞けずにいるけど、
毎年、彼を泣かせてしまっているのはきっと……わたしだ。
バス停が見えてくる。
彼はベンチにいた。
わたしに気がついて、そっと立ち上がった。
「ただいま、青くん」
青くんはなにも言わないまま微笑む。
わたしは傘を投げ捨てて彼の胸に飛び込む。
「お帰り、翠ちゃん」
青くんはただ優しくわたしを抱き締めた。
さーと雨の音がする。
紫陽花の咲くバス停で
しばらくしてから二人でベンチにすわり、青くんの隣で座るわたしは片方の足をぶらぶらさせていじけていた。
「また私は忘れてたんだね」
「翠ちゃん。傘、まだその逆さ持ち方なんだね。不審者対策だっけ? 変わらないね」
青くんはわたしの手元をみる。
「いまはその話してないんだよ」
少々ふてくされながらちらりと青くんを見ると、青くんはふふと笑った。
「僕のことを忘れるのは仕方ないよ。人間の君と紫陽花の妖精である僕はそういう運命なんだ」
「でも」
「言ったでしょ? ぼくは紫陽花でその花が枯れて種になってまた紫陽花になっても記憶があるけど、人間である翠ちゃんは梅雨しか僕との思い出を思い出すことができないんだよ」
青くんは少し微笑む。
「青くんは人間から紫陽花に戻る、梅雨明けの朝にバス停にいるじゃない?」
「うん、あそこにいれば最後に翠ちゃんに会えるから」
「でもあの時にはもう」
「翠ちゃんは僕の記憶を封印されている。翠ちゃんは僕をいなかったとして、現実世界を歩いていく」
「どうしたら青くんを忘れないのかな」
「翠ちゃんは毎年悩んでるね」
「うーん」
そりゃ悩むよ。
大切な人なのに、梅雨が明けて青くんが昼間でには紫陽花に戻る。
梅雨があけると青くんのことを忘れてしまう。
はあとため息をつくと、青くんが笑う。
「せっかく再会できたんだし、梅雨入りは今日からだよ。またしばらく一緒にいられるし楽しまなきゃ」
「うーん」
「翠ちゃん、どうしたの? せっかく再会できたのに嬉しくないの?」
「え……嬉しいよ、それは」
「僕たちには会える期間が定められてる」
青くんはベンチに添えていたわたしの手を
握る。
「今日からまた思い出作り開始だね」
「うん」
今度は忘れない思い出がいい。
雨が上がっても覚えていられるような。
「今年こそ、青くんと忘れない思い出をつくるんだ」
梅雨が明けるまでに運命に終止符を打ちたい。
私は青くんの手をぎゅっと握り返した。