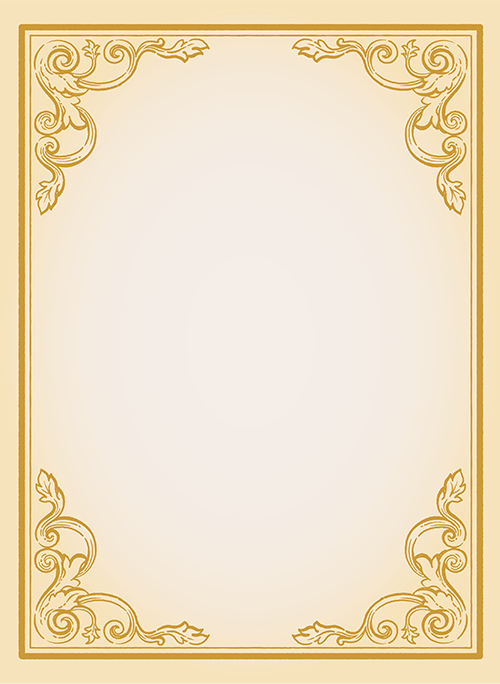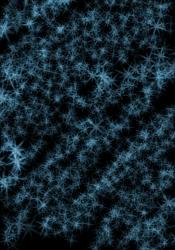大雨《おおさめ》の降る、ある都会の深夜二時。
じめっとした夏の匂いを感じながら、ある一本の電柱の一番上に、少年は平然と立っていた。
黒髪で年齢は十八才。紺色の着物を着ていた。
上は着物を着ているのに、下の靴は真っ黒のスニーカーという、何とも不格好な姿だ。
少年はこの大雨の中、そんな場所に立ち、傘もさしていないのに、何故か濡れていない。
都会を穏やかな表情で見つめている。都会は、あちこちでさまざまな電灯の光が灯って明るいが、深夜ということもあり、静まりかえっている。
それでもちらほら歩く人々もいる。だが、その人々が少年に気づく気配はない。
そこに一匹の雀がやって来た。
この雀は、雨に濡れているが、慣れているのか、雨で濡れていることをそれほど気にしていない。
その雀は、少年を見つけると何の躊躇もなく近づいて、少年の肩に止まった。
雨に打たれた雀が、突然肩に乗っても少年は動じなかった。
そもそも少年は雀が止まったところで、雀の雨の水滴が落ちて濡れることはない。そして、この雀が少年の肩に乗ることも、少年《かれ》にとっては日常茶飯事だった。
「フィンセント」
雀が、少年に話しかけた。雀は、言葉が話せるようだ。
「何?」
雨の中で、少年は穏やかな声で口を開いた。フィンセントというのは、彼の名前のようだ。
「また、見つけたの?」
雀が不安そうにそう聞くと、フィンセントは、ほんの少しだけ笑みを浮かべて、ゆっくり頷く。そしてこう話す。
「大雨が降れば降るほど、降っている雨と自分の心を共感させてしまうのか、誰かの悲しい気持ちを見つけやすいよ」
雀は、フィンセントの肩の上で、心配そうに少年を見つめた。そして、口を開く。
「また食べてあげるの? 誰かの悲しみを」
フィンセントは微笑んだまま、雀を見た。
「ロン」
フィンセントは雀の名前を口にする。そして、こう続けた。
「そんなに悲しまないで」
フィンセントはそう笑っているが、フィンセントを見るロンの曇った表情は変わらない。
そしてロンはこう切り出す。
「悲しみを食べた分、フィンセントの命は少しずつなくなっていくのに、まだフィンセントは誰かを助ける気なの?」
フィンセントはそれを聞き、表情を変えることなく、またそっと頷いた。
「なんでそんな簡単に頷けるの……」
あまりにあっさりしたフィンセントの態度にロンは少し口ごもったが、すぐにまた話を続ける。
「フィンセントに初めて会った三ヶ月前、この電柱の上に佇むフィンセントを見て、その時は……何の感情も抱かなかった。……でもフィンセントは他の誰よりも優しくて、温かくて、いつの間にかボクは、フィンセントと一緒に過ごすうちに感情移入してしまって、今のボクは……フィンセントを失うのが怖いよ」
肩の上で悲しそうに話すロンに、フィンセントはそっと微笑んだままロンの話に耳を傾けて、ゆっくりと何度か相づちをうつ。
「雨なんか、降らなきゃいいんだ。雨なんて降らなければ、みんなが悲しんだりしなければ、フィンセントは誰かの悲しみを食べたりしないのに」
フィンセントは、落ち込み続けるロンの頭を人差し指で優しく撫でた。そして口を開いた。
「ごめんね。でも、世の中には抱えきれないほどの悲しみを、一人で抱えてどうしようもなく過ごしている人がいるんだよ。雨の日しかないんだ、僕がその人を助けることができるのは……だから許してほしいんだ」
それを聞き、ロンは急に怒鳴った。
「フィンセントが犠牲になる必要はないじゃないか! ……本当に死んじゃうよ。フィンセントじゃなくても、他の誰かが……」
悲しみの混じったその怒ったロンを見て、フィンセントはまた、肩の上にいるロンの頭を人差し指で優しく撫でた。
「ロン、泣かないで」
「……泣いてないよ」
「涙がこぼれ落ちそうだよ」
ロンは片方の羽根で、こぼれ落ちそうな涙をぬぐった。フィンセントは優しくロンに話しかける。
「他の誰かじゃだめなんだ。大丈夫だよ、まだ僕は少し先まで生きれるさ」
フィンセントは微笑んでいるが、ロンは全然納得してなかった。
「……何が大丈夫なんだよ。全然大丈夫じゃない! 保証がないじゃないか!! ……フィンセントの体がほんの少しずつであれ、どんどん悪くなってるのをボクは知ってる。それなのにまた誰かの悲しみを食べてしまったら、フィンセントの寿命はさらに縮まるんだろ…?」
フィンセントはそれを聞き、ふっと、ロンから目を離してまた何故か穏やかな顔で都会を眺める。
「それでも行かなくちゃ……見つけたから」
フィンセントは、高い電柱の上から躊躇することもなく飛び降りた。
その時にロンは電柱の上付近に取り残され、フィンセントと距離が離れる。
「待って! 待ってフィンセント、ボクも行く!!」
ロンもすぐに、フィンセントの後を追いかけた。
大雨は降りやまない。
今日の深夜から明け方まで降り続けると予報がでている。
都会に降り立つフィンセントは、軽やかに、そして素早く、まるで忍者のように、着物姿のまま移動する。
ロンはそのスピードに難なくついていっている。
都会でも車通りのない、その道を移動する。
その時も誰かとすれ違うが、やはりフィンセントには気づかない。
フィンセントの170cmの背に合わせて低空飛行しているロンに振りかえる人がいても。
フィンセントは、ある古風な二階建ての一軒家前で止まった。
見た目は無惨な形で、庭には草も生い茂り、見た目ではとても人が住んでいる様子はない。
「この家なの? ボロボロだよ、かわいそうなくらい。屋根とか壁に穴はないみたいだけど」
家を悲しげに見つめるロンに気にせず、フィンセントは入り口の門を開けて、草をかき分け、数メートル先の家の扉を目指す。
ロンはフィンセントの背中を少し見つめ、口をきつく閉じて、フィンセントの後を追う。フィンセントは、扉の入り口までたどり着くと、玄関のドアの取っ手を握る。
「扉開けなくても、すり抜けて入れるでしょ」
ロンは冷静にフィンセントに言う。
「なるべく驚かせたくないんだ。まあ、どっちにしろ驚かせてしまうことになるんだろうけど」
「呼び鈴鳴らしたら?」
ロンの言葉に、フィンセントは首を振る。
「この家のは壊れてたよ。それに、鳴ったところで、きっと怖がって出てきてくれないよ」
フィンセントは、玄関の扉を開ける。鍵はかかっていなかった。
中に入って扉を閉め、フィンセントは辺りを見回す。
中は見た感じ散らかってはないものの、やはりかなりの老朽化が進んでいる。
「誰かいるの? こんなボロボロな家に」
ロンはそう言い床に足をつけると、羽根をバタバタしたり、体をぶるぶるとして、雨の水滴を落とした。
「ここから、悲しみを感じるんだ」
「悲しみ……誰の?」
「子供かな、小学生かな。低学年の男の子。姿が頭に浮かんでくる」
「子供……?」
「……それ以上のことは、その子供の手に触れてみないと分からないな……」
フィンセントはそう呟いて、靴のまま家に上がった。
「ねえフィンセント。その階段、抜けて落ちたりしないのかな……大丈夫なの?」
ロンはフィンセントの近くで飛びながら、不安そうに下を見つめている。
「大丈夫、多分」
フィンセントは、二階へ続く階段をゆっくりと上っていく。一段一段上ると、床がきしむ音がする。
階段を上りきると、渡り廊下をまっすぐ歩くと、扉が一つあった。
二階はこの扉しかない。
ロンは、ふいにフィンセントの肩に乗り、扉を見つめる。
フィンセントは、ゆっくりと扉を開けた。その部屋は、畳の敷いてある八畳ほどの広さの部屋だった。
開けたら下を覗けそうな窓が目の前にひとつ。
部屋には物というものが一切なく、とても殺風景だ。
「誰もいないじゃないか」
ロンは、フィンセントの肩から離れて羽を広げて飛び、部屋の回りをぐるぐると二周してまた、フィンセントの肩の上に乗った。
フィンセントは部屋の入り口から動かずに目を閉じる。そしてゆっくりとまた目を開けて、歩き出す。
立ち止まったのは、押し入れの前だった。
押し入れの扉をフィンセントがゆっくり開けると、二段式の押し入れの下で膝を抱えた男の子がいた。驚いてフィンセントを見る。
いや、フィンセントを見ているわけじゃない。
どうして、扉が勝手に独りでに開いたのかと不安がって言葉を失っている。
フィンセントは強く目を閉じる。そして、目を開けると、少年の目にフィンセントが見えるようになった。
男の子にとっては見知らぬ少年がいきなり目の前に現れて、男の子は、短く小さな悲鳴をあげて、震えながら、この少年がどこからやってきたのだと、きょろきょろしている。
その後すぐにまたフィンセントに目線を合わせた。
「こんにちは」
「うわあああ!!」
フィンセントが優しく声をかけると、今度は男の子が大声を出して、頭も抱えて、震えながら体を先程よりも小さく丸めている。
押し入れは小さく、奥行きもないので、逃げ道に困った男の子はかなり怯えた様子で、フィンセントを見ている。
「名前は……?」
フィンセントが優しくそう聞くと、男の子はびくっと体を震わせた。
「わ……航」
思わず名前をいってしまったようで、しまったという顔を男の子はしている。
「航くん? 僕の名前はフィンセント」
名前を言い、フィンセントはそっと笑う。
怯えながらも男の子は、フィンセントから目を離さない。
誰なのだろう?
フィンセントという名前からして、外人なのだろうか……? いや、でも見た目は日本人しか見えないのに、と少し考えている。
フィンセントは、そっと膝を抱えていた男の子の手に触れる。
その瞬間、男の子はすぐに手を振り払った。
そして、すごい剣幕で叫んだ。
「触るな!! 俺は施設に戻らない!! 家にも帰らない!! 絶対に!!」
フィンセントは、その声に少し驚いた。
ロンはいつの間にか少し離れた窓の近くに移動している。
手を出したい気持ちは山々だが、ロンはその位置で二人の様子をみることにした。
フィンセントがちらりと航を見る。黙視する限りでも、彼の腕や足に痛々しいアザが見える。
ロンはもう、彼のアザにはフィンセントよりも先に気づいていたようだ。
フィンセントは、驚きながらも優しく航に声をかける。
「僕はね、航くんを助けに来たんだ」
それを聞くと、航は急いで首を振る。そしてフィンセントを睨み付けて、こう叫んだ。
「施設のやつは、みんなそう言うんだ! 俺は、もうだまされない……!」
「僕は施設の人じゃないよ」
フィンセントは静かに答えた。
「じゃあ……お前は誰だ?」
フィンセントは、少し黙ってからこう答えた。
「……僕は、死神だよ」
航は言葉を失った。フィンセントはこう続ける。
「僕は死神の家系に生まれたんだ。晴れた日はね、君みたいに死にたがってそうな人の命を奪っているよ」
航は嘘に決まってる……と思えなかった。
何故だろう、彼の目が嘘をついていないと感じる。だからこそ、少し恐怖が込み上げる。
「じゃあ俺を……?」
「ううん、今日はその仕事をしないよ。だって今日は雨だから。それに僕は死神になんて本当はなりたくないんだよ。だから、雨の日は死神になんてならない」
「どういうこと……?」
航は恐る恐る聞いてみた。フィンセントはこう続ける。
「晴れた日は遠くにいても、死神同士で電波みたいなものがあってね、離れていてもどの死神がいつどこで何をしているのか筒抜けなの。だから、僕が死神の仕事をしてないとすぐにばれてしまう。ところが、雨の日は小雨だろうとなんだろうと、その死神の電波が雨に消えてなくなっているから、僕は死神の仕事をしなくても、他の死神に筒抜けにはならない。だから僕は雨の日は、昔から憧れてた人助けができるようなやつになることにしたんだ。まあ、僕は死神として生まれてしまったから、どんなに監視の目が離れようと、人助けなんて仕事に背くことをしたら、命に代償が残るけどね」
「命に代償? ……死んでるんじゃないのか、死神は」
「死んでるよ。でも、本来人間は死んだ後も魂は残ってるんだ。そしてその魂には永遠が続いていて、生き返ったり、死んだりを繰り返すんだけど、俺の場合は、死神という運命に少し背いて生きてきてしまったから、その分魂を削り取られてしまった。だから僕の命は、この世から完全に消える、カウントダウンがはじまってるところさ」
航は言葉に詰まっている。
ロンは険しい表情で、フィンセントをみつめている。フィンセントははっとした。
「子供の君に難しい話をしてしまったね。でも大丈夫。僕は死神だけど、君のこと必ず助けるから」
航は完全に固まってしまった。何が起きているのか、よく分からなかった。航は頭の中を整理し始める。
探しに来たのは、施設のやつはだと思っていたが、彼は死神と名乗り、そして自分を助けるといっている。
何なんだ……? これは。
そしてフィンセントを見た。
何故だか、こんな無茶苦茶なことを口にしているのに……あの目のせいだ。あのまっすぐな目が……自分を助けてくれる、気がする。
フィンセントは、航の手にまた触れた。そして、優しく握りしめて目を閉じる。
航は、頭の思考回路がついていけてないのか、彼を信じ始めたのか、フィンセントの手を今度は振り払わなかった。
フィンセントは、閉じた目をすぐに開いた。手をにぎったまま、航を見てこう話す。
「航くんのこと、今情景が浮かんで分かった。家庭で悲惨な目にあって、逃げた養護施設でも助けてくれる人がいなかったんだね。それでまた逃げ出してきて、やっとの思いで隠れられるこの場所を見つけた」
「何で……?」
「よく勇気を出して、逃げてきたね。頑張ったんだね、航くんは」
フィンセントのその言葉ではっとして、ふと糸が切れたように航の目から涙が幾つも溢れてこぼれ落ちた。
「航くんの悲しみは、僕が食べてあげるよ」
「食べる……?」
ぼやけた視界で、航はフィンセントの方を見る。
「うん。そしたら、この苦しみから君は抜け出せる」
フィンセントは目を閉じて、航の手を先程よりも少し強く握りしめる。
どこか近くで何かが光り、航は涙を拭いた。
すると、航の心臓の位置からでている光だとわかり、白く濁ったような丸い光がそっと航の体から出てきた。
シューっというような、本当に小さな音が、その時聞こえた。
フィンセントはその音を聞き取り目を開けて自分の手のひらを出すと、丸い光は磁石のように引き寄せられて、フィンセントの手のひらの上に乗った。
丸い光が手のひらに乗ると、それはふっと形を変えて、薬のような小さな粒に変わる。
それをフィンセントは口にいれて、ごくんと飲み込んだ。飲み込んだ瞬間に、航の意識が少しずつ薄れていった。
目の前のフィンセントの顔が先ほどよりもどんどんぼやけていく。
だけど、フィンセントがまっすぐこっちを見ているのが航に分かる。
そしてフィンセントは航にこう言った。
「悲しみは僕が食べたから、心が軽くなったはずだよ。これから先は、強く生きるんだよ航くん。死にたがってると、晴れの日に僕が迎えにいかなきゃいけなくなるから」
フィンセントがそう言うと、航は完全に意識を失ってその場に倒れた。
――あれから数日たった小雨の日。
深夜二時。
フィンセントは、また着物姿でいつものように電柱の上に立っている。
ロンはフィンセントの肩に乗って、フィンセントと一緒に都会の街を眺めている。
「航くん、あれからよく笑うようになったんだって。環境もだいぶよくなったみたい」
ロンが静かに言い、フィンセントは微笑む。
詳細について、フィンセントは、あえてロンに触れなかった。
ロンは話を続ける。
「でもね、航くんがいくら幸せになったからといって、その後で悲しみを食べたフィンセントが苦しむ姿をやっぱり見るのが辛いよ。今回も大分苦しんでたじゃないか」
フィンセントは、肩に乗るロンを穏やかな目つきで見る。
「ありがとう、その時もそばにいてくれて」
「もう、雀の命も三年と短いんだからね。ひやひやするよ。ボクはまだその中で生きてるけど……でも僕が例えば死んでも、永遠の魂で何度生まれ変わろうとも、フィンセントの側にいてあげるよ」
「ロンは優しいんだね。晴れの日は、僕は人の命を奪う死神なのに」
ロンは、フィンセントを見る。
「でも、フィンセントは命を奪いたくて奪ってる訳じゃない」
「でも、死神だよ」
「う……うるさいなぁ。フィンセントは……フィンセントは死神というかボクの親友なの!!」
「……ありがとう、ロン」
雨は都会に降り続く。
「ねえフィンセント、また今日も悲しみを食べに行くの? 命を削っても……?」
フィンセントは、そっと頷く。
「うん。だって、今日は雨が降ってるからね」
じめっとした夏の匂いを感じながら、ある一本の電柱の一番上に、少年は平然と立っていた。
黒髪で年齢は十八才。紺色の着物を着ていた。
上は着物を着ているのに、下の靴は真っ黒のスニーカーという、何とも不格好な姿だ。
少年はこの大雨の中、そんな場所に立ち、傘もさしていないのに、何故か濡れていない。
都会を穏やかな表情で見つめている。都会は、あちこちでさまざまな電灯の光が灯って明るいが、深夜ということもあり、静まりかえっている。
それでもちらほら歩く人々もいる。だが、その人々が少年に気づく気配はない。
そこに一匹の雀がやって来た。
この雀は、雨に濡れているが、慣れているのか、雨で濡れていることをそれほど気にしていない。
その雀は、少年を見つけると何の躊躇もなく近づいて、少年の肩に止まった。
雨に打たれた雀が、突然肩に乗っても少年は動じなかった。
そもそも少年は雀が止まったところで、雀の雨の水滴が落ちて濡れることはない。そして、この雀が少年の肩に乗ることも、少年《かれ》にとっては日常茶飯事だった。
「フィンセント」
雀が、少年に話しかけた。雀は、言葉が話せるようだ。
「何?」
雨の中で、少年は穏やかな声で口を開いた。フィンセントというのは、彼の名前のようだ。
「また、見つけたの?」
雀が不安そうにそう聞くと、フィンセントは、ほんの少しだけ笑みを浮かべて、ゆっくり頷く。そしてこう話す。
「大雨が降れば降るほど、降っている雨と自分の心を共感させてしまうのか、誰かの悲しい気持ちを見つけやすいよ」
雀は、フィンセントの肩の上で、心配そうに少年を見つめた。そして、口を開く。
「また食べてあげるの? 誰かの悲しみを」
フィンセントは微笑んだまま、雀を見た。
「ロン」
フィンセントは雀の名前を口にする。そして、こう続けた。
「そんなに悲しまないで」
フィンセントはそう笑っているが、フィンセントを見るロンの曇った表情は変わらない。
そしてロンはこう切り出す。
「悲しみを食べた分、フィンセントの命は少しずつなくなっていくのに、まだフィンセントは誰かを助ける気なの?」
フィンセントはそれを聞き、表情を変えることなく、またそっと頷いた。
「なんでそんな簡単に頷けるの……」
あまりにあっさりしたフィンセントの態度にロンは少し口ごもったが、すぐにまた話を続ける。
「フィンセントに初めて会った三ヶ月前、この電柱の上に佇むフィンセントを見て、その時は……何の感情も抱かなかった。……でもフィンセントは他の誰よりも優しくて、温かくて、いつの間にかボクは、フィンセントと一緒に過ごすうちに感情移入してしまって、今のボクは……フィンセントを失うのが怖いよ」
肩の上で悲しそうに話すロンに、フィンセントはそっと微笑んだままロンの話に耳を傾けて、ゆっくりと何度か相づちをうつ。
「雨なんか、降らなきゃいいんだ。雨なんて降らなければ、みんなが悲しんだりしなければ、フィンセントは誰かの悲しみを食べたりしないのに」
フィンセントは、落ち込み続けるロンの頭を人差し指で優しく撫でた。そして口を開いた。
「ごめんね。でも、世の中には抱えきれないほどの悲しみを、一人で抱えてどうしようもなく過ごしている人がいるんだよ。雨の日しかないんだ、僕がその人を助けることができるのは……だから許してほしいんだ」
それを聞き、ロンは急に怒鳴った。
「フィンセントが犠牲になる必要はないじゃないか! ……本当に死んじゃうよ。フィンセントじゃなくても、他の誰かが……」
悲しみの混じったその怒ったロンを見て、フィンセントはまた、肩の上にいるロンの頭を人差し指で優しく撫でた。
「ロン、泣かないで」
「……泣いてないよ」
「涙がこぼれ落ちそうだよ」
ロンは片方の羽根で、こぼれ落ちそうな涙をぬぐった。フィンセントは優しくロンに話しかける。
「他の誰かじゃだめなんだ。大丈夫だよ、まだ僕は少し先まで生きれるさ」
フィンセントは微笑んでいるが、ロンは全然納得してなかった。
「……何が大丈夫なんだよ。全然大丈夫じゃない! 保証がないじゃないか!! ……フィンセントの体がほんの少しずつであれ、どんどん悪くなってるのをボクは知ってる。それなのにまた誰かの悲しみを食べてしまったら、フィンセントの寿命はさらに縮まるんだろ…?」
フィンセントはそれを聞き、ふっと、ロンから目を離してまた何故か穏やかな顔で都会を眺める。
「それでも行かなくちゃ……見つけたから」
フィンセントは、高い電柱の上から躊躇することもなく飛び降りた。
その時にロンは電柱の上付近に取り残され、フィンセントと距離が離れる。
「待って! 待ってフィンセント、ボクも行く!!」
ロンもすぐに、フィンセントの後を追いかけた。
大雨は降りやまない。
今日の深夜から明け方まで降り続けると予報がでている。
都会に降り立つフィンセントは、軽やかに、そして素早く、まるで忍者のように、着物姿のまま移動する。
ロンはそのスピードに難なくついていっている。
都会でも車通りのない、その道を移動する。
その時も誰かとすれ違うが、やはりフィンセントには気づかない。
フィンセントの170cmの背に合わせて低空飛行しているロンに振りかえる人がいても。
フィンセントは、ある古風な二階建ての一軒家前で止まった。
見た目は無惨な形で、庭には草も生い茂り、見た目ではとても人が住んでいる様子はない。
「この家なの? ボロボロだよ、かわいそうなくらい。屋根とか壁に穴はないみたいだけど」
家を悲しげに見つめるロンに気にせず、フィンセントは入り口の門を開けて、草をかき分け、数メートル先の家の扉を目指す。
ロンはフィンセントの背中を少し見つめ、口をきつく閉じて、フィンセントの後を追う。フィンセントは、扉の入り口までたどり着くと、玄関のドアの取っ手を握る。
「扉開けなくても、すり抜けて入れるでしょ」
ロンは冷静にフィンセントに言う。
「なるべく驚かせたくないんだ。まあ、どっちにしろ驚かせてしまうことになるんだろうけど」
「呼び鈴鳴らしたら?」
ロンの言葉に、フィンセントは首を振る。
「この家のは壊れてたよ。それに、鳴ったところで、きっと怖がって出てきてくれないよ」
フィンセントは、玄関の扉を開ける。鍵はかかっていなかった。
中に入って扉を閉め、フィンセントは辺りを見回す。
中は見た感じ散らかってはないものの、やはりかなりの老朽化が進んでいる。
「誰かいるの? こんなボロボロな家に」
ロンはそう言い床に足をつけると、羽根をバタバタしたり、体をぶるぶるとして、雨の水滴を落とした。
「ここから、悲しみを感じるんだ」
「悲しみ……誰の?」
「子供かな、小学生かな。低学年の男の子。姿が頭に浮かんでくる」
「子供……?」
「……それ以上のことは、その子供の手に触れてみないと分からないな……」
フィンセントはそう呟いて、靴のまま家に上がった。
「ねえフィンセント。その階段、抜けて落ちたりしないのかな……大丈夫なの?」
ロンはフィンセントの近くで飛びながら、不安そうに下を見つめている。
「大丈夫、多分」
フィンセントは、二階へ続く階段をゆっくりと上っていく。一段一段上ると、床がきしむ音がする。
階段を上りきると、渡り廊下をまっすぐ歩くと、扉が一つあった。
二階はこの扉しかない。
ロンは、ふいにフィンセントの肩に乗り、扉を見つめる。
フィンセントは、ゆっくりと扉を開けた。その部屋は、畳の敷いてある八畳ほどの広さの部屋だった。
開けたら下を覗けそうな窓が目の前にひとつ。
部屋には物というものが一切なく、とても殺風景だ。
「誰もいないじゃないか」
ロンは、フィンセントの肩から離れて羽を広げて飛び、部屋の回りをぐるぐると二周してまた、フィンセントの肩の上に乗った。
フィンセントは部屋の入り口から動かずに目を閉じる。そしてゆっくりとまた目を開けて、歩き出す。
立ち止まったのは、押し入れの前だった。
押し入れの扉をフィンセントがゆっくり開けると、二段式の押し入れの下で膝を抱えた男の子がいた。驚いてフィンセントを見る。
いや、フィンセントを見ているわけじゃない。
どうして、扉が勝手に独りでに開いたのかと不安がって言葉を失っている。
フィンセントは強く目を閉じる。そして、目を開けると、少年の目にフィンセントが見えるようになった。
男の子にとっては見知らぬ少年がいきなり目の前に現れて、男の子は、短く小さな悲鳴をあげて、震えながら、この少年がどこからやってきたのだと、きょろきょろしている。
その後すぐにまたフィンセントに目線を合わせた。
「こんにちは」
「うわあああ!!」
フィンセントが優しく声をかけると、今度は男の子が大声を出して、頭も抱えて、震えながら体を先程よりも小さく丸めている。
押し入れは小さく、奥行きもないので、逃げ道に困った男の子はかなり怯えた様子で、フィンセントを見ている。
「名前は……?」
フィンセントが優しくそう聞くと、男の子はびくっと体を震わせた。
「わ……航」
思わず名前をいってしまったようで、しまったという顔を男の子はしている。
「航くん? 僕の名前はフィンセント」
名前を言い、フィンセントはそっと笑う。
怯えながらも男の子は、フィンセントから目を離さない。
誰なのだろう?
フィンセントという名前からして、外人なのだろうか……? いや、でも見た目は日本人しか見えないのに、と少し考えている。
フィンセントは、そっと膝を抱えていた男の子の手に触れる。
その瞬間、男の子はすぐに手を振り払った。
そして、すごい剣幕で叫んだ。
「触るな!! 俺は施設に戻らない!! 家にも帰らない!! 絶対に!!」
フィンセントは、その声に少し驚いた。
ロンはいつの間にか少し離れた窓の近くに移動している。
手を出したい気持ちは山々だが、ロンはその位置で二人の様子をみることにした。
フィンセントがちらりと航を見る。黙視する限りでも、彼の腕や足に痛々しいアザが見える。
ロンはもう、彼のアザにはフィンセントよりも先に気づいていたようだ。
フィンセントは、驚きながらも優しく航に声をかける。
「僕はね、航くんを助けに来たんだ」
それを聞くと、航は急いで首を振る。そしてフィンセントを睨み付けて、こう叫んだ。
「施設のやつは、みんなそう言うんだ! 俺は、もうだまされない……!」
「僕は施設の人じゃないよ」
フィンセントは静かに答えた。
「じゃあ……お前は誰だ?」
フィンセントは、少し黙ってからこう答えた。
「……僕は、死神だよ」
航は言葉を失った。フィンセントはこう続ける。
「僕は死神の家系に生まれたんだ。晴れた日はね、君みたいに死にたがってそうな人の命を奪っているよ」
航は嘘に決まってる……と思えなかった。
何故だろう、彼の目が嘘をついていないと感じる。だからこそ、少し恐怖が込み上げる。
「じゃあ俺を……?」
「ううん、今日はその仕事をしないよ。だって今日は雨だから。それに僕は死神になんて本当はなりたくないんだよ。だから、雨の日は死神になんてならない」
「どういうこと……?」
航は恐る恐る聞いてみた。フィンセントはこう続ける。
「晴れた日は遠くにいても、死神同士で電波みたいなものがあってね、離れていてもどの死神がいつどこで何をしているのか筒抜けなの。だから、僕が死神の仕事をしてないとすぐにばれてしまう。ところが、雨の日は小雨だろうとなんだろうと、その死神の電波が雨に消えてなくなっているから、僕は死神の仕事をしなくても、他の死神に筒抜けにはならない。だから僕は雨の日は、昔から憧れてた人助けができるようなやつになることにしたんだ。まあ、僕は死神として生まれてしまったから、どんなに監視の目が離れようと、人助けなんて仕事に背くことをしたら、命に代償が残るけどね」
「命に代償? ……死んでるんじゃないのか、死神は」
「死んでるよ。でも、本来人間は死んだ後も魂は残ってるんだ。そしてその魂には永遠が続いていて、生き返ったり、死んだりを繰り返すんだけど、俺の場合は、死神という運命に少し背いて生きてきてしまったから、その分魂を削り取られてしまった。だから僕の命は、この世から完全に消える、カウントダウンがはじまってるところさ」
航は言葉に詰まっている。
ロンは険しい表情で、フィンセントをみつめている。フィンセントははっとした。
「子供の君に難しい話をしてしまったね。でも大丈夫。僕は死神だけど、君のこと必ず助けるから」
航は完全に固まってしまった。何が起きているのか、よく分からなかった。航は頭の中を整理し始める。
探しに来たのは、施設のやつはだと思っていたが、彼は死神と名乗り、そして自分を助けるといっている。
何なんだ……? これは。
そしてフィンセントを見た。
何故だか、こんな無茶苦茶なことを口にしているのに……あの目のせいだ。あのまっすぐな目が……自分を助けてくれる、気がする。
フィンセントは、航の手にまた触れた。そして、優しく握りしめて目を閉じる。
航は、頭の思考回路がついていけてないのか、彼を信じ始めたのか、フィンセントの手を今度は振り払わなかった。
フィンセントは、閉じた目をすぐに開いた。手をにぎったまま、航を見てこう話す。
「航くんのこと、今情景が浮かんで分かった。家庭で悲惨な目にあって、逃げた養護施設でも助けてくれる人がいなかったんだね。それでまた逃げ出してきて、やっとの思いで隠れられるこの場所を見つけた」
「何で……?」
「よく勇気を出して、逃げてきたね。頑張ったんだね、航くんは」
フィンセントのその言葉ではっとして、ふと糸が切れたように航の目から涙が幾つも溢れてこぼれ落ちた。
「航くんの悲しみは、僕が食べてあげるよ」
「食べる……?」
ぼやけた視界で、航はフィンセントの方を見る。
「うん。そしたら、この苦しみから君は抜け出せる」
フィンセントは目を閉じて、航の手を先程よりも少し強く握りしめる。
どこか近くで何かが光り、航は涙を拭いた。
すると、航の心臓の位置からでている光だとわかり、白く濁ったような丸い光がそっと航の体から出てきた。
シューっというような、本当に小さな音が、その時聞こえた。
フィンセントはその音を聞き取り目を開けて自分の手のひらを出すと、丸い光は磁石のように引き寄せられて、フィンセントの手のひらの上に乗った。
丸い光が手のひらに乗ると、それはふっと形を変えて、薬のような小さな粒に変わる。
それをフィンセントは口にいれて、ごくんと飲み込んだ。飲み込んだ瞬間に、航の意識が少しずつ薄れていった。
目の前のフィンセントの顔が先ほどよりもどんどんぼやけていく。
だけど、フィンセントがまっすぐこっちを見ているのが航に分かる。
そしてフィンセントは航にこう言った。
「悲しみは僕が食べたから、心が軽くなったはずだよ。これから先は、強く生きるんだよ航くん。死にたがってると、晴れの日に僕が迎えにいかなきゃいけなくなるから」
フィンセントがそう言うと、航は完全に意識を失ってその場に倒れた。
――あれから数日たった小雨の日。
深夜二時。
フィンセントは、また着物姿でいつものように電柱の上に立っている。
ロンはフィンセントの肩に乗って、フィンセントと一緒に都会の街を眺めている。
「航くん、あれからよく笑うようになったんだって。環境もだいぶよくなったみたい」
ロンが静かに言い、フィンセントは微笑む。
詳細について、フィンセントは、あえてロンに触れなかった。
ロンは話を続ける。
「でもね、航くんがいくら幸せになったからといって、その後で悲しみを食べたフィンセントが苦しむ姿をやっぱり見るのが辛いよ。今回も大分苦しんでたじゃないか」
フィンセントは、肩に乗るロンを穏やかな目つきで見る。
「ありがとう、その時もそばにいてくれて」
「もう、雀の命も三年と短いんだからね。ひやひやするよ。ボクはまだその中で生きてるけど……でも僕が例えば死んでも、永遠の魂で何度生まれ変わろうとも、フィンセントの側にいてあげるよ」
「ロンは優しいんだね。晴れの日は、僕は人の命を奪う死神なのに」
ロンは、フィンセントを見る。
「でも、フィンセントは命を奪いたくて奪ってる訳じゃない」
「でも、死神だよ」
「う……うるさいなぁ。フィンセントは……フィンセントは死神というかボクの親友なの!!」
「……ありがとう、ロン」
雨は都会に降り続く。
「ねえフィンセント、また今日も悲しみを食べに行くの? 命を削っても……?」
フィンセントは、そっと頷く。
「うん。だって、今日は雨が降ってるからね」