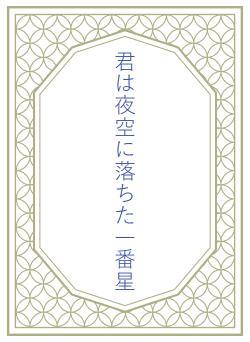最初に彼女を見たとき、思った――この人は、どこにも属していない。
召喚の間、玉座の上から光が降り注ぎ、僕たちは神の加護を授かった。
亜蓮君は剣を掲げ、理奈さんは光の粒をこぼすように笑っていた。
王も、兵士も、歓声を上げた。
その中で、彼女――藤堂美咲だけが、微動だにしなかった。
何も手に入らなかったくせに、敗北の顔をしていなかった。
泣かず、怒らず、ただそこに立っていた。
まるで、もともとこの場に呼ばれることを知っていたみたいに。
僕はその時、妙に気になった。
誰よりも地味で、誰よりも静かな女。
でも、どこか現実の匂いがした。
神も、加護も、希望も――全部知った上で、それを拒絶しているような。
そんな人間、初めて見た。
▽
勇者隊に配属されてからも、彼女は変わらなかった。
他の召喚者たちは浮かれていた。
異世界で、魔法を使えるようになって、王に褒められて。
それを当然のように享受していた。
でも彼女だけは、常に何かを警戒していた。
誰かが笑えば、目を細めて観察し、
誰かが剣を振れば、姿勢の癖を見抜く。
誰かが泣けば、何も言わずに背中を叩く。
無関心なようでいて、全部見ていた。
僕は――その目が好きだった。
他人を測るようでいて、どこか寂しげで。
世界を見下ろしているくせに、自分だけは【下】に置いているような目。
あの目に、僕が映った時。
なんだか、自分という存在が【現実】になった気がした。
▽
訓練の日。
亜蓮君が勝手に突っ込んで、模擬戦の結界を壊した。
僕は、少し離れた位置で見ていた。
火の粉が舞い、兵士たちの悲鳴が上がる。
あれは、混乱というより【事故】だった。
けれど、誰よりも早く動いたのは、美咲さんだった。
血を流して倒れた兵士に駆け寄り、布を裂き、圧迫止血をしていた。
その表情は、まるで戦場に戻ったみたいに冷たくて――美しかった。
手が震えていた。
でも、それでも止めようとしない。
口元が少しだけ引きつって、それでも、目だけは真っ直ぐだった。
あのとき僕は、心臓が動く音をはっきり聞いた。
――ああ、この人は、壊れてるんだ。
そう思った。
壊れてるのに、必死で保とうとしてる。
まるで壊れてないふりをすることでしか、生きられないみたいに。
そういう人間に、僕は惹かれる。
人が壊れていく瞬間って、綺麗だと思う。
理奈さんの光の魔法より、ずっと綺麗だった。
▽
その日を境に、美咲さんは勇者隊から外された。
「士気を下げた」「無能」「足手まとい」――そんな理由で。
兵士たちはざわつき、理奈はほっとした顔をしていた。
亜蓮は「せいせいした」と言い、茜は何も言わなかった。
僕は笑った。
あの人がいなくなると聞いて、心のどこかで嬉しかった。
やっと、観察する側から見守る側になれる気がしたから。
でも、いざ本当に出て行く姿を見た時――少し、息が詰まった。
荷物をまとめた小さな背中。
何も言わず、誰にも頼らず、ただ歩いていく姿。
その歩幅はゆっくりで、でも一度も迷わなかった。
亜蓮君が冷たく言い放ったときも、彼女は笑った。
あの笑い方、怒りでも哀しみでもない。
ただ「そうなることを分かっていた」人の笑い方。
――だから、あの瞬間、僕は心の中で叫んだ。
――行かないで!
でも、声にはならなかった。
代わりに、心の奥で何かがひび割れる音がした。
▽
夜、美咲さんの部屋に行った。
もう誰もいない部屋。
机の上に置かれた書状と、折り畳まれた上着。
彼女の匂いが、まだ残っていた。
焚き火の煙と、鉄と、古い革の匂い。
温度のない残り香が、やけに生々しかった。
「……嘘つきだな」
呟いた。
『傍にいる』とは言わなかったくせに、そんな気配を残していく。
僕の頭の中では、まだ彼女の声が響いていた。
――「私は死なない。ただ、ここじゃ生きられないだけだ」
なんでそんな風に言えるんだろう。
誰に向けて言ってるんだろう。
まるで、自分の死に場所を探してるみたいな言い方じゃないか。
胸の奥が、じくじくと痛んだ。
怖い。
けど、見たい。
あの人がどんな風に壊れていくのか、ちゃんと見届けたい。
そう思ってしまった自分に、心底ゾッとした。
でも、それでも止まらなかった。
召喚の間、玉座の上から光が降り注ぎ、僕たちは神の加護を授かった。
亜蓮君は剣を掲げ、理奈さんは光の粒をこぼすように笑っていた。
王も、兵士も、歓声を上げた。
その中で、彼女――藤堂美咲だけが、微動だにしなかった。
何も手に入らなかったくせに、敗北の顔をしていなかった。
泣かず、怒らず、ただそこに立っていた。
まるで、もともとこの場に呼ばれることを知っていたみたいに。
僕はその時、妙に気になった。
誰よりも地味で、誰よりも静かな女。
でも、どこか現実の匂いがした。
神も、加護も、希望も――全部知った上で、それを拒絶しているような。
そんな人間、初めて見た。
▽
勇者隊に配属されてからも、彼女は変わらなかった。
他の召喚者たちは浮かれていた。
異世界で、魔法を使えるようになって、王に褒められて。
それを当然のように享受していた。
でも彼女だけは、常に何かを警戒していた。
誰かが笑えば、目を細めて観察し、
誰かが剣を振れば、姿勢の癖を見抜く。
誰かが泣けば、何も言わずに背中を叩く。
無関心なようでいて、全部見ていた。
僕は――その目が好きだった。
他人を測るようでいて、どこか寂しげで。
世界を見下ろしているくせに、自分だけは【下】に置いているような目。
あの目に、僕が映った時。
なんだか、自分という存在が【現実】になった気がした。
▽
訓練の日。
亜蓮君が勝手に突っ込んで、模擬戦の結界を壊した。
僕は、少し離れた位置で見ていた。
火の粉が舞い、兵士たちの悲鳴が上がる。
あれは、混乱というより【事故】だった。
けれど、誰よりも早く動いたのは、美咲さんだった。
血を流して倒れた兵士に駆け寄り、布を裂き、圧迫止血をしていた。
その表情は、まるで戦場に戻ったみたいに冷たくて――美しかった。
手が震えていた。
でも、それでも止めようとしない。
口元が少しだけ引きつって、それでも、目だけは真っ直ぐだった。
あのとき僕は、心臓が動く音をはっきり聞いた。
――ああ、この人は、壊れてるんだ。
そう思った。
壊れてるのに、必死で保とうとしてる。
まるで壊れてないふりをすることでしか、生きられないみたいに。
そういう人間に、僕は惹かれる。
人が壊れていく瞬間って、綺麗だと思う。
理奈さんの光の魔法より、ずっと綺麗だった。
▽
その日を境に、美咲さんは勇者隊から外された。
「士気を下げた」「無能」「足手まとい」――そんな理由で。
兵士たちはざわつき、理奈はほっとした顔をしていた。
亜蓮は「せいせいした」と言い、茜は何も言わなかった。
僕は笑った。
あの人がいなくなると聞いて、心のどこかで嬉しかった。
やっと、観察する側から見守る側になれる気がしたから。
でも、いざ本当に出て行く姿を見た時――少し、息が詰まった。
荷物をまとめた小さな背中。
何も言わず、誰にも頼らず、ただ歩いていく姿。
その歩幅はゆっくりで、でも一度も迷わなかった。
亜蓮君が冷たく言い放ったときも、彼女は笑った。
あの笑い方、怒りでも哀しみでもない。
ただ「そうなることを分かっていた」人の笑い方。
――だから、あの瞬間、僕は心の中で叫んだ。
――行かないで!
でも、声にはならなかった。
代わりに、心の奥で何かがひび割れる音がした。
▽
夜、美咲さんの部屋に行った。
もう誰もいない部屋。
机の上に置かれた書状と、折り畳まれた上着。
彼女の匂いが、まだ残っていた。
焚き火の煙と、鉄と、古い革の匂い。
温度のない残り香が、やけに生々しかった。
「……嘘つきだな」
呟いた。
『傍にいる』とは言わなかったくせに、そんな気配を残していく。
僕の頭の中では、まだ彼女の声が響いていた。
――「私は死なない。ただ、ここじゃ生きられないだけだ」
なんでそんな風に言えるんだろう。
誰に向けて言ってるんだろう。
まるで、自分の死に場所を探してるみたいな言い方じゃないか。
胸の奥が、じくじくと痛んだ。
怖い。
けど、見たい。
あの人がどんな風に壊れていくのか、ちゃんと見届けたい。
そう思ってしまった自分に、心底ゾッとした。
でも、それでも止まらなかった。