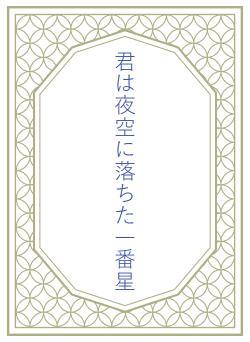夜の余韻が、まだ空気の中に残っていた。
焚き火の赤い火はとうに消え、灰になった木片だけがわずかなぬくもりを残している。
夜露に濡れた野草が、私の足元でやわらかく揺れた。
その上に、すとん、と小さな鞄を置く。
――やっと、朝か。
息を吐いて見上げた空には、二つの月が浮かんでいた。
一つは銀色で、透き通るように美しい。
もう一つは赤銅色で、どこか血のように鈍く光っている。
この世界では、それが「普通」なのだろう。
「……きれいだな。ここにも、朝は来るんだな」
思わず声に出していた。
その呟きは誰にも届かず、薄明の空に溶けていく。
昨夜、城を出てからは一言も喋っていない。
誰かと別れの言葉を交わす気にもなれなかった。
ただ歩いて、野営地を見つけて、火を焚いて、少しだけ横になった。
眠れなかった――火の音が消えたあとの沈黙が、耳の奥に痛いほど響いている。
夜は長く、冷たく、妙に静かだった。
城の喧騒や人の声があった頃が、まるで遠い昔のことのように思える。
それでも――。
(……生きてるだけ、まだマシか)
そんな言葉が自然に浮かんだ。
小さく自嘲して、鞄の紐を締め直す。
背に背負い直し、肩を軽く回す。筋肉が冷え切っていて、関節がぎしりと鳴った。
さて、歩こう。
そう思った瞬間――ふわり、と風に何かが舞い降りた。
「ん?」
乾いた紙の音が耳から聞こえた。
地面にひらりと落ちたのは、一枚の羊皮紙。
拾い上げてみると、黄ばんでいて、端が少し焦げている。
それでも、文字ははっきりと読めた。
――『家庭教師募集』。
思わず眉を上げた。
この世界にも求人広告なんてあるんだな、と。
さらに読み進める。
*年齢・性別不問。責任感ある方、歓迎。
*給与応相談。住み込み可。
*興味のある方は封蝋を押印し、返信を。
「……責任感、ね」
小さく笑ってしまった。
今さら、そんな言葉を自分に当てはめる人間なんて、どこにもいないと思っていたのに。
裏返すと、赤い封蝋が目に入る。
押された紋章は、見たことのない意匠だった。
二枚の翼が円を描くように重なり合い、黒く、鋭く尖っている。
羽根というより、刃のようだった。
「……変わった紋章だな」
そのときの私は、まだ知らなかった。
この紋章が『魔王国』の王家を示すものだなんて。
だが、そのときの私にとって、そんなことはどうでもよかった。
ただ――【仕事】がある。
その一点だけが、心を動かした。
地面に目を落とす。
破れかけたブーツ、擦り切れた袖。
ここには軍も、階級も、命令もない。
私はもう、誰の部下でもなければ、誰の味方でもない。
それでも。
「……仕事は、仕事だ」
自分でも驚くほど、声は静かだった。
もう誰にも命令されない。
誰かのために戦うとしても、それは私自身の意思で決める。
今度こそ、自分の足で立つために。
紙をゆっくりと折り畳み、鞄の中にしまった。
朝の風が吹く。
冷たい空気の中に、草の匂いと、どこか懐かしい焦げの匂いが混じっていた。
東の空が、淡い橙に染まり始める。
夜の名残を追い払うように、光が少しずつ地面を照らしていく。
私は顔を上げた。
目の前には、まだ何もない広い道。
誰もいない、けれど確かに続いている道。
「……行ってみる価値はあるかもな」
独り言のように呟き、歩き出す。
小さな鞄の中で、羊皮紙がかすかに鳴った。
新しい街へ。
見知らぬ世界へ。
そして――やがて私を【家族】と呼ぶことになる、あの奇妙な子供のもとへ。
運命は、もう静かに動き始めていた。
たった一枚の紙切れが、その扉を開くきっかけになるなんて――あの時の私は、知る由もなかった。
焚き火の赤い火はとうに消え、灰になった木片だけがわずかなぬくもりを残している。
夜露に濡れた野草が、私の足元でやわらかく揺れた。
その上に、すとん、と小さな鞄を置く。
――やっと、朝か。
息を吐いて見上げた空には、二つの月が浮かんでいた。
一つは銀色で、透き通るように美しい。
もう一つは赤銅色で、どこか血のように鈍く光っている。
この世界では、それが「普通」なのだろう。
「……きれいだな。ここにも、朝は来るんだな」
思わず声に出していた。
その呟きは誰にも届かず、薄明の空に溶けていく。
昨夜、城を出てからは一言も喋っていない。
誰かと別れの言葉を交わす気にもなれなかった。
ただ歩いて、野営地を見つけて、火を焚いて、少しだけ横になった。
眠れなかった――火の音が消えたあとの沈黙が、耳の奥に痛いほど響いている。
夜は長く、冷たく、妙に静かだった。
城の喧騒や人の声があった頃が、まるで遠い昔のことのように思える。
それでも――。
(……生きてるだけ、まだマシか)
そんな言葉が自然に浮かんだ。
小さく自嘲して、鞄の紐を締め直す。
背に背負い直し、肩を軽く回す。筋肉が冷え切っていて、関節がぎしりと鳴った。
さて、歩こう。
そう思った瞬間――ふわり、と風に何かが舞い降りた。
「ん?」
乾いた紙の音が耳から聞こえた。
地面にひらりと落ちたのは、一枚の羊皮紙。
拾い上げてみると、黄ばんでいて、端が少し焦げている。
それでも、文字ははっきりと読めた。
――『家庭教師募集』。
思わず眉を上げた。
この世界にも求人広告なんてあるんだな、と。
さらに読み進める。
*年齢・性別不問。責任感ある方、歓迎。
*給与応相談。住み込み可。
*興味のある方は封蝋を押印し、返信を。
「……責任感、ね」
小さく笑ってしまった。
今さら、そんな言葉を自分に当てはめる人間なんて、どこにもいないと思っていたのに。
裏返すと、赤い封蝋が目に入る。
押された紋章は、見たことのない意匠だった。
二枚の翼が円を描くように重なり合い、黒く、鋭く尖っている。
羽根というより、刃のようだった。
「……変わった紋章だな」
そのときの私は、まだ知らなかった。
この紋章が『魔王国』の王家を示すものだなんて。
だが、そのときの私にとって、そんなことはどうでもよかった。
ただ――【仕事】がある。
その一点だけが、心を動かした。
地面に目を落とす。
破れかけたブーツ、擦り切れた袖。
ここには軍も、階級も、命令もない。
私はもう、誰の部下でもなければ、誰の味方でもない。
それでも。
「……仕事は、仕事だ」
自分でも驚くほど、声は静かだった。
もう誰にも命令されない。
誰かのために戦うとしても、それは私自身の意思で決める。
今度こそ、自分の足で立つために。
紙をゆっくりと折り畳み、鞄の中にしまった。
朝の風が吹く。
冷たい空気の中に、草の匂いと、どこか懐かしい焦げの匂いが混じっていた。
東の空が、淡い橙に染まり始める。
夜の名残を追い払うように、光が少しずつ地面を照らしていく。
私は顔を上げた。
目の前には、まだ何もない広い道。
誰もいない、けれど確かに続いている道。
「……行ってみる価値はあるかもな」
独り言のように呟き、歩き出す。
小さな鞄の中で、羊皮紙がかすかに鳴った。
新しい街へ。
見知らぬ世界へ。
そして――やがて私を【家族】と呼ぶことになる、あの奇妙な子供のもとへ。
運命は、もう静かに動き始めていた。
たった一枚の紙切れが、その扉を開くきっかけになるなんて――あの時の私は、知る由もなかった。