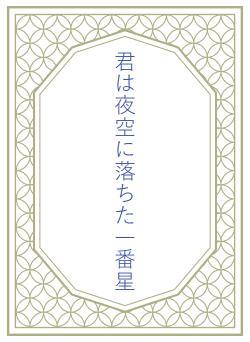静かな夜だった。
窓の外では、城下町の灯が遠く瞬いている。
昼間の訓練の騒ぎが嘘のように、今はただ静寂だけが部屋を満たしていた。
私は小さな鞄を机に置き、黙って布を畳んでいた。
寝巻きも、戦場で拾った癖のある生活用品も全部まとめて袋に押し込む。
――扉を叩く音、その静けさを破るように重い声が響いた。
「入るぞ」
そこに立っていたのは王の側近である、宰相バルザックと言う男だった。
鎧の金属音が、石の床に鈍く反響する。
「お前は役立たずの存在となった」
乾いた声、その言葉は刃より鋭く感じた。
「明日から勇者たち……いや、この国を離れよ。これは王命である」
「ああ、了解した」
書状が机の上に置かれる。
『士気を下げた』『戦意を阻害した』――まるで判決書のような文字。
私は一言も反論しなかった。
ただ、それを見下ろし、素直に受け取る。
「何か申し開きはあるか?」
「ないよ。国の方針なら従うしかないからね」
怯えも怒りもなかった。
ただ、静かに受け入れた。
その姿がかえって気に障ったのか、バルザックは鼻で笑う。
「ふん……年増の女に勇者の補佐が務まると思った我々が愚かだったな」
吐き捨てるように続けた。
「無駄に冷静ぶって若者の士気を削ぐ。年齢だけ重ねて中身は空っぽ。剣も振れず、魔法も使えず、戦場で役にも立たん――お前は、この国に不要な荷物だ」
侮蔑と倦怠の混じった声。
けれど、私はまばたきひとつしなかった。
「……そうか。荷物なら早めに下ろして正解だな」
皮肉でも挑発でもない。
ただ、事実を言っただけだ。
バルザックは眉をひそめ、吐き捨てるように言い残した。
「二度とこの城の敷居を跨ぐな。平民の世話でもして生きるがいい」
重い扉が閉まり、冷気だけが部屋に残った。
私はふっと笑った。
「役立たず、か……まぁ、わかってたけどね。戦いになるなら、負ける気はしなかったんだけどな」
独り言を落とし、背伸びをする。
窓の外を見ると雲を裂いて月が浮かんでいた。
戦場の夜とは違う――今度は、自分から離れていける夜だ。
(また、失うのかな……)
一瞬だけ胸が刺すように痛んだ。
けれどすぐに息を整える。
(生きてるだけ、まだマシだ)
鞄の紐を締めた時、外の廊下で足音がした。
振り向くと、亜蓮が立っていた。
「よかったな、ババア。これで足手まといがいなくなる」
そこには少年特有の傲慢な笑み。
けれど、どこかに焦りの影が見えた。
「……ああ。あんたたちの【戦場】がどんな場所か、すぐわかるよ」
「何っ……」
「そして、自分が愚かだったって言うのも、すぐにね」
一応、忠告のつもりだった。
亜蓮は舌打ちし、何も言わずに去っていった。
その背を見送る影の中に、銀髪の青年が立っていた。
以前、声をかけてくれたあの青年だ。
「……あなたのような大人が、この国には必要だったのに」
「私はただ、年を取っただけですよ……ええっと」
「私はエルディス。この国の第二王子だ」
「お、王子様でしたか。すみません」
「ああ、固くならなくていい。本当にすまない……しかし、私には止める権利がない」
申し訳なさそうに言う彼に、私は淡く笑った。
「年を取れば、誰だって何を守るか選ぶようになります」
エルディスは黙り、深く頭を下げて立ち去っていった。
廊下に灯る火が、心細く揺れる。
――その時、駆け足の音。
「美咲さん!!」
息を切らして望が飛び込んできた。
目には涙がにじんでいる。
「……もう寝る時間だぞ、望」
「嘘だ!出ていくって聞いた!本当なの!?」
そのまま抱きつかれた。
強く、強く、まるで腕の中から逃げられるのを恐れるように。
「傍にいてくれるって言ったじゃない!」
私は苦笑する。
「うーん……言った覚えはないんだけどな」
「言ったよ! 言ったのに……!もっともっと美咲さんが壊れていくの、見たい!」
「……望、それはだいぶズレてるぞ」
指がぴくりと動く。
望は無邪気な声で笑い続けた。
「だって、あの時の顔、すごく綺麗だったもん!泣きそうで、でも笑ってて……もっと見せてよ、美咲さんが壊れてくの! 僕だけにさ!」
「聞かなかったことにしておくな、望」
私は両耳を軽く押さえる。
望は笑いながら体を揺らし、まるで遊んでいるようで――どこか壊れていた。
「……まったく、どうしてこうも手のかかる子ばかりなんだろうな」
頭を撫でると、望はますます強く抱きしめてきた。
その腕には、子どもの甘えではなく、独占欲が滲んでいた。
「もう遅い。泣くな、望」
「でも……!」
「私は死なないよ。ただ、ここじゃ生きられないだけだ」
望は涙を拭い、かすれた声で呟いた。
「……絶対に、美咲さんを取り戻すからね。誰が邪魔しても、どこに逃げても――絶対に!」
その言葉には、幼さと狂気が同居していた。
私は淡々と、呆れたように返す。
「いや、求めてないから大丈夫だぞ、望」
それでも彼は笑った。
けれど、目は笑っていなかった。
私はその顔を見つめ、最後にひとつだけ呟いた。
「望を置いていくのも怖いが……この歳で無職は、きついなぁ」
そう言って私は鞄を肩にかけ、静かに部屋を後にした。
窓の外では、城下町の灯が遠く瞬いている。
昼間の訓練の騒ぎが嘘のように、今はただ静寂だけが部屋を満たしていた。
私は小さな鞄を机に置き、黙って布を畳んでいた。
寝巻きも、戦場で拾った癖のある生活用品も全部まとめて袋に押し込む。
――扉を叩く音、その静けさを破るように重い声が響いた。
「入るぞ」
そこに立っていたのは王の側近である、宰相バルザックと言う男だった。
鎧の金属音が、石の床に鈍く反響する。
「お前は役立たずの存在となった」
乾いた声、その言葉は刃より鋭く感じた。
「明日から勇者たち……いや、この国を離れよ。これは王命である」
「ああ、了解した」
書状が机の上に置かれる。
『士気を下げた』『戦意を阻害した』――まるで判決書のような文字。
私は一言も反論しなかった。
ただ、それを見下ろし、素直に受け取る。
「何か申し開きはあるか?」
「ないよ。国の方針なら従うしかないからね」
怯えも怒りもなかった。
ただ、静かに受け入れた。
その姿がかえって気に障ったのか、バルザックは鼻で笑う。
「ふん……年増の女に勇者の補佐が務まると思った我々が愚かだったな」
吐き捨てるように続けた。
「無駄に冷静ぶって若者の士気を削ぐ。年齢だけ重ねて中身は空っぽ。剣も振れず、魔法も使えず、戦場で役にも立たん――お前は、この国に不要な荷物だ」
侮蔑と倦怠の混じった声。
けれど、私はまばたきひとつしなかった。
「……そうか。荷物なら早めに下ろして正解だな」
皮肉でも挑発でもない。
ただ、事実を言っただけだ。
バルザックは眉をひそめ、吐き捨てるように言い残した。
「二度とこの城の敷居を跨ぐな。平民の世話でもして生きるがいい」
重い扉が閉まり、冷気だけが部屋に残った。
私はふっと笑った。
「役立たず、か……まぁ、わかってたけどね。戦いになるなら、負ける気はしなかったんだけどな」
独り言を落とし、背伸びをする。
窓の外を見ると雲を裂いて月が浮かんでいた。
戦場の夜とは違う――今度は、自分から離れていける夜だ。
(また、失うのかな……)
一瞬だけ胸が刺すように痛んだ。
けれどすぐに息を整える。
(生きてるだけ、まだマシだ)
鞄の紐を締めた時、外の廊下で足音がした。
振り向くと、亜蓮が立っていた。
「よかったな、ババア。これで足手まといがいなくなる」
そこには少年特有の傲慢な笑み。
けれど、どこかに焦りの影が見えた。
「……ああ。あんたたちの【戦場】がどんな場所か、すぐわかるよ」
「何っ……」
「そして、自分が愚かだったって言うのも、すぐにね」
一応、忠告のつもりだった。
亜蓮は舌打ちし、何も言わずに去っていった。
その背を見送る影の中に、銀髪の青年が立っていた。
以前、声をかけてくれたあの青年だ。
「……あなたのような大人が、この国には必要だったのに」
「私はただ、年を取っただけですよ……ええっと」
「私はエルディス。この国の第二王子だ」
「お、王子様でしたか。すみません」
「ああ、固くならなくていい。本当にすまない……しかし、私には止める権利がない」
申し訳なさそうに言う彼に、私は淡く笑った。
「年を取れば、誰だって何を守るか選ぶようになります」
エルディスは黙り、深く頭を下げて立ち去っていった。
廊下に灯る火が、心細く揺れる。
――その時、駆け足の音。
「美咲さん!!」
息を切らして望が飛び込んできた。
目には涙がにじんでいる。
「……もう寝る時間だぞ、望」
「嘘だ!出ていくって聞いた!本当なの!?」
そのまま抱きつかれた。
強く、強く、まるで腕の中から逃げられるのを恐れるように。
「傍にいてくれるって言ったじゃない!」
私は苦笑する。
「うーん……言った覚えはないんだけどな」
「言ったよ! 言ったのに……!もっともっと美咲さんが壊れていくの、見たい!」
「……望、それはだいぶズレてるぞ」
指がぴくりと動く。
望は無邪気な声で笑い続けた。
「だって、あの時の顔、すごく綺麗だったもん!泣きそうで、でも笑ってて……もっと見せてよ、美咲さんが壊れてくの! 僕だけにさ!」
「聞かなかったことにしておくな、望」
私は両耳を軽く押さえる。
望は笑いながら体を揺らし、まるで遊んでいるようで――どこか壊れていた。
「……まったく、どうしてこうも手のかかる子ばかりなんだろうな」
頭を撫でると、望はますます強く抱きしめてきた。
その腕には、子どもの甘えではなく、独占欲が滲んでいた。
「もう遅い。泣くな、望」
「でも……!」
「私は死なないよ。ただ、ここじゃ生きられないだけだ」
望は涙を拭い、かすれた声で呟いた。
「……絶対に、美咲さんを取り戻すからね。誰が邪魔しても、どこに逃げても――絶対に!」
その言葉には、幼さと狂気が同居していた。
私は淡々と、呆れたように返す。
「いや、求めてないから大丈夫だぞ、望」
それでも彼は笑った。
けれど、目は笑っていなかった。
私はその顔を見つめ、最後にひとつだけ呟いた。
「望を置いていくのも怖いが……この歳で無職は、きついなぁ」
そう言って私は鞄を肩にかけ、静かに部屋を後にした。