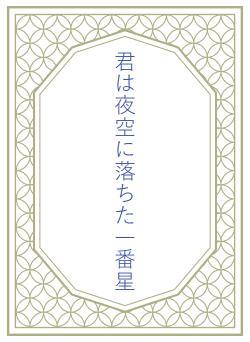召喚から一週間、王都の訓練場では今日も勇者たちが歓声を浴びていた。
稲葉亜蓮が剣を振るい、魔法の光を纏いながら木製の標的を叩き割る。
その後ろで、加藤理奈が神官服を翻し、癒しの光で彼の肩の傷を瞬時に治した。
「やっぱ俺たち、最強じゃね?」
「ふふん、当たり前じゃない。神の加護を授かったんだから」
互いに笑い合いながら、誇らしげに手を振る二人。
兵士たちは拍手を送り、神官たちは跪いて祈りを捧げている――だけど、私にはその光景がまるで悪夢に見えた。
(……一週間で、ここまで酔うのか)
力を与えられた子どもほど、扱いを誤る。
それを何度、現実の戦場で見てきただろう。
訓練場の隅で腕を組み、私は勇者たちを眺めていた。
亜蓮が剣を振り、理奈が光を操り、茜が支援魔法を展開する。
周囲の兵士たちは称賛し、神官たちは神の奇跡と讃えていた。
――だが、誰も気づいていない、その瞳に宿り始めた傲慢を。
「……彼ら、まるで子どもみたいだね」
隣から声がしたので振り向くと、斎藤望が立っていた。
分厚い魔導書を抱え、冷めた目で訓練場を見下ろしている。
「まぁ、子どもだからな……お前もだろう、望?」
「はは、そうですね」
柔らかく笑うその声に、どこか芯のない響きを感じる。
私は短く答えた。
「力を与えられた人間が最初にするのは、敵を倒すことじゃない――自分の力を試すことだ」
望は小さく口角を上げる。
穏やかな笑みなのに、どこか観察者めいていた。
「……美咲さんは、見えてますね?」
「何がだ?」
「ここにある危うさですよ。でも、僕は嫌いじゃない、人が慢心していく姿を見るのって……面白いですから」
その言葉に、私は眉をひそめた。
彼の声は優しい。
けれど、その奥に潜むのは、好奇心か、あるいは――狂気か。
(一番危ないのが、やっぱり望だな)
そう思いながらも、言葉にはしなかった。
▽
「王国兵との連携訓練、開始!」
訓練官の号令に、空気が熱を帯びる。
勇者班と兵士隊が陣を組み、模擬戦が始まった。
「亜蓮、前に出るな。まず陣形を整えろ。補給線を確保して――」
私は冷静に声をかける。
だが返ってきたのは、鼻で笑う声だった。
「うるせぇな。戦いのことなら俺に任せとけよババア」
理奈も笑いながら光の魔法を構える。
「現実の戦争と違うんだし、もっと派手にいこうよ!」
茜だけが小さく眉を寄せた。
「でも……一応、藤堂さんの言ってることも――」
「茜、あんたまであのおばさんの味方すんの?」
理奈の声が鋭く響く。
茜は唇を噛んで黙り込んだ。
「行くぞ、突撃だ!」
亜蓮の叫びと同時に、光が弾けた。
轟音、爆風、そして結界を突き破る閃光――模擬のはずの戦場が、瞬く間に【現実】へ変わる。
砂煙、焦げた匂い、そして聞こえてくる悲鳴。
灼けた鉄と血の臭気が鼻を突いた。
(まただ……結局、どの世界でも戦場は変わらない)
「や、やべ……そんなつもりじゃ――!」
「亜蓮!後ろ見て!」
理奈の声が裏返る。
地面に倒れた兵士の肩には、木片が深く突き刺さっていた。
赤い色がじわりと石畳に広がっていく。
私は考えるより先に走っていた。
膝をつき、布を裂き、血を押さえつける。
「大丈夫動かないで。すぐ圧迫する」
声は冷静だった。
けれど、胸の奥では心臓が痛いほど鳴っている。
何度も繰り返した動作――でも、救った命より救えなかった顔の方が記憶に残る。
「……あの人、本当に何者なんだ?」
「軍医のようだな……」
周囲がざわめく。
けれど、輪の外から理奈の叫びが響いた。
「この人が余計なこと言うからよ!私たち、調子狂ったじゃない!」
震える声。恐怖と責任の色が混じっている。
茜が口を開きかける。
「でも……彼女の言ってた通りにしていれば――」
「黙ってて!」
理奈の怒声に、空気が一瞬で冷えた。
私は何も言わず、ただ血を押さえる手に力を込めた。
焦げた空気の中で、血の温度だけが妙に生々しい。
(……これが、【勇者】か)
遠くで神官たちが記録を取っている。
無機質な目、まるで死体の数でも数えるように。
(多分、きっとそろそろ私はいらない存在になるだろうな)
そう思った時、背後から声がした。
「……やっぱり、美咲さんは綺麗だよ」
突然の声に、振り返る。
そこに望が立っていた。
淡い光を背に、静かに笑っている。
「戦ってる時の美咲さんが、一番綺麗だ」
その言葉で指先が止まる。
その声は優しいのに、底が見えない。
壊れていくモノに恋するような眼をしていた。
「望……今は、そういう話をしてる場合じゃない」
「いや、僕はあなたがどう壊れていくのか、ちゃんと見ておきたくて」
「何を――」
言いかけた瞬間、空気が止まった。
世界の音が消え、望の姿が別の何かに見える。
瞳が、氷のように光を失っていた。
「……僕は戻りますね、美咲さん」
柔らかく笑い、背を向ける。
その笑みが、ひどく冷たく感じた。
私は深く息を吐く。
手の中の血の温度だけが、私を現実につなぎ止めていた。
だが、沈黙を破るように背後から声が落ちた。
「すまない、君……名は?」
振り返ると、銀髪の青年が立っていた。
紺のマントに王家の紋章を刻み陽光を背に受けている。
その姿は絵画のようで、近づく風さえ息を潜めた。
「……藤堂美咲です。ミサキで構いません」
「そうか――君のような人を、もっと早く知りたかった」
その声は、まるで救いのように響いた。
けれど、私は知っている。
優しさの裏にこそ、世界を変える力が潜んでいることを。
兵士たちがひざまずき、神官が祈りを捧げる。
夕陽の赤が、白い城壁を染めた。
(ああ……やっぱり)
その光は、戦場の火と同じ色だ。
(……戦場に戻るのは、嫌だなぁ)
稲葉亜蓮が剣を振るい、魔法の光を纏いながら木製の標的を叩き割る。
その後ろで、加藤理奈が神官服を翻し、癒しの光で彼の肩の傷を瞬時に治した。
「やっぱ俺たち、最強じゃね?」
「ふふん、当たり前じゃない。神の加護を授かったんだから」
互いに笑い合いながら、誇らしげに手を振る二人。
兵士たちは拍手を送り、神官たちは跪いて祈りを捧げている――だけど、私にはその光景がまるで悪夢に見えた。
(……一週間で、ここまで酔うのか)
力を与えられた子どもほど、扱いを誤る。
それを何度、現実の戦場で見てきただろう。
訓練場の隅で腕を組み、私は勇者たちを眺めていた。
亜蓮が剣を振り、理奈が光を操り、茜が支援魔法を展開する。
周囲の兵士たちは称賛し、神官たちは神の奇跡と讃えていた。
――だが、誰も気づいていない、その瞳に宿り始めた傲慢を。
「……彼ら、まるで子どもみたいだね」
隣から声がしたので振り向くと、斎藤望が立っていた。
分厚い魔導書を抱え、冷めた目で訓練場を見下ろしている。
「まぁ、子どもだからな……お前もだろう、望?」
「はは、そうですね」
柔らかく笑うその声に、どこか芯のない響きを感じる。
私は短く答えた。
「力を与えられた人間が最初にするのは、敵を倒すことじゃない――自分の力を試すことだ」
望は小さく口角を上げる。
穏やかな笑みなのに、どこか観察者めいていた。
「……美咲さんは、見えてますね?」
「何がだ?」
「ここにある危うさですよ。でも、僕は嫌いじゃない、人が慢心していく姿を見るのって……面白いですから」
その言葉に、私は眉をひそめた。
彼の声は優しい。
けれど、その奥に潜むのは、好奇心か、あるいは――狂気か。
(一番危ないのが、やっぱり望だな)
そう思いながらも、言葉にはしなかった。
▽
「王国兵との連携訓練、開始!」
訓練官の号令に、空気が熱を帯びる。
勇者班と兵士隊が陣を組み、模擬戦が始まった。
「亜蓮、前に出るな。まず陣形を整えろ。補給線を確保して――」
私は冷静に声をかける。
だが返ってきたのは、鼻で笑う声だった。
「うるせぇな。戦いのことなら俺に任せとけよババア」
理奈も笑いながら光の魔法を構える。
「現実の戦争と違うんだし、もっと派手にいこうよ!」
茜だけが小さく眉を寄せた。
「でも……一応、藤堂さんの言ってることも――」
「茜、あんたまであのおばさんの味方すんの?」
理奈の声が鋭く響く。
茜は唇を噛んで黙り込んだ。
「行くぞ、突撃だ!」
亜蓮の叫びと同時に、光が弾けた。
轟音、爆風、そして結界を突き破る閃光――模擬のはずの戦場が、瞬く間に【現実】へ変わる。
砂煙、焦げた匂い、そして聞こえてくる悲鳴。
灼けた鉄と血の臭気が鼻を突いた。
(まただ……結局、どの世界でも戦場は変わらない)
「や、やべ……そんなつもりじゃ――!」
「亜蓮!後ろ見て!」
理奈の声が裏返る。
地面に倒れた兵士の肩には、木片が深く突き刺さっていた。
赤い色がじわりと石畳に広がっていく。
私は考えるより先に走っていた。
膝をつき、布を裂き、血を押さえつける。
「大丈夫動かないで。すぐ圧迫する」
声は冷静だった。
けれど、胸の奥では心臓が痛いほど鳴っている。
何度も繰り返した動作――でも、救った命より救えなかった顔の方が記憶に残る。
「……あの人、本当に何者なんだ?」
「軍医のようだな……」
周囲がざわめく。
けれど、輪の外から理奈の叫びが響いた。
「この人が余計なこと言うからよ!私たち、調子狂ったじゃない!」
震える声。恐怖と責任の色が混じっている。
茜が口を開きかける。
「でも……彼女の言ってた通りにしていれば――」
「黙ってて!」
理奈の怒声に、空気が一瞬で冷えた。
私は何も言わず、ただ血を押さえる手に力を込めた。
焦げた空気の中で、血の温度だけが妙に生々しい。
(……これが、【勇者】か)
遠くで神官たちが記録を取っている。
無機質な目、まるで死体の数でも数えるように。
(多分、きっとそろそろ私はいらない存在になるだろうな)
そう思った時、背後から声がした。
「……やっぱり、美咲さんは綺麗だよ」
突然の声に、振り返る。
そこに望が立っていた。
淡い光を背に、静かに笑っている。
「戦ってる時の美咲さんが、一番綺麗だ」
その言葉で指先が止まる。
その声は優しいのに、底が見えない。
壊れていくモノに恋するような眼をしていた。
「望……今は、そういう話をしてる場合じゃない」
「いや、僕はあなたがどう壊れていくのか、ちゃんと見ておきたくて」
「何を――」
言いかけた瞬間、空気が止まった。
世界の音が消え、望の姿が別の何かに見える。
瞳が、氷のように光を失っていた。
「……僕は戻りますね、美咲さん」
柔らかく笑い、背を向ける。
その笑みが、ひどく冷たく感じた。
私は深く息を吐く。
手の中の血の温度だけが、私を現実につなぎ止めていた。
だが、沈黙を破るように背後から声が落ちた。
「すまない、君……名は?」
振り返ると、銀髪の青年が立っていた。
紺のマントに王家の紋章を刻み陽光を背に受けている。
その姿は絵画のようで、近づく風さえ息を潜めた。
「……藤堂美咲です。ミサキで構いません」
「そうか――君のような人を、もっと早く知りたかった」
その声は、まるで救いのように響いた。
けれど、私は知っている。
優しさの裏にこそ、世界を変える力が潜んでいることを。
兵士たちがひざまずき、神官が祈りを捧げる。
夕陽の赤が、白い城壁を染めた。
(ああ……やっぱり)
その光は、戦場の火と同じ色だ。
(……戦場に戻るのは、嫌だなぁ)