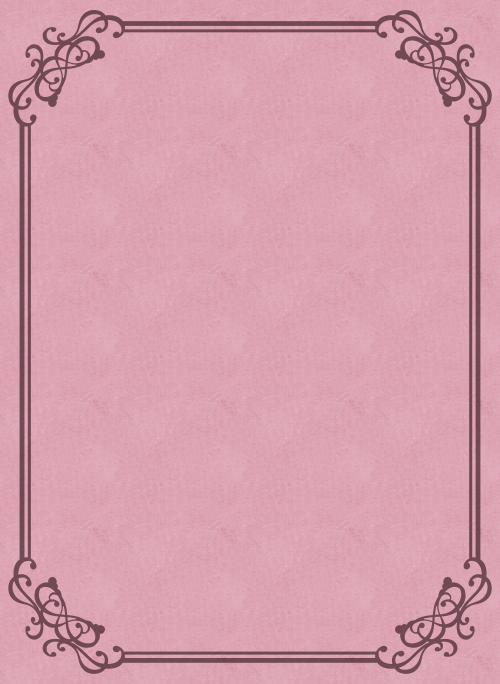俺は、ずっと今まで一人で生きてきた。
だって、友達も恋人もいなかったから。
「裕太せーんぱいっ!帰りますよ!」
こうやって、初めて慕ってくれる後輩ができて………って、なぜ慕われてんだ?
「なぁ、なんで俺に興味持ったんだよ」
「えー?なんでかって?」
ここで、少し溜めるから余計気になるだろ。
「この学校って共学じゃないですか、僕、正直な話割と1年の中では有名なほうなんです、注目浴びがちというか」
「まぁ、想像はつく」
「あはは…ですよね。割とモテるんですよ、2年とか3年の先輩からも告白されたりとかありますよ」
「……モテ自慢大会?」
「まだです、終わってません聞いてください。……先輩って名前と顔覚えないじゃないですか、興味深かったんですよ。僕のこと興味持たない人間がいるのかなって」
「……まぁ、誰にも興味は無いな」
「でも、顔は覚えてくれたじゃないですか、知りたかったんですよ!」
「……顔は覚えたと言うより、ほかに寄ってくる人居ないからさすがに気付くけど」
「……僕のこと興味ありませんか?」
「ないと言われればないし、なんで俺に興味持ったのか気になると言えば気になるし、ただまぁ、すぐ飽きるんだろうなとは思ってる」
「…ひどい。ねえ裕太先輩」
一緒に歩いて帰ってる途中に、周りに人がいない路地に引っ張られたかと思うと、後輩は俺の制服のネクタイを引っ張った。
「…ちょ、く、苦しいって、なんだよ…」
「裕太先輩、顔、こっち見て」
「……っ……」
唇に温かい柔らかい感触に、初めての感覚を覚える。
「裕太先輩が振り向いてくれないのがいけないんですからね」
「……お前っ…、恋人でもねえのに変なことすんなよ…!」
「先輩、僕に口聞いていいと思ってるんですか?」
「逆だろ普通」
「ほら、すぐそうやって反発する、本当は今まで誰かに甘えたかったんじゃないんですか」
「……く、くるしい……」
ネクタイを引っ張られてる間、ずっと主導権が後輩にあるのが悔しい。
でも、悪い気は…………しない。
「先輩、欲しそうな顔してますよ、ほらこっち向いて」
「………んんっ………」
「先輩の甘えた声、大好き」
「……うっせ…」
「今日はこの辺にしておきます。また明日校門前で待ってますから、明日は早く来てくださいよ」
そう言って、強く抱きしめられた。
「………気が向いたら」