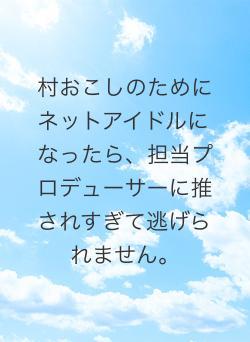「ご馳走様」
玲乃がその後もずっと「あーん」の催促をしてきたので、僕は幼児に離乳食を食べさせるようにして餌付けをしていた。
その間、自分の分を食べる余裕はなくてまだ僕のお腹は減ったままだった。
ずっと腕を曲げて玲乃に餌付けをしていたからか、右肘がびいんと痺れていた。それを悟られないように机の下に手を引っ込めた。
「っひゃ!」
不意に、つんつんと玲乃が僕の腕をつついてきた。ぴりりっと電流が流れるように右肘が悲鳴をあげる。
僕は「うぅ」と呻き声を上げて玲乃の顔を見上げる。するとその顔は悪戯っ子のように口をによによと引き上げている。少しむすっと膨れた僕は、好き放題してくる玲乃に牽制をする。
「もうちょっかいかけるのやめて。お腹空いたから僕もご飯が冷めないうちに食べたい。さっきからずっと玲乃ばっかり食べてる」
「……」
珍しく僕が反抗したせいか玲乃はぽかんと口を開いて数秒固まった。しかし、次第にくくくと喉の奥で笑う声が聞こえてきて僕はさらにむくれてしまう。
「そんなほっぺぷくぷくにして言われてもノーダメージだから、睦の気が済むまでもっとやりなよ」
僕の怒りの沸点が許容量のコップから溢れた瞬間だった。
「もう僕怒ったからね。今日はご飯食べたらすぐ帰るからっ!」
するとさっきまでくすくす笑っていた玲乃の表情が凍りついた。
ふやけた頬をゆっくり落として唇を真一文字に結ぶ。目線は次第に下がり睫毛が微かに震えているのが見えて、僕は言いすぎたかなと心配になる。
「か、代わりに玲乃が僕にあーんってしてくれたら許してあげないでもない……よ」
僕の精一杯の譲歩だった。後半は尻すぼみになっていたのできちんと玲乃の耳に届いたか多少不安ではあるが、玲乃がぱぁあっと表情を明るくさせたのでちゃんと聞こえていたことに安堵する。
そのとき「なんで僕が安心してるんだろう? 元はと言えば玲乃にちょっかいかけられてむすむすしてたのは僕のほうなのに」と疑問すら浮かぶ。
そんな僕をよそに、玲乃は自分の椅子を僕の隣に置いて座り満面の笑顔で「あーん」とムニエルをフォークにのせて食べさせてくれる。
「はい。あーん」
「……ん」
すっかり玲乃のペースに持っていかれた僕は、もっもっ、と玲乃が与えてくれる食事を味わう。お腹が八分目くらいになった頃、僕は静かに「ご馳走様でした」と玲乃に伝えた。
「わ。完食じゃん。苦手なミニトマトも食べられて睦は偉いねー」
「っ……だって拒否しても玲乃が口に突っ込んでくるから仕方なく、だよ」
サラダの底に隠されていた赤いピンポン玉くらいの大きさのミニトマトが僕の苦手な食べ物だ。
それを知っているから玲乃はあえてこんもりとベビーリーフやサニーレタスをミニトマトに被せて隠していたのだろう。
「はは。散歩拒否する黒いポメラニアンみたいな顔してて見てて癒されたよ」
「無意識に煽るのやめてよ。それ玲乃の悪い癖だよ」
いたって本人は思ったことを口に出しているだけなのだろうが、人を不快にさせていることも確かだ。幼い頃から玲乃の隣にいるから玲乃の性格や得意なこと、不得意なことをよく知っている。
「ふぁー。食った食った」
洗い物を終えた玲乃がリビングのソファにばたんきゅーしてきた。
3人がけのソファの隅っこで体育座りをしていた僕の身体がぴょこんと波打つ。
バランスを崩して玲乃のお尻に頭をぶつけて「うっ」と変な声が洩れた。おでこを押さえて鈍い痛みに耐えていると、目の前に黒い影が伸びてきた。はっとして顔を上げれば玲乃が神妙な面持ちで僕の顔を覗きこんできていた。
「なっ、何?」
まじまじと何も言わずに見つめてくる玲乃の本意がわからずにじりじりと後ろに下がれば、玲乃もぐーっと顔を近づけてきて僕は逃げられなくなった。
「いや。前髪伸びたなーって」
「っ!」
さらりと前髪をかきあげられおでこが露わになる。そのままおでこの上を柔らかくマッサージされてしまい、僕の身体の力が抜けてソファに身体が溶けていく。
「睦。ふにゃふにゃになっちゃったね」
玲乃のマッサージはすごく上手で、まるで美容院で髪を洗ってもらったりヘッドスパを受けている感覚になるのだ。
「黒髪さらさらでいいね。まさに清楚って感じする。天使のわっかできてるし、つやつやだし、前世は黒ポメラニアンだったのかな?」
耳元で囁いてくるから、距離が近くて動揺してしまう。僕は何も言えずに目線を下げていた。おでこをつん、と人差し指で小突かれて後ろへ仰け反る。
「わっ」
ソファの端から落下した。僕は襲ってくるであろう床に叩きつけられる痛みを想像して、慌ててぎゅっと頭を両腕で抱えた。目をきゅっとつむり身体を縮こませる。
しかし、数秒待っても痛みは襲ってこない。その代わりに背中に回された腕が熱くて、触れるところから体温が伝わってきて胸の奥がきゅっと締め付けられた。
「あっぶな。ごめんね。落としちゃうとこだった」
「……あ、ありがとう」
ソファから落ちるところを玲乃が抱きとめてくれたらしい。
玲乃の制服のワイシャツの隙間から放たれた甘い匂いが鼻を掠めた。玲乃のお気にいりの香水だった。バニラの香りに包まれ僕の身体の力が抜けていく。ワイシャツ越しに玲乃の硬い胸まわりが伝わってきて、玲乃は綺麗な顔をしていても男の人なんだなあと思い知る。
「……玲乃?」
ソファからの落下を防いでくれたことには感謝しつつも、未だに離れる素振りのない玲乃に僕は小さく呼びかける。
突如すんすん、と僕の耳元に鼻を近づけてきた。心臓がばくん、と一際大きく跳ね上がる。身体中の血液が心臓と顔に集まっていくような感覚にぱっと顔を伏せた。
「睦、いい匂いする。ねえ、今日も『あれ』して欲しいな」
『あれ』というのは僕と玲乃だけに伝わる秘密の言葉だ。僕は目を右と左に泳がせながらこくんと頷き返した。
玲乃がその後もずっと「あーん」の催促をしてきたので、僕は幼児に離乳食を食べさせるようにして餌付けをしていた。
その間、自分の分を食べる余裕はなくてまだ僕のお腹は減ったままだった。
ずっと腕を曲げて玲乃に餌付けをしていたからか、右肘がびいんと痺れていた。それを悟られないように机の下に手を引っ込めた。
「っひゃ!」
不意に、つんつんと玲乃が僕の腕をつついてきた。ぴりりっと電流が流れるように右肘が悲鳴をあげる。
僕は「うぅ」と呻き声を上げて玲乃の顔を見上げる。するとその顔は悪戯っ子のように口をによによと引き上げている。少しむすっと膨れた僕は、好き放題してくる玲乃に牽制をする。
「もうちょっかいかけるのやめて。お腹空いたから僕もご飯が冷めないうちに食べたい。さっきからずっと玲乃ばっかり食べてる」
「……」
珍しく僕が反抗したせいか玲乃はぽかんと口を開いて数秒固まった。しかし、次第にくくくと喉の奥で笑う声が聞こえてきて僕はさらにむくれてしまう。
「そんなほっぺぷくぷくにして言われてもノーダメージだから、睦の気が済むまでもっとやりなよ」
僕の怒りの沸点が許容量のコップから溢れた瞬間だった。
「もう僕怒ったからね。今日はご飯食べたらすぐ帰るからっ!」
するとさっきまでくすくす笑っていた玲乃の表情が凍りついた。
ふやけた頬をゆっくり落として唇を真一文字に結ぶ。目線は次第に下がり睫毛が微かに震えているのが見えて、僕は言いすぎたかなと心配になる。
「か、代わりに玲乃が僕にあーんってしてくれたら許してあげないでもない……よ」
僕の精一杯の譲歩だった。後半は尻すぼみになっていたのできちんと玲乃の耳に届いたか多少不安ではあるが、玲乃がぱぁあっと表情を明るくさせたのでちゃんと聞こえていたことに安堵する。
そのとき「なんで僕が安心してるんだろう? 元はと言えば玲乃にちょっかいかけられてむすむすしてたのは僕のほうなのに」と疑問すら浮かぶ。
そんな僕をよそに、玲乃は自分の椅子を僕の隣に置いて座り満面の笑顔で「あーん」とムニエルをフォークにのせて食べさせてくれる。
「はい。あーん」
「……ん」
すっかり玲乃のペースに持っていかれた僕は、もっもっ、と玲乃が与えてくれる食事を味わう。お腹が八分目くらいになった頃、僕は静かに「ご馳走様でした」と玲乃に伝えた。
「わ。完食じゃん。苦手なミニトマトも食べられて睦は偉いねー」
「っ……だって拒否しても玲乃が口に突っ込んでくるから仕方なく、だよ」
サラダの底に隠されていた赤いピンポン玉くらいの大きさのミニトマトが僕の苦手な食べ物だ。
それを知っているから玲乃はあえてこんもりとベビーリーフやサニーレタスをミニトマトに被せて隠していたのだろう。
「はは。散歩拒否する黒いポメラニアンみたいな顔してて見てて癒されたよ」
「無意識に煽るのやめてよ。それ玲乃の悪い癖だよ」
いたって本人は思ったことを口に出しているだけなのだろうが、人を不快にさせていることも確かだ。幼い頃から玲乃の隣にいるから玲乃の性格や得意なこと、不得意なことをよく知っている。
「ふぁー。食った食った」
洗い物を終えた玲乃がリビングのソファにばたんきゅーしてきた。
3人がけのソファの隅っこで体育座りをしていた僕の身体がぴょこんと波打つ。
バランスを崩して玲乃のお尻に頭をぶつけて「うっ」と変な声が洩れた。おでこを押さえて鈍い痛みに耐えていると、目の前に黒い影が伸びてきた。はっとして顔を上げれば玲乃が神妙な面持ちで僕の顔を覗きこんできていた。
「なっ、何?」
まじまじと何も言わずに見つめてくる玲乃の本意がわからずにじりじりと後ろに下がれば、玲乃もぐーっと顔を近づけてきて僕は逃げられなくなった。
「いや。前髪伸びたなーって」
「っ!」
さらりと前髪をかきあげられおでこが露わになる。そのままおでこの上を柔らかくマッサージされてしまい、僕の身体の力が抜けてソファに身体が溶けていく。
「睦。ふにゃふにゃになっちゃったね」
玲乃のマッサージはすごく上手で、まるで美容院で髪を洗ってもらったりヘッドスパを受けている感覚になるのだ。
「黒髪さらさらでいいね。まさに清楚って感じする。天使のわっかできてるし、つやつやだし、前世は黒ポメラニアンだったのかな?」
耳元で囁いてくるから、距離が近くて動揺してしまう。僕は何も言えずに目線を下げていた。おでこをつん、と人差し指で小突かれて後ろへ仰け反る。
「わっ」
ソファの端から落下した。僕は襲ってくるであろう床に叩きつけられる痛みを想像して、慌ててぎゅっと頭を両腕で抱えた。目をきゅっとつむり身体を縮こませる。
しかし、数秒待っても痛みは襲ってこない。その代わりに背中に回された腕が熱くて、触れるところから体温が伝わってきて胸の奥がきゅっと締め付けられた。
「あっぶな。ごめんね。落としちゃうとこだった」
「……あ、ありがとう」
ソファから落ちるところを玲乃が抱きとめてくれたらしい。
玲乃の制服のワイシャツの隙間から放たれた甘い匂いが鼻を掠めた。玲乃のお気にいりの香水だった。バニラの香りに包まれ僕の身体の力が抜けていく。ワイシャツ越しに玲乃の硬い胸まわりが伝わってきて、玲乃は綺麗な顔をしていても男の人なんだなあと思い知る。
「……玲乃?」
ソファからの落下を防いでくれたことには感謝しつつも、未だに離れる素振りのない玲乃に僕は小さく呼びかける。
突如すんすん、と僕の耳元に鼻を近づけてきた。心臓がばくん、と一際大きく跳ね上がる。身体中の血液が心臓と顔に集まっていくような感覚にぱっと顔を伏せた。
「睦、いい匂いする。ねえ、今日も『あれ』して欲しいな」
『あれ』というのは僕と玲乃だけに伝わる秘密の言葉だ。僕は目を右と左に泳がせながらこくんと頷き返した。