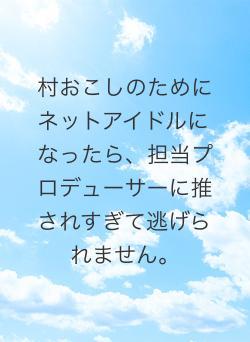「ん……?」
ふんわりと鼻をつく優しい匂いに目が覚めた。僕は眠まなこの目をぱしぱしとさせながらベッドを見つめる。そこに居たはずの玲乃が見当たらない。ゆっくりと大きく伸びをするとぱさりと何かが床に落ちる音が聞こえた。
「これ、玲乃の……」
おそらく寝落ちしてしまった自分の背中に掛けてくれたのだろう。白くてぽこぽことしたラビットファーのブランケットに触れる。まだ僕の体温が残っており温かい。
このブランケット。玲乃のだ。毎日、玲乃が使ってるもの……。
辺りをきょろきょろとして玲乃がいないことに安堵して、すんすんと鼻を近づける。良くないことだと頭では理解していても、溢れてくる好奇心は止められなかった。
あ……大好きな玲乃のおひさまみたいな良い匂い。
玲乃の匂いに癒されて、つま先を開いたり閉じたりしながらすんすんとしていると、身体が一気に熱くなってきて慌ててブランケットから手を引っ込めた。
だめだめ。僕、悪い子になりたくない。
その直後、ガチャリと部屋のドアが開いてびくっと肩を跳ねさせる。
見られてない、よね?
背中にどっと冷や汗が伝う。おそるおそる後ろを振り返れば、静かに微笑む玲乃の瞳と目が合った。胸がとくんと心地よく鼓動し始める。
「おねむだった? 起こしてごめん」
僕はふるふると小さく首を横に振る。
あ。玲乃は僕がブランケットの匂いをすんすんしてたこと知らないないみたい。良かった……。玲乃に変な子って思われたくないから。
「ううん。僕のほうこそごめん。勉強教える約束だったのに寝落ちしちゃった……」
「いいよ。俺も寝てたし。さ、お腹空いたね。こっちおいで」
そっと差しだされる手のひらに静かに自分の指先をのせて立ち上がった。指先だけを絡めて廊下を進みリビングへ連れられる。
玲乃はいつもこう。僕の手のひらを握ってエスコートしてくれる。なんだか玲乃のお姫様になったみたい。玲乃は王子様。そう。ずっとずっと昔から、僕の王子様なんだ。
香ばしい匂いがふわふわと漂ってきてお腹がぐううっと大きく鳴いた。
「はは。お腹ぺこぺこでしょ」
「う……いつも夜ご飯作ってくれてありがとう。何も手伝いできなくて……」
申し訳なさそうに目を伏せる僕に玲乃はふふっと口元を緩める。
「睦がお手伝いするとキッチンが爆発しちゃうからね」
「ゔ……ごもっともです……」
以前、1度だけ無理を言って玲乃に頼み込んで夜ご飯の手伝いをしたのだが、生卵をそのままレンジでチンしてしまい爆発させてしまった。
一緒にポテトサラダを作ろうとしてじゃがいもの芽を取り除くことを知らなくてそのまま茹でてマッシャーで潰してしまった。
それを事後報告すると玲乃は
「もー。まだまだ睦には花嫁修業が必要だね」
とお腹を抱えて笑って、じゃがいもの芽をひと欠片ずつ取り除いてくれたことがあった。
それを思い出していると、玲乃が僕のためにダイニングテーブルの椅子を引いてくれた。
「さあ。お姫様、こちらのお席へどうぞ」
「……僕、お姫様じゃないもん」
胸元に片手を置いてウェイター役になりきる玲乃をむっと頬を膨らませて睨む。しかし玲乃はそんな僕の眼力なんて効かないよというばかりに、綺麗にスルーして料理を運んでくる。
「こちら、本日のサラダとかぼちゃのスープでございます。熱いのでちゃんとフーフーしてからお召し上がりください」
フーフーって……! 僕、子どもじゃないのに……!
目の前に置かれた料理と玲乃の顔を交互に見つめる。
これは食べるまで観察されてしまう流れだ。
僕はゆっくり行儀よくスプーンを持ってかぼちゃのスープに口をつける。きちんと玲乃の指示通りフーフーした。はむ、とスプーンが唇が触れてスープが口の中に入る。ほっこりとした味わいで温かい。身体の芯から温まりそうだ。
次いでサラダも口に運ぶ。薄く透き通っている生ハムが慎ましくかけられていて、まるでサラダを包むドレスみたいだ。シャキシャキとした食感に食欲をそそられる。
ものの5分足らずでサラダとスープを平らげてしまった。
その間も玲乃はじっと僕のことを見つめて観察しているようだった。
「玲乃も一緒に食べようよ」
僕の言葉に玲乃は「うん」と頷いた。ウェイター役を辞めて、キッチンからメインディッシュを持ってきた。
「わあ。すごくいい匂いの正体ってこれだったんだ……!」
「俺も作ってるときからお腹が鳴ってたよ」
くすくす微笑む玲乃を見て僕もほっとする。
「さあ。睦。お食べ」
「いただきます……!」
鮭のムニエルにパセリが添えられている。フォークとナイフをぎこちなく使いこなして口へ運ぶ。ハーブの香りが鼻先からおでこにかけて突き抜けていった。
「んん。美味しい!」
思わずそう唸ってしまった。その様子を玲乃が満足そうに見つめていた。向かい合わせでテーブルを囲んでいると、玲乃が僕のことを見つめて「あーん」と甘く響く声で呟き口を開いた。
「えっと……?」
戸惑う僕をよそに玲乃は頬杖をついて黙って黒い瞳で見つめてくるだけ。瞳の奥は墨を水で溶いたように灰色に潤んでいる。
僕はその妖艶な瞳から目を逸らせずに、おそるおそる鮭のムニエルをフォークにのせて玲乃の口に運んだ。ぷるぷるとした血色感のある唇から仄紅い舌がちらりとのぞいた。
僕はそれを何か見てはいけないものを見たような気持ちで目を逸らしながら横目で見とれていた。
「ん。おーいし」
ぺろ、と仄紅い舌で唇を舐め玲乃が呟く。
僕はばくばくする心臓の鼓動に「早くおさまれ」と言い聞かせる。
ふんわりと鼻をつく優しい匂いに目が覚めた。僕は眠まなこの目をぱしぱしとさせながらベッドを見つめる。そこに居たはずの玲乃が見当たらない。ゆっくりと大きく伸びをするとぱさりと何かが床に落ちる音が聞こえた。
「これ、玲乃の……」
おそらく寝落ちしてしまった自分の背中に掛けてくれたのだろう。白くてぽこぽことしたラビットファーのブランケットに触れる。まだ僕の体温が残っており温かい。
このブランケット。玲乃のだ。毎日、玲乃が使ってるもの……。
辺りをきょろきょろとして玲乃がいないことに安堵して、すんすんと鼻を近づける。良くないことだと頭では理解していても、溢れてくる好奇心は止められなかった。
あ……大好きな玲乃のおひさまみたいな良い匂い。
玲乃の匂いに癒されて、つま先を開いたり閉じたりしながらすんすんとしていると、身体が一気に熱くなってきて慌ててブランケットから手を引っ込めた。
だめだめ。僕、悪い子になりたくない。
その直後、ガチャリと部屋のドアが開いてびくっと肩を跳ねさせる。
見られてない、よね?
背中にどっと冷や汗が伝う。おそるおそる後ろを振り返れば、静かに微笑む玲乃の瞳と目が合った。胸がとくんと心地よく鼓動し始める。
「おねむだった? 起こしてごめん」
僕はふるふると小さく首を横に振る。
あ。玲乃は僕がブランケットの匂いをすんすんしてたこと知らないないみたい。良かった……。玲乃に変な子って思われたくないから。
「ううん。僕のほうこそごめん。勉強教える約束だったのに寝落ちしちゃった……」
「いいよ。俺も寝てたし。さ、お腹空いたね。こっちおいで」
そっと差しだされる手のひらに静かに自分の指先をのせて立ち上がった。指先だけを絡めて廊下を進みリビングへ連れられる。
玲乃はいつもこう。僕の手のひらを握ってエスコートしてくれる。なんだか玲乃のお姫様になったみたい。玲乃は王子様。そう。ずっとずっと昔から、僕の王子様なんだ。
香ばしい匂いがふわふわと漂ってきてお腹がぐううっと大きく鳴いた。
「はは。お腹ぺこぺこでしょ」
「う……いつも夜ご飯作ってくれてありがとう。何も手伝いできなくて……」
申し訳なさそうに目を伏せる僕に玲乃はふふっと口元を緩める。
「睦がお手伝いするとキッチンが爆発しちゃうからね」
「ゔ……ごもっともです……」
以前、1度だけ無理を言って玲乃に頼み込んで夜ご飯の手伝いをしたのだが、生卵をそのままレンジでチンしてしまい爆発させてしまった。
一緒にポテトサラダを作ろうとしてじゃがいもの芽を取り除くことを知らなくてそのまま茹でてマッシャーで潰してしまった。
それを事後報告すると玲乃は
「もー。まだまだ睦には花嫁修業が必要だね」
とお腹を抱えて笑って、じゃがいもの芽をひと欠片ずつ取り除いてくれたことがあった。
それを思い出していると、玲乃が僕のためにダイニングテーブルの椅子を引いてくれた。
「さあ。お姫様、こちらのお席へどうぞ」
「……僕、お姫様じゃないもん」
胸元に片手を置いてウェイター役になりきる玲乃をむっと頬を膨らませて睨む。しかし玲乃はそんな僕の眼力なんて効かないよというばかりに、綺麗にスルーして料理を運んでくる。
「こちら、本日のサラダとかぼちゃのスープでございます。熱いのでちゃんとフーフーしてからお召し上がりください」
フーフーって……! 僕、子どもじゃないのに……!
目の前に置かれた料理と玲乃の顔を交互に見つめる。
これは食べるまで観察されてしまう流れだ。
僕はゆっくり行儀よくスプーンを持ってかぼちゃのスープに口をつける。きちんと玲乃の指示通りフーフーした。はむ、とスプーンが唇が触れてスープが口の中に入る。ほっこりとした味わいで温かい。身体の芯から温まりそうだ。
次いでサラダも口に運ぶ。薄く透き通っている生ハムが慎ましくかけられていて、まるでサラダを包むドレスみたいだ。シャキシャキとした食感に食欲をそそられる。
ものの5分足らずでサラダとスープを平らげてしまった。
その間も玲乃はじっと僕のことを見つめて観察しているようだった。
「玲乃も一緒に食べようよ」
僕の言葉に玲乃は「うん」と頷いた。ウェイター役を辞めて、キッチンからメインディッシュを持ってきた。
「わあ。すごくいい匂いの正体ってこれだったんだ……!」
「俺も作ってるときからお腹が鳴ってたよ」
くすくす微笑む玲乃を見て僕もほっとする。
「さあ。睦。お食べ」
「いただきます……!」
鮭のムニエルにパセリが添えられている。フォークとナイフをぎこちなく使いこなして口へ運ぶ。ハーブの香りが鼻先からおでこにかけて突き抜けていった。
「んん。美味しい!」
思わずそう唸ってしまった。その様子を玲乃が満足そうに見つめていた。向かい合わせでテーブルを囲んでいると、玲乃が僕のことを見つめて「あーん」と甘く響く声で呟き口を開いた。
「えっと……?」
戸惑う僕をよそに玲乃は頬杖をついて黙って黒い瞳で見つめてくるだけ。瞳の奥は墨を水で溶いたように灰色に潤んでいる。
僕はその妖艶な瞳から目を逸らせずに、おそるおそる鮭のムニエルをフォークにのせて玲乃の口に運んだ。ぷるぷるとした血色感のある唇から仄紅い舌がちらりとのぞいた。
僕はそれを何か見てはいけないものを見たような気持ちで目を逸らしながら横目で見とれていた。
「ん。おーいし」
ぺろ、と仄紅い舌で唇を舐め玲乃が呟く。
僕はばくばくする心臓の鼓動に「早くおさまれ」と言い聞かせる。