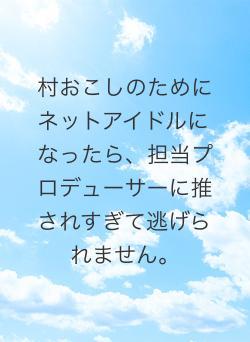「あーそ。まあいいや。帰って即シャワー浴びてきたでしょ」
意外にも、玲乃は僕の話を聞いて納得してくれたようだ。そのことにまずはほっとして肩の力を抜く。
「えっ。なんでわかるの?」
すんすんと玲乃が顔を近づけて僕の首筋辺りに高い鼻をくっつける。顔、ちっちゃいな……。
「ボディーソープの匂いするから」
「……!」
不意の至近距離に僕の身体が発火するように熱くなる。それを玲乃に悟られまいとして冷静さを保とうとする。
「うん。汗くさかったらやだなって」
「別にいいのに。俺と睦の仲でしょ」
くすりと微笑む玲乃の様子を見て僕はほっと胸を撫で下ろす。どうやらもう怒ってはなさそうだ。
僕と主濱 玲乃は幼馴染だ。
同じマンションのお隣さん。
親同士が仲が良くて赤ちゃんの頃から一緒に遊ぶ仲だったとお母さんから聞いている。赤ちゃん教室でも一緒だったそうだ。家のアルバムには幼い頃の僕と玲乃が遊んだり喧嘩したり、仲良くしてる写真がたくさんある。僕はそれらの写真を時々思い出しては見返したりする。小さい頃の玲乃は女の子みたいに可愛くて、目がくりくりしてて大人からも子どもからも大人気だったのを覚えている。
それ以来、幼稚園、小学校、中学校も一緒だ。
高校は正直なところ玲乃と同じ学校に行きたくて選んだ。家からも徒歩で通えるのは楽ちんだし、何より玲乃と離れたくなかったから。猛勉強したことは玲乃には内緒にしている。
学校ではほとんど話さないけれど、放課後になるとこうして会う。放課後だけは、昔みたいに内緒の幼馴染に戻る。こんな生活がずっと続いていけばいいのに、と僕は心の底から願っている。毎年、七夕でも短冊に書くくらいに玲乃との2人きりの時間は大切なものだった。
僕は学校の人には玲乃との関係は内緒だと思って秘密にしている。
学校では決して自分からは玲乃に話しかけないし、玲乃も同じクラスになっても話しかけてこないから。
1年生のときはクラスが違うから学校で話すことはなかった。けど、放課後になるとよく会っていた。
主に玲乃に呼び出されてテスト勉強を一緒にしたり、玲乃の趣味のギター演奏を聞かされたり、一緒に部屋で映画を見たり。
僕が思うに自分というのは玲乃にとって都合のいい友達なんだと思う。それ以上を望むことは駄目だと思っていた。
本当はもっとたくさん話したいし一緒にいたい。けれど玲乃にはたくさん友達がいるし、しかも若者に人気の高校生インフルエンサーだ。
女をとっかえひっかえしている、クズ男。
そんな噂が、玲乃にはつきまとっている。
声は低くて寡黙。髪はハイトーンのホワイトカラーのセンターパートで襟足が長く毛束が後ろに流れている。
最近トレンドの「中華ウルフ」という髪型らしい。
メンズアイドルのように華やかな髪型だ。玲乃の性格にピッタリだと女子ウケが良く、見た目からしてクズっぽいと好評だ。
何故好評なのか僕にはよくわからないが、玲乃のSNSのフォロワー数は10万人を超えている。
実際にそのSNSを僕が鍵アカウントでフォローしているだなんてこと、玲乃には口が裂けても言えない。
「睦。むーつ」
突如ぷにぷにと頬に人差し指を突き立てられ我に返る。
「わっ」
「なぁに。ぼーっとしてる。ほらテスト勉強しよ」
「うん……」
机の上に古典の教科書とノート、大学受験用の参考書を広げると玲乃が僕の手首を掴んできた。骨ばったごつごつとした手のひらに触れて、心臓が甘く震え出す。
「この参考書って大学受験用? もう準備してるの?」
「うん。もう高校2年生だしそろそろ本腰入れようかなって」
絶対に顔に出しちゃダメだ。玲乃に触られて嬉しいってことは内緒にしないと。僕は動揺が悟られないように玲乃にいつものような声音で返答する。
「偉すぎ。さすが睦だ。この参考書わかりやすい? 俺も見ていい?」
「うん。もちろん」
玲乃が大学受験用の参考書をペラペラと試し読みしている顔を見ながら思う。
玲乃は高校を卒業したら、進路どうするんだろう。大学進学するのかな。それとも大好きな服飾系の専門学校とか美容専門学校に行くのかな。
僕も同じ進路になれたら……なんて。
「ふむふむ。なるほどねえ。これはわかりやすいわ。俺も買おっかな」
大学受験用の参考書を閉じると、玲乃は僕のほうをじっと見つめてきた。なんだろうと不思議に思い見つめ返す。すると突然頭をぽんぽんと撫でられて肩が跳ねた。
「睦はほんとにお利口さん」
「……っ」
これ、反則。学校ではこんなこと絶対しないのに。僕といるときだけ特別扱いしてくれるの嬉しいからもっとして欲しい。
そんな思いを抱えながらも決して口にしてはいけないとわかっている。今はただ隣に玲乃がいるだけでいい。一緒に他愛のない話をして笑っているくらいで十分だ。それ以上を望んではダメだ。
僕はこんな幸せな時間がずっと続くと思ってしまった。このままの距離で、玲乃の隣にいられるのなら。
意外にも、玲乃は僕の話を聞いて納得してくれたようだ。そのことにまずはほっとして肩の力を抜く。
「えっ。なんでわかるの?」
すんすんと玲乃が顔を近づけて僕の首筋辺りに高い鼻をくっつける。顔、ちっちゃいな……。
「ボディーソープの匂いするから」
「……!」
不意の至近距離に僕の身体が発火するように熱くなる。それを玲乃に悟られまいとして冷静さを保とうとする。
「うん。汗くさかったらやだなって」
「別にいいのに。俺と睦の仲でしょ」
くすりと微笑む玲乃の様子を見て僕はほっと胸を撫で下ろす。どうやらもう怒ってはなさそうだ。
僕と主濱 玲乃は幼馴染だ。
同じマンションのお隣さん。
親同士が仲が良くて赤ちゃんの頃から一緒に遊ぶ仲だったとお母さんから聞いている。赤ちゃん教室でも一緒だったそうだ。家のアルバムには幼い頃の僕と玲乃が遊んだり喧嘩したり、仲良くしてる写真がたくさんある。僕はそれらの写真を時々思い出しては見返したりする。小さい頃の玲乃は女の子みたいに可愛くて、目がくりくりしてて大人からも子どもからも大人気だったのを覚えている。
それ以来、幼稚園、小学校、中学校も一緒だ。
高校は正直なところ玲乃と同じ学校に行きたくて選んだ。家からも徒歩で通えるのは楽ちんだし、何より玲乃と離れたくなかったから。猛勉強したことは玲乃には内緒にしている。
学校ではほとんど話さないけれど、放課後になるとこうして会う。放課後だけは、昔みたいに内緒の幼馴染に戻る。こんな生活がずっと続いていけばいいのに、と僕は心の底から願っている。毎年、七夕でも短冊に書くくらいに玲乃との2人きりの時間は大切なものだった。
僕は学校の人には玲乃との関係は内緒だと思って秘密にしている。
学校では決して自分からは玲乃に話しかけないし、玲乃も同じクラスになっても話しかけてこないから。
1年生のときはクラスが違うから学校で話すことはなかった。けど、放課後になるとよく会っていた。
主に玲乃に呼び出されてテスト勉強を一緒にしたり、玲乃の趣味のギター演奏を聞かされたり、一緒に部屋で映画を見たり。
僕が思うに自分というのは玲乃にとって都合のいい友達なんだと思う。それ以上を望むことは駄目だと思っていた。
本当はもっとたくさん話したいし一緒にいたい。けれど玲乃にはたくさん友達がいるし、しかも若者に人気の高校生インフルエンサーだ。
女をとっかえひっかえしている、クズ男。
そんな噂が、玲乃にはつきまとっている。
声は低くて寡黙。髪はハイトーンのホワイトカラーのセンターパートで襟足が長く毛束が後ろに流れている。
最近トレンドの「中華ウルフ」という髪型らしい。
メンズアイドルのように華やかな髪型だ。玲乃の性格にピッタリだと女子ウケが良く、見た目からしてクズっぽいと好評だ。
何故好評なのか僕にはよくわからないが、玲乃のSNSのフォロワー数は10万人を超えている。
実際にそのSNSを僕が鍵アカウントでフォローしているだなんてこと、玲乃には口が裂けても言えない。
「睦。むーつ」
突如ぷにぷにと頬に人差し指を突き立てられ我に返る。
「わっ」
「なぁに。ぼーっとしてる。ほらテスト勉強しよ」
「うん……」
机の上に古典の教科書とノート、大学受験用の参考書を広げると玲乃が僕の手首を掴んできた。骨ばったごつごつとした手のひらに触れて、心臓が甘く震え出す。
「この参考書って大学受験用? もう準備してるの?」
「うん。もう高校2年生だしそろそろ本腰入れようかなって」
絶対に顔に出しちゃダメだ。玲乃に触られて嬉しいってことは内緒にしないと。僕は動揺が悟られないように玲乃にいつものような声音で返答する。
「偉すぎ。さすが睦だ。この参考書わかりやすい? 俺も見ていい?」
「うん。もちろん」
玲乃が大学受験用の参考書をペラペラと試し読みしている顔を見ながら思う。
玲乃は高校を卒業したら、進路どうするんだろう。大学進学するのかな。それとも大好きな服飾系の専門学校とか美容専門学校に行くのかな。
僕も同じ進路になれたら……なんて。
「ふむふむ。なるほどねえ。これはわかりやすいわ。俺も買おっかな」
大学受験用の参考書を閉じると、玲乃は僕のほうをじっと見つめてきた。なんだろうと不思議に思い見つめ返す。すると突然頭をぽんぽんと撫でられて肩が跳ねた。
「睦はほんとにお利口さん」
「……っ」
これ、反則。学校ではこんなこと絶対しないのに。僕といるときだけ特別扱いしてくれるの嬉しいからもっとして欲しい。
そんな思いを抱えながらも決して口にしてはいけないとわかっている。今はただ隣に玲乃がいるだけでいい。一緒に他愛のない話をして笑っているくらいで十分だ。それ以上を望んではダメだ。
僕はこんな幸せな時間がずっと続くと思ってしまった。このままの距離で、玲乃の隣にいられるのなら。