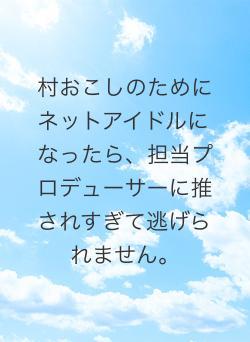「……睦。ちょっと外、散歩しよ」
「え?」
玲乃に腕を引かれ、そのまま部屋を出た。ホテルの玄関先まで来て、ようやく手を離してくれる。
外の空気はもわっと生ぬるく、夏の匂いがした。黙って玲乃の背中についていくと、花火大会が行われる川辺へと誘われる。
花火見物の人たちが敷いたレジャーシートが、川沿いに点々と並んでいる。その一番端、石段の空いている場所に玲乃が腰を下ろした。僕も少し距離を空けて、同じように座る。
川のせせらぎだけが静かに耳に届き、夏の夜の闇に包まれている。
隣で、玲乃が大きく息を吸い込む音がした。
「睦。聞いて」
「……うん」
いつもの余裕のある玲乃とは違って、どこか緊張しているのが伝わってくる。額を伝う汗が、花火の灯りに微かに光った。
「俺が今まで睦にしてきたこと、その理由……知りたいんだよね?」
確かめるような視線に、僕は小さく頷く。すると玲乃は、僕の手のひらをぎゅっと包み込むように握った。
「好きなんだ。睦のこと」
「……っ」
その瞬間、川辺から試し打ちの花火が上がった。
夜空に咲いた淡いピンク色の輪が、きらきらと揺れている。花火の光に照らされた玲乃の横顔が、少しだけ赤く染まって見えた。
「睦は、俺のことを『内緒の友達』だと思ってくれてたみたいだけど」
玲乃は小さく、照れたように笑う。
「俺はずっと、睦に意識してほしくて接してきたつもりだった」
「……意識?」
「そう。友達以上だってこと、伝えたかった。でも睦が全然気づいてくれないから……少し強引になったこともあった」
「……そう、だったんだ」
信じられなくて、目を見開く。胸の奥から、じわじわと熱いものがこみ上げてきた。
玲乃が、僕を友達以上に思ってくれていた。
放課後に見せる甘えた態度も、距離の近さも──全部、好意だったんだ。
気づいた途端、頬が一気に熱くなる。昨夜の添い寝も、今日のお風呂も、全部『特別』だったのだと今さら理解してしまう。
積極的に気持ちを示してくれていたのに、それに気づかず、自分の想いに蓋をしていたのは……僕のほうだった。
「睦のこと、大好き。この世で一番好き」
両手で包まれた僕の手は、少し震えていた。僕はその手を、そっと握り返す。勇気を振り絞り、玲乃の目をまっすぐ見つめた。
「……僕も、玲乃のこと好き。小さい頃から、ずっと」
言葉が、喉につかえそうになる。
「でも……玲乃は人気者で、高校生インフルエンサーで……それに、僕は男だし。好きって言ったら、もう二度と傍にいられなくなるんじゃないかって……怖かった」
最後は声が震え、涙が滲んでいた。
玲乃は何も言わず、そっと顔を近づけてくる。高い鼻筋が、僕の鼻先に触れた。
「泣かないで。睦には、笑ってる顔が一番似合う」
次の瞬間、唇にふわりと柔らかい感触が触れた。
温かくて、やさしくて、すぐに離れてしまう短い口づけ。胸の奥に、じんわりと余韻だけが残る。
「ほら。泣いてる子には、こうして安心させてあげないと」
悪戯っぽく僕を覗き込む玲乃の瞳は、嬉しそうに細められていた。
「いいな」と僕は思った。
ずっとずっと幼い頃から抱き続けてきた気持ちを、ついに伝えられた。大好きだと口にできて、初めてのキスもして──心が今にも天に昇りそうなほど、嬉しくてたまらなかった。
隠し続けた日々は、本当に辛くて苦しかった。だけどその時間があったから、僕は玲乃のいろんな表情を知ることができたんだ。
学校で見せる気だるげで不機嫌そうな顔も、放課後に僕だけに見せる甘えた仕草も、はにかむような笑顔も、甘く低い声も──。
全部、玲乃の一部で、かわいいところもかっこいいところも、独り占めできるのは自分だけだと気づいた瞬間、嬉しさで胸がいっぱいになり、気づけば僕は玲乃の腕の中に飛び込んでいた。
一生分の勇気を振り絞り、玲乃の胸に顔をくっつける。最初は少し驚いていたようだけど、すぐに背中に手を回して頭を優しく撫でてくれた。その手のひらの温かさと柔らかさに、僕は自然と力を抜いて身を委ねる。
「僕も好き。大好きだから、離れないで」
「うん。離れないよ。これからもずっと睦と一緒にいる」
どんどん、と夜空に花火が上がる。川辺に座る人々の歓声と色とりどりの光が、夏の夜を染めていた。
「玲乃と見る花火、初めてだね」
「これから何度でも一緒に見に行こう」
上を向いた瞬間、玲乃がそっと唇に触れてきた。短く、柔らかく、優しいキス──心臓がぎゅっとなるくらいに甘くて、胸がいっぱいになった。
花火の光が僕たちの間に漂う。息が重なり、互いの温もりを感じる。何度も見つめ合って、笑い合って──それだけで、僕はこの夏のすべてを忘れられないものにした。
高校2年生の夏の終わり、川辺に咲く花火と一緒に、僕たちの思い出も夜空に輝いた。
「え?」
玲乃に腕を引かれ、そのまま部屋を出た。ホテルの玄関先まで来て、ようやく手を離してくれる。
外の空気はもわっと生ぬるく、夏の匂いがした。黙って玲乃の背中についていくと、花火大会が行われる川辺へと誘われる。
花火見物の人たちが敷いたレジャーシートが、川沿いに点々と並んでいる。その一番端、石段の空いている場所に玲乃が腰を下ろした。僕も少し距離を空けて、同じように座る。
川のせせらぎだけが静かに耳に届き、夏の夜の闇に包まれている。
隣で、玲乃が大きく息を吸い込む音がした。
「睦。聞いて」
「……うん」
いつもの余裕のある玲乃とは違って、どこか緊張しているのが伝わってくる。額を伝う汗が、花火の灯りに微かに光った。
「俺が今まで睦にしてきたこと、その理由……知りたいんだよね?」
確かめるような視線に、僕は小さく頷く。すると玲乃は、僕の手のひらをぎゅっと包み込むように握った。
「好きなんだ。睦のこと」
「……っ」
その瞬間、川辺から試し打ちの花火が上がった。
夜空に咲いた淡いピンク色の輪が、きらきらと揺れている。花火の光に照らされた玲乃の横顔が、少しだけ赤く染まって見えた。
「睦は、俺のことを『内緒の友達』だと思ってくれてたみたいだけど」
玲乃は小さく、照れたように笑う。
「俺はずっと、睦に意識してほしくて接してきたつもりだった」
「……意識?」
「そう。友達以上だってこと、伝えたかった。でも睦が全然気づいてくれないから……少し強引になったこともあった」
「……そう、だったんだ」
信じられなくて、目を見開く。胸の奥から、じわじわと熱いものがこみ上げてきた。
玲乃が、僕を友達以上に思ってくれていた。
放課後に見せる甘えた態度も、距離の近さも──全部、好意だったんだ。
気づいた途端、頬が一気に熱くなる。昨夜の添い寝も、今日のお風呂も、全部『特別』だったのだと今さら理解してしまう。
積極的に気持ちを示してくれていたのに、それに気づかず、自分の想いに蓋をしていたのは……僕のほうだった。
「睦のこと、大好き。この世で一番好き」
両手で包まれた僕の手は、少し震えていた。僕はその手を、そっと握り返す。勇気を振り絞り、玲乃の目をまっすぐ見つめた。
「……僕も、玲乃のこと好き。小さい頃から、ずっと」
言葉が、喉につかえそうになる。
「でも……玲乃は人気者で、高校生インフルエンサーで……それに、僕は男だし。好きって言ったら、もう二度と傍にいられなくなるんじゃないかって……怖かった」
最後は声が震え、涙が滲んでいた。
玲乃は何も言わず、そっと顔を近づけてくる。高い鼻筋が、僕の鼻先に触れた。
「泣かないで。睦には、笑ってる顔が一番似合う」
次の瞬間、唇にふわりと柔らかい感触が触れた。
温かくて、やさしくて、すぐに離れてしまう短い口づけ。胸の奥に、じんわりと余韻だけが残る。
「ほら。泣いてる子には、こうして安心させてあげないと」
悪戯っぽく僕を覗き込む玲乃の瞳は、嬉しそうに細められていた。
「いいな」と僕は思った。
ずっとずっと幼い頃から抱き続けてきた気持ちを、ついに伝えられた。大好きだと口にできて、初めてのキスもして──心が今にも天に昇りそうなほど、嬉しくてたまらなかった。
隠し続けた日々は、本当に辛くて苦しかった。だけどその時間があったから、僕は玲乃のいろんな表情を知ることができたんだ。
学校で見せる気だるげで不機嫌そうな顔も、放課後に僕だけに見せる甘えた仕草も、はにかむような笑顔も、甘く低い声も──。
全部、玲乃の一部で、かわいいところもかっこいいところも、独り占めできるのは自分だけだと気づいた瞬間、嬉しさで胸がいっぱいになり、気づけば僕は玲乃の腕の中に飛び込んでいた。
一生分の勇気を振り絞り、玲乃の胸に顔をくっつける。最初は少し驚いていたようだけど、すぐに背中に手を回して頭を優しく撫でてくれた。その手のひらの温かさと柔らかさに、僕は自然と力を抜いて身を委ねる。
「僕も好き。大好きだから、離れないで」
「うん。離れないよ。これからもずっと睦と一緒にいる」
どんどん、と夜空に花火が上がる。川辺に座る人々の歓声と色とりどりの光が、夏の夜を染めていた。
「玲乃と見る花火、初めてだね」
「これから何度でも一緒に見に行こう」
上を向いた瞬間、玲乃がそっと唇に触れてきた。短く、柔らかく、優しいキス──心臓がぎゅっとなるくらいに甘くて、胸がいっぱいになった。
花火の光が僕たちの間に漂う。息が重なり、互いの温もりを感じる。何度も見つめ合って、笑い合って──それだけで、僕はこの夏のすべてを忘れられないものにした。
高校2年生の夏の終わり、川辺に咲く花火と一緒に、僕たちの思い出も夜空に輝いた。