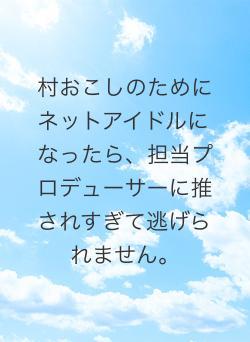僕は玲乃のベッドの近くに座り込み、しばらく様子を伺った。
はむ、と玲乃がれんげに口をつける。口の僅かな隙間から覗く紅い舌につい視線が向かってしまう。
「ん」
と玲乃が僕の手にお粥の残った器を手渡してきた。
「お腹いっぱいになった?」
「あーんして」
潤んだ瞳に吸い込まれそうになり、顔の距離が近くなる。玲乃が僕のほうへ顔を寄せてきたからだ。
「あ、あーん?」
「そ」
玲乃はおもむろに口を開いて餌を待つ雛鳥のように無垢な瞳で見つめてくる。
僕はおそるおそるれんげにお粥を掬って、ふーふーと口もとで冷ましてから玲乃の口の中へれんげを差し出した。はむ、と艶びた桃色の唇がれんげに触れる。こくん、と玲乃の高い喉仏が跳ねた。僕はそれを見た途端なぜか心臓がギュ、と掴まれたように胸が締め付けられた。
「おかわり」
少し頬を紅潮させた玲乃が僕の腕を掴む。いつもは華奢なくせに力強い手のひらが今日は力なくへたりとベッドに落ちていく。
すっかり甘えた様子の玲乃に従いキッチンへ向かい、鍋にかけたお粥を掬いとる。ほんのりと温かい器を手に玲乃の部屋へ戻った。玲乃はぽーっとしたまま正面の壁を見つめている。僕はひとまず部屋の真ん中にある丸テーブルにお粥とれんげの載ったお盆を置いた。
「睦」
「……」
玲乃がちょんちょんと僕の服の袖をつまむ。名前を呼ばれてはっと後ろを振り向けば玲乃がベッドの上に膝立ちをして上身体を起こしていた。
「わっ……!」
気づいたときには玲乃の胸元が至近距離にあった。ふわりと鼻をつく甘い匂い。玲乃の香水の匂いだ。僕は玲乃に腰を抱き寄せられてそのままベッドへと押し倒される。玲乃が身体に覆いかぶさってきた。服越しに重なる熱が恥ずかしくて、でもなぜか心地よく感じて身体を硬直させていると玲乃の華奢でごつごつとした長い指に前髪を梳かれた。
「睦……」
夢うつつなのだろうか。玲乃は薄目を開いて僕の名前を呼ぶ。壊れ物に触れるようにやさしく、あたたかい手のひらで。
「睦。俺、睦の前ではいい子にしてるからね。俺を絶対離さないで。ひとりにしないで」
しゅんと眉を垂らした玲乃の表情は迷子になった子どものように不安げだ。熱が出たときには人は誰しも心細くなるものだ。僕はきっとそれが原因なのだろうと安直に感じ取り玲乃の頬に手を添える。
「大丈夫だよ。僕はどこも行かない。僕のいる場所は玲乃の隣だから。玲乃が僕の帰る場所なんだよ」
偽りのない想いだった。普段こういうことを口にすることはないけれど今日くらいいいよね、と無意識に本音を伝えていた。すると玲乃は何度かゆっくりと瞬きをしてから僕の手に自分の手を添えた。
「俺も睦が帰る場所だよ。おそろい」
ちゅ、と微かに玲乃の唇が僕の指先に触れた。睦が惚けていると、ちゅちゅちゅと立て続けに指先を吸われてしまう。
「こらこら。僕の指はおしゃぶりじゃないってば」
本当は嬉しかった。こうして玲乃に触れられるのが大好きだった。叶うことならずっとこうして欲しい。玲乃の隣に僕だけを置いてほしかった。そうすれば玲乃に全てを捧げられる。いっそ玲乃への想いを伝えてしまえればどれだけ楽になるだろう。そう考えてからふるふると首を横に振る。
ダメだ。熱がある玲乃につけ込むなんて酷いこと僕にはできないよ。
玲乃がふわっと微笑みを浮かべた。花束みたいに綺麗だった。そのままギュっと身体を抱きしめられる。落ち着いた寝息を立て始めた玲乃を起こさないように僕も瞳を閉じる。
夢の中でくらい、大好きな玲乃の一番になりたかった。
はむ、と玲乃がれんげに口をつける。口の僅かな隙間から覗く紅い舌につい視線が向かってしまう。
「ん」
と玲乃が僕の手にお粥の残った器を手渡してきた。
「お腹いっぱいになった?」
「あーんして」
潤んだ瞳に吸い込まれそうになり、顔の距離が近くなる。玲乃が僕のほうへ顔を寄せてきたからだ。
「あ、あーん?」
「そ」
玲乃はおもむろに口を開いて餌を待つ雛鳥のように無垢な瞳で見つめてくる。
僕はおそるおそるれんげにお粥を掬って、ふーふーと口もとで冷ましてから玲乃の口の中へれんげを差し出した。はむ、と艶びた桃色の唇がれんげに触れる。こくん、と玲乃の高い喉仏が跳ねた。僕はそれを見た途端なぜか心臓がギュ、と掴まれたように胸が締め付けられた。
「おかわり」
少し頬を紅潮させた玲乃が僕の腕を掴む。いつもは華奢なくせに力強い手のひらが今日は力なくへたりとベッドに落ちていく。
すっかり甘えた様子の玲乃に従いキッチンへ向かい、鍋にかけたお粥を掬いとる。ほんのりと温かい器を手に玲乃の部屋へ戻った。玲乃はぽーっとしたまま正面の壁を見つめている。僕はひとまず部屋の真ん中にある丸テーブルにお粥とれんげの載ったお盆を置いた。
「睦」
「……」
玲乃がちょんちょんと僕の服の袖をつまむ。名前を呼ばれてはっと後ろを振り向けば玲乃がベッドの上に膝立ちをして上身体を起こしていた。
「わっ……!」
気づいたときには玲乃の胸元が至近距離にあった。ふわりと鼻をつく甘い匂い。玲乃の香水の匂いだ。僕は玲乃に腰を抱き寄せられてそのままベッドへと押し倒される。玲乃が身体に覆いかぶさってきた。服越しに重なる熱が恥ずかしくて、でもなぜか心地よく感じて身体を硬直させていると玲乃の華奢でごつごつとした長い指に前髪を梳かれた。
「睦……」
夢うつつなのだろうか。玲乃は薄目を開いて僕の名前を呼ぶ。壊れ物に触れるようにやさしく、あたたかい手のひらで。
「睦。俺、睦の前ではいい子にしてるからね。俺を絶対離さないで。ひとりにしないで」
しゅんと眉を垂らした玲乃の表情は迷子になった子どものように不安げだ。熱が出たときには人は誰しも心細くなるものだ。僕はきっとそれが原因なのだろうと安直に感じ取り玲乃の頬に手を添える。
「大丈夫だよ。僕はどこも行かない。僕のいる場所は玲乃の隣だから。玲乃が僕の帰る場所なんだよ」
偽りのない想いだった。普段こういうことを口にすることはないけれど今日くらいいいよね、と無意識に本音を伝えていた。すると玲乃は何度かゆっくりと瞬きをしてから僕の手に自分の手を添えた。
「俺も睦が帰る場所だよ。おそろい」
ちゅ、と微かに玲乃の唇が僕の指先に触れた。睦が惚けていると、ちゅちゅちゅと立て続けに指先を吸われてしまう。
「こらこら。僕の指はおしゃぶりじゃないってば」
本当は嬉しかった。こうして玲乃に触れられるのが大好きだった。叶うことならずっとこうして欲しい。玲乃の隣に僕だけを置いてほしかった。そうすれば玲乃に全てを捧げられる。いっそ玲乃への想いを伝えてしまえればどれだけ楽になるだろう。そう考えてからふるふると首を横に振る。
ダメだ。熱がある玲乃につけ込むなんて酷いこと僕にはできないよ。
玲乃がふわっと微笑みを浮かべた。花束みたいに綺麗だった。そのままギュっと身体を抱きしめられる。落ち着いた寝息を立て始めた玲乃を起こさないように僕も瞳を閉じる。
夢の中でくらい、大好きな玲乃の一番になりたかった。