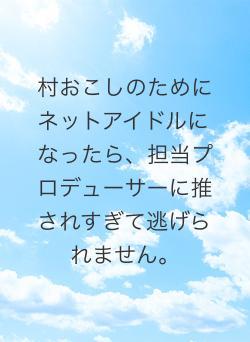僕は目の前の葉月先生にそれが見えていないか不安になって玲乃をちらりと見上げた。しかし玲乃はそんなの気にしていないと言わんばかりに食べ放題コース〈極〉のメニュー表を眺めている。僕は注文用のタブレットを近くに寄せて玲乃に声をかける。
「食べたいのあったら注文番号教えて。僕が打つよ」
「ん。ありがと」
玲乃はぱらぱらとメニュー表を一通り眺めると僕に上タン、はちみつ胡椒豚カルビ、ユッケの注文番号を伝えた。僕はそれを打ち間違いのないように慎重にタブレットに入力する。
「うん。できた」
注文確定ボタンを押してから玲乃を見つめると、なぜかぱちりと目が合ってしまった。まじまじと見つめられて僕は「えっと」と目線を逸らす。すると玲乃は僕の前髪をくしゃりとかきあげた。
「なあに。眉毛いつもと違うね。それにアイライン引いてる? 唇もいつもより血色感あるし、メイクした?」
僕はきゅ、と自身の手のひらを握りしめた。実は玲乃の言う通りで今日初めてメンズメイクをしてみたのだ。クラスのみんなには何も言われなかったから気づかれないと思っていたのに。僕は照れ笑いを浮かべてパイナップルジュースの入ったグラスを持ち上げる。
「うん。文化祭で西園寺さんにメイクしてもらっていつもと雰囲気が変わって気分が上がったんだ。自分でもドラッグストアでコスメを買ってメイクしてみた。……変かな?」
内心どきどきしながら聞いてみれば玲乃は
「いーんじゃない?」
と自身の顎に手を置いて僕を再度まじまじと見つめてきた。そしてテーブルの下で不意に僕の手を掴んできた。僕は目の前でガツガツとご飯を頬張っている葉月先生に気づかれないかはらはらした。
一方の玲乃は気にする様子はまったくないようで、提供されたお肉を網に置いて焼き始めた。指先を絡めて、にぎにぎと2回強く握られる。僕もそれに返事をするように、にぎにぎと2回手を握った。なんだか秘密の合図みたいで、恥ずかしくてたまらないはずなのに嬉しい。
僕は自分の手のひらにじっとり汗が滲んでいないか、そればかり気になった。そんな時、九重くんが僕たちのテーブルの前に現れた。はっとして手を離そうとすると玲乃にさらに強く握りしめられた。決して離さないと言わんばかりの強さだった。
「玲乃ー。どう? 葉月先生と食う焼肉。格別美味いだろ」
九重くんが玲乃の肩に腕をまわしてきた。それを見て僕の心は鈍く固まるような心地がした。心の奥を、冷たい風が撫でていった。
なんだろう。これじゃまるで九重くんが玲乃に触れるのが嫌みたいな……。
自分の心と向き合っていると玲乃は1度箸を置いて九重くんに鋭い目線を送った。
「お前、スキンシップ激しすぎ。くっついてくるのだるいからやめてくんない?」
隣で聞いていた僕は玲乃の声の低さに、これは本気だと直感した。九重くんの受け答えを注視する。
「えー。別によくね? 男同士じゃん」
へらへら笑う九重くんに玲乃の眉間に深いシワが刻まれるのを見てからはあっというまだった。
「ゔっ」
「男同士だろうが関係ないよ。見てて不快。俺の見てるとこでそれやったら……わかるよね」
玲乃が立ち上がり、九重くんの胸ぐらを掴んで持ち上げた。九重くんの足が床からふわと浮き苦しそうに眉を顰めている。流石の葉月先生も目の前で喧嘩が始まったのを見て仲裁に入る。
「おいおい。今回はお祝いの席だ。店の中だし面倒かけさせるな」
呆れたような葉月先生の声に玲乃は静かに九重くんから手を離す。すると僕の耳もとにそっと口を近づけた。
「帰ろ。疲れた」
玲乃の表情がなんとなくいつもの余裕のある顔じゃなくて、僕はこくりと頷き玲乃の手荷物と自分のトートバッグを持って席から立ち上がる。九重くんはバツが悪そうに玲乃を見つめた。
「悪かった。今後気をつける」
玲乃は九重くんの言葉が聞こえなかったようなふりをして店の出口へ足を運ぶ。僕は葉月先生にぺこりとお辞儀をして玲乃の後を追いかけた。幸い、クラスのみんなはそれぞれのお喋りに花を咲かせていて九重くんと玲乃との対立に気づいていないようだった。
焼肉屋さんは玲乃と僕の最寄り駅のすぐ近くにあったので、そのまま家の方向へと足を進めた。その間、玲乃は無言だった。もしかしたら機嫌が悪いのかもしれない。あるいは、インフルエンサーの仕事に疲れてへとへとなのかもしれない。
マンションのエントランスについてから僕は気遣うように玲乃の肘を掴んだ。
「玲乃。大丈夫?」
玲乃は一瞬目を見開くとそのまま瞳を閉じた。
「やばいかも。このままひとりで帰ったら死んじゃう」
「え!?」
「死んじゃうのは嘘。けど睦とは一緒にいたい」
普段より力なく呟く玲乃を見て僕はなんだか心配が募ってきた。玲乃は歩くのもやっとの様子で、僕に体重を預けるようにしながらエレベーターに乗り込んだ。
心なしか玲乃の顔が火照っているように見える。僕は玲乃の部屋へ直行するとベッドに横にならせた。
「あ。やっぱり熱あるよ、玲乃」
「……熱」
玲乃の額に手のひらを重ねる。額は汗が滲み濡れていてものすごく熱を持っていた。ぽーっと力なく僕を見上げる瞳が今は弱々しい。眼光が鋭い玲乃にしては幼い子どものような不安げな表情に見えた。
「僕の家の冷蔵庫から何か持ってくるね」
家の鍵を手に取り一旦玲乃の部屋から出ていこうとすると「待って」というか細い声が聞こえて振り返る。
「置いてかないで」
熱にうなされているのだろうか。とろん、と溶けた瞳は潤んでいる。僕は玲乃の頭をよしよしと撫でてから安心させるように微笑む。
「大丈夫。5分で帰ってくるからね。ちょっとだけ我慢してて」
「……我慢する」
玲乃はゆっくりと瞳を閉じて枕に頬を押し付けた。
「食べたいのあったら注文番号教えて。僕が打つよ」
「ん。ありがと」
玲乃はぱらぱらとメニュー表を一通り眺めると僕に上タン、はちみつ胡椒豚カルビ、ユッケの注文番号を伝えた。僕はそれを打ち間違いのないように慎重にタブレットに入力する。
「うん。できた」
注文確定ボタンを押してから玲乃を見つめると、なぜかぱちりと目が合ってしまった。まじまじと見つめられて僕は「えっと」と目線を逸らす。すると玲乃は僕の前髪をくしゃりとかきあげた。
「なあに。眉毛いつもと違うね。それにアイライン引いてる? 唇もいつもより血色感あるし、メイクした?」
僕はきゅ、と自身の手のひらを握りしめた。実は玲乃の言う通りで今日初めてメンズメイクをしてみたのだ。クラスのみんなには何も言われなかったから気づかれないと思っていたのに。僕は照れ笑いを浮かべてパイナップルジュースの入ったグラスを持ち上げる。
「うん。文化祭で西園寺さんにメイクしてもらっていつもと雰囲気が変わって気分が上がったんだ。自分でもドラッグストアでコスメを買ってメイクしてみた。……変かな?」
内心どきどきしながら聞いてみれば玲乃は
「いーんじゃない?」
と自身の顎に手を置いて僕を再度まじまじと見つめてきた。そしてテーブルの下で不意に僕の手を掴んできた。僕は目の前でガツガツとご飯を頬張っている葉月先生に気づかれないかはらはらした。
一方の玲乃は気にする様子はまったくないようで、提供されたお肉を網に置いて焼き始めた。指先を絡めて、にぎにぎと2回強く握られる。僕もそれに返事をするように、にぎにぎと2回手を握った。なんだか秘密の合図みたいで、恥ずかしくてたまらないはずなのに嬉しい。
僕は自分の手のひらにじっとり汗が滲んでいないか、そればかり気になった。そんな時、九重くんが僕たちのテーブルの前に現れた。はっとして手を離そうとすると玲乃にさらに強く握りしめられた。決して離さないと言わんばかりの強さだった。
「玲乃ー。どう? 葉月先生と食う焼肉。格別美味いだろ」
九重くんが玲乃の肩に腕をまわしてきた。それを見て僕の心は鈍く固まるような心地がした。心の奥を、冷たい風が撫でていった。
なんだろう。これじゃまるで九重くんが玲乃に触れるのが嫌みたいな……。
自分の心と向き合っていると玲乃は1度箸を置いて九重くんに鋭い目線を送った。
「お前、スキンシップ激しすぎ。くっついてくるのだるいからやめてくんない?」
隣で聞いていた僕は玲乃の声の低さに、これは本気だと直感した。九重くんの受け答えを注視する。
「えー。別によくね? 男同士じゃん」
へらへら笑う九重くんに玲乃の眉間に深いシワが刻まれるのを見てからはあっというまだった。
「ゔっ」
「男同士だろうが関係ないよ。見てて不快。俺の見てるとこでそれやったら……わかるよね」
玲乃が立ち上がり、九重くんの胸ぐらを掴んで持ち上げた。九重くんの足が床からふわと浮き苦しそうに眉を顰めている。流石の葉月先生も目の前で喧嘩が始まったのを見て仲裁に入る。
「おいおい。今回はお祝いの席だ。店の中だし面倒かけさせるな」
呆れたような葉月先生の声に玲乃は静かに九重くんから手を離す。すると僕の耳もとにそっと口を近づけた。
「帰ろ。疲れた」
玲乃の表情がなんとなくいつもの余裕のある顔じゃなくて、僕はこくりと頷き玲乃の手荷物と自分のトートバッグを持って席から立ち上がる。九重くんはバツが悪そうに玲乃を見つめた。
「悪かった。今後気をつける」
玲乃は九重くんの言葉が聞こえなかったようなふりをして店の出口へ足を運ぶ。僕は葉月先生にぺこりとお辞儀をして玲乃の後を追いかけた。幸い、クラスのみんなはそれぞれのお喋りに花を咲かせていて九重くんと玲乃との対立に気づいていないようだった。
焼肉屋さんは玲乃と僕の最寄り駅のすぐ近くにあったので、そのまま家の方向へと足を進めた。その間、玲乃は無言だった。もしかしたら機嫌が悪いのかもしれない。あるいは、インフルエンサーの仕事に疲れてへとへとなのかもしれない。
マンションのエントランスについてから僕は気遣うように玲乃の肘を掴んだ。
「玲乃。大丈夫?」
玲乃は一瞬目を見開くとそのまま瞳を閉じた。
「やばいかも。このままひとりで帰ったら死んじゃう」
「え!?」
「死んじゃうのは嘘。けど睦とは一緒にいたい」
普段より力なく呟く玲乃を見て僕はなんだか心配が募ってきた。玲乃は歩くのもやっとの様子で、僕に体重を預けるようにしながらエレベーターに乗り込んだ。
心なしか玲乃の顔が火照っているように見える。僕は玲乃の部屋へ直行するとベッドに横にならせた。
「あ。やっぱり熱あるよ、玲乃」
「……熱」
玲乃の額に手のひらを重ねる。額は汗が滲み濡れていてものすごく熱を持っていた。ぽーっと力なく僕を見上げる瞳が今は弱々しい。眼光が鋭い玲乃にしては幼い子どものような不安げな表情に見えた。
「僕の家の冷蔵庫から何か持ってくるね」
家の鍵を手に取り一旦玲乃の部屋から出ていこうとすると「待って」というか細い声が聞こえて振り返る。
「置いてかないで」
熱にうなされているのだろうか。とろん、と溶けた瞳は潤んでいる。僕は玲乃の頭をよしよしと撫でてから安心させるように微笑む。
「大丈夫。5分で帰ってくるからね。ちょっとだけ我慢してて」
「……我慢する」
玲乃はゆっくりと瞳を閉じて枕に頬を押し付けた。