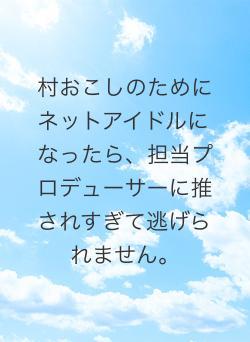「ねえ。さっきのあれ、なに?」
とん、と玲乃が僕を壁際に追い込み壁に手をつける。真顔の玲乃を見て自分は何かやらかしてしまったのだろうかと不安になる。
「あれって?」
おそるおそる口を開くと玲乃は不貞腐れた顔をして僕を見つめた。
「九重だよ。前も言ったけど距離近くてやだ」
「……うん。ごめん。向こうはたぶんフレンドシップのつもりなんだと思う。僕以外にもボディタッチ激しいよ。九重くん」
「……ふうん」
僕が玲乃の目を真っ直ぐ捉えて答えたのを見て、不貞腐れていたその表情が少し和らいだ。
「それならまあ仕方ないか」
独り言のように呟くと今度は僕の衣装のメイド服に触れてきた。白いエプロンの部分をすーっと華奢で骨ばった指がなぞる。ごつごつとしたシルバーのリングを幾つか付けていてそれが光に反射して輝く。きっと自分には縁がないくらい高い指輪なのだろうと僕は推測する。
玲乃は昔から周りの皆が羨むような品を軽々と身にまとっていた。それを羨望として見つめるか、嫉妬として見るかで玲乃への人あたりが変わるのをすぐそばで見てきた。
玲乃はたとえ相手にマウントを取られてもどこ吹く風といったふうに流すことができる稀有な男だった。僕はそんな他人に左右されない自己を持つ玲乃のことが本当に頼もしくて、いつか自分も玲乃みたくなりたいと思ったものだ。
昔話に耽っていると玲乃の指先はどんどん下へと降りていき、ついに僕の腰を支えて、スカートの裾にたどりついた。僕は玲乃の妖しげな手の動きに翻弄されて言葉が出てこない。だんだんと顔も近づいてきて、自分の心臓が跳ねる音がやけに大きく聞こえた
「はあ。ほんとかわいい。食べちゃいたいくらい」
耳もとで囁かれた言葉に僕の全神経が反応した。背筋がぴくと跳ねて全身が熱を帯びる。甘くとろけそうな言葉に吐息混じりの低音が腰の辺りに響いた。
「や……食べちゃやだ」
僕が言えたのはそれだけだった。
「やだって言われるとしたくなる」
「待っ──」
耳もとに触れられただけで、身体が言うことをきかなくなる。息がかかる距離に、頭が真っ白になる。
「っ!」
僕は何かにすがりつかなければ身体ごと宙に浮いてしまいそうな感覚になり、咄嗟に玲乃の腕を掴んだ。
壁に背中を押し付けて少しでも玲乃から離れようとするが、向こうは逃がさないと言わんばかりに僕の腕を壁に縫いつける。
「あ……う……耳、息が当たってくすぐった、い……から」
吐息混じりの僕の言葉に玲乃は「ふうん」と意地悪な笑みを浮かべて
「くすぐったいの? 気持ちいいの間違いじゃない?」
と訂正してきた。
これ以上続いたら、きっと元には戻れない。
そう思ったのに、止めたいのか、止めてほしくないのか、自分でも分からなかった。
僕はまるで自分の心と身体の声が玲乃に聞こえてしまっているんじゃないかと思い紅い顔をさらに赤面させた。頭のつむじから湯気が出てきそうに熱い。それではまるでやかん人間だ。
「そんなに顔真っ赤っかにして。この衣装のメイド服も丈がかなり短くて太もも見えてるよ。はー……かなり際どいし……俺のこと誘ってる?」
獲物を見据えるように鋭くなった瞳に見つめられると動けなかった。
「さ、誘ってない……」
「言葉では否定してても、そんな顔されると勘違いするよ」
くすくすと玲乃が笑い出す。さっきまでの妖しげな雰囲気はいつのまにか消えていて、壁に押付けていた僕の身体を玲乃が離してくれた。
「まさか睦が女装するなんて思ってもみなかった。とっても似合っててかわいい。だから他の奴には見られたくない」
玲乃はそう言うと僕の髪の毛をさらりと撫でながら呟いた。
「この髪型もみんなに見られたくないのに。みんなが睦のかわいいところに気づいたら俺、どうにかなりそう」
冗談として聞いていいのか、玲乃の本心として聞いていいのか判断に迷った。僕は恥ずかしさのあまり目を合わせられずに
「……僕もだよ。僕も同じ気持ち。こんなにかわいい玲乃のこと他の人に見られたくない」
と零した。
「じゃあ内緒にしててね」
玲乃はふわりと微笑み自身の唇に人差し指をあてた。左目の下にある薄い涙ほくろが一瞬宝石のように煌めいて僕は目を瞬かせる。しかし、次の瞬間には玲乃のほくろはいつも見る色っぽいほくろだと認識できた。
僕、もしかして玲乃に対してフィルターかかってる?
言うならば『王子様フィルター』を無意識にかけているのかもしれない。皆が理想とする王子様像を玲乃の言動にあてはめて見てしまっているのかもしれない。僕はだめだめと己を律しながら玲乃にお願いした。
「玲乃。そろそろくっつくのやめて。衣装シワできちゃうかも」
「……えー。まあもっともらしい意見だけど。いつのまにコンカフェ嬢のプロ意識芽生えたの、睦」
くっくっくと喉を鳴らして玲乃が笑う。僕はむーっと頬を膨らませて玲乃の胸をぽかぽかと優しくパンチする。
「もー。からかわないで。接客するときすごく緊張するんだから、今のうちに休んでおかないと心臓持たないよ」
「ふうん」と猫目でなにかを思いついたような表情を浮かべた玲乃が僕の手のひらを引いた。
「じゃあ俺のとっておきのお客さんの口説き方を教えてあげる」
「えっ。なになに? 教えて!」
僕は文化祭の成功のためならばと身を乗り出して玲乃を見上げる。玲乃は微かに弓なりの唇を引き上げてから僕の前で膝をついて手の甲に接吻した。
「わ。なに……?」
「いらっしゃいませ。みゃうみゃうカフェへようこそおいでくださいました。お姫様」
「……ん?」
僕が愛想笑いを浮かべていると玲乃がすくっと立ち上がり互いの腰を引き寄せた。ごつん、と腰骨があたる。互いに細身で、腰骨同士が服越しに擦れ僕はひゅくと息を詰めた。首筋に触れるか触れないかの距離で玲乃が囁いてくる。
「もし俺とツーショット撮ってくれたら、チェキに連絡先を落書きしてあげる」
甘い声音と両腕にまわされた大きくてごつごつしている手のひらに包まれて、自分は本当にお姫様になったんじゃないかと錯覚する。
玲乃は王子様のような余裕たっぷりの微笑みを僕に向けてくる。なぜだか今はその瞳の中に自分だけが囚われているのが嬉しくて、なぜ嬉しいのかの理由はわからなくても、息をするのも忘れて迫りくる唇に目を奪われていた。
「……っ」
「とかね。まあ落書きするのは仕事用のSNSの連絡先だけど」
唇がくっつくかくっつかないかのギリギリのところで玲乃が動きを止める。僕の心臓は今までになく早鐘を打っていた。
僕はへたっと腰が抜けてしまいその場に座り込んだ。
「睦? なあに。これくらいで腰抜かしちゃって。これくらいでそうなっちゃうなら、この先は耐えられるのかな?」
むふふと含み笑いをする玲乃に僕は何も言えなくなって唇をきゅっと紡ぐ。玲乃の言う通りだった。
僕はまだ誰かと恋人関係になったことはない。キスも未経験でその先はもっと知らないことだらけだ。玲乃の言葉だけで腰砕けになっているのでは先が思いやられる。
そこで僕は玲乃にやり返しを試みた。
ひらひらと手を振って玲乃に腰を落として座らせる。「はいはい」と赤ちゃんに対応するような余裕たっぷりの玲乃に僕はちゅ、と自分の人差し指にキスをしてそのまま人差し指を玲乃の頬っぺにくっつけた。
『指キス』といって指越しにキスをするポーズだ。このくらいは僕でも知っていた。なぜなら指キスは祖母の家の黒猫にやっていたからだ。
直接キスしたくなるくらい愛おしい黒猫で、小さい頃ちゅーをしようとしていたのを祖母に見つかり叱られた。
「黒猫の同意を得ずキスするのはよくないことよ」と。それ以来、僕は黒猫にキスをしたくなったときには自身の指にキスをしてその指を黒猫にくっつけていた。
それを咄嗟に思い出しての指キスだった。玲乃は不意を打たれたのか黙り込んでいる。たまにはやり返せて嬉しくなった僕は自信満々に玲乃を見つめる。
「僕だってもう高校生だよ。いつまでも玲乃にお世話される赤ちゃんじゃないんだからね」
「……」
暫しの無言の後、玲乃は温度のない瞳で僕を見つめてきた。その強い眼差しから決して目が離せなくなる。
「それ、俺以外に絶対やらないで」
「……う、うん」
いつものふにゃふにゃ甘えたくんの玲乃とは違い、冗談にも聞こえない低い声のトーンで言われて僕は玲乃のまだ知らない一面があることを知って記憶に上書きした。
とん、と玲乃が僕を壁際に追い込み壁に手をつける。真顔の玲乃を見て自分は何かやらかしてしまったのだろうかと不安になる。
「あれって?」
おそるおそる口を開くと玲乃は不貞腐れた顔をして僕を見つめた。
「九重だよ。前も言ったけど距離近くてやだ」
「……うん。ごめん。向こうはたぶんフレンドシップのつもりなんだと思う。僕以外にもボディタッチ激しいよ。九重くん」
「……ふうん」
僕が玲乃の目を真っ直ぐ捉えて答えたのを見て、不貞腐れていたその表情が少し和らいだ。
「それならまあ仕方ないか」
独り言のように呟くと今度は僕の衣装のメイド服に触れてきた。白いエプロンの部分をすーっと華奢で骨ばった指がなぞる。ごつごつとしたシルバーのリングを幾つか付けていてそれが光に反射して輝く。きっと自分には縁がないくらい高い指輪なのだろうと僕は推測する。
玲乃は昔から周りの皆が羨むような品を軽々と身にまとっていた。それを羨望として見つめるか、嫉妬として見るかで玲乃への人あたりが変わるのをすぐそばで見てきた。
玲乃はたとえ相手にマウントを取られてもどこ吹く風といったふうに流すことができる稀有な男だった。僕はそんな他人に左右されない自己を持つ玲乃のことが本当に頼もしくて、いつか自分も玲乃みたくなりたいと思ったものだ。
昔話に耽っていると玲乃の指先はどんどん下へと降りていき、ついに僕の腰を支えて、スカートの裾にたどりついた。僕は玲乃の妖しげな手の動きに翻弄されて言葉が出てこない。だんだんと顔も近づいてきて、自分の心臓が跳ねる音がやけに大きく聞こえた
「はあ。ほんとかわいい。食べちゃいたいくらい」
耳もとで囁かれた言葉に僕の全神経が反応した。背筋がぴくと跳ねて全身が熱を帯びる。甘くとろけそうな言葉に吐息混じりの低音が腰の辺りに響いた。
「や……食べちゃやだ」
僕が言えたのはそれだけだった。
「やだって言われるとしたくなる」
「待っ──」
耳もとに触れられただけで、身体が言うことをきかなくなる。息がかかる距離に、頭が真っ白になる。
「っ!」
僕は何かにすがりつかなければ身体ごと宙に浮いてしまいそうな感覚になり、咄嗟に玲乃の腕を掴んだ。
壁に背中を押し付けて少しでも玲乃から離れようとするが、向こうは逃がさないと言わんばかりに僕の腕を壁に縫いつける。
「あ……う……耳、息が当たってくすぐった、い……から」
吐息混じりの僕の言葉に玲乃は「ふうん」と意地悪な笑みを浮かべて
「くすぐったいの? 気持ちいいの間違いじゃない?」
と訂正してきた。
これ以上続いたら、きっと元には戻れない。
そう思ったのに、止めたいのか、止めてほしくないのか、自分でも分からなかった。
僕はまるで自分の心と身体の声が玲乃に聞こえてしまっているんじゃないかと思い紅い顔をさらに赤面させた。頭のつむじから湯気が出てきそうに熱い。それではまるでやかん人間だ。
「そんなに顔真っ赤っかにして。この衣装のメイド服も丈がかなり短くて太もも見えてるよ。はー……かなり際どいし……俺のこと誘ってる?」
獲物を見据えるように鋭くなった瞳に見つめられると動けなかった。
「さ、誘ってない……」
「言葉では否定してても、そんな顔されると勘違いするよ」
くすくすと玲乃が笑い出す。さっきまでの妖しげな雰囲気はいつのまにか消えていて、壁に押付けていた僕の身体を玲乃が離してくれた。
「まさか睦が女装するなんて思ってもみなかった。とっても似合っててかわいい。だから他の奴には見られたくない」
玲乃はそう言うと僕の髪の毛をさらりと撫でながら呟いた。
「この髪型もみんなに見られたくないのに。みんなが睦のかわいいところに気づいたら俺、どうにかなりそう」
冗談として聞いていいのか、玲乃の本心として聞いていいのか判断に迷った。僕は恥ずかしさのあまり目を合わせられずに
「……僕もだよ。僕も同じ気持ち。こんなにかわいい玲乃のこと他の人に見られたくない」
と零した。
「じゃあ内緒にしててね」
玲乃はふわりと微笑み自身の唇に人差し指をあてた。左目の下にある薄い涙ほくろが一瞬宝石のように煌めいて僕は目を瞬かせる。しかし、次の瞬間には玲乃のほくろはいつも見る色っぽいほくろだと認識できた。
僕、もしかして玲乃に対してフィルターかかってる?
言うならば『王子様フィルター』を無意識にかけているのかもしれない。皆が理想とする王子様像を玲乃の言動にあてはめて見てしまっているのかもしれない。僕はだめだめと己を律しながら玲乃にお願いした。
「玲乃。そろそろくっつくのやめて。衣装シワできちゃうかも」
「……えー。まあもっともらしい意見だけど。いつのまにコンカフェ嬢のプロ意識芽生えたの、睦」
くっくっくと喉を鳴らして玲乃が笑う。僕はむーっと頬を膨らませて玲乃の胸をぽかぽかと優しくパンチする。
「もー。からかわないで。接客するときすごく緊張するんだから、今のうちに休んでおかないと心臓持たないよ」
「ふうん」と猫目でなにかを思いついたような表情を浮かべた玲乃が僕の手のひらを引いた。
「じゃあ俺のとっておきのお客さんの口説き方を教えてあげる」
「えっ。なになに? 教えて!」
僕は文化祭の成功のためならばと身を乗り出して玲乃を見上げる。玲乃は微かに弓なりの唇を引き上げてから僕の前で膝をついて手の甲に接吻した。
「わ。なに……?」
「いらっしゃいませ。みゃうみゃうカフェへようこそおいでくださいました。お姫様」
「……ん?」
僕が愛想笑いを浮かべていると玲乃がすくっと立ち上がり互いの腰を引き寄せた。ごつん、と腰骨があたる。互いに細身で、腰骨同士が服越しに擦れ僕はひゅくと息を詰めた。首筋に触れるか触れないかの距離で玲乃が囁いてくる。
「もし俺とツーショット撮ってくれたら、チェキに連絡先を落書きしてあげる」
甘い声音と両腕にまわされた大きくてごつごつしている手のひらに包まれて、自分は本当にお姫様になったんじゃないかと錯覚する。
玲乃は王子様のような余裕たっぷりの微笑みを僕に向けてくる。なぜだか今はその瞳の中に自分だけが囚われているのが嬉しくて、なぜ嬉しいのかの理由はわからなくても、息をするのも忘れて迫りくる唇に目を奪われていた。
「……っ」
「とかね。まあ落書きするのは仕事用のSNSの連絡先だけど」
唇がくっつくかくっつかないかのギリギリのところで玲乃が動きを止める。僕の心臓は今までになく早鐘を打っていた。
僕はへたっと腰が抜けてしまいその場に座り込んだ。
「睦? なあに。これくらいで腰抜かしちゃって。これくらいでそうなっちゃうなら、この先は耐えられるのかな?」
むふふと含み笑いをする玲乃に僕は何も言えなくなって唇をきゅっと紡ぐ。玲乃の言う通りだった。
僕はまだ誰かと恋人関係になったことはない。キスも未経験でその先はもっと知らないことだらけだ。玲乃の言葉だけで腰砕けになっているのでは先が思いやられる。
そこで僕は玲乃にやり返しを試みた。
ひらひらと手を振って玲乃に腰を落として座らせる。「はいはい」と赤ちゃんに対応するような余裕たっぷりの玲乃に僕はちゅ、と自分の人差し指にキスをしてそのまま人差し指を玲乃の頬っぺにくっつけた。
『指キス』といって指越しにキスをするポーズだ。このくらいは僕でも知っていた。なぜなら指キスは祖母の家の黒猫にやっていたからだ。
直接キスしたくなるくらい愛おしい黒猫で、小さい頃ちゅーをしようとしていたのを祖母に見つかり叱られた。
「黒猫の同意を得ずキスするのはよくないことよ」と。それ以来、僕は黒猫にキスをしたくなったときには自身の指にキスをしてその指を黒猫にくっつけていた。
それを咄嗟に思い出しての指キスだった。玲乃は不意を打たれたのか黙り込んでいる。たまにはやり返せて嬉しくなった僕は自信満々に玲乃を見つめる。
「僕だってもう高校生だよ。いつまでも玲乃にお世話される赤ちゃんじゃないんだからね」
「……」
暫しの無言の後、玲乃は温度のない瞳で僕を見つめてきた。その強い眼差しから決して目が離せなくなる。
「それ、俺以外に絶対やらないで」
「……う、うん」
いつものふにゃふにゃ甘えたくんの玲乃とは違い、冗談にも聞こえない低い声のトーンで言われて僕は玲乃のまだ知らない一面があることを知って記憶に上書きした。