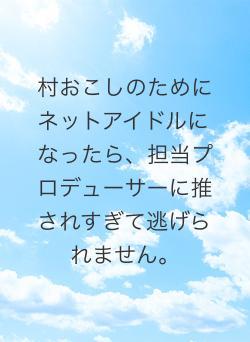「ようこそ。みゃうみゃうカフェへ」
文化祭2日目がスタートして1時間が経った頃、僕はお客さんへの接客に駆り出されていた。
急遽キャストを変更した旨を九重くんが文化祭専用アカウントでお知らせしたところ、質問が相次いだそうだ。
『代わりのキャスト誰ですか? 宣材写真見たいので載せて欲しいです』
というコメントが複数目立った。
そこで九重くんは急遽SNSフォトブースの前に僕を立たせて適当にポーズをとらせて宣材のための写真撮影を行った。
もちろん写真を撮りなれていない僕はぎこちないポーズを連発したが、九重くんが監督のように細かく指示を出して撮影してくれたおかげでなんとか宣材写真をSNSに載せることができた。
すると、僕の写真に1万いいねがつきお客さんがどっと廊下に押し寄せてきたのだ。
「やば。思ったよりバズっちゃったから、守須、頑張れ! 俺も手伝うから」
それは文化祭2日目がスタートする数分前のことだった。
僕の宣材写真がバズったおかげでアカウントの知名度がアップし、他のキャスト目当てのお客さんも増えた。
昨日から連日来てくれる継続ファンの人もいるため、店内はかなり混雑していた。
もともと1時間ワンドリンク・ワンオーダー制としていたが、30分ワンドリンクまたはワンオーダー制と変更せざるをえなかった。
ドリンク・フード担当のBチームと連携をとりつつ、ようやく開始1時間を無事に終えることができた。
「守須ちゃん! 3番の席に新規のお客さん2名入ったからお冷とお手ふきの提供よろしくね」
Bチームのリーダーの高島さんの正確で素早い指示を仰ぎながら、僕は店内を動き回った。慣れないワンピースに足元がすーすーして落ち着かない。
「はいっ」
僕はお冷とお手ふきを載せた白くて丸いトレイを片手に3番の席へ向かう。2人がけの机に女性のお客さんが2人座ってこちらを見つめている。
僕は緊張して背中に変な汗をかきつつも、なるべく笑顔で接客にあたる。
「こ、こんにちは。守須です」
机の上に持ってきたものを置いてからぺこりとお辞儀をする。すると目の前の2人が僕の頭につけているうさ耳をつんつん触ってきた。
「かわいいー。ねえねえ。なんで守須ちゃんはひとりだけうさ耳なの? 他のキャストみんな猫耳なのに」
ぎく、と僕は頬をひくつかせる。こんな質問もあるだろうとあらかじめ西園寺さんから教えてもらった受け答えを実行することにした。
「みゃうみゃうカフェはその名の通り英語で猫ちゃんの鳴き声を表現する言葉なのですが、1匹だけ突然変異でうさぎになっちゃったのが僕なんです……」
上手く言えたかな……?
ちらりと2人の顔を交互に見れば、すぐさま
「なにそれ斬新! 面白い設定だね」
くすくす笑う2人を見て僕はふるふると首を横に振る。
「設定なんかじゃないです。みゃうみゃうカフェの世界ではそうなっているんです」
自分ながら無理な説明とこじつけだなあと目を潤ませて呟くと、2人の女性はすぐさまメニュー表を開いてオーダーを入れてきた。
「わたしはこの『みゃうみゃうオムライス~キャストのお絵描き付き~』と『オレンジジュース』で」
僕はいそいそとスマホのチェック項目にオーダーされたメニューにチェックを入れていく。
「あたしは『めろめろプリン』と『エナジードリンク』をよろしく」
「はい。かしこまりました」
2人のオーダーをとってからその場を去ろうとすると
「「あと守須ちゃんのツーショットチェキ10枚お願いしますっ」」
と2人重ねて追加注文してくれた。
「あ、ありがとうございます。食後にいっぱいお写真撮りましょう……!」
なるべく笑顔で伝えたが緊張すると早口になる癖をここでも発揮してしまい、その場からすたすたと立ち去った。僕が去った後で2人が
「なにあの子超天然記念物。早口なの緊張してるのかな。かわいい」
そんなふうに思われていることなど、僕は知る由もなかった。
「はい。最後の10枚目でーす。はい、みゃうみゃう」
ぱしゃ、と乾いた音を立てて撮影したツーショットチェキが出てきた。
九重くんが撮影担当をしていたので安心して任せることができた。先程の2人のお客さんはきゃっきゃっと盛り上がりながら僕と撮った写真を片手に笑いあっている。そして再度歩み寄り溢れんばかりの笑みを浮かべた。
「守須ちゃん。一緒に撮影してくれてありがとう。これ私の宝物にするね。一生懸命お話してくれて本当に嬉しい。このあともお仕事頑張ってね」
「あ、ありがとうございます」
まさかここまで丁寧にお礼をしてくれるとは思わなくて僕はどきどきしながらお客さんからの言葉を胸に刻んだ。
「今年の天満高校の文化祭の圧倒的なんばーわんの推しは守須ちゃんで決まりだから」
「推し」という言葉に照れている自分がいた。
今までの僕は心無いクラスメイトから『もやしくん』と呼ばれてからかわれたり、掃除を押し付けられたりと寂しい日々を送っていた。
けれど今、いろいろ巡り巡って文化祭の出し物のキャストとして奮闘している。
引っ込み思案で大人しいタイプの自分がまさかここまでお客さんと話せるなんてまるで夢みたいだった。なにより、お客さん一人一人が僕と話していると笑顔になってくれたり喜んでくれる姿を見ると胸が熱くなるのも事実だった。
その後も僕目当てのお客さんが多く足を運び、店内は満員御礼の状態だった。
廊下に並ぶ列は途絶えることなく、九重くんによると約40分待ちらしい。それを聞いた他のキャストも気合いが入り、いたるところで楽しげな笑い声が飛び交っている。
僕は午後1時になってから1時間休憩をもらった。裏方で手荷物をまとめて移動する準備をする。エアコンの効いた映画研究同好会の部室でお昼ご飯でも食べてゆっくり休もうかと思っていたところ、後ろから肩を叩かれて振り向く。
ぷに、と頬っぺに骨ばった指が押し込まれていた。こんなことをするのは玲乃に違いないと思って顔を見上げると、意外にもその指は別の人物のものだった。
「おつかれ守須。俺も休憩1時間もらったからこれからメシ行かない?」
無邪気な少年のような笑顔を浮かべる九重くんに僕は曖昧に笑って断ろうと思った。するとそれを遮るように別の腕が後ろから伸びてきた。
ふわりと鼻をつくアプリコットバニラの香水の匂い。その匂いを感じただけで心だけでなく身体も落ち着く。張り詰めた僕の緊張をすべて溶かしてくれる。
「九重。睦はこれから俺と用があるからダメ」
玲乃の牽制するような瞳に九重くんは何かを察したのか残念そうに眉を垂らす。
「えー。先約入ってたんかぁ。それなら仕方ねえや。また今度な」
裏方から九重くんが出ていくのを見届けると、玲乃は僕の腕をとって無言で歩き出した。
裏方から出て廊下へ出ると途端にキャーという黄色い悲鳴が上がった。衣装を着たままのキャストが2人歩いているのだ。当然廊下にいるお客さんの注目を浴びる。
嫉妬するような目線。憧れるような視線。
その両方が針になって僕の全身を貫いているように感じた。
こんなふうに大勢の人から注目されたことがない僕は足が冷たくなっていた。まるでショーケースに並べられたマネキンのように他人は僕に無遠慮な視線を送っているように思えた。
値踏みされているような感覚に胸の奥が渦を巻く。そんな張り詰めた心の僕とは違って、玲乃はこうした状況に慣れているようで何食わぬ顔で廊下を突き進んでいく。
僕は人とすれ違う度に頭から爪先までじろじろと見定められていると感じてあまり気分が良くなかった。だから早足で部室へ向かい、部室に入ると無意識に安堵の溜息を洩らしていた。
部室には他の部員の姿は見当たらなかった。少しほっとした。学校内で玲乃と二人きりのところを見られるのは抵抗があった。
内緒の友達として玲乃の傍にいられるのが僕の特権だからだ。玲乃と僕が実は幼馴染で互いの部屋にも入り浸るくらいの仲だと他の人に知られたくなかった。大切な宝物は決して他の人に見せずに自分の部屋だけでこっそり鑑賞していたいから。
文化祭2日目がスタートして1時間が経った頃、僕はお客さんへの接客に駆り出されていた。
急遽キャストを変更した旨を九重くんが文化祭専用アカウントでお知らせしたところ、質問が相次いだそうだ。
『代わりのキャスト誰ですか? 宣材写真見たいので載せて欲しいです』
というコメントが複数目立った。
そこで九重くんは急遽SNSフォトブースの前に僕を立たせて適当にポーズをとらせて宣材のための写真撮影を行った。
もちろん写真を撮りなれていない僕はぎこちないポーズを連発したが、九重くんが監督のように細かく指示を出して撮影してくれたおかげでなんとか宣材写真をSNSに載せることができた。
すると、僕の写真に1万いいねがつきお客さんがどっと廊下に押し寄せてきたのだ。
「やば。思ったよりバズっちゃったから、守須、頑張れ! 俺も手伝うから」
それは文化祭2日目がスタートする数分前のことだった。
僕の宣材写真がバズったおかげでアカウントの知名度がアップし、他のキャスト目当てのお客さんも増えた。
昨日から連日来てくれる継続ファンの人もいるため、店内はかなり混雑していた。
もともと1時間ワンドリンク・ワンオーダー制としていたが、30分ワンドリンクまたはワンオーダー制と変更せざるをえなかった。
ドリンク・フード担当のBチームと連携をとりつつ、ようやく開始1時間を無事に終えることができた。
「守須ちゃん! 3番の席に新規のお客さん2名入ったからお冷とお手ふきの提供よろしくね」
Bチームのリーダーの高島さんの正確で素早い指示を仰ぎながら、僕は店内を動き回った。慣れないワンピースに足元がすーすーして落ち着かない。
「はいっ」
僕はお冷とお手ふきを載せた白くて丸いトレイを片手に3番の席へ向かう。2人がけの机に女性のお客さんが2人座ってこちらを見つめている。
僕は緊張して背中に変な汗をかきつつも、なるべく笑顔で接客にあたる。
「こ、こんにちは。守須です」
机の上に持ってきたものを置いてからぺこりとお辞儀をする。すると目の前の2人が僕の頭につけているうさ耳をつんつん触ってきた。
「かわいいー。ねえねえ。なんで守須ちゃんはひとりだけうさ耳なの? 他のキャストみんな猫耳なのに」
ぎく、と僕は頬をひくつかせる。こんな質問もあるだろうとあらかじめ西園寺さんから教えてもらった受け答えを実行することにした。
「みゃうみゃうカフェはその名の通り英語で猫ちゃんの鳴き声を表現する言葉なのですが、1匹だけ突然変異でうさぎになっちゃったのが僕なんです……」
上手く言えたかな……?
ちらりと2人の顔を交互に見れば、すぐさま
「なにそれ斬新! 面白い設定だね」
くすくす笑う2人を見て僕はふるふると首を横に振る。
「設定なんかじゃないです。みゃうみゃうカフェの世界ではそうなっているんです」
自分ながら無理な説明とこじつけだなあと目を潤ませて呟くと、2人の女性はすぐさまメニュー表を開いてオーダーを入れてきた。
「わたしはこの『みゃうみゃうオムライス~キャストのお絵描き付き~』と『オレンジジュース』で」
僕はいそいそとスマホのチェック項目にオーダーされたメニューにチェックを入れていく。
「あたしは『めろめろプリン』と『エナジードリンク』をよろしく」
「はい。かしこまりました」
2人のオーダーをとってからその場を去ろうとすると
「「あと守須ちゃんのツーショットチェキ10枚お願いしますっ」」
と2人重ねて追加注文してくれた。
「あ、ありがとうございます。食後にいっぱいお写真撮りましょう……!」
なるべく笑顔で伝えたが緊張すると早口になる癖をここでも発揮してしまい、その場からすたすたと立ち去った。僕が去った後で2人が
「なにあの子超天然記念物。早口なの緊張してるのかな。かわいい」
そんなふうに思われていることなど、僕は知る由もなかった。
「はい。最後の10枚目でーす。はい、みゃうみゃう」
ぱしゃ、と乾いた音を立てて撮影したツーショットチェキが出てきた。
九重くんが撮影担当をしていたので安心して任せることができた。先程の2人のお客さんはきゃっきゃっと盛り上がりながら僕と撮った写真を片手に笑いあっている。そして再度歩み寄り溢れんばかりの笑みを浮かべた。
「守須ちゃん。一緒に撮影してくれてありがとう。これ私の宝物にするね。一生懸命お話してくれて本当に嬉しい。このあともお仕事頑張ってね」
「あ、ありがとうございます」
まさかここまで丁寧にお礼をしてくれるとは思わなくて僕はどきどきしながらお客さんからの言葉を胸に刻んだ。
「今年の天満高校の文化祭の圧倒的なんばーわんの推しは守須ちゃんで決まりだから」
「推し」という言葉に照れている自分がいた。
今までの僕は心無いクラスメイトから『もやしくん』と呼ばれてからかわれたり、掃除を押し付けられたりと寂しい日々を送っていた。
けれど今、いろいろ巡り巡って文化祭の出し物のキャストとして奮闘している。
引っ込み思案で大人しいタイプの自分がまさかここまでお客さんと話せるなんてまるで夢みたいだった。なにより、お客さん一人一人が僕と話していると笑顔になってくれたり喜んでくれる姿を見ると胸が熱くなるのも事実だった。
その後も僕目当てのお客さんが多く足を運び、店内は満員御礼の状態だった。
廊下に並ぶ列は途絶えることなく、九重くんによると約40分待ちらしい。それを聞いた他のキャストも気合いが入り、いたるところで楽しげな笑い声が飛び交っている。
僕は午後1時になってから1時間休憩をもらった。裏方で手荷物をまとめて移動する準備をする。エアコンの効いた映画研究同好会の部室でお昼ご飯でも食べてゆっくり休もうかと思っていたところ、後ろから肩を叩かれて振り向く。
ぷに、と頬っぺに骨ばった指が押し込まれていた。こんなことをするのは玲乃に違いないと思って顔を見上げると、意外にもその指は別の人物のものだった。
「おつかれ守須。俺も休憩1時間もらったからこれからメシ行かない?」
無邪気な少年のような笑顔を浮かべる九重くんに僕は曖昧に笑って断ろうと思った。するとそれを遮るように別の腕が後ろから伸びてきた。
ふわりと鼻をつくアプリコットバニラの香水の匂い。その匂いを感じただけで心だけでなく身体も落ち着く。張り詰めた僕の緊張をすべて溶かしてくれる。
「九重。睦はこれから俺と用があるからダメ」
玲乃の牽制するような瞳に九重くんは何かを察したのか残念そうに眉を垂らす。
「えー。先約入ってたんかぁ。それなら仕方ねえや。また今度な」
裏方から九重くんが出ていくのを見届けると、玲乃は僕の腕をとって無言で歩き出した。
裏方から出て廊下へ出ると途端にキャーという黄色い悲鳴が上がった。衣装を着たままのキャストが2人歩いているのだ。当然廊下にいるお客さんの注目を浴びる。
嫉妬するような目線。憧れるような視線。
その両方が針になって僕の全身を貫いているように感じた。
こんなふうに大勢の人から注目されたことがない僕は足が冷たくなっていた。まるでショーケースに並べられたマネキンのように他人は僕に無遠慮な視線を送っているように思えた。
値踏みされているような感覚に胸の奥が渦を巻く。そんな張り詰めた心の僕とは違って、玲乃はこうした状況に慣れているようで何食わぬ顔で廊下を突き進んでいく。
僕は人とすれ違う度に頭から爪先までじろじろと見定められていると感じてあまり気分が良くなかった。だから早足で部室へ向かい、部室に入ると無意識に安堵の溜息を洩らしていた。
部室には他の部員の姿は見当たらなかった。少しほっとした。学校内で玲乃と二人きりのところを見られるのは抵抗があった。
内緒の友達として玲乃の傍にいられるのが僕の特権だからだ。玲乃と僕が実は幼馴染で互いの部屋にも入り浸るくらいの仲だと他の人に知られたくなかった。大切な宝物は決して他の人に見せずに自分の部屋だけでこっそり鑑賞していたいから。